
こんにちは。ファングリーでWebディレクターとして、日々さまざまなステークホルダーに揉まれている佐藤です。
ここ最近、「AI」を活用しているという声を多く耳にするようになりました。実際にサイト制作の現場ではお客様側でもAIを活用していることがあり、AIがぐっと身近になったように感じます。
そこで今回は、AIの進化にちょっとした危機感を持ちつつも、AIを活用する側として「どのように生き残っていくか」を考え、サイト制作とAIの関係について書いてみようと思います。
「AIによってサイト制作はどのように変わっていくか」
今回はその第1弾になります。
Web担当者の方や制作に関わる方々のヒントになれば幸いです。
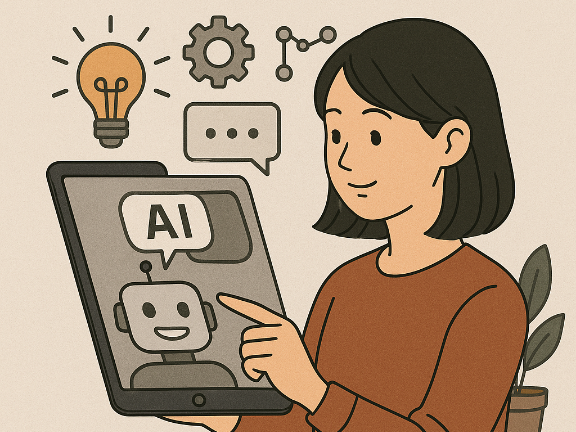
さて、皆さんはAIを使っていますか?
おそらく多くの方は既に何かしらのAIを利用していると思います。
また、AIに対して「仕事がなくなる」という不安や、「便利すぎてもはや手放せない」という感情を抱いているかもしれません。
私自身も普段、ChatGPTを毎日使っています。CSSやJavaScriptのコード、Excelの関数、複雑な計算など、業務上で不安な部分を補ってくれるAIの存在はとても大きく、もはやChatGPTなしでは仕事が回らないという感覚すらあります。
では、過去はどうだったのか。4年前まではスマホに搭載されたAIぐらいしか印象がなく、ほとんど使っていませんでした。
しかし、ChatGPTやGeminiといったブラウザで使えるAIの登場により、情報検索のスタイルは大きく変わりました。もはや「ググる」ことが減り、直接AIに聞くようになっています。
最終的な検証やファクトチェックは必要ですが、すっかりAIが身近な存在となり、実務にも取り入れられるようになったことから、働き方自体も変わってきています。
近年、AIはサイト制作でも使われていますが、まずはサイト制作の一般的なフローを整理していきます。Webサイトの制作フローは、以下のような工程で構成されています。
サイトの種類(ECサイト、会員サイト、コーポレートサイトなど)によって多少の違いはありますが、基本的な流れは共通です。
それぞれのフェーズには、営業、ディレクター、デザイナー、ライター、コーダー、エンジニアといった専門職が関与しますが、これらの各工程にAIが取り入れられ始めています。
CMS構築やシステム開発の領域でも、AIが仕様に基づいたコードやデータベース設計のドラフトを出力することが可能になってきています。
それぞれの専門職人材が「業務の効率化」「費用の削減」「スピードの向上」といった目的でAIを導入している状況です。また、使用者次第ではありますが、様々なアイディアをスピーディーに検証できるため、品質の向上に役立っている一面もあると考えます。
既存サイトの運用においては、データ分析にAIを使用しているケースもあるでしょう。
最近ではWixやJimdoのように、質問に答えるだけでAIがデザインと構成を自動生成してくれるサービスも登場しています。テンプレートの提供やノーコード編集も可能なため、非エンジニア職種でもサイトを短期間で作れる環境が整ってきました。特に小規模事業者や個人事業主にとっては外注費を抑えることができ、自身で運用もしやすいため、有力な選択肢の一つになると思います。
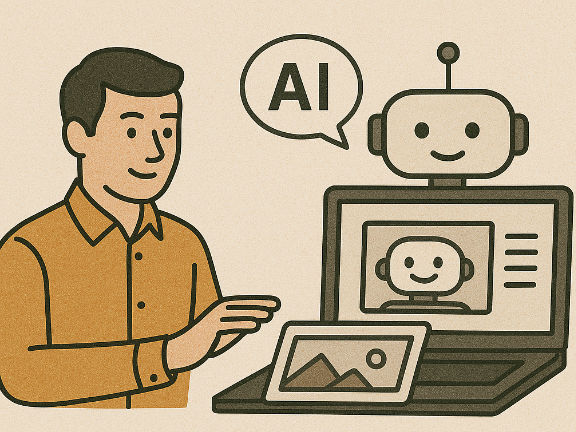
既にサイト制作の現場で様々なAIが活用されていることは上述した通りです。続いてはサイトの作り手ではなく、「委託する側」に与える影響を考えます。
自社のWebサイトを制作する際、多くの企業は制作プロセスを外部業者へ委託しているでしょう。そんな中、AIの登場によって「どの工程までを自社で行い、何を外注するか」という線引きが変わりつつあります。
上述したように、サイト制作には複数の工程があります。掲載する写真や動画、イラストといった素材も用意する場合、さらに多くの人が携わることになります。これらの工程のうち、「どこまで委託するか」によって見積もりや作業負担が変わります。
「全て外部に委託しよう」となれば、我々のような制作会社が全ての工程を担いますが、多くの会社はAIを活用して「できるだけコストを抑えよう」という発想になると思います。
例えば、「これまではライティングも含めて依頼していたが、ライティングはAIを活用して自社でまかなおう」といったシフトが考えられます。委託する側の作業範囲は増えますが、AIを活用することでこれまでよりも作業負担は少なくなり、依頼する作業量(=外注費)が減るためコストメリットが得られます。
特に委託する側にとってAIを活用するメリットが大きい工程としては下記と考えています。
AIによって情報整理やアイディア出しがスムーズになり、SEOを考慮したコンテンツ案なども自社で作成可能です。制作会社からの提案を待つよりスピーディーに進められ、ビジネス理解が深い内容を作ることができるしょう。
いわゆる「お任せデザイン」で問題ないのであれば、既にWixやJimdoで実現されています。また、キービジュアルの素材をAIで作成したり、バナーをAIで作成したりと、サイト内の素材を制作することも可能です。
デザインを全てAIで制作せずとも、自社のイメージをAIで見える化して、制作会社に仕上げをお願いする形を取れば、コストを抑え、よりイメージに近いサイトに仕上がるかと思います。
ライティングはまさにAIが得意とするところだと感じています。情報の分類、見出しによる整理、表現の調整まで可能なため、情報を用意できればひとまず文章は作成できてしまいます。
キャッチコピーもターゲットや打ち出したい内容を整理できれば、表現を変えた案をAIからもらい、絞っていくこともできます。
制作会社に依頼する場合、相手のビジネス理解が浅いと「ぺらぺらなコンテンツ」になってしまうため、自社内で完結したほうがむしろ「中身のあるコンテンツ」になるかもしれません。
このように、委託する側に「こうしたい」というイメージがある場合や、イメージが無くとも自社でアイディア出しを行い、イメージを形作ることが可能な場合は、AI活用によるコスト面、品質面のメリットが大きいと考えます。

さて、ここまでサイト制作のAIの活用について書きましたが、以下では「制作会社はどんな価値を発揮できるのか」について考えます。極論、委託する側に全ての機能が揃っていれば制作会社の出番はないのですが、よくあるサイト制作における制作会社の価値について書いていきます。
自分が思うAI、は一言で置き換えるなら「優秀な助手」です。必要な情報を与えれば、その情報をわかりやすく整理したり、要約したり。“ネットに落ちているような情報“であれば、情報を体系立てて提供してくれる。そしてそのレスポンスがとても早い。
他のデザインやコーディングにおいても同様で、“こうしたい“を具体化し、それをAIに指示することで意図した成果物が上がってきます。
しかしながら、自分の代わりに情報を収集し、戦略・戦術を定め、意思決定し、各プロジェクトの目的や方針を定め、そのプロジェクトを設計しマネジメントをすることは期待できません。
サイト制作においても、上流になればなるほど「戦略的思考」や「コミュニケーション力」「マネジメント力」といった、状況や相手に合わせることが求められる業務となります。
こういった業務はAIが自律し、信頼を得ない限りは難しいと感じます。
よく「対人の仕事はAIでは代替できない」と言いますが、結局のところ現状のAIは「助手でしかない」ので指示が必要です。そして、指示を出せなければ何も進みません。しかし、考慮すべき事項が多いので指示を出すのも大変です。
ここに、制作会社の価値があると考えます。
AIは助手であり、色々な人の助手になってくれます。ただし、軍師のように提案をくれ、プロジェクトを任せたらあとはうまくいく――と安心することはできません。
また、作業をAIに任せるとしても、良い成果物を期待するなら具体的な指示を出せないといけません。
制作会社の理想的な使い方としては、上流の企画・要件定義・画面設計をまずは一任し、そのうえでデザインやライティングをどのように進めるかを、一緒に検討してもらうと良いと思います。
後から上流工程に見直しが入ると下流工程が進まなくなり、予算超過や納期が間に合わなくなります。まずは企画、要件定義、画面設計まで進めていくことで解像度を上げ、必要に応じて要件定義に立ち戻り、下流工程の進め方を再検討する形を取る。そうすることで、結果的に納期や品質、予算面でもスムーズに進めやすくなるでしょう。
全体と、各工程において「こういうものが作りたい」を言語化できれば、あとは成果物を作っていく、「作業」の工程にスムーズに移ることができます。
下流工程では社内リソースやAIを使っても良いし、よりクリエイティブにこだわりたいニーズがあればデザイン事務所のような領域に特化した会社やフリーランスに依頼しても良い。もちろん他に依頼するための契約やコミュニケーション、品質などに不安がある場合や、その時間を省くメリットが大きければ制作会社に依頼するのも良いでしょう。
サイトの成果を高めるためには、ターゲットの明確化や競合分析、USP(独自の強み)の設計といった戦略的な上流工程が重要になります。制作会社には、さまざまな業界や目的のサイト制作に携わった経験が蓄積されているため、「誰に届けるべきか」「何を訴求すべきか」「どこで差別化を図るべきか」といった本質的な問いに対して、客観的かつ具体的な提案が可能です。単なる情報掲載にとどまらず、ビジネス成果につながる設計・構成が可能になります。
AIでは拾いきれない、リアルなマーケット感覚や競争環境に基づいた提案こそが、制作会社に委託する大きな価値のひとつです。
世の中には細やかに動ける制作会社やフリーランスの優秀なクリエイターがたくさんいるため、各プロジェクトに合わせて柔軟に体制を構築したほうが満足度の高いサイトを作りやすくなります。
ファングリーはお客様の要望や予算に合わせて柔軟にアサインできるフリーランスクリエイターのプラットフォームを有しており、社内の制作体制とは別に1,000人を超えるフリーランスの方々と繋がりを持っています。ファングリー創設前から繋がりを持っているパートナー企業も多くいるので、連携面も安心です。
過去の事例で見ると、デザインの一部をお客様側の社内メンバーと協同で作成したり、お客様側で普段からお付き合いのある会社とともにシステム開発を進めたりといったパターンもあります。取材や撮影、ライティングなどでもその業界・領域に詳しいフリーランスの方をアサインするなど、ニーズに合わせて対応しています。
通常、サイト制作を委託する側にはプロジェクトマネージャーが存在し、制作側でもプロジェクトマネージャーが立つ構図になります。名称はリーダーとか、●●担当とか、プロジェクトマネージャーとは呼ばない場合もありますが、委託する側には制作会社から上がってくる成果物の承認やフィードバック、社内への説明の役割を担う役割が必要です。
おそらく、これまでサイト制作を依頼したことのある方ならば、「意外と自社の負担が大きい」と思った経験があるのではないでしょうか。
普段サイト制作を依頼することはまれで、リニューアルともなれば数年に一回程度になると思います。プロジェクトが立ち上がり、そこで担当者になったとしても、何をどうマネジメントして良いのか――。タスクやステークホルダーが明確にできない状況などでは、負担の大きさから正直面倒だと感じられるかもしれません。
こういった依頼する側の負担を軽減するのが、制作会社です。毎日サイト制作に携わる制作会社側ならタスクを明確にしたり、各工程の承認者や確認者、ステークホルダーを明確にしたりできるので、担当者の負担を軽減しながらスムーズにサイト制作のプロジェクトを進めていくことができます。
ファングリーでは個人事業主の方から上場されている会社様まで、会社規模や業種を問わず幅広いお客様のWebサイト制作に携わってきました。お客様によって当然予算やニーズも全く異なるため、都度柔軟に対応できるようプロジェクトを設計しています。
ブランディングやコンテンツマーケティングといった領域にも対応していますので、サイト制作のクオリティ面やコスト面、フリーランスの方とのコミュニケーション面などにお困りの方は、一度相談の機会をいただけると嬉しく思います。