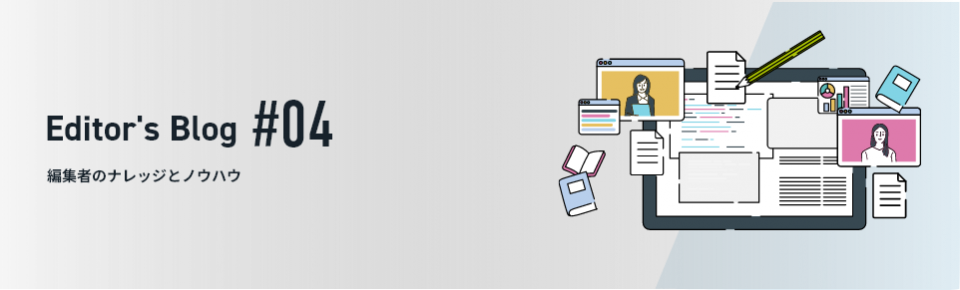
株式会社ファングリーのコンテンツディレクター・編集者 新森と申します。
ファングリーはコンテンツプロデュースカンパニーとして、企業のブランディングやマーケティングに貢献する多様なコンテンツ制作を支援している会社です。
2022年11月のChatGPT登場から2025年の現在に至るまで、生成AIの進化はWebコンテンツの在り方を根底から覆しました。AIで誰もが簡単にコンテンツを作れるようになった一方、Google検索にはAIによる要約(AI Overview)が表示され、従来のSEOは大きな転換点を迎えています。
実際、多くの企業のWeb担当者様からの「AI生成コンテンツとどう差別化すればいいのか」「これまで成果の出ていたSEOの効果が薄れてきた」といったご相談が急増しています。
これまで常識とされた「1キーワード1記事」という考え方や、表層的な情報をまとめただけのコンテンツでは、ユーザーに選ばれることはおろか、AIに参照されることすら難しくなりつつあるのです。
このブログでは、私自身がオウンドメディア運営で試行錯誤しながら実践している、AI時代の検索エンジン最適化「LLMO/AIO」の考え方をベースに、AIには生み出せない独自の価値を提供し、未来の検索エンジンとユーザーから選ばれ続けるコンテンツの作り方を実践レベルで紹介します。
具体的な実践の話に入る前に、まず私たちが今立っている「場所」を正確に理解する必要があります。AIは検索の世界をどのように変えたのか、そして私たちは何を目指すべきなのでしょうか。
ユーザーは検索窓にキーワードを打ち込み、表示された青いリンクの中から自分の疑問を解決してくれそうなページを探し、クリックする――これが、かつての「検索」という行為の基本でした。
しかし、AI OverviewやPerplexityのようなAI検索の登場により、この構造は大きく変わります。ユーザーはAIに対して、より自然な言葉で「質問」や「相談」を投げかけるようになったのです。
▼検索行動の例
従来:
プロジェクト管理 ツール 無料
現在:
スタートアップ企業向けの無料で使いやすいプロジェクト管理ツールを5つ、それぞれの長所と短所を比較して教えて
このような複雑な問いに対して、AIはWeb上のさまざまな情報を瞬時に収集・要約し、最適化された「答え」を直接生成します。ユーザーはもはや、複数のページを渡り歩いて情報を探す必要がなくなりつつあるのです。
この変化は、Webサイト運営者にとって何を意味するのでしょうか?
それは、「AIの回答の参照元に選ばれなければ、ユーザーの目に触れる機会すら失ってしまう」という現実です。
この新しい検索環境で成果を出すために、私たちは新しい概念を理解する必要があります。それが「LLMO(AIO)」です。
LLMO(Large Language Model Optimization)とは、ChatGPTのようなLLM(大規模言語モデル)が回答を生成する際に、自社のコンテンツを信頼できる情報源として参照・引用されやすくするための最適化を指します。AIが「この記事の情報は正確で、ユーザーの質問に答える上で非常に有益だ」と判断してくれるようなコンテンツ作りを目指す考え方です。
なお、LLMOと一緒に使用されることの多い「AIO(AI Optimization)」は、LLMOを含むより広範な概念となります。AIが検索体験の中心となる時代に合わせて、SEO戦略全体を適応させていく総合的な取り組みのことです。
具体的には、以下のような施策が挙げられます。
簡単に言えば、AIOという「AI時代に適応する」という大きな戦略目標の中に、LLMOという「AIに選ばれるコンテンツを作る」という核となる戦術が含まれている、ということになります。
なぜLLMO/AIOが重要なのか。結論から言えば、LLMO/AIOを意識しないコンテンツは、これからのWeb上でその存在価値を急速に失っていくからです。
AIが生成する回答は、Web上の無数のコンテンツを「土台」として成り立っています。もしあなたのコンテンツが、AIから見て信頼性が低かったり、構造が分かりにくかったり、情報が浅かったりすれば、その土台の一部にすらなることができません。
これは、検索結果100位にいるのと大差ないと言えるでしょう。ユーザーがAIとの対話で満足してしまえば、あなたのサイトへのトラフィックは永遠に生まれません。LLMO/AIOは、もはや一部の先進的な取り組みではなく、すべてのコンテンツ制作者が向き合うべき必須施策なのです。
LLMO/AIOの重要性を理解した上で、次に取り組むべきは具体的なキーワード戦略の見直しです。AI時代の検索では、もはやひとつのキーワードで上位表示を目指す「点」の戦略は通用しません。
かつてのSEOでは、「このキーワードで1位を取る」という目標を立て、そのキーワードだけに最適化した記事を作成する「1記事1キーワード」という考え方が主流でした。しかし、この手法はユーザーの本当のニーズを見過ごしてしまう限界があります。
なぜなら、ユーザーの検索意図はもっと立体的だからです。
例えば、「インタビュー記事 書き方」と検索するユーザーは、単に執筆のフローを知りたいだけではありません。同時に「読者を引き込むコツは?」「最適な構成は?」「魅力的なタイトルの付け方は?」といった、関連する複数の疑問を抱えています。
ここで「インタビュー記事 書き方」「インタビュー記事 コツ」「インタビュー記事 構成」「インタビュー記事 タイトル」といったキーワード群は、それぞれが独立しているのではなく、「質の高いインタビュー記事を書き上げたい」という、ひとつの大きな検索意図を構成しているのです。
「1記事1キーワード」という思考では、これらのニーズに個別に対応しようとしてしまい、ユーザーは満足な答えを得るために何ページも回遊しなくてはなりません。これからのSEOでは、ひとつの記事でこの一連の疑問にまとめて答えることで、より高いユーザー満足度と検索エンジンからの評価を得ることを目指します。
そこで重要になるのが、個別のキーワード(点)ではなく、それらが集まって形成されるトピック(面)で検索意図を捉えるという考え方です。
前項の「インタビュー記事 書き方」の例で言えば、「インタビュー記事の書き方」という大きなテーマ(トピック)に対して、関連する複数のキーワード群をひとつの集合体として捉えます。そして、これらの検索意図の集合体をひとつの非常に網羅性の高い記事、あるいは相互に連携した複数の記事(トピッククラスター)で満たしていくのです。
このアプローチにより、検索エンジンや生成AIは「このサイトは“インタビュー記事の書き方”というトピック全体に対して、非常に専門性が高く、権威がある情報源だ」と認識するようになります。結果として、個別のキーワードでの評価も底上げされ、より多くの関連キーワードで上位表示されやすくなるのです。
トピックを網羅するための具体的な実践フローを解説します。
まずは、軸となるテーマに関連するキーワードを洗い出します。
ラッコキーワードのようなサジェストツールや、Ahrefs、SEMrushといった競合分析ツールを使い、「ユーザーは他にどんな言葉で検索しているか」を徹底的に調査しましょう。そして、洗い出したキーワードの中から検索意図が近いものをグループ化(グルーピング)していきます。
キーワードの裏にある「なぜ、ユーザーはこの言葉で検索したのか?」という背景(潜在ニーズ)を深く考えることが重要です。
例えば「インタビュー記事 書き方」と検索した人は、単に書き方のコツを知りたいだけでありません。「インタビュー記事の構成の作り方」や「魅力的でキャッチーなタイトルの付け方」を知りたいといった、より深い課題を抱えている可能性があります。
コンテンツ内にFAQセクション(よくある質問)を設けるなどして、ユーザーが次に知りたくなるであろう情報を予測し、先回りして答えを提供することで、ユーザー満足度とAIからの評価は格段に向上します。
AIは既存の情報を学習し、最適化して出力することは得意ですが、「無から有を生み出す」こと、つまりオリジナルの情報や体験を創出することはできません。
この点に、私たち人間がAI生成コンテンツと差別化する最大のチャンスがあります。「あなたから聞きたい」とユーザーに思わせるための、独自性を高める5つの具体的な方法を紹介します。
一次情報とは、あなた自身が情報源となって発信する、他にはないオリジナルのデータや事実のこと。例えば特定のテーマについて実施した独自のアンケートや市場調査の結果も、独自の一次情報となります。
その結果をインフォグラフィックなどと合わせて記事にすることで、多くのメディアから引用される価値の高いコンテンツになります。
情報の「正しさ」や「深さ」において、専門家の知見は絶大な信頼性を持ちます。
社内にいるその道のプロフェッショナルや外部の有識者にインタビューを行い、その内容を記事に反映させることで、コンテンツの専門性と権威性が飛躍的に高まります。
作成した記事を専門家に監修してもらい、「この記事は〇〇(役職)の△△が監修しました」と明記するだけで、検索エンジンとAI、そしてユーザーに対する信頼性の証明となります。
人は、単なる情報の羅列よりも感情を揺さぶるストーリーに強く惹きつけられる傾向にあります。AIには、実際の体験に基づいたストーリーを語ることはできません。
製品開発の裏側で起きた苦労話、あるプロジェクトが大成功した要因、あるいは大きな失敗から学んだ教訓など、当事者にしか語れない生々しいストーリーがあります。これは、ユーザーに強い共感と記憶を残すのに有力です。
顧客があなたの製品やサービスを通じて、どのように課題を解決し、成功を収めたのか。具体的なエピソードを交えて紹介することで、単なる機能説明よりもはるかに説得力のあるコンテンツになります。
世の中に溢れている情報やニュースであっても、独自の視点を加えることで、全く新しい価値を持つコンテンツに生まれ変わります。
例えば「新しい法律が施行された」というニュースに対して、弁護士が「実務上、企業が注意すべき3つのポイント」という切り口で解説すれば、それは唯一無二の価値ある情報になります。
同じ情報でも伝え方を変えるだけで、ユーザーの理解度は大きく変わります。
複雑な仕組みや大量のデータを、文章だけで説明するのではなく、視覚的に分かりやすい図解やインフォグラフィックにまとめることで、情報の価値を高められるでしょう。
さらに解説動画や料金シミュレーションツール、診断コンテンツなど、テキスト以外のインタラクティブな要素を提供することも、強力な差別化要因となります。
ここまでの理論を踏まえ、今日から使える具体的なコンテンツ制作フローを4つのステップで紹介します。
まず、自社の製品やサービスが持つ専門性(強み)と、ターゲットが抱える課題(ユーザーニーズ)が重なり合う領域から、発信するべき「トピック」を決定します。
そして、そのトピックに関連するキーワード群を洗い出し、どのような検索意図の集合体で構成されているかを設計しましょう。
前述のように「1記事1キーワード」ではなく、関連するキーワードがあれば「複数キーワード」を対策することを意識します。
コンテンツの執筆を始める前に、AIが内容を理解しやすく、引用しやすい「骨格」を作ることが最も重要です。具体的には、以下のポイントを押さえましょう。
ユーザーがAIに投げかけるであろう具体的な質問(「LLMOとは?」「コンテンツの独自性を高める方法は?」など)を予測し、見出しだけでその答えがわかるような構成を意識します。
複雑な情報は、箇条書き(リスト)や表(テーブル)で整理する箇所をあらかじめ設計します。構造化されたデータは、AIが引用しやすい形式です。
トピックに関する情報を網羅し、h2やh3などのhタグを適切に使って論理的な階層構造を設計しましょう。
AIは文脈を読み取りますが、曖昧な表現は誤解の元です。誰が(AIが)読んでも一意に解釈できる、明確な文章を書きましょう。
各見出しの冒頭で結論を述べ、その後に理由や具体例を続けることで、AIが要点を掴みやすくなります。
「多くの企業が導入」ではなく「導入企業数は1,500社を突破」のように、具体的な数値やデータを用いましょう。
専門用語は平易な言葉に言い換えるか、初めてその用語が出てきたときに「〇〇(以下、△△)」のように定義を明確にします。
人名、組織名、製品名、場所などの固有名詞は、正式名称で正確に記述しましょう。
主語と述語を明確にし、簡潔な文章を心がけます。
最後に、このコンテンツが信頼に足る情報であることを、AIと人間の両方に証明するための仕上げを行います。
「誰が(Author)」「どのような専門性を持ってこの記事を書いたのか」といった、著者情報を明確にします。テーマによっては、専門家による監修を入れましょう。
統計データや他者の研究を引用した場合は、必ず出典元を明記し、リンクを設置します。
既存記事の中に、今回執筆した記事と関連する記事があれば、記事内の該当箇所に内部リンクとして設置しましょう。
ユーザーの興味を広げ回遊率を高めることにつながり、これは検索エンジンやAIからメディア内部の評価を高める効果も期待できます。
記事は「作って終わり」ではなく、公開後も継続的にその価値を維持・向上させていく必要があります。一度公開したコンテンツも、検索エンジンの評価やユーザーニーズの変化に合わせて定期的に見直すことが重要です。
既存記事がなぜ評価されていないのかを分析し、最適化する「リライト」作業も、AI時代のSEOにおいて欠かせない施策と言えるでしょう。
リライト方法については、SEOコンテンツを評価して最適なリライトをする方法(オロパス社)でも詳しく解説されています。
ユーザーの多様な検索意図(複数キーワード)をトピックとして網羅的に捉え、その答えをほかにはない独自の価値を乗せて、AIにも人にも分かりやすい形で提供する。これが、これからのコンテンツ制作の核となると考えています。
もはや、小手先のテクニックで検索エンジンのアルゴリズムを追いかける時代は終わりました。これからのSEOで最も重要なことは、ユーザーの問いに対して、誰よりも深く、誠実に、そして“あなたらしく”答えることです。
ファングリーが運営するコンテンツマーケティング情報を発信するメディアC-NAPS(シナプス)では、SEOやLLMOに関する記事を公開しています。ぜひあわせてご覧ください。
「自社でも、次世代のSEOコンテンツに取り組みたい」
「何から手をつければいいか、専門家の意見を聞きたい」
もしこのようにお考えでしたら、ぜひ一度ファングリーにご相談ください。貴社の課題に合わせた最適なコンテンツ戦略をご提案します。