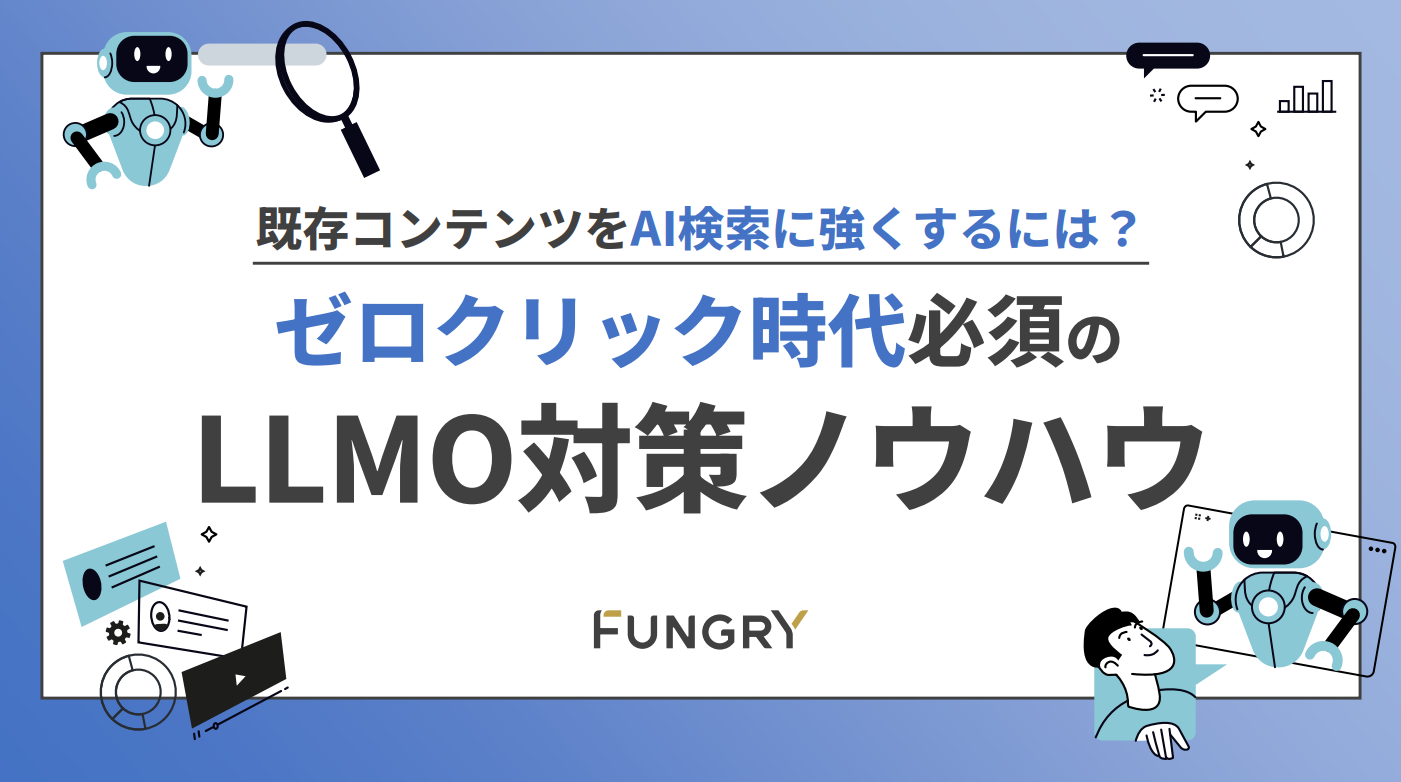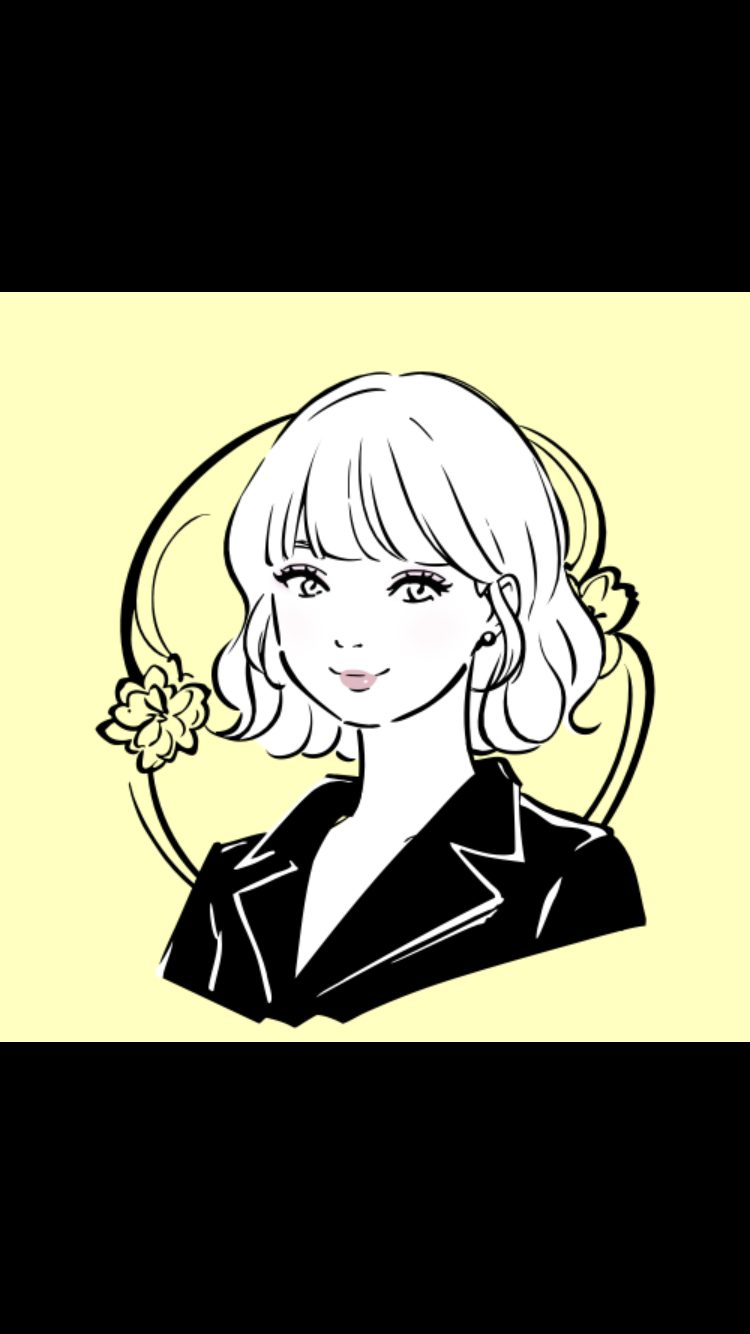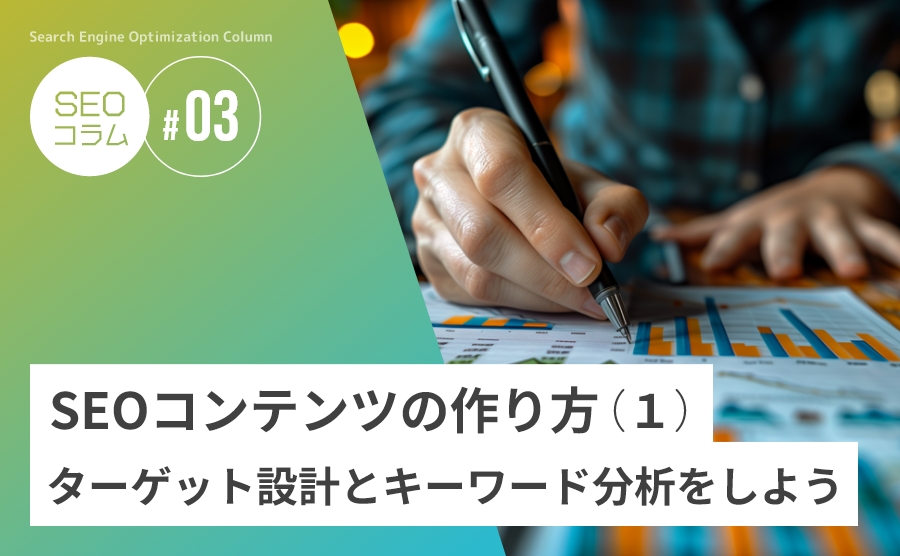AIを活用したSEOコンテンツ制作|メリットからおすすめツール選び、注意点まで解説【2026年版】
本記事では、AIをSEOコンテンツ制作に活用する際のメリット・デメリット、活用するための具体的な方法、失敗しないための注意点について解説します。
「AIを導入したいが、どこから手をつければ良いか分からない」と悩んでいる企業担当者の方に向けて、AIを使いこなすための基礎知識から実践的なツールの選び方まで、分かりやすく紹介。
この記事を読めば、専門知識に自信がなくてもAIをSEO対策の強力な味方とし、効率的かつ高品質なコンテンツ制作をスタートできるようになります。
Table of Contents
AIを活用してSEOコンテンツを作るメリット
AIをSEOコンテンツ制作に活用すれば、「コスト」「時間」「戦略」の3つの側面で大きなメリットが得られます。
はじめに、それぞれのメリットについて解説します。
コストを削減できる
AIを導入すれば、コンテンツ制作にかかる費用を大きく抑えられます。
これまで外部のライターへ記事作成を依頼していた場合は、外注費がかかっていたはずです。また、社内でライティングに対応する場合でも、そのメンバーの人件費は発生しています。
こうした文章作成にかかるコスト(内製の場合は時間)を大幅にカットしてくれるのが、AIです。AI導入によって削減できた予算やリソースを、記事の企画立案や編集など、より人の判断が必要となる重要な業務に充てられるようになります。
さらにAIの力を借りることで、ライター職種でなくともコンテンツを制作しやすくなり、そのノウハウについても社内で蓄積しやすくなります。
短時間でより多くのコンテンツを作成できる
AIは、人間より圧倒的に速く記事を書くことができます。
世の中は、検索ニーズ(月間検索数)は少ないけれど、一部の人が深く悩んでいる「ニッチなお悩み」で溢れています。人間が記事を書く場合、このような検索ボリュームの小さい記事は作成に手間がかかる割に読む人が少ないので、後回しにされがちでした。
ですが、AIなら短時間で記事を作成できるため、そのような記事も効率良く作ることができます。幅広いニーズに応える記事が増えると、検索エンジンから「情報が豊富に揃う専門的なサイト」と評価されやすくなるでしょう。
データ分析による戦略を最適化できる
文章を作るだけでなく、コンテンツの戦略を立てる段階で頼れるところもAIの大きなメリットです。
例えば下記のような内容に対して、膨大なデータを瞬時に分析してくれます。
- 競合他社のWebサイトの傾向
- 検索している顧客の意図(何を知りたいのか)
- 記事に含めるべき関連キーワード
これによって感覚や経験則ではなく、データに裏付けられた客観的な視点で効果的なコンテンツ制作を計画できるのです。
また、記事の公開後にはアクセス状況の分析や改善すべき点を効率的に特定してくれます。PDCAサイクルを高速で回せるため、継続的な成果を上げやすくなります。
AIを活用してSEOコンテンツを作るデメリット
多くのメリットがある一方、AIの特性を理解せずに利用することには大きなリスクが伴います。とくに注意すべき3つのデメリットを解説します。
独自性を出すのが難しい
AIは文章を生成する際、インターネット上にある既存の大量なデータを学習するため、そのアウトプットはどうしても「ありきたり」で「一般的」な文章になりがちです。
自社や事業が持つオリジナルな経験談やデータ、専門家の知識や考えなど、コンテンツの個性・独自性となるような要素をAIに反映させるのは容易ではありません。
また、AIが生成した文章に手を加えずにそのまま公開すると、どうしても他社コンテンツと似たような内容になってしまいます。検索エンジンや読者、そしてLLMO(AIO)の観点からはAIからも、「差別化されていないコンテンツ」と判断される恐れがあります。
ファクトチェックを徹底する必要がある
AIが出力する情報には、間違った情報やすでに古くなった情報が含まれる可能性があります。これはハルシネーション(虚偽・誤解を含む情報を事実かのように提示する事象)とも呼ばれ、AIが持つ大きな弱点のひとつです。
とくに医療や金融、法律など、人々の健康や資産に大きく影響する「YLYM領域」の分野では、不正確な情報の掲載が致命的な問題に発展することもあります。具体的には、読者に間違った行動を取らせてしまうリスク、そしてそれによって企業の信頼を失うリスクです。
AIが作成した文章は、公開する前に編集者や専門家による事実関係の確認(ファクトチェック)を徹底するようにしましょう。
検索エンジンからスパム評価される可能性がある
Googleが発表する「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」では、「有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツ」を作るようWebサイトの運営者に求めています。
そのため、順位を上げることだけを目的としてAIに大量のコンテンツを作らせ、人の目を通さずにそのまま公開するのは避けましょう。検索エンジンから「内容が薄く、ユーザーにとって価値の低い記事」と判断され、ペナルティの対象になる恐れがあるためです。
AIはあくまで、ユーザーに価値のあるコンテンツを「効率よく作るためのツール」として活用する必要があります。
AIによるライティングがSEOにもたらす4つの効果
AIはSEOのさまざまな施策を効率化し、その効果を高めるポテンシャルを秘めています。ここでは具体的な4つの効果を紹介します。
コンテンツの鮮度・品質を維持できる
過去に公開した記事で期待通りの成果が出ない場合、その記事を手直しする「リライト」はSEOにおいて大切な作業です。
AIは既存コンテンツを分析し、「競合と比べて何の情報が不足しているのか」というように具体的な問題点を見つけて改善案を提示してくれます。さらに、現在の検索トレンドや顧客が求めている内容に合わせて、効率的に記事を書き直すための作業もサポートしてくれます。
コンテンツの鮮度や品質を保ち、検索エンジンからの評価を向上させ続けやすくなります。
対策キーワードを最適化しやすい
SEOコンテンツの基本は、顧客が検索するキーワードを最適な形で文章中に含めること。
AIは記事のテーマとなるメインキーワードだけでなく、キーワードとして一緒に使われやすい「共起語」や、顧客が次に知りたいと思う潜在的なキーワードを調べ、それらを不自然にならない文脈で文章に組み込む作業を手伝ってくれます。
その結果、検索意図をより広くカバーできるようになり、網羅性や質が高いコンテンツを作ることが可能です。
また、検索結果に表示されるタイトルやディスクリプションの案も生成してくれるため、これらを反映することで多くのアクセスを集めやすくなります。
検索意図に応じたライティングができる
ユーザーがGoogleなどの検索エンジンを使う際には、必ず次のような明確な目的(検索意図)があります。
- 何かを知りたい
- どこかへ行きたい
- 何かをしたい
- 何かを買いたい(契約したい)
AIは検索結果の上位に表示されている記事の傾向を分析し、キーワードに隠されたユーザーの本当の検索意図を突き止めます。そして、その意図に沿った最適な記事の構成や、盛り込むべき内容を提案してくれます。
例えば、キーワードについて「知りたい」と思っているユーザーには解説記事を、「買いたい」と考えているユーザーには比較レビュー記事を制作します。 このように使い分けることで、ユーザーが求めるでコンテンツを届けられるようになるのです。
内部リンクと外部リンクを最適化しやすい
コンテンツ単体だけでなく「Webサイト全体」のSEO評価を高めるには、適切なページへの「発リンク」が重要です。「発リンク」には、関連性の高い記事同士を結びつける内部リンクと、信頼できる外部の情報源を表す外部リンクの2種類があります。
「発リンク」の施策にAIを活用すれば、AIはサイト内を巡回して対象となる記事と関連性が高いページ(関連記事や外部のページ)を見つけ出し、リンクの設置を提案してくれます。
特定の記事から関連性の高い記事へアクセスしやすい構造にしていくことで、ユーザーはサイト内を積極的に回遊できるようになります。また、権威性の高い参照元への外部リンクがあれば、記事の信頼性も高まると考えられます。
SEOコンテンツ制作に活用するAIツールを選ぶ6つのポイント
数あるAIツールの中から自社に最適なものを選ぶために、確認すべき6つのポイントを解説します。
搭載している大規模言語モデル(LLM)の種類
使用したいツールが、どのAIを基盤にしているか確認しましょう。
現在主流となっている「GPT-4」などの大規模言語モデル(LLM)の種類や性能は、生成される文章の自然さや情報の精度に直結するため、SEOコンテンツ制作での活用でも大切な選定ポイントです。
ユーザビリティの高さ
どんなに高性能なAIでもうまく使いこなせなければ、かえって作業効率が下がってしまう恐れがあります。
そこで、以下のような「ユーザビリティ」についてもチェックしましょう。
- 直感的に操作できる
- UI/UXが優れている
- AIツールに慣れていない人でもストレスなく使える
効率性の高さ
コンテンツを生成するスピードはもちろん、構成案の自動作成やキーワード分析など、文章作成以外の関連機能がどれだけ充実しているかも重要です。
機能が多いほど作業全体を効率化できる可能性が高いので、どのような機能が備わっているのかしっかり確認しましょう。
生成データの保存・編集の可否
AIが一度生成したコンテンツをツール内で保存・管理できるか、また、チームメンバーと共同で編集・推敲できる機能が備わっているかを確認しておきましょう。
情報源の正確性
下記のような情報元に関する機能があるかどうかも、ファクトチェックの効率を左右する重要なポイントです。
- 対応する情報の最新性
- 情報の引用元(参照元の明示)
料金の妥当性
搭載されている機能が豊富であるか、その性能はどのようなものかだけでなく、これらに対して料金のバランスが取れているかについても要チェックです。
自社のコンテンツを制作する頻度や規模に合わせて、最適な料金プランがあるかどうかも確認しましょう。
SEOコンテンツの「構成案作成」におすすめのAIツール3選
ここでは、キーワードに対する競合分析や、含めるべきトピックの網羅性を高める構成案作成に役立つAIツールを3つ厳選して紹介します。
ChatGPT

ChatGPTは、現在使われているAIの基礎とも言える汎用性の高い対話型AIです。
ユーザーからのプロンプト(指示文)を工夫することで、ターゲットの設定から、競合サイトの分析、記事の見出し(構成)や概要の提案まで柔軟に対応してくれます。
質の高いコンテンツを作るための土台として、まずは使いこなせるようになっておきたいAIの基本ツールです。
Surfer SEO
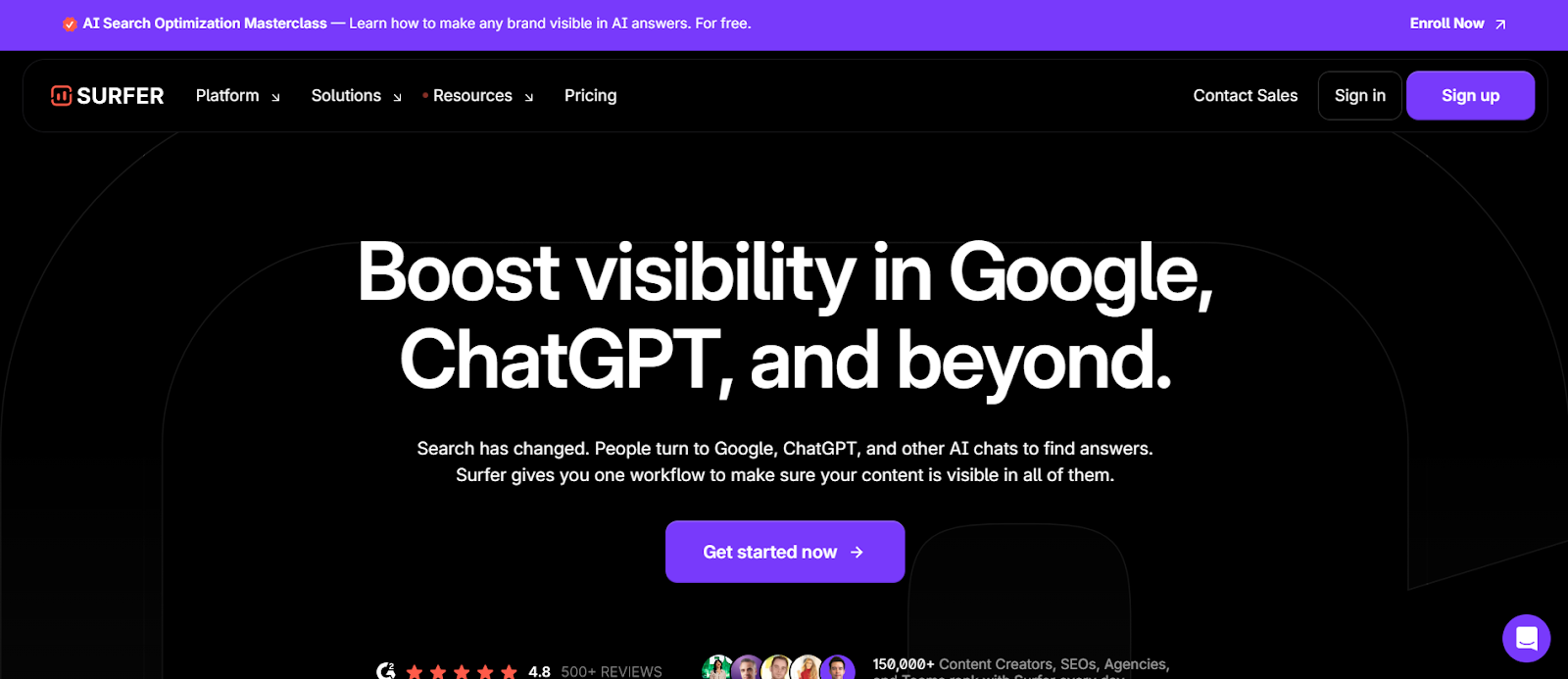
海外でとくに高い人気を誇る、SEOコンテンツの最適化に特化したツールです。
対策したいキーワードについて、Googleの検索結果で上位に表示されている記事を細かく分析。また、その結果から記事に含めるべき共起語・内容・最適な見出しの構成・目安となる文字数など、データに基づいた具体的な提案をしてくれます。
EmmaTools(エマツールズ)

「SEOに強いAIライティングツール」としてよく知られている国産のツールです。
競合サイトの分析から精度の高い構成案の作成、本文の執筆まで、コンテンツ制作に関するすべての工程を一気通貫でサポートしてくれます。
日本の検索エンジン環境に最適化されているため、国産ならではの安心感や使いやすさも大きな強みです。
SEOコンテンツの「ライティング」におすすめのAIツール3選
作成した構成案をもとに、高品質で自然な文章を効率的に生成するためのライティングツールを3つ紹介します。
Gemini(ジェミニ)
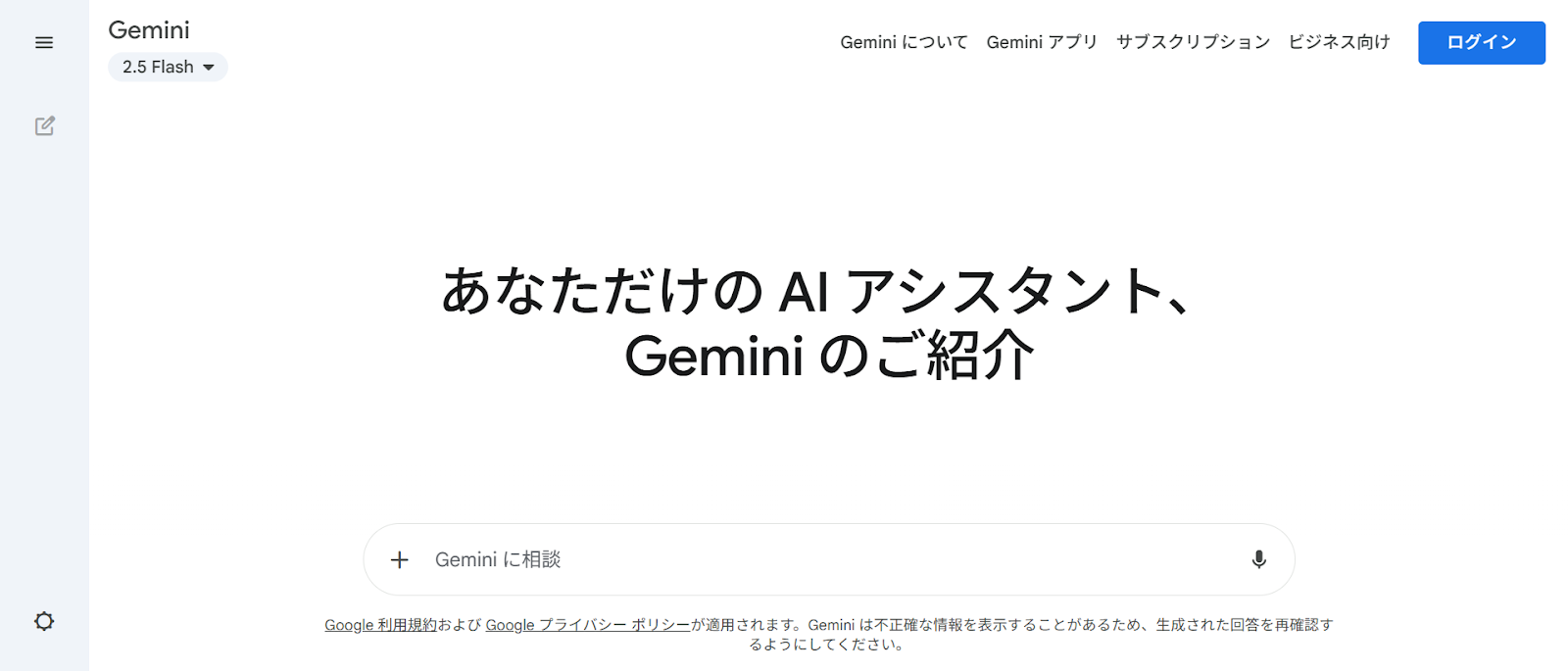
出典:https://gemini.google.com/?hl=ja
GeminiはGoogleが開発した最先端の生成AIで、Google検索の情報と連携しています。最新の情報を反映しながら、自然で精度の高い日本語の文章を生成できることが特徴です。
SEOコンテンツのライティングにおいて中心的な役割を担うことができる、制作現場で非常に頼りになるツールです。
Catchy(キャッチー)

出典:https://lp.ai-copywriter.jp/
日本のユーザーのために開発された、国産AIライティングアシスタントの代表的なツールです。
ブログ記事の生成だけでなく、広告のキャッチコピーやメールの文章など、100種類以上の豊富なテンプレートが用意されています。AIツール初心者でも、直感的に使い始めやすいのが魅力です。
SAKUBUN(サクブン)
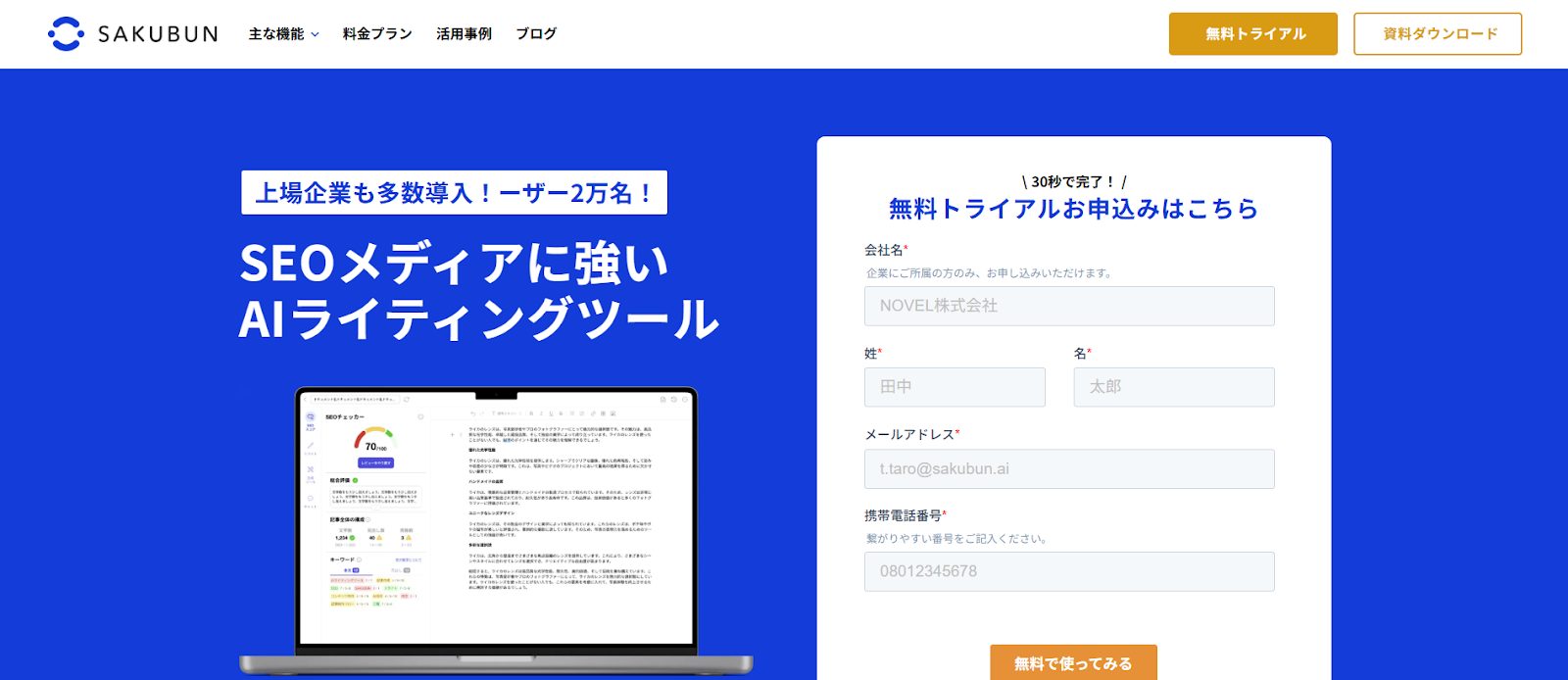
SEO記事の作成に特化して作られた国産のAIライティングツールです。
エディタ形式のシンプルなUIが使いやすく、AIが提案する文章をあなたが編集しながら、共同で文章をブラッシュアップしていく感覚で利用できます。
チームでコンテンツ制作を行う場合にも役立つ機能が揃っているため、チーム全体の業務効率化にもおすすめです。
SEOコンテンツの「分析」におすすめのAIツール3選
既存コンテンツのSEO評価を分析し、改善点を見つけたり、リライト作業を効率化したりするためのツールを3つ紹介します。
SEARCH WRITE(サーチライト)

国産のコンテンツSEOに特化したツールです。Webサイト内の以下のようなデータを分析してくれます。
- リライトすべき記事
- 記事に追加すべきキーワード
- 関連性の高い内部リンク候補
成果改善に直結する施策を自動で提案してくれる分析機能が、豊富に備わっています。
MIERUCA(ミエルカ)

AIがユーザーの検索意図を深く分析し、コンテンツを改善するための具体的なヒントを提供してくれるツールです。SEOやコンテンツマーケティングのツールとして、国内トップクラスの実績を持っています。
とくにサイト全体のテーマ性を強化する「トピッククラスター」の分析に優れており、SEO評価の戦略的な向上やコンテンツの整理にも活躍します。
Semrush(セムラッシュ)

構成案作成に役立つ機能だけでなく、すでに公開済みのページに対してエラー検出などの診断を行う機能も搭載しています。
キーワードの過不足やサイトの構造的な問題点をスコアでわかりやすく表示してくれるほか、具体的な改善アクションまで提示してくれる、世界的に人気の高いツールです。
AIを活用したSEOコンテンツ制作に関するよくある質問
AIを活用したSEOコンテンツ制作に関するよくある質問をまとめました。
AIが生成した記事をそのまま公開しても問題ない?
AIが作成したコンテンツをそのまま公開するのは避けましょう。AIが作った文章は、あくまで「叩き台」や「原稿の下書き」として考えるべきです。
詳しくは、記事内の「AIを活用してSEOコンテンツを作るデメリット」をご覧ください。
AIにSEOコンテンツ制作の作業をどこまで任せて良い?
AIにすべて丸投げするのではなく、AIと人間で明確に役割分担することがSEOコンテンツ制作でAIを活用するポイントです。データ収集や競合サイトの傾向分析、文章の叩き台作成など、時間や労力がかかる作業はAIに任せましょう。
詳しくは、記事内の「AIによるライティングがSEOにもたらす4つの効果」で解説しています。
AIを利用してSEOコンテンツを作るとGoogleのペナルティ対象になる?
SEOにおいてGoogleが問題視するのは、AIで生成したかどうかではなく、ユーザーにとって価値の低い低品質なコンテンツを乱発することです。AIを活用して作成しても、ユーザーにとって有益で信頼性が高い記事であれば問題ありません。
Googleのペナルティ対象については、「検索エンジンからスパム評価される可能性がある」の項目でも詳しくお話ししています。
まとめ
コンテンツを制作するうえで、AIはあなたにとって頼れる相棒になってくれますが、コンテンツの質や顧客への提供価値に関する責任は、常に人間であるあなたにあります。
便利だからと何も知らないままAIを使うのではなく、AIについてきちんと知り、上手に活用することで、コンテンツマーケティングの成果につなげていきましょう。
LATEST
最新記事
TAGS
タグ