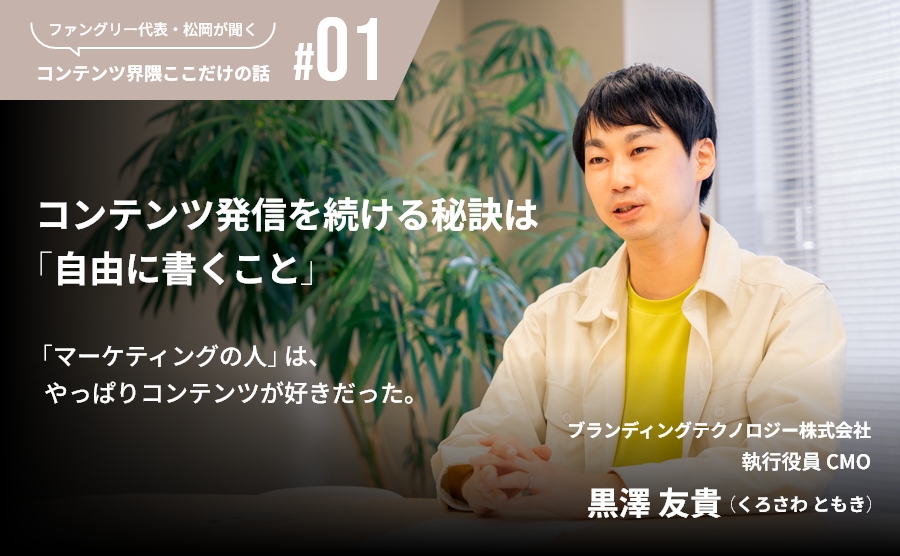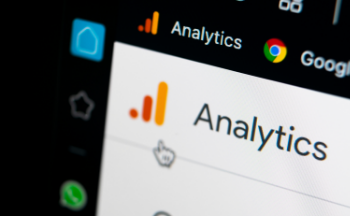メールマーケティング失敗例から学ぶ成功の鍵を専門家が解説
メールマーケティングに取り組んでいるものの、期待した成果が得られずにお困りではありませんか?
予算やリソース不足を理由に、メールマーケティング戦略が後回しにされていたり、効果測定や検証を怠り、単にメールを配信するだけになっていたりするケースも少なくありません。
メールマーケティングはECサイトとの親和性が高い上、顧客データを活用してアプローチをパーソナライズでき、売上向上と顧客関係構築に大きく貢献します。
では、メールマーケティングの成功と失敗を分ける要因は一体何なのでしょうか。
本記事では、1993年の設立以来、メールマーケティング業界をリードしてきた株式会社ディレクタスの菊池氏に、効果的なメールマーケティングの取り組み方について詳しくお話を伺いました。メールマーケティング戦略の見直しや、効果的なツール活用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

菊池 春彦(きくち はるひこ)氏
株式会社 ディレクタスのコミュニケーションデザイングループに所属。ディレクターとして、自動車メーカーや紳士服メーカー、生命保険会社など、大手クライアントのWebサイトやメールコンテンツの企画・制作および運用を担当している。
| 株式会社 ディレクタス 1993年設立。データドリブンなOne-to-Oneコミュニケーションの実行を支援するマーケティングエージェンシーとして、クライアントと顧客のダイレクトかつインタラクティブなコミュニケーションをワンストップで提供。メールマーケティングの黎明期から時宜にかなったサービス・ソリューションを提供し続け、現在はMA(マーケティングオートメーション)ツールを使ったクロスチャネル施策に力を入れている。 |
マーケティングについては以下の記事もご覧ください。
Table of Contents
メールマーケティングとは
メールマーケティングとは、電子メール(Eメール)を活用して、企業が既存顧客や見込み顧客との関係性を構築し、ビジネス目標を達成するためのマーケティング手法です。
メール配信システムやツールを用いて、顧客とのコミュニケーションを促進していきます。段階的なアプローチを経て、集客やコンバージョンの獲得、最終的に顧客ロイヤリティの向上を目指します。
以下は、具体的なメールマーケティングの活用例です。
| 活用例 | 内容 |
|---|---|
| 新商品・サービスのお知らせ | 最新情報を届け、顧客の購買意欲を高める。 |
| キャンペーン情報 | 特別な割引や特典を提供し、売上を促進する。 |
| アンケート・調査 | 顧客の意見を収集し、商品開発やサービス改善に役立てる。 |
| 購入後のフォローアップ | 感謝のメッセージや関連情報を提供し、顧客満足度を高める。 |
| ニュースレター | 業界の最新情報や役立つコンテンツを提供し、顧客との継続的な関係を築く。 |
メールマーケティングは、単にメールを送信して終わりではありません。その効果を最大化するため、分析と効果測定が不可欠です。メールの開封率やクリック率、コンバージョン率などを分析し、戦略を改善することで、より高いマーケティング効果を実現できます。
効果的なメールマーケティング戦略は、顧客エンゲージメントを高め、ビジネス成長を加速させるための重要な要素にもなるでしょう。
メールマーケティングとメールマガジンの違い
メールマーケティングとメールマガジン(メルマガ)は、似ているようで異なる意味を持つ言葉です。メルマガは「ユーザーに情報を届けること(内容を読ませること)」を目的に作成・送信されるもの。一方、メールマーケティングは「ユーザーに特定のアクションを起こしてもらうこと」を目的に行われるマーケティング活動全般を指します。
「認知する→興味・関心を持つ→購買意欲が高まる」といったようにユーザーの購買心理や行動が変化していくことを「態度変容」と言います。この態度変容を促すアプローチとして、Eメールを活用するのがメールマーケティングです。
メールマーケティングを行うメリット

コストを抑えて顧客ごとに最適化された情報を送れる
近年、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNS、そしてLINEやDiscordといった手軽なチャットツールが販促にも多く活用されています。そのため、「メールはもう古い」「メールなんて必要ない」といった意見も耳にするようになりました。実際、顧客や取引先とのやり取りをLINEのみで済ませる企業も増えています。
ですが、ビジネスを成功させるにはメールというツールの力が欠かせない、と私は思っています。
というのも、メディアとしてのメールには、ほかのツールにはない以下の「3つの特性」があるからです。
- 顧客に「直接」情報を届けられる「プッシュ型」
- パーソナライズされたコミュニケーションを実現できる「One-to-One」
- 顧客との長期的な関係構築を可能にする「オウンドメディア」
顧客に「直接」情報を届けられる「プッシュ型」
多様なマーケティングツールが存在する中で、企業側から積極的に情報を発信できる「プッシュ型」の機能を持つツールは、意外と限られています。テレビCMや新聞広告、電話営業などは代表的なプッシュ型の手法ですが、多大なコストと手間がかかります。SNSやチャットツールもプッシュ型のアクションはできますが、不特定多数にも働きかけやすいという点でメールが優位です。
パーソナライズされたコミュニケーションを実現できる「One-to-One」
「One-to-One」とは顧客一人ひとりの興味やニーズに合わせて、パーソナライズされた情報を提供するコミュニケーションのこと。顧客が興味を持たない商品やサービスの広告は迷惑行為と捉えられがちですが、興味のある情報であれば顧客体験を向上させる効果が期待できます。
さらに、メールの件名や本文に顧客の名前を含めることで、顧客側としても「自分に合った情報だ」と感じやすくなり、企業への親近感や信頼感を高めやすくなるでしょう。このような個別最適化されたコミュニケーションを実現しやすいのも、メールの強みです。
顧客との長期的な関係構築を可能にする「オウンドメディア」
メールは企業のウェブサイトや製品カタログと同様に、「オウンドメディア」(企業が自社で管理・運用するメディア)に分類されます。
広告(ペイドメディア)やSNS(アーンドメディア)とは異なり、自社で顧客データという情報資産を管理し、マーケティング施策の費用対効果を最大化できます。つまり、導入や利用のハードルが低く、費用を抑えて始めやすいということです。
こういった点から、企業側から既存顧客や見込み顧客に対して伝えたいことを伝えやすく、コストを抑えてユーザーごとに最適化された情報を送れるメールは、ビジネスにうってつけのツールと言えます。
30代以上にはSNSよりメールが刺さる
最新のチャットツールやSNSが注目を集める一方で、ビジネスシーンでは、メールマーケティングが依然として重要な役割を果たしていることを示すデータがあります。
2021年に総務省が発表した「情報通信白書 令和3年版」の「コミュニケーション手段としてのインターネット利用時間、行為者率」という分析データによると、全年代においてメールの平均利用時間が長いという結果に。さらに、平日はSNSよりのメールのほうが平均利用時間が長くなっています。
とくに、ビジネスの中心を担う30代以上では、SNSよりもメールが主要なコミュニケーションツールとして利用されていることが分かりました。
さらに、一般社団法人日本ビジネスメール協会が2021年6月に発表した「ビジネスメール実態調査2024」によれば、「仕事で使っている主なコミュニケーション手段」の1位はメールで、なんと98.6%もの人が利用しています。
1日に1回以上メールを確認する人は98.87%と、こちらも“ほぼ全員”という結果に。1日に送信するメールの平均は12.27通通、受信するメールの平均は47.83通というデータからも、企業のコミュニケーションチャネルとしてメールの存在感は非常に大きいと言えるでしょう。
これらのデータからも、30代以上のビジネスパーソンにとって、メールは依然として重要なコミュニケーションツールであり、メールマーケティングは、この世代にアプローチする上で非常に有効な手段であることが分かります。
メールマーケティングで明確にしたい2つの柱
マーケティング全般に共通することですが、メールマーケティングで明確にしたい2つの柱について解説します。
1. 配信(情報発信)の目的
まずは、メール配信(情報発信)の目的を明確にしましょう。具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- イチオシ商品の購入促進
- キャンペーンや関連サービスの認知拡大
- 継続購入の促進
- セミナー・ウェビナーの申し込み
- 資料のダウンロード
目的が異なれば、打ち出し方や作成する文章も変わってきます。
2. ターゲット像(ペルソナ)
目的を明確にしたら、そのメールのターゲット像(ペルソナ)を考えましょう。
ターゲット像は、次の軸で設定します。
- 誰に商品を購入させたいのか
- 認知させたいのは対象(既存顧客・新規顧客)
前項で解説したように、「One-to-One」コミュニケーションがメインのメールでは、ターゲット像とズレのあるコンテンツを配信しても読んでもらえず、効果も得られません。
これらの2つの柱が固まったら、メールを作成しましょう。ターゲティングに合わせたコンテンツを作成することによって、読んだユーザーの「態度変容」が期待できます。
メールマーケティングがうまくいかない理由と対策
メールの特性と重要性についてご理解いただけたところで、続いては今回のテーマである「メールマーケティングがうまくいかない理由」についてお話しします。

失敗例の共通点:運用体制が確立されていないこと
当社へのご相談でとくに多いのは、「メールマーケティングプロジェクトを見直したい」という内容です。一定以上の企業規模になると、「とりあえずやってみる」というフェーズはクリアしていることが多く、「メールマーケティングが適切に運用できなくなってきたから仕切り直したい」というニーズが増えてくる傾向にあります。
具体的には、以下のようなお悩みをお持ちの企業様からよくご相談をいただきます。
| ●これまで現場担当者が手作業でメールマーケティングの企画・制作を行ってきたが、配信数が増えたため、もう限界を迎えている……。 ●メールマガジン施策の効果が鈍化してきたため、配信方針やコンテンツ内容のリニューアルを検討したい! ●現在使用しているメールマーケティングシステムが古く、機能面やサポート体制に不安があるため、システムの変更を検討したい。 |
時間の経過とともにメールマーケティングがうまくいかなくなる理由はさまざまですが、比較的どのケースにも共通するのは「社内でメールマーケティングの運用体制が確立されていないこと」。
計画性や戦略性なくメールマーケティングを始めた担当者が、そのまま目標もなく続ける状態では成果が出にくいのは当然です。異動や退職などで担当者が何度か入れ替わるうちに、「誰が何をやるべきか」という担当業務が曖昧になり、メールマーケティング組織が機能しなくなる、といったケースもよく見られます。
メールマーケティングプロジェクトを成功させるためには、プロジェクト立ち上げ当時の運用体制からどの程度変化しているのか、現在の運用体制が妥当なのかを振り返ることが重要です。
また、体制が整っていないと、顧客データ管理もずさんになりやすいでしょう。過去には、「営業担当者がメールのBCCに1,000以上もの顧客アカウントを大量に入れて一斉配信していた」という非常に危険なケースも……。
さすがにこのご時世でそういった状況を放置している企業様は少ないと思いますが、この事例は「情報管理の面でも適切なメールマーケティング体制の構築が重要である」ということを示す良い教訓となります。
メールマーケティングを成功させる重要ポイント:コミュニケーション設計の最適化
メールマーケティングプロジェクトを成功させる上で、もっとも重要なのは明確な「ゴール設定」です。なんとなくメールマーケティングを始めた場合、KGI(重要目標達成指標)などの指標が設定されていない、もしくは形骸化しているケースが多いため、まずはゴールを再定義することが重要です。
ゴールが明確でないと、「何のためにメールマーケティングを行うのか」分からず、施策の効果を検証することもできません。やりたいことが明確にある企業様に対しては、まずはその施策をゴールに紐付ける作業を行うようにしています。
中には、「メールマーケティングプロジェクトを立ち上げ、指標も設定している」という企業様もいらっしゃいます。このような場合に「ECサイトでどれくらいの売上をアップさせる目標なのか」と具体的に質問すると、目標が曖昧だったり、根拠が薄かったりすることも少なくありません。KPI(重要業績評価指標)に関しても、重視するのが開封率なのか、クリック数なのか、コンバージョン率なのか、はっきりしないケースは意外に多いですね。
そういった情報を整理し、今あるものを見直してメールマーケティングにおけるコミュニケーション設計を最適化することが、メールマーケティングで失敗しないための最重要事項と言えます。
コミュニケーション設計を最適化する流れ
マーケティングでは、レビットの「ドリルの穴理論」という有名な考えがあります。これは、「ホームセンターを訪れた客が真に実現したいのは、ドリルを買うことではなく穴を開けることだ」という話です。
この理論のように、ユーザーインサイト(顧客の深層心理)を踏まえてプロジェクトの全体像を見直し、カスタマージャーニー(顧客体験の全体像)を引き直すことが重要と言えるでしょう。
例えば、「お客様の会員ランクをグレードアップする」という目的があったとします。この場合、以下のようにゴールに沿って適切なカスタマージャーニーを設計します。
| 1. 会員登録してくれた顧客に、サンクスメールを送信する2. 会員登録1ヶ月後から、隔週で商品レコメンドメールを送信する3.不定期でキャンペーン誘導メールを送信する4. カートに商品を入れたままサイトを離脱した顧客に、カゴ落ち(カート放棄)メールを送信する |
これによって、「どのタイミングで、どのような接点を持つべきか」というコミュニケーション戦略を明確化できます。少し大げさかもしれませんが、このようなシナリオ設計ができれば、メールマーケティングプロジェクトの半分は成功したと言っても過言ではありません。
実務に活かしたいメールマーケティングのTIPS

メールマーケティングの勝ち筋として「ゴールに沿って適切なカスタマージャーニーを作る」というお話をしましたが、最後は実務における知識やノウハウの部分についていくつかご紹介できればと思います。
件名だけでなく、差出人やプリヘッダーも工夫する
メールマーケティングにおいて、最初にユーザーの目に入ってくるのは、差出人・件名・プリヘッダーといった3つの情報です。いくらメール本文やデザインにこだわっても、受信ボックスの一覧に埋もれてしまっては、その努力は無駄になってしまいます。メールマーケティングの効果を最大化するためには、この3つをセットで考える必要があります。
まず、差出人と重複するような件名では効果がありません。情報が重複すると、限られた表示スペースを有効活用できず、非常にもったいないです。
プリヘッダーは、件名の補足として表示されるテキストですが、件名と重複すると、ユーザーに伝える情報が少なくなってしまいます。
メールマーケティングの効果を高めるためには、差出人も重要な要素であることを認識しましょう。差出人の情報を適当に設定しているケースも少なくないのが実情です。
開封率を高める工夫としては、件名の左端に最重要キーワードを置き、【】で囲うのも有効です。ちなみに、海外では絵文字もよく件名に使われています。文字化けのリスクはありますが、国内では大手家電量販店のメルマガに絵文字が使われており、メールに視覚的な魅力を加えることができます。
ほかにも、PCよりも表示される文字数が少ないスマートフォンでは、「件名を全角25文字以内にする」など、表示文字数を意識することも重要です。
「テキスト」と「HTML」は長所を踏まえて使い分ける
メールには、大きく分けて「テキストメール」と「HTMLメール」の2種類があります。HTMLメールはデザインの自由度が高いので、Webサイトや企業のイメージを具体的でリッチに伝えられるのがメリットです。Webサイトと色、デザイン、フォントなどのトンマナを合わせることでブランドイメージや信頼性も高まります。
ここまで聞くと、「テキストメールは不要」のように思えるかもしれませんが、テキストメールにもメリットはあります。ひとつは、フィーチャーフォン(ガラケー)でも閲覧できるので、ご年配のユーザーが多い場合は有効なツールと言えます。
また、HTMLメールと比較して、作成にかかる時間や手間が少ないため、通知メールやセミナーのお知らせ、在庫確認などでは、今もテキストメールを使っている企業様が多くあります。「パスワードを登録しました」「会員登録が完了しました」といった簡単な連絡のときは、テキストメールでも十分だと個人的には思います。
ただし、テキストメールでは仕組み上、開封率のデータを取得できないというデメリットがあります。また、クリック率やコンバージョン率は、一般的にテキストメールよりもHTMLメールの方が高い傾向にあるため、こうしたメリット・デメリットを把握した上で、使い分けができると良いですね。
チェック項目だけでなくフローも固めておく
前章でも触れましたが、メールマーケティングにおけるデータ管理は、顧客情報を安全かつ効率的に活用するために非常に重要です。
当社では、セキュリティールーム内で厳重にデータ管理を行っていますが、企業様においては、自社で同様の運用体制を構築できるのか、あるいは専門の会社に運用を委託するのか、といった判断が求められます。
情報管理で言えば、メールのクオリティを保つためにチェックシートを作成することも有効です。件名がメールの内容と合致しているか、表記の揺れや誤字脱字がないか、機種依存文字を使用していないか、などチェックすべきポイントをリスト化し、「誰が、いつ、どのようにチェックを行うのか」といった第三者チェックのフローまで明確に決めておきましょう。
また、Webサイトとは異なり、メールは一度送信してしまうと修正することができません。「キャンペーンサイトへのリンクが間違っていた」「金額が一桁ずれていた」といったミスが発生した場合、取り返しのつかない事態に陥る可能性も。スピードは重要ですが、それ以上にエラーが発生しないような体制を構築することが重要です。
まとめ
今回は、菊池さんに効果的なメールマーケティングの取り組み方をお聞きしました。チャットツールが普及している現代においても、WebサイトやECサイトと連携しやすいメールマーケティングは、依然として重要かつ可能性のあるビジネスツールと言えそうですね。
菊池さんがおっしゃっていたように、「メールマーケティングを担当者ひとりで対応している」「担当者が頻繁に変わり、目的が曖昧になっている」「メールを送ること自体が目的になっている」といった状況では、メールマーケティングで高い成果を出すことは難しいでしょう。
メールマーケティング戦略を成功させるためには、マーケティングプロセスにおけるゴールを明確にし、最適なコミュニケーション設計をカスタマージャーニーに落とし込むことが重要です。
株式会社ファングリーでは、Webサイト、メールマーケティング、オフラインツールなどを組み合わせた総合的なコンテンツマーケティング支援を行っています。カスタマージャーニー設計を含むマーケティング戦略立案から、記事、動画、メルマガ、ホワイトペーパー、パンフレットといった各種コンテンツの制作まで、幅広いサービスを提供しています。メールマーケティングに関するお悩みや課題をお持ちの担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。
LATEST
最新記事

カスタマーマーケティングはなぜ重要?成功事例から見る施策と成果
2025.4.17

コンテンツマーケティング会社選びのポイント!他社の成功事例も紹介
2025.4.15

ホームページ(Webサイト)の作成費用を依頼先・種類・ページ数別に詳しく解説
2025.4.10