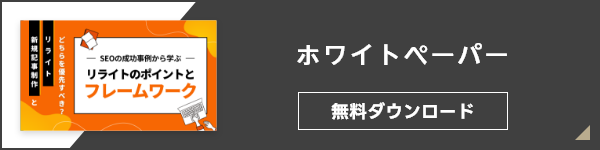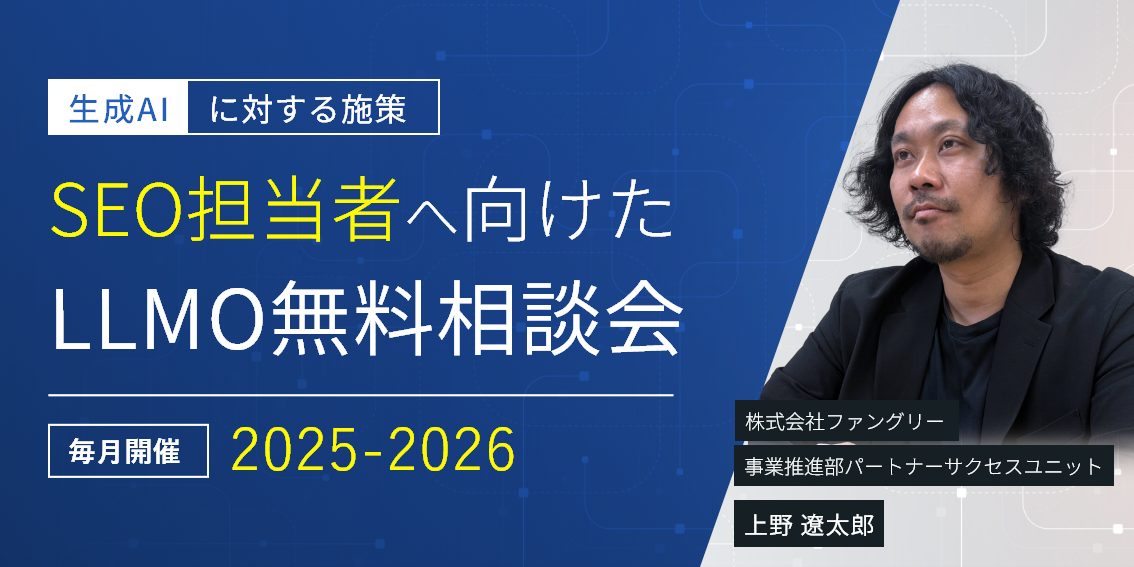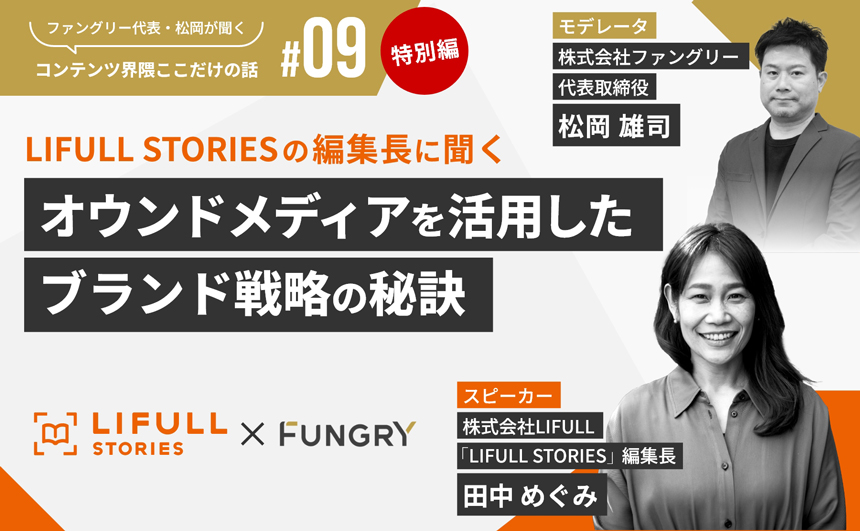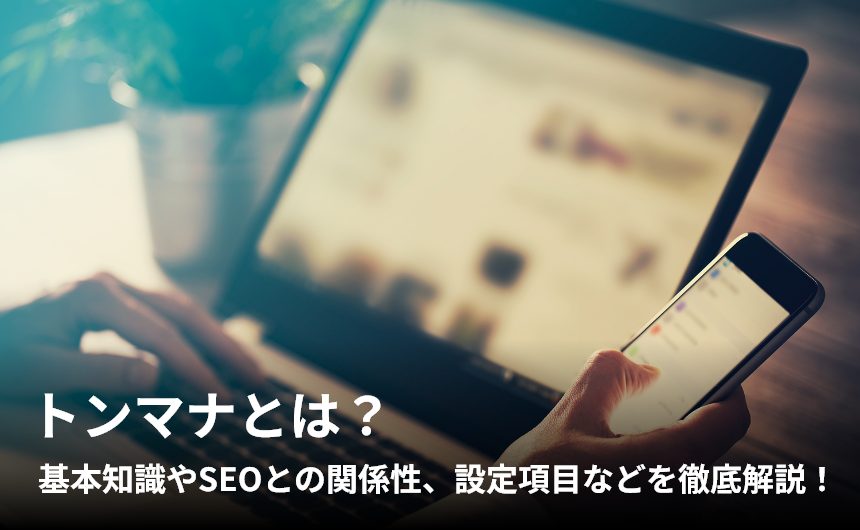
トンマナとは?基本知識やSEOとの関係性、設定項目などを徹底解説!
トンマナ(トーン&マナー)とは、WebサイトやSNS、広告など、企業が発信する情報に一貫性を持たせ、ブランドの世界観を正しく伝えるための大切なルールです。
「媒体ごとにデザインや文章の雰囲気がバラバラ」
「複数人でコンテンツを作ると品質にムラができてしまう」
そんな悩みを抱えるマーケティング担当者やコンテンツ制作者に向けて、本記事ではトンマナの基本から具体的な設定方法、策定項目、運用の注意点までを丁寧に解説します。
この記事を読むことで、誰が担当しても一貫性のある質の高いアウトプットを生み出せる、トンマナ策定のステップと仕組みが明確になります。
\SEOリライトのポイントはこちら/
目次
トンマナとは?文章やデザインに一貫性を持たせる重要なルール
トンマナとは、「トーン アンド マナー(トーン&マナー)」の略称です。Webサイトや広告、SNS投稿、各種ドキュメントなど、あらゆる文章やデザインなどのコンテンツに一貫性を持たせるためのルールを指します。
「トーン(tone)」は文章やビジュアルの雰囲気や感情を示し、「マナー(manner)」は表記ルールや構成など形式的なルールを意味します。
独自の特徴や価値を持つ製品・サービス・企業を「ブランド」と呼びますが、そのブランドを形作るうえで欠かせないのが徹底したトーン アンド マナーです。
トンマナを統一することで読み手に一貫した印象を与え、ブランドの信頼性や親近感を高める効果があります。Webサイトや広告、パンフレットだけでなく、さまざまなメディアで活用される重要な指針です。
トンマナの重要性
トンマナが重要視される理由は、ブランドの世界観や価値観をユーザーに分かりやすく伝えるためです。例えば、親しみやすさを重視するサービスが堅苦しい言葉遣いや無機質なデザインを使うと、ユーザーは違和感を覚え、ブランドイメージを損なう恐れがあります。
一貫したトンマナに基づくコンテンツは、企業の個性や価値観を明確に伝え、ユーザーの記憶に残りやすくなります。これによりブランドイメージの確立と浸透を促進し、競合との差別化も可能です。
また、複数人が関与するプロジェクトでは、情報発信のトーンやデザインがバラバラになりやすくなります。そこでトンマナを明確にすることによって、担当者ごとの解釈の違いを防ぎ、統一されたコンテンツを継続的に提供できるのです。
トンマナの設定方法
トンマナを効果的に設定するには、以下の流れで進めます。
- ペルソナの設定
- コンセプトの明確化
- 具体的なトンマナの作成
1.ペルソナの設定
ペルソナとは、ターゲットユーザーを具体的にイメージした架空の人物像を指します。
ペルソナの設定は、トンマナを決める上で最も基本的なステップになります。まずは、ターゲットユーザーの年齢や性別、職業、居住地、趣味、ライフスタイル、価値観、情報収集の方法、悩みなどを詳細に設定しましょう。
ペルソナを明確にすることで、どのような情報や表現が響くかを理解しやすくなります。これにより、ペルソナに響く最適なトンマナを策定できるようになります。
ペルソナ設定については、別記事「ターゲット設計とキーワード分析をしよう」をご覧ください。
2.コンセプトの明確化
次に、コンテンツやプロジェクトの「コンセプト」を明確にしましょう。「なぜこのコンテンツを作るのか」「誰に何を伝えたいのか」「伝えた結果どうなってほしいのか」といった目的やゴールを具体的に定義します。
例えば、発信する内容が専門家向けなのか、それとも初心者向けなのかによって、言葉遣いやデザインの方向性は大きく変わります。コンセプトが明確であれば、それに合ったトンマナをブレずに設定できます。
3.具体的なトンマナの作成
ペルソナとコンセプトが定まったら、具体的なトンマナの作成を行います。文章やデザインの各項目について、具体的なルールとして明文化し、複数の担当者で共有できる分かりやすいドキュメントとしてまとめることが重要です。
例えば、「文章はです・ます調を基本とし、専門用語には適宜解説を加える」「キーカラーは青を基調とし、清潔感と信頼感を表現する」といった具体的な指針を定めていきます。
なお、ライティングルールを記載するライティングレギュレーションなどに、トンマナについても含めることが一般的です。レギュレーションについては、別記事「ライティングレギュレーションの作り方!具体例や作成ポイントを紹介」もご覧ください。
トンマナの基本的な設定項目
トンマナは、大きく分けて「文章のトンマナ」と「デザインのトンマナ」に分類できます。それぞれの項目で具体的なルールを設定することで、一貫性のあるコンテンツ制作が可能になります。
文章のトンマナ
文章のトンマナは読者に伝えたいメッセージを効果的に届けるために、言葉遣いや表現方法を統一するものです。
主に、「表記」「文末表現」「文章のテイスト」「段落・改行」といった項目が挙げられます。
表記統一
表記統一とは、言葉や記号、数字などの表記方法を統一することです。「ひらがな・カタカナ・漢字の使い分け」や、「数字は全角か半角か」などのルールを明確に定めます。
表記統一を行う際には、以下のポイントを押さえましょう。
| 表記統一の項目 | 例 |
|---|---|
| ひらがな・カタカタ・漢字の使い分け | ・「できる」と「出来る」 ・「わかる」と「分かる」 ・「スマートフォン」と「スマートホン」など |
| 英数字の半角・全角 | ・「123」と「123」 ・「ABC」と「ABC」など |
| 送り仮名の表記方法 | ・「申し込み」と「申込」 ・「見積もり」と「見積」 ・「問い合わせ」と「問合せ」など |
| 専門用語・固有名詞の統一 | ・「YouTube」と「ユーチューブ」 ・「Amazon」と「アマゾン」など |
表記が統一されていないと、読者は違和感を覚えたり、内容を理解するのに時間がかかったりする可能性があります。
表記統一のひとつである「とじ・ひらき」については、別記事「漢字の『とじ・ひらき』の使い分けでブランドイメージを確立」もあわせてご覧ください。
文末表現(文章の語尾)
文末表現は、文章のトーンを大きく左右する要素のひとつです。一般的に「です・ます調(丁寧語)」と「だ・である調(常体)」があります。コンテンツの目的やターゲット層に合わせて、以下のように使い分けましょう。
- です・ます調 丁寧で読みやすく、幅広い層に受け入れられやすい。企業の公式ブログや顧客向けコンテンツに適している。
- だ・である調 専門的で信頼性を高めやすく、論理的な説明や学術的な内容に適している。論文や技術記事などで用いられるケースが一般的。
どちらか一方に統一する形式が基本ですが、見出しは「だ・である調」、本文は「です・ます調」といった使い分けも可能です。
テイストの統一
文章テイストの統一は、文章全体の雰囲気やスタイルを決定するものです。コンテンツを通して読者にどのような印象を与えたいかによって、そのテイストを定めます。
▼テイストのトンマナ例
- フォーマル 丁寧で堅実な印象を与える。企業のプレスリリースやIR情報などに適している。
- カジュアル 親しみやすく、気軽に読める印象を与える。若年層向けのブログやSNS投稿などに適している。
- ユーモラス 読者の興味を引き、記憶に残りやすい。一方で、使い方を誤ると不快感を与える可能性もある。
- テクニカル(専門的) 信頼性が高く、特定の分野に特化した記事や技術情報などに最適。
例えば「当社の製品は業務効率化に寄与します。めっちゃ便利なんで、ぜひ使ってみてくださいね!」といった文章だと、前半は堅めなトーンで始まっているのに、後半はいきなりフレンドリーな口調に切り替わり統一感がありません。読み手によっては混乱し、企業やコンテンツへの信頼感を損なう恐れがあります。
段落・改行の統一
段落や改行の統一は、文章の読みやすさに直結します。適切な段落分けや改行は、読者が内容をスムーズに理解するために不可欠です。
▼段落・改行のトンマナ例
- 段落の長さ ひとつの段落が長すぎると読みにくくなるため、適切な長さや文章量を定める。
- 改行のルール 適切な位置での改行は文章にリズムを与え、視覚的な負担を軽減する。意味の切れ目での改行など、一定のルールを設ける。
- 箇条書きの活用 情報が羅列される場合などに、視認性を高めるために箇条書き活用する。
デザインのトンマナ
デザインのトンマナは、視覚的な要素を通じてブランドイメージを構築し、ユーザーに快適な体験を提供するために不可欠です。
主に配色やレイアウト、フォント、画像・イラストが挙げられます。
配色
配色は、コンテンツの印象を決定づける重要な要素です。企業のロゴやブランドカラーを基調とし、それに合わせた補助色やアクセントカラーを定めます。
以下のポイントを押さえて配色を決定することで、デザインのトンマナを統一できます。
▼配色のトンマナ例
- メインカラー ブランドのイメージを象徴する色を決める。
- サブカラー メインカラーを補完し、コンテンツに統一感を与える色を決める。
- アクセントカラー 特定の情報を目立たせるための色を決める。
- 文字色・背景色 コントラストがはっきりした色の組み合わせを設定する。
色の持つ心理的効果も考慮し、ブランドイメージに合った配色を選定することが重要です。
レイアウト
レイアウトはコンテンツの情報を整理し、ユーザーがスムーズに情報にアクセスできるように配置するルールです。以下のポイントについてルールを定めることで、視認性やUI/UXが高まります。
▼レイアウトのトンマナ例
- グリッドシステム デザイン要素を格子状に配置し、視覚的な整然さを確保する手法のルールを決める。
- 余白 情報過多にならないよう視認性を高めるスペースの入れ方を決める。
- 要素の配置 Webサイトなどのメニュー、ヘッダー、フッター、サイドバーなどの配置ルールを決める。
- 情報の優先順位 重要な情報を目立つ位置に配置する、視線誘導を意識したレイアウトルールを決める。
フォント
フォントは、文章の可読性やデザインの印象に大きく影響します。使用するフォントの種類やサイズ、太さなどについてもルールを定めることが推奨されます。
▼フォントのトンマナ例
- 種類 ゴシック体、明朝体などイメージに合ったフォントを選定する。
- サイズ 見出し、本文、キャプションなど、役割に応じた適切なフォントサイズを決定する。
- 太字・色 情報の重要度を示すためにフォントの太字設定や色の設定を決める。
なお、見出しと本文で異なるフォントを使うケースもありますが、全体のバランスを取り可読性や視認性を意識することが重要です。
画像・イラスト
画像やイラストは、視覚的に情報を伝える強力なツールです。その選定や加工方法にもトンマナを設定します。
▼画像・イラストのトンマナ例
- テイスト 抽象的な写真や手書き風イラストなど、全体の雰囲気に合わせて選定する。
- 色調・加工 画像の色調補正やフィルターに関する使用ルール。イラストであれば線の太さや塗りの方法を統一する。
- サイズ・比率 掲載する画像のサイズやアスペクト比を統一することで、レイアウトの崩れを防ぐ。
統一された画像やイラストは、コンテンツに一体感をもたらし、ブランドの世界観をより深く伝えられます。
トンマナ設定のメリット
トンマナを統一するとコンテンツの印象や品質が安定するだけでなく、社内外の制作メンバーが共通の基準で制作・運用できるようになります。
ここでは、トンマナを明確に設定するメリットについて解説します。
企業ブランディングに貢献する
トンマナの一貫性は、企業のブランディングに貢献します。統一されたデザインや表現は、企業の個性や価値観を明確に伝え、ユーザーの記憶に残ります。
これにより、企業は特定のイメージを確立しやすくなり、競合他社との差別化を図りやすくなります。
SEO評価向上にもつながる
文章のトンマナが整っているコンテンツは、SEO評価の向上にもつながります。一貫したコンテンツはユーザーにとって読みやすく、サイトの滞在率や回遊率が上がれば、Googleなどの検索エンジンが「このサイトはユーザーにとって価値がある」と判断し、検索順位の向上につながりやすくなります。
また、表記ゆれがなくなることで、検索エンジンがコンテンツの内容を正確に認識しやすくなり、特定のキーワードでの検索上位表示に貢献する可能性が高まります。
制作コストを削減できる
明確なトンマナがあれば、コンテンツ制作にかかるコストを削減できます。デザインや文章の方向性が事前に定まっているため、担当者ごとの認識のズレが少なくなり、手戻りや修正作業を減らせます。
新しい担当者が加わった場合でも、トンマナに関するガイドラインを共有するだけで迅速に制作体制に組み込めます。
トンマナ設定時の注意点
トンマナを設定する際には、いくつかの注意点もあります。ただ形式を整えるだけでなく、ターゲットやメディア、Webサイトの特性に合った柔軟な運用が求められます。
ターゲット層へ最適化させる
トンマナは、あくまでもターゲット層に最適化されていることが前提となります。実際に運用していく中で、ターゲット層の反応を見ながら微調整することも必要です。
例えば若年層向けのコンテンツで硬すぎる表現を使ったり、高齢者向けのコンテンツで複雑なデザインを採用したりすると、本来伝えたいメッセージが届かない可能性があります。
常にユーザーの視点に立ち、もっとも受け入れやすいトンマナであるかを検証し続けることが大切です。
NG表現など具体的なガイドラインを策定する
トンマナは「こうあるべき」というだけでなく、「これは避けるべき」というNG表現についても具体的に定めましょう。
例えば「差別的表現」や「不適切な言葉遣い」「誇大広告や誤解を招く表現」などのNG表現を明文化することで、担当者ごとの認識のずれを防ぎ、炎上リスクやブランドイメージの毀損を防ぐことができます。
トンマナに関するよくある質問
ここではトンマナに関するよくある質問をまとめました。
トンマナとはどういう意味?
トンマナは「トーン&マナー」の略称で、Webサイトや広告など、発信するコンテンツに一貫性を持たせるためのルールのことです。「トーン」は雰囲気、「マナー」は表記などの形式的なルールを指し、ブランドイメージを統一する目的で設定されます。
詳しくは、記事内の「トンマナとは?文章やデザインに一貫性を持たせる重要なルール」をご覧ください。
トンマナはどのように設定すれば良い?
トンマナは以下の3つのステップで設定するのが効果的です。
- ペルソナの設定
- コンセプトの明確化
- 具体的なルールの作成
具体的な設定内容は、記事内の「トンマナの設定方法」で解説しています。
トンマナを設定するメリットは?
トンマナを明確に設定することで以下のようなメリットが得られます。
- 企業ブランディングに貢献する
- SEO評価向上にもつながる
- 制作コストを削減できる
詳しくは記事内の「トンマナ設定のメリット」で解説しています。
まとめ
トンマナ(トーンアンドマナー)は、Webサイトや広告、SNS、各種ドキュメントなど、企業が発信するあらゆるコンテンツにおいて、表現やデザインに一貫性を持たせるための重要な指針です。
トンマナは一度設定したら終わりではなく、時代の変化やユーザーのニーズに合わせて、定期的な見直しと更新が求められます。一貫性のあるコンテンツ発信を通じて、企業とユーザーの信頼関係を深め、ビジネスの成長につなげていきましょう。
株式会社ファングリーでは、制作支援とマーケティング支援を一貫して行っています。とりわけBtoB向けのコンテンツ制作に強みを持っており、ブランディングを軸としたWebサイト制作・コンテンツ制作を通じてお客様のビジネス課題の解決に取り組んでいます。「リソース不足で記事を内製できない」「記事制作のノウハウが分からない」とお悩みの企業様は、ぜひ気軽にお問い合わせください。

執筆者
コンテンツディレクター/ライター
Miho Shimmori
2023年ファングリーに入社。以前はWebマーケティング会社で約2年半コンテンツマーケティングに携わり、不動産投資メディアの編集長を務める。SEOライティングが得意。ほかにも士業関連や政治など複数メディア運営の経験あり。Z世代の端くれ。趣味はサウナと競馬と街歩き。
LATEST
最新記事
TAGS
タグ