
Googleの「AI Overviews」とは?基本的な使い方からSEO・広告への影響まで徹底解説
本記事では、Google検索を大きく変える「AI Overviews」の基本的な使い方からSEO・マーケティングへの影響、広告の変化、そして今後の課題まで、AI時代のコンテンツマーケティングのために知っておくべき全情報を、当メディアの独自分析を交えて網羅的に解説します。
「AI Overviewsの登場でマーケティングはどのように変わった?」「Web担当者として何をすべき?」といった、漠然とした不安や疑問を抱えながら業務に向き合っている方も少なくないはずです。今すぐ実践できる具体的な対策と考え方を押さえて、日々の業務に活かしましょう。
この記事を読めば、AI Overviewsに対する漠然とした不安が「攻め」と「守り」両面の具体的な戦略へと変わります。これからのAI時代を勝ち抜くための羅針盤となるよう、全体像をしっかり理解しておきましょう。
\LLMO対策の土台となる「Webマーケティングの基礎」はこちら/
Table of Contents
AI Overviewsとは?検索体験を根本から変えるGoogleの機能
AI Overviews(エーアイ オーバービュー)とは、Google検索結果の最上部にAIが生成した「答えの要約」を表示する機能です。ユーザーが入力した質問(検索クエリ)に対し、AIがWeb上の膨大な情報から要点をまとめて、分かりやすく提示してくれます。
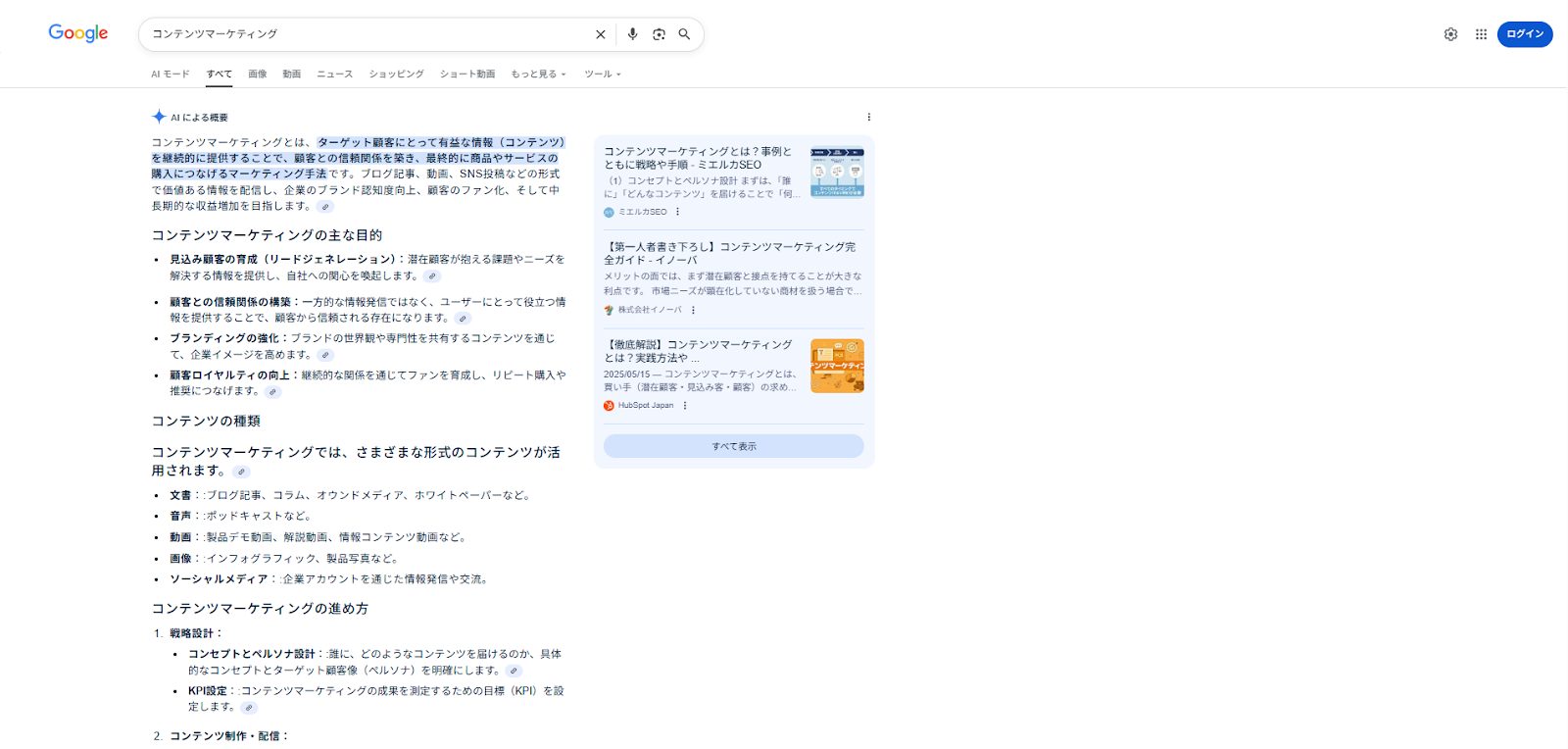
これまでのように、気になるリンクを一つひとつ開いて情報を探す必要はもうありません。この機能により、複雑なトピックでも検索結果ページを見るだけですぐに概要を掴めるようになりました。
従来の検索が「情報の入口となるリンクの一覧」だったとすれば、AI Overviewsは「要約された答えそのもの」と言えるでしょう。これはGoogle検索が単なる「情報探し」から、「AIとの対話による問題解決」へと進化していることを示す、大きな一歩です。
AI Overviewsの基盤技術「Gemini」とは
AI Overviewsの高度な回答生成能力を支えるのは、Googleが開発するAIモデル「Gemini(ジェミニ)」です。Geminiは複数の条件を含む複雑な質問をステップに分解して処理する「マルチステップ推論能力」を備えています。
さらにテキストや画像、音声、動画といった多様な情報を統合的に理解する「ネイティブ・マルチモーダル」という機能を持ちます。これにより、まるで人間のように複数の情報を同時に、かつ文脈に沿って深く理解することが可能です。
このGeminiの能力を基盤として、GoogleではAI OverviewsとAI Mode(AIモード)という2つの新しい検索体験を提供しています。AI Modeはより対話的・深掘り型の検索体験で、2025年に登場しました。ユーザーは追加の質問をしたり、回答の視点を変えたりしながら、トピックをより深く探求できるのが特徴です。
▼ AI Modeイメージ

なお、Googleサーチコンソールのデータ上ではこれらAI機能由来の表示やクリックは区別されず、「Web検索」タイプに合算して計上されます。
この進化はコンテンツ制作者に対して、ユーザーが抱く複雑な問いへ多角的に応えることを求めています。そのためにはテキストだけでなく、画像や動画、統計データといったあらゆる情報形式の質を高め、最適化していく必要があります。
▼ Googleサーチコンソールについては、以下の記事をご覧ください。
AI Overviewsの実装はいつから?日本の現状とユーザーのリアルな反応
GoogleのAI Overviewsは、2024年5月に米国で正式にスタートし、日本では同年8月15日から提供が開始されました。2025年10月現在、多くの検索クエリで表示される標準機能として定着しつつあります。
この機能はかつての試験運用版「SGE」(Search Generative Experience)とは異なり、事前の登録や設定なしで全ユーザーにデフォルトで表示されます。これは、「AIによる新しい検索体験をスタンダードにしたい」というGoogleの強い意志の表れとも言えるでしょう。
しかし、国内では評価が分かれています。情報の取得が速くなったと好意的に受け止める声がある一方で、検索結果のサジェストに「AIの概要は邪魔」といったキーワードが現れるなど、従来のシンプルな検索結果を好むユーザーからの戸惑いの声も少なくありません。
AI Overviewsの表示パターン
AI Overviewsは、Googleがユーザーにとって有益と判断した場合にのみ表示されます。とくに「○○とは何か」「△△のやり方」「○○と△△の違い」「おすすめの○○は?」といった、情報探索型の長めのクエリで表示されやすいのが特徴です。
一方、以下のようなパターンでは表示が出ない傾向にあります。
- 健康・医療、金融、法律などのYMYL領域
- 政治、差別、危険行為などのセンシティブなトピック
- 速報性の高いニュース
- 企業名などの指名検索
「Amazon 公式サイト」のような特定サイトへの移動を意図するクエリや、ごく短い単語のみの簡単な検索、天気・計算など単一の事実で十分な場合も表示されません。AI Overviewsは通常の検索結果に付加価値を提供できる場合にのみ表示され、複雑で対話的な情報ニーズがあるクエリで出現しやすいと言えます。
なお、自分のサイトがAI Overviewsに引用されているかを把握するには、手動で検索して引用元を目視で確認する方法があります。
- 引用されたい内容に関するキーワードや、具体的な質問文でGoogle検索する
- 検索結果の最上部にAIによる要約(AI Overviews)が表示されているか確認する
- 要約の下部または横に表示される引用元のリスト(ソースリンク)を開き、自社サイトのタイトルやURLが含まれているかをチェックする
要約文中の特定の情報に「鎖のアイコン」が表示されていれば、そこから直接引用元を確認できます。引用されている場合、そのクエリであなたのサイトが信頼性の高い情報源としてAIに選ばれたことを意味します。
AI Overviewsをオフにする設定方法
AI Overviewsをオフにする方法は、いくつかあります。
検索結果画面上部のフィルタで「ウェブ」を選択
以下のように、検索結果画面上部のフィルタで「ウェブ」を選択。AI Overviewsが非表示になり、通常のリンクのみの検索結果が表示されます。

検索結果のURL末尾に「&udm=14」を追加
検索結果のURL末尾に「&udm=14」を追加してページを再読み込みすると、AI概要が表示されなくなります。
その他の方法
ほかにも、シークレットモードでの検索やGoogleにログインしない状態で検索すると、AI概要の表示頻度が下がるとの報告があります。
また、自身のサイトに以下のタグを設定すると、そのページのコンテンツがAI概要の引用元として使われる可能性が低くなります。ただし、通常検索でのスニペットも表示されなくなることには注意が必要です。
<meta name="robots" content="nosnippet">
AI概要を無効化する公式のオプションはありませんが、これらの工夫によってAI概要の非表示が可能です。
AI Overviewsの基本的な使い方
AI Overviewsは、情報収集や企画立案といった知的作業を加速させる強力なツールです。AIとの「対話」を意識して少し質問を工夫するだけで、その能力を最大限に引き出せるでしょう。
- 効果的な質問方法を身につけ、回答を読み解く
- 効率的に情報収集する
- 複雑なトピックを速習する
- 新しいアイデアを創出する
- 英文の要約・翻訳する
- プログラミングを生成・デバッグする(エンジニア向け)
これらのポイントを押さえることで、AI Overviewsを日々の知的活動に役立てやすくなります。
効果的な質問方法を身に付け、回答を読み解く
質の高い回答を引き出すコツは、具体的なキーワードを複数組み合わせること。AIは、あなた自身が何を知りたいのかを正確に理解するほど、的確な要約を生成できます。
例えば単に「コーヒー豆」と検索するのではなく、「コーヒー豆 選び方 酸味 苦味 初心者」のように、知りたいことの軸(選び方)や条件(酸味・苦味・初心者向け)を追加してみましょう。AIはあなたの意図を正確に汲み取り、質の高い回答を返してくれます。
一方で、生成された回答を鵜呑みにするのは危険です。AIは稀に、事実に基づかない情報を生成することがあります(ハルシネーション)。重要な情報を扱う際は、必ず回答に表示されている引用元リンクをクリックし、元の記事で裏付けを取る習慣をつけましょう。「AIの回答はヒント」と捉え、最終確認は自分で行うことが、賢いAIとの付き合い方です。
効率的に情報収集する
AI Overviewsは、日常的な情報収集を劇的に効率化してくれます。最大のメリットは、複数のWebサイトを自分で見比べる手間が省けることです。
最新iPhone Google Pixel カメラ 比較
複数のレビューサイトの情報を要約し、「Aサイトによると暗所撮影はPixelが優位、Bサイトでは動画の手ブレ補正はiPhoneに軍配が上がると評価されています」といった各製品の長所・短所をまとめて提示してくれる
これにより、数十分かかっていた情報収集がわずか数十秒で完了することもあります。製品比較や旅行先の情報収集など、手間のかかる調べ物で特にその効果を発揮するのです。
複雑なトピックを速習する
専門的な技術や難解な科学理論など、理解に時間のかかるトピックを短時間で学習する際にもAI Overviewsは強力な助けとなります。AI Overviewsは情報を要約するだけでなく、指定されたレベルに合わせて内容を「翻訳」し、要点を整理する能力を持っています。
ブロックチェーンの仕組みを中学生にも分かるように説明して
専門用語を避け、取引記録が鎖のようにつながっているイメージなど、比喩を使って基本的な概念を解説してくれる
これにより、専門書を読み解く前の予備知識のインプットや、時事問題のキャッチアップが効率的に行えます。
新しいアイデアを創出する
考えが煮詰まってしまったとき、AI Overviewsはアイデア出しの壁打ち相手にもなってくれます。多様な視点から、発想のヒントを引き出すことが可能です。
IT企業のエンジニア向け社内交流イベントのユニークなアイデアを10個提案して
Web上にある様々なイベント事例を基に、「脱出ゲーム」や「eスポーツ大会」「他社との合同交流会」など、自分では思いつかなかったようなアイデアを提案してくれる
AIを「発想を広げるための触媒」として活用することで、イノベーションの種を見つけ出しやすくなるでしょう。
英文の要約・翻訳する
海外の最新ニュースや研究論文など、長文の英語コンテンツを効率的に理解したい場合にも非常に有効です。単なる翻訳だけでなく、要点を正確に把握するのに役立ちます。
(海外ニュースのURL)この記事の要点を3行で日本語で教えて
長文の記事を読み込み、その核心部分だけを抽出して、自然な日本語の要約を生成してくれる
これにより、情報収集のスピードが飛躍的に向上し、海外の一次情報にもアクセスしやすくなります。
プログラミングを生成・デバッグする(エンジニア向け)
エンジニアの日常的な作業もサポートしてくれます。簡単なコードの生成やエラーの原因特定などに活用することで、開発効率がアップします。
PythonのPandasライブラリを使ってCSVファイルを読み込み、’age’列が30以上の行だけを抽出し、新しいCSVファイルとして保存するためのコードを書いてください
すぐに使えるサンプルコードを提示
JavaScriptのエラー ‘Uncaught TypeError: Cannot set properties of null’ の原因は?
DOM要素が読み込まれる前にスクリプトが実行されている可能性など、典型的な原因と解決策を解説してくれる
このように、簡単な定型処理やエラー解決の初動調査にかかる時間を短縮し、より本質的な開発作業に集中できます。
AI Overviews時代の新しいWebマーケティング戦略
AI Overviewsの登場は、SEOだけでなくWebマーケティング戦略全体の再構築を促すものです。ユーザーが情報を発見し意思決定に至るプロセス(カスタマージャーニー)が根本から変わるため、企業はこれまでの常識を見直す必要があります。
マーケティングの戦場はもはや自社サイトではなく、AIが生成する検索結果そのものへ移ったと考えられます。つまり、「検索結果にて言及されること」を勝ち取るのが、新たな勝利条件となったのです。
【課題】「ゼロクリックサーチ」の増加とコンテンツ戦略の変化
Pew Research Centerの調査によると、Googleにおける検索結果画面のセッション数の約3分の2は、ユーザーが外部リンクをクリックせずに終了しています。AI Overviewsの登場は、このような「ゼロクリックサーチ」の流れをさらに加速させると考えられます。
これにより、コンテンツ戦略の目的は「クリック獲得」から「認知拡大」と「引用獲得」に変化しました。AIに引用されることでブランド認知が高まるため、AIの回答中に自社コンテンツが言及されることが重要になります。
具体的なコンテンツ戦略については、「AI Overviewsに引用されるためのコンテンツ戦略」で後述します。
指名検索とブランディングを重視する
AIが情報仲介者となる現代において、従来のSEO戦略だけで安定したトラフィックを確保するのは困難です。そのため、「指名検索(特定のブランド名での検索)」と「ブランディング」の重要性が一層高まっています。
指名検索はAI Overviewsの影響を受けにくく、安定したアクセス源となります。ブランドの検索量が多いほどAIはそのブランドを信頼性の高い情報源と認識し、引用する可能性が高まる傾向にあるのです。
質の高い専門的なコンテンツを継続的に発信し、SNSなどを活用してブランドへの言及を増やすことでオンラインでの存在感を高めやすくなります。最終的には、ユーザーが疑問を持った際に自ら進んでそのブランドを指名してくれる状態を目指しましょう。
AI Overviewsを起点とした新しいカスタマージャーニーの考え方
AI Overviewsの登場で、カスタマージャーニーは検索結果上で完結・ループする形に変化します。
従来、ユーザーは「認知→興味→検索→比較→購買」とステップを踏みました。しかし今は、AIが最初の「認知・興味・比較」までを要約して提示します。
新しいカスタマージャーニーの起点は、AIの回答内に引用されることです。そこから、深掘りのための対話(「AとBの違いは?」)や引用元サイトへの訪問が始まります。AIの対話ループの中でいかに自社情報を提示し続け、最終的な指名検索やサイト訪問につなげるかが、今後のマーケティングの鍵となります。
▼ カスタマージャーニーマップについては、以下記事をあわせてご覧ください。
テキスト以外のコンテンツの重要性
AI Overviewsを通して、YouTubeの動画やポッドキャストの音声の中身も理解できます。
例えば、あなたが魚のさばき方を解説した動画をYouTubeに投稿したとします。するとAI Overviewsは、その動画を見て「まずウロコを取ります。次に……」と、手順を要約して検索結果に表示してくれるのです。
つまり、これまで文字の記事だけが対象だった検索結果に、動画や音声がAI Overviewsによって「新しい入り口」として登場するということ。だからこそ動画には正確な字幕を、音声には内容の要約を添えるといった「AI Overviewsが中身を理解しやすくなる工夫」が、これからのWebマーケティングでは非常に重要になります。
AI OverviewsがもたらすSEOへの影響
AI Overviewsの登場で、これまでのSEOの常識が通用しなくなる可能性があります。
従来の「検索順位の獲得」に加え、「AIに引用される価値ある情報源となる」という新たな視点が必要になりました。この視点はSEOが「検索エンジンをハックする技術」から「AIに価値ある情報を提供し、引用される権利を勝ち取る戦略」へと本質的に変化したことを意味します。
ここでは、AI時代を勝ち抜くための具体的かつ実践的な対策を専門家の視点から詳説します。
AI OverviewsとSEOの関連性
AI Overviewsは、Googleが信頼できると判断した複数のWebページから情報を抽出し、要約して回答を生成します。重要なのは、引用元となるページが必ずしもオーガニック検索1位のページであるとは限らない点です。
ある調査では、引用元URLの約60%が通常検索結果の上位20位以内に位置しましたが、残り約40%は21位以下のページからも引用されていました。さらに別の分析では、AI概要に引用されたURLの実に66%が従来の検索結果にはランクインしていなかったという報告もあります。
出典:Pew Research Center「Google users are less likely to click on links when an AI summary appears in the results」
これは従来のランキング要因に加え、AIが情報を抽出しやすいこと「=引用されやすさ」という新たな評価軸が加わったことを意味します。言い換えると、検索アルゴリズムが高品質と判断して上位表示しているサイトだけでなく、「そのテーマについて役立つ記述があるページ」であれば順位に関わらずAI概要が拾ってくる可能性があるということです。
つまり、これからのマーケティング戦略ではSEOで検索上位を目指す努力を継続しつつ、コンテンツそのものをAIにとって「利用価値の高い情報資産」へ最適化する必要があります。
AIとの対話を促す「トピッククラスター」の新戦略
AIに選ばれ続けるには、ユーザーの「次の疑問」を予測し、コンテンツで先回りするトピッククラスター戦略が重要です。
例えば「ふるさと納税とは?」という記事から「ワンストップ特例制度のやり方は?」といった関連ページへ内部リンクでつなぎ、ユーザーとAIの思考を導きます。これは単なるリンク集ではなく、AIに対話の道筋を示す行為です。
この網羅性によりAIはサイトを「特定分野の専門家」と認識し、続く対話の中で繰り返しあなたのコンテンツを情報源として引用しやすくなるのです。
AI Overviewsに引用されるためのコンテンツ戦略
AIに情報源として選ばれ、AI Overviewsに引用されるためには、コンテンツの作り方そのものを見直す必要があります。AIが評価するのは情報の正確性や網羅性だけでなく、「その情報がどのように構造化され、誰によって発信されているか」という信頼性のシグナルです。
ここでは、当メディアの独自分析で見えてきた「AIに引用されやすいコンテンツの9つの共通点」を、具体的なライティング術とともに解説します。
AIに引用される9つの共通点とライティング術【独自分析】
実際にAI Overviewsに引用されている国内外のコンテンツを分析した結果、そこにはAIの情報処理の仕組みに根差した「9つの明確な共通点」が見えてきました。
単に「何が有効か」だけでなく、「なぜAIはそれを好むのか」という原理まで理解することで、本質的なコンテンツ改善に応用できます。
1. 質問に直接答える「Q&A形式」と「結論ファースト」
ユーザーが検索するであろう質問(例:「〇〇とは?」)をそのまま見出しにし、その直下で結論を簡潔に述べる「一問一答」形式は、AIに引用される上で極めて有効です。
AIの基本動作は、ユーザーの質問と意味的に最も近い答えをWeb上から探し出すこと。質問と答えが明確に対応付けられたコンテンツは、AIが「この記事に答えがある」と判断する上で信頼性の高いシグナルとなります。
2. 情報を分解して整理する「箇条書き」と「表」
手順やメリット・デメリット、比較といった情報は、長い文章ではなく箇条書きや表で分かりやすく構造化しましょう。
AIは文章を熟読するのではなく、情報を機械的に「抽出」します。箇条書きや表は、情報が「項目」という単位で機械的に分解・認識できるためAIにとって最も理解しやすく、回答の一部として再構成しやすくなります。
3. 文書の骨格を伝える「論理的な見出し構造」
「h1→h2→h3」と見出しタグが階層構造として正しく使われており、見出しだけで記事全体の論理構成が分かるようにしましょう。
見出し構造は、AIにとって記事全体の「目次」や「設計図」の役割を果たします。これによりAIは各セクションの関係性を正確に把握し、文脈に合った適切な部分を引用できます。
4. 具体性と客観性を示す「数値」と「固有名詞」
「多い」「さまざま」といった曖昧な表現を避け、「3つの方法」「50%以上」といった具体的な数値や、製品名・組織名などの固有名詞を積極的に使用しましょう。
AIが重視するのは回答の正確性と信頼性です。具体的な数値やデータといった客観的な事実は、AIがそのコンテンツを「信頼できる情報源」と評価する上で決定的な役割を果たします。
5. 情報の信頼性を担保する「引用・発リンク」
情報の信頼性を担保するため、公的機関のデータや専門家の論文などを引用し、出典元へリンクを設置しましょう。これはE-E-A-T(とくに権威性・信頼性)を高める強力なシグナルです。
信頼できる外部サイトへの発リンク(他のページへ遷移できるように設定されたリンク)は、その情報がWeb上の信頼できる情報ネットワークの一部であることをAIに示します。これにより、コンテンツ全体の評価が高まります。
- 文中での引用例: 総務省の「令和5年版 情報通信白書」によると、日本のインターネット利用率は84.9%に達しています。
- 記事末尾での参考文献リスト例: 【参考文献】総務省 (2023)「令和5年版 情報通信白書」
6. AIの誤解を防ぐ「シンプルで明確な文章」
複雑な比喩や冗長な表現は避け、一文を短く、主語と述語を明確にしたシンプルな構文で書きましょう。
AIは進化しているものの、複雑な構文や多義的な言葉の解釈は苦手な場合があります。AIが情報を誤解なく正確に抽出できるよう、機械が処理しやすい明確な文章を心がけることが重要です。
7. 網羅性と専門性を示す「関連トピックへの言及」
ひとつのテーマを解説するだけでなく、関連する専門用語の解説や、ユーザーが次に抱くであろう疑問に先回りして答えましょう。また、関連性の高いページ同士を内部リンクで結ぶことも専門性を示す上で非常に重要です。
網羅性の高いページは、AIが横断的な回答を生成する際の価値ある情報源となります。また、内部リンクによってコンテンツ群が大きなトピックを形成しているとAIが認識すれば、サイト全体の権威性が高まり、引用元として選ばれやすくなります。
8. AIにコンテンツの種類を明示する「構造化データ」
FAQページや手順解説など、コンテンツの種類に合わせて適切な構造化データを実装しましょう。
構造化データは、ページの内容が「何であるか」を、AIが理解できる共通言語で伝えるためのものです。例えば「このテキストはQ&Aの『質問』です」とAIに直接教えることができるため、AIはより確信を持って情報を利用できます。とくにFAQPageスキーマやHowToスキーマは引用されやすい傾向にあります。
Personスキーマを用いて、著者情報を検索エンジンに正確に伝えます。このコードをページの<head>内か<body>内に記述します。
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Person",
"name": "山田 太郎",
"jobTitle": "Webマーケティングコンサルタント",
"image": "https://example.com/profile.jpg",
"url": "https://example.com/author-page"
}▼上記のコンテンツ戦略については、次の記事でより詳細に解説しています。
a9. AIに新たな情報を提供する「独自性のある内容」
独自の調査データや一次情報、専門家としての経験や考察など、他のサイトにはないユニークな情報を含めましょう。
AI OverviewsはWeb上の情報を統合・要約する機能ですが、ありふれた情報だけでは質の高い要約を作れません。競合にはない独自の事実や視点は、AIが生成する回答の付加価値を大きく高めるため、極めて価値の高い情報源となります。
競合サイトがどのようにE-E-A-Tや独自性を構築しているかを知ることで、自サイトが強化すべき点が見えてきます。
- 著者・監修者は誰か?
- 引用・被リンク元はどこか?(Ahrefsなどのツールで分析可能)
- 独自の価値は何か?(独自の調査データ、事例、専門家インタビューなど)
【テクニカル編】AIクローラーのアクセスを制御する「llms.txt」
GoogleのAI向けクローラー「Google-Extended」は、AI Overviewsなどのモデル学習のためにサイト情報を収集します。このクローラーのアクセスは、既存のrobots.txtファイルで制御可能です。
アクセスを拒否する場合は、以下のように記述します。
Disallow:
重要なのはサーバーログを分析し、このクローラーの動きを監視することです。ログからGoogle-Extendedがどのページに頻繁にアクセスしているかを把握すれば、GoogleのAIがサイト内のどのコンテンツを価値ある学習データと見なしているか推測できます。この分析結果は、今後のコンテンツ戦略を立てる上で重要なヒントとなります。
▼ llms.txtについては、以下記事もあわせてご覧ください。
AI Overviewsの広告(Google広告)への影響
AI Overviewsの登場は、Google広告のあり方を根本から変える可能性を秘めています。広告主は、これまで常識だった「検索結果の上位に表示させる」という考え方だけでなく、「AIが生成する回答の中でいかにユーザーに選ばれるか」という新しい視点を持つ必要があります。
AI Overviews内に表示される広告の種類と形式
Googleの仕様ではAI Overviews内に広告が表示される場合があり、その広告は検索結果上部の広告(Top Ads)として集計されます。広告主側でAI Overviews内への表示を直接指定したり、非表示(オプトアウト)にしたりすることはできません。国や検索クエリによって、広告の出現頻度は異なると考えられます。
現在、AI Overviews内では従来の検索広告(テキスト広告)やショッピング広告が表示されることが確認されています。これらの広告はAIが生成した回答の文中や、関連情報がまとめられたカード形式のセクションに自然に組み込まれるのが特徴です。例えば製品を検索した場合、AIの回答の下に関連製品のショッピング広告が並ぶことがあります。
広告の表示順位やクリック率への影響
AI Overviewsが検索結果の最上部を占めるため、その下に表示される従来の広告枠の視認性が低下し、クリック率(CTR)に影響を与える可能性があります。これまで1位から4位に表示されていた広告でさえ、AI Overviewsの表示量によってはスクロールしないと見えない位置に押し下げられるケースもあるでしょう。
一方でAIの回答内に広告が直接表示される場合は、ユーザーの検索意図との関連性が非常に高く、質の高いクリックにつながる可能性があります。
AI Overviews時代における広告運用の新しい考え方
AI Overviewsの普及が進むと、従来の広告運用における考え方の見直しが求められます。具体的には、以下のような見直しが必要です。
従来の検索結果上部の広告枠への依存度が下がる可能性があるため、表示回数(インプレッション)のシェアを重視する戦略から、コンバージョン価値など実際の成果に基づいた評価への転換がより重要になる
AIの回答を超えた価値の提示
AIの要約が提供する客観的な情報に対し、広告では感情に訴えるコピーや限定オファーなど、ブランドの個性を際立たせるクリエイティブが有効に。「AIの回答にはない付加価値」を提示し、ユーザーに選ばれる工夫が一層求められる
AI Overviewsの注意点と今後の課題
AI Overviewsがもたらす課題は、単なる技術的な注意点に留まりません。それは、私たちが情報とどう向き合い、知識をどう形成し、コンテンツ制作者がどう報われるかという、インターネットの根幹をなすエコシステム全体を揺るがす構造的な問題です。
情報の正確性と信頼性の課題(ハルシネーション問題)
AI Overviewsが抱える最大の課題は、事実に基づかない情報を生成する現象「ハルシネーション」です。AIは複数のWebサイトから情報を統合して要約しますが、その過程で文脈を誤解したり、存在しない事実を断定的に提示したりすることがあります。
これにより、誤った医療情報や危険なアドバイスが拡散するリスクが指摘されています。AIの回答を鵜呑みにせず、必ず情報源のリンクを確認するリテラシーがユーザーには欠かせません。一方のサイト運営者側は、AIに誤解されないよう、正確で構造化された情報を提供し続けることが重要となります。
著作権やコンテンツの盗用リスク
AI Overviewsは既存のWebサイトのコンテンツを学習・要約して回答を生成するため、著作権や盗用の問題が懸念されます。AIが生成した文章が元のコンテンツの表現や構成に酷似している場合、著作権侵害と見なされる恐れがあります。
また、サイト運営者にとっては時間とコストをかけたコンテンツがAIに要約され、ユーザーが自サイトを訪れなくなるという懸念があります。これは、トラフィックや収益機会を奪われる「ただ乗り」のリスクに直結します。
プライバシーに関する懸念点
AI Overviewsの進化は、プライバシーに関する新たな懸念を生じさせます。とくにパーソナライズが進むと、AIはユーザーの過去の検索履歴や位置情報、さらにはGmailの内容など、Googleエコシステム内の膨大な個人データを参照して回答を生成する可能性があります。
ユーザー自身が気づかないうちに、非常にプライベートな情報がAIの学習や回答生成に利用されるリスクがあるのです。データの利用範囲や透明性の確保、ユーザーが自身の情報をコントロールできる仕組み作りが強く求められます。
AI Overviewsの今後のアップデート予想
今後のAI Overviewsは、「高度なパーソナライズ」と「マルチモーダル化」が進化の軸です。単なる検索語だけでなく、あなたの検索履歴や位置情報から意図を汲み取り、「あなただけの答え」を生成するようになります。
また、テキストだけでなく画像や動画の内容を直接理解し、それらを組み合わせて視覚的で分かりやすい回答を提示してくれるようになるでしょう。
こうした未来に適応するため、今からサイト上のテキスト以外の資産をAIが理解できる形に整備することが重要です。具体的には、以下のような対策が不可欠となります。
- 動画に詳細な説明や字幕を付ける
- 画像内容を具体的に説明する代替テキスト(altテキスト)を設定する
検索結果の多様性が失われるリスク
AI Overviewsが検索結果の最上部に単一の「答え」を提示することで、情報の多様性が失われるリスクがあります。
従来、ユーザーは複数のWebサイトを比較検討し、多様な視点や意見に触れることができました。しかし、AIが生成した要約で満足するユーザーが増えると、特定の有力なサイトの情報ばかりが参照されます。ニッチなサイトや新しい視点を持つブログなどは、ユーザーの目に触れる機会が減少してしまいます。これにより、情報のエコーチェンバー化が進む可能性が懸念されるのです。
AI Overviewsに関するよくある質問
AI Overviewsに関してよく寄せられる質問を紹介します。
AI Overviewsの回答は常に正しい?
常に正しい保証はありません。引用元に基づき生成されますが、生成AI特有の誤り(ハルシネーション)の可能性があるため、複数の引用元を確認することが推奨されます。
詳しくは、記事内の「AI Overviewsの基本的な使い方」で解説しています。
AI Overviewsはすべての検索で表示される?
AI Overviewsはすべての検索時に表示されるわけではありません。AI Overviews(AIによる概要)の表示は、ユーザーの検索意図とクエリの種類によって制御されています。GoogleはAIが回答することがユーザーにとって本当に役立つ場合にのみ、AI Overviewsを表示するよう調整しています。
詳しくは、記事内の「AI Overviewsの表示パターン」をご覧ください。
自分のサイトがAI Overviewsに引用されているか確認する方法は?
自分のサイトがAI Overviewsに引用されているかを把握するには、手動で検索して引用元を目視で確認する方法があります。
詳しいやり方は、記事内の「AI Overviewsの表示パターン」をご確認ください。
まとめ
AI Overviewsの登場によって検索エンジンの使い方そのものが大きく変わりつつあるため、従来のSEO戦略や広告戦略の見直しが求められています。
とくに重要なのは、AIには要約できない「独自性」と「体験価値」をコンテンツに持たせることです。一次情報や専門的な洞察、ブランド独自の世界観を提示し、ユーザーに「このサイトを直接訪れたい」と思わせることが、これからのマーケティングを成功させる鍵となります。
この変化を脅威と捉えるのではなく、自社の強みを再定義し、ユーザーとの新しい関係を築く好機と捉えて戦略的に取り組んでいきましょう。

執筆者
生成AIエンジニア / Webマーケティング・生成AI講師
シバッタマン(柴田義彦)
Webマーケティング講師 兼 生成AIエンジニアとして、GA4×BigQueryで計測設計と分析基盤を構築します。研修と伴走で自走化を促進し、広告・SEO・CRMを成果につなげます。
LATEST
最新記事
TAGS
タグ






























