
受注率が伸びない本当の理由とは?マーケティング施策が営業成果につながらない設計ミス
※株式会社エッジコネクションより寄稿いただいた内容を掲載しています。
「商談数は目標を達成しているのに、なぜか売上につながらない」
マーケティング施策を強化し、順調にリード(見込み顧客)が増えている企業ほど、この「受注率の停滞」という壁に突き当たります。
多くの現場では、受注に至らない原因を「営業個人のスキル」や「リードの質」に求める傾向にあります。しかし、真の問題はそこではありません。商談が発生した後の「プロセスの設計」に隠れているのです。
本記事では、商談数が伸びても受注につながらない企業に共通する「商談後プロセスの設計ミス」を整理し、マーケティング・インサイドセールス・営業がどのように連動すれば商談を受注に近づけられるのかを具体的に解説します。
目次
商談数は増えたのに、なぜ受注が増えないのか
マーケティング施策を強化して商談数は明らかに増えたのに、受注が伸びない――。これは、多くの企業から実際によく聞く声です。
さまざまなコンテンツマーケティング施策を通じてリードを獲得し、KPIとして設定した商談数も達成しているのに、売上や受注件数には結びつかない……。このギャップに、違和感や行き詰まりを感じている経営者や営業責任者は少なくありません。
この状況で起こりがちなのが、「商談を作ること」自体がゴールになってしまっているという問題です。本来、商談は受注までのプロセスの一部に過ぎません。
しかし、商談数が評価指標として強く設定されていると、いつの間にか「商談を獲得した時点で目的は果たされた」という空気が生まれます。その影響で、商談の質やその後の営業プロセスとの接続が十分に設計されないまま、リードが営業現場に渡されます。
そして、そのしわ寄せを受けるのが営業現場です。営業はこのような温度感の分からない商談や背景情報が不足した案件、なぜ自社に興味を持ったのかが見えない顧客に対して、ひとつずつ対応しなければなりません。結果として、営業担当者は「数は多いのに決まらない」商談の対応に追われ、疲弊していきます。努力が成果に結びつかない状態が続けば、モチベーションや生産性が下がるのも無理はありません。
これらの問題の本質は、マーケティング施策の良し悪しや営業個人の力量ではありません。「商談の“その後”をどう設計しているか」に目を向けなければ、商談数が増えても、受注は増えないままです。
商談後に起こりがちな3つの「設計ミス」
マーケティング施策によって商談数は増えているのに、営業成果につながらない企業では、共通して「商談後の設計」に歪みが見られます。
まずは、商談後に起こりがちな3つの設計ミスについて解説します。
1. 情報が営業に引き継がれないまま、商談が始まっている
とくに多いのが、役割分担や情報の引き継ぎが曖昧なまま、商談が営業に渡されてしまうケース。これは一見すると連携しているようで、実際にはプロセスが分断されている状態と言えます。
マーケティングやインサイドセールスの段階で、顧客は資料請求やセミナー参加など、複数回の接触を経て商談に至っています。しかし、その過程で得られた課題意識や検討背景、関心テーマなどが、営業側に十分に共有されていないケースもあるのです。
このような場合、営業は初回商談であらためて基本的なヒアリングから始めなければならず、顧客から「同じ話を何度もさせられている」という印象を持たれてしまいます。
2. 商談の温度感が正しく伝わらない
「商談」と一口に言っても、「今すぐ導入を検討している顧客」と「情報収集の延長線上で話を聞いてみたいだけの顧客」では、対応の仕方は大きく異なります。
しかし、商談の基準や定義が曖昧だと、営業側はすべてを同じ熱量で対応せざるを得ません。なぜなら、「本来なら提案に力を入れるべき案件」と「まだ関係構築やナーチャリングが必要な案件」が混在し、優先順位の判断が難しくなってしまうためです。
3. 商談後の判断やフォローが営業任せになっている
情報共有や判断基準が整っていないということは、商談後のフォローや提案内容の調整、検討状況の見極めといった設計が不十分であることを意味します。そのため、本来はマーケティングやインサイドセールスと連携すべき部分まで、すべて営業の裁量に委ねられてしまうでしょう。
このような場合、成果は個人の力量や経験に依存しやすくなり、受注率にばらつきが生じます。「再現性のある成果」が出ないのは、営業個人の問題ではなく、仕組みとしてそうなっているからです。
成果が出る企業の「商談後」プロセス設計
前述した3つの設計ミスに共通しているのは、「商談したら次は営業」という単純なバトンパスでプロセスを終わらせている点です。商談はゴールではなく、あくまで通過点。その後の動きをどこまで具体的に設計できているかが、マーケティング施策を営業成果につなげられるかどうかの分かれ目になります。
商談数が増え、かつ受注率も安定して高い企業には、明確な共通点があります。
それは、商談後のプロセスが「マーケ・インサイドセールス・営業」をまたいで一貫して設計されていること。商談を境目に分業で切り替わるのではなく、受注までをひとつの流れとして捉え、各役割がどう連動するかが言語化されています。
では、成果が出ている企業において、商談後プロセスが具体的にどのように設計されているのでしょうか。ここでは、とくに成果の差を生みやすい4つの設計視点に絞って整理します。
1. 商談前後をつなぐ情報設計がある
成果が出ている企業では、商談に至るまでの接点履歴や顧客の反応、課題感の仮説が、営業にとって「使える情報」として整理されています。
これは単なる行動ログではありません。「なぜ問い合わせたのか」「どの情報に反応したのか」「何に迷っていそうか」といった文脈まで共有されているため、営業は初回商談から的外れのない会話が可能になります。
これによりヒアリングの精度が上がり、顧客側の納得感も高まるのです。
2. 営業が迷わず動ける判断軸が用意されている
成果が出ていない企業では、営業が毎回ゼロベースで考え、判断しなければならない場面が多くなりがちです。
一方、成果を出している企業では、商談後の次アクションや判断基準がある程度型化されています。たとえば、温度感に応じたフォローの方向性や、提案に進む条件、再ナーチャリングに戻す判断などが明確です。
営業は「次に何をすべきか」で悩む必要がなくなり、案件を前に進めるための戦術に集中できるようになります。
3. 受注までをひと続きのプロセスとして設計している
成果を出す上でもっとも重要なのが、受注までを「ひと続きのプロセス」として設計することです。
これは、商談・提案・見積・クロージングをそれぞれ独立した工程として扱うのではありません。「どこまで合意できていれば次に進めるのか」を明確にした上で、受注に至るまでの道筋をひとつの流れとして設計していきます。
そのため商談段階で確認すべき論点や合意水準が定義されており、前段階で条件を満たしていなければ次の工程には進まない設計になっています。結果として、案件が「なんとなく前に進む」ということがなくなり、各ステップでやるべき、あるいは次に取るべきアクションが自然と明確になるのです。
4. 共通プロセスを前提に、チーム全体で改善が回っている
営業担当者全員は、前述の「受注までをひと続きのプロセスとして設計している」ことを前提に動いています。これにより、「次のステップに進むために、どのやり方が最適か」を、チーム全体で議論できるようになるのです。
その結果として営業チームとしての学習スピードが格段に速まるとともに、ノウハウの共有が進みます。誰かが効果的なやり方を見つけたら、それがチーム全体の取り組み内容に一気に派生します。個々人がそれぞれのやり方で営業をしている組織では、このようなことは起こりません。
このように、成果が出る企業は「商談を作ること」ではなく、「商談からどう受注に近づけるか」を起点に設計しています。商談後のプロセスを曖昧にしないことが、マーケティング施策を本当の意味で営業成果につなげる鍵となるのです。
ナーチャリング設計と営業成果をつなぐ視点
ここでは、ナーチャリングで高めた関心が、なぜ営業成果につながらないまま失われてしまうのか、その構造を整理します。
「営業に渡して終わり」が、顧客の温度感を下げてしまう
前回のテーマでも触れた通り、ナーチャリングは「リードを温めるための施策」ではなく、「次のアクションにつなぐための設計」であるという認識が重要です。
にもかかわらず、多くの企業ではナーチャリングによって一定の反応が得られた時点で、「営業に渡して終わり」になってしまっています。この瞬間に、せっかく高めてきた温度感が失われてしまうケースは少なくありません。
成果を阻むのは、部門間に生じる「意図の断絶」
成果が出ない理由のひとつは、ナーチャリングと営業の間に“意図の断絶”がある点です。
マーケティングやインサイドセールスは「関心は高まっている」と判断して商談していても、営業はその背景やプロセスを十分に理解せず商談に臨んだ場合について見ていきましょう。
この場合、結果として「顧客が関心を持ったテーマ」と「営業が話す内容」にズレが生じ、「思っていた内容と違う」と相手に感じさせてしまいかねません。
インサイドセールスは、情報を営業へつなぐ「翻訳者」
ここで重要な役割を果たすのが、インサイドセールスです。インサイドセールスは単なる“商談獲得部隊”ではなく、ナーチャリングで蓄積した情報を営業につなぐ“翻訳者”であるべきです。
顧客がどの段階にいて、何に期待し、どこに不安を感じているのか――。その整理ができて初めて、営業は効果的な次の一手を打てます。商談設定の可否だけでなく、「今、営業が入るべき理由」を明確にすることが成果を左右するポイントです。
なお、ナーチャリングは商談を作るための前工程ではありません。受注までのプロセス全体を前に進めるための一部と心得ておきましょう。その視点で設計されてこそ、マーケティング施策は営業成果として結実します。商談につなぐ「その瞬間」が、もっとも設計が問われるポイントなのです。
まとめ|商談はゴールではなく「通過点」
商談はマーケティング施策の成果を測る上で重要な指標ですが、それ自体がゴールではありません。商談はあくまで受注に至るまでのプロセスの一部であり、そこから先をどう設計するかによって、成果は大きく変わります。商談数が増えているのに受注が伸びない企業ほど、この前提が見落とされがちなのです。
マーケティング施策が営業成果につながらない背景には、「役割は分かれているが、成約に向けての意図や狙いはつながっていない」という構造的な問題があります。マーケティング、インサイドセールス、営業がそれぞれのKPIを追う中で、商談の先にある受注までの道筋が曖昧になってしまう――。その結果、営業現場に負荷が集中し、疲弊や成果のばらつきが生まれてしまいます。
一方、成果を出している企業は、商談後の動きを起点に全体を設計しています。どの情報を、どのタイミングで、どの役割が引き継ぐのか。どの状態になったら営業が入り、どこでナーチャリングに戻すのか。こうした判断基準が共有されているからこそ、商談は「受注に近づくための通過点」として機能します。
マーケティング施策を本当の意味で成果に変えるために必要なのは、新しいツールや施策を増やすことではありません。商談のその先までを含む、一貫したプロセスの設計です。「商談をゴールにしない」という視点を持てるかどうかが、マーケと営業の連携を“機能するもの”に変える分かれ道になるでしょう。
LATEST
最新記事
TAGS
タグ










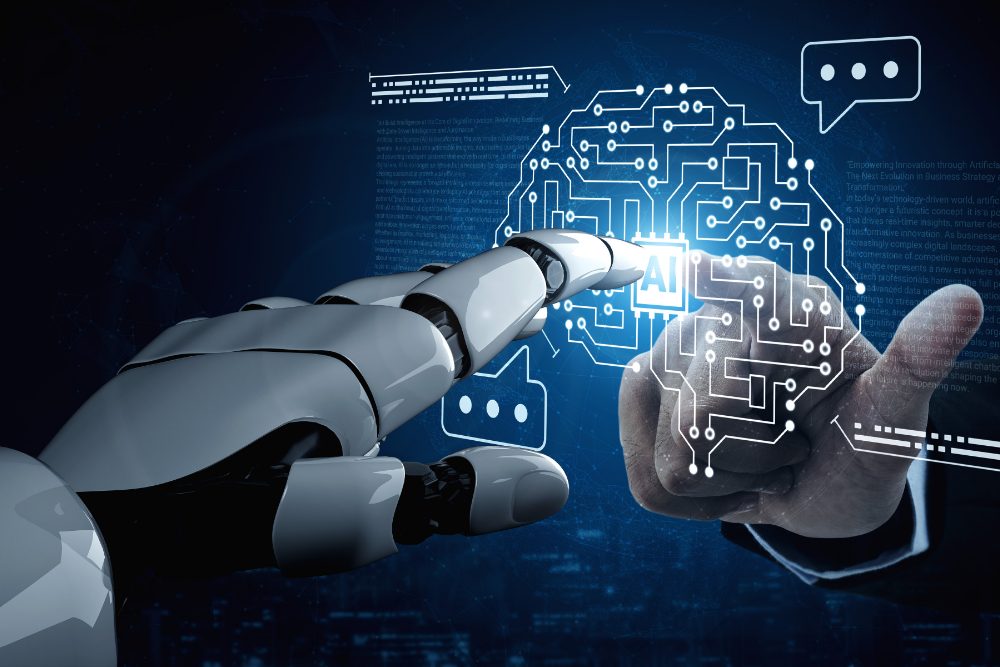




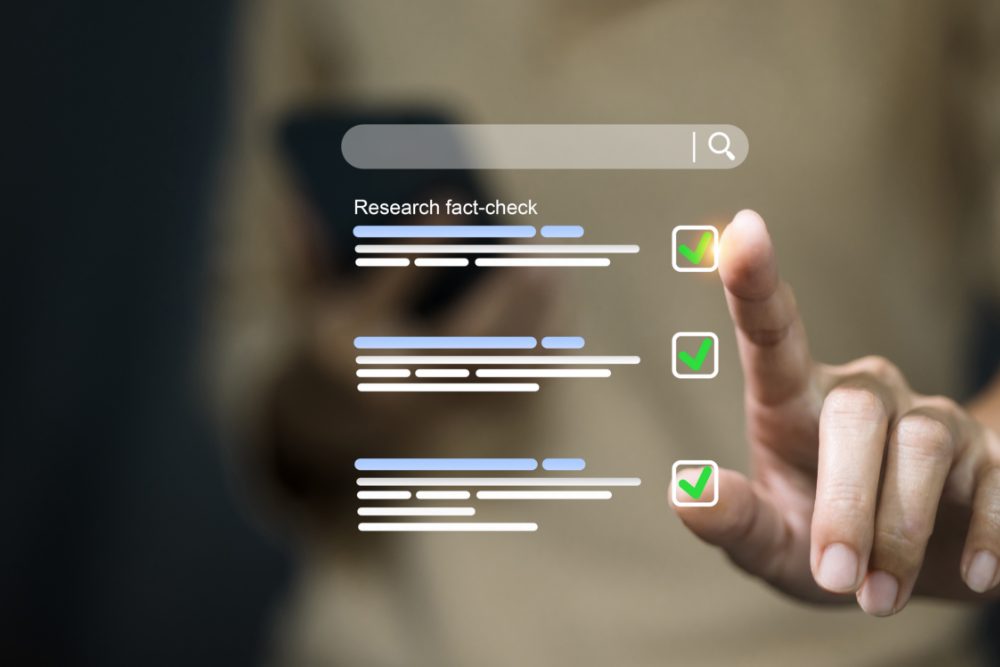










_s-1-1-1.jpg)


