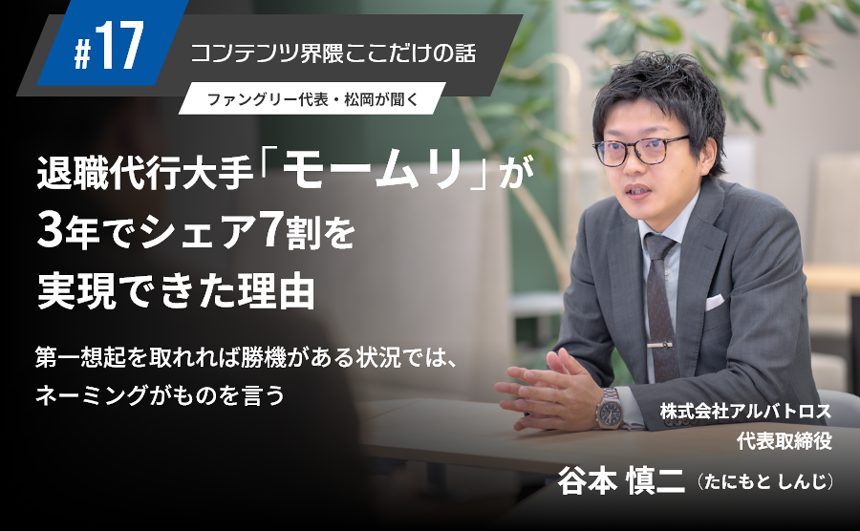Interview
# 24
ファン増と離職防止を同時に実現するカラダファクトリーの個店マーケティング|チェーン店でもパーソナライズされたサービス価値の追求を
株式会社ファクトリージャパングループ
代表取締役社長
髙橋 健介(たかはし・けんすけ)
コンテンツプロデュースカンパニーとして、企業のコンテンツマーケティングやブランディング活動を伴走支援する株式会社ファングリーの代表・松岡でございます。
「コンテンツ界隈ここだけの話」、第24話のゲストは、整体×骨盤サロン「カラダファクトリー」を国内外で320店舗以上展開する株式会社ファクトリージャパングループの代表・髙橋健介さんです。
競合が多く、離職率が高いという市場環境の中、2024年5月から経営の舵を取っている髙橋さん。会社の成長と従業員の満足度向上を両立するために変えたもの、変えなかったものとは――。功を奏しているファンマーケティングやインナーブランディングの各種施策について、詳しく伺いました。

株式会社ファクトリージャパングループ
代表取締役社長
髙橋 健介(たかはし・けんすけ)
大学卒業後は大手総合商社で海外営業に携わり、「経営を学びたい」との思いから外資系経営コンサルティング会社へ転職。経営課題の改善に関するさまざまなプロジェクトに従事する。2008年に独立し、地域活性化コンサルティング会社を起業。その後、フィットネスクラブやヘアサロンチェーンの代表を歴任し、2024年5月から株式会社ファクトリージャパングループの代表取締役社長を務める。

最も大きかった課題は、「チェーン化が進み過ぎたこと」
──本日は取材をお受けいただきありがとうございます。早速ですが、まずは髙橋さんの自己紹介をお願いします。
ファクトリージャパングループの代表に就任したのは昨年の5月です。なので、ちょうど1年くらいになりますね。
大学卒業後に総合商社でビジネスのいろはを学び、その後アメリカにある経営コンサルティング会社に転職。そこで十数年勤務した後、独立してコンサル会社を設立しました。
──フィットネスやヘルスケアの領域にずっと携わっていたわけではないんですね。
現在の事業に近い領域に足を踏み入れたのは、コンサル会社時代にクライアントから頼まれて、あるフィットネスクラブの経営に参画したときが最初ですかね。その会社は一定期間後に退任し、別の会社の経営に参画――というのをいくつか経験しています。直近では、全国180店舗ほどの美容室を運営する会社の代表を7年くらい務めました。
──その後、現職に就任したという流れでしょうか。プロ経営者的なキャリアですね。
そうです。前職を退任するタイミングで、ファクトリージャパングループから経営参画の提案をいただきました。
先ほど「現在の事業領域にずっと携わっていたわけではない」というお話をしましたが、コンサルファームというのは基本的に自分自身で専門性を磨き作っていくところなんです。私はもともと業界再生やM&Aの分野にいて、そこで飲食店やホテルといったホスピタリティ業界の状況や人が介在するサービスの面白さを知りました。
──美容院も店舗ビジネス、いわゆるローカルビジネスという意味では共通しています。
そうですね、そのほかにも美容室と整体にはものすごく大きな共通点があって。それは施術家、いわゆる職人がサービスの価値を提供しているところです。職人が価値を生めば生むほどお客様に喜んでいただけて、その後の集客にもつながり、会社が成長できるという構造になっています。
──確かに、先ほどお話があった「人が介在するサービス」という部分は共通ですね。髙橋さんが1年前に代表に就任してから、どんなことを変えていったのでしょうか?
「変えてはいけないこと」と「変えるべきこと」がそれぞれありました。前者に関しては、一番は技術に対するこだわりです。当社には1,400人を超える施術家がおり、価値提供の源泉である彼ら全員への技術教育に注力しています。実施している研修プログラムは計500時間で、同業の会社さんより圧倒的に教育コストをかけていると思います。お客様の健康と予防意識を広めていくことが会社の成長に欠かせないので、教育は今よりむしろ強化していきたいくらいですね。
その一方で、最も大きかった課題は「チェーン化が進み過ぎたこと」です。
──具体的に教えていただけますか?
「カラダファクトリー」では、全国どこのお店に行っても得られる満足感・安心感をお客様との約束事として掲げています。ではその満足感はどうやって得られるのか――という問題になるわけです。お客様によって来店の目的は違う。体の状態も異なる。そんな中で均一化されたサービスを提供しても、満足につながらないじゃないですか。

だからこそ「カラダファクトリー」では、チェーン店でもサービスの中身はフルカスタムであることを大事にし、パーソナライズされたサービス価値を追求したい。その結果、店舗ごと、施術家ごとの個性がない状況は避けるべきという判断をしました。
──なるほど、それは大きな戦略方針の変更ですね。
この方針変更は、お客様だけでなく施術家にとってもメリットがあると思っています。
施術家はスキルが身に付くと、「お客様のためにもっと上質なサービスを」と考え、いろいろやりたくなってしまうものなんです。ただ、柔道整復師や鍼灸の資格を持っていても会社のマニュアル上使えないというケースはあります。そこにやりにくさを感じている施術家も少なくありません。当社ではそういった視点も踏まえて、個々の技術を活かせる余地を広げているところです。
──「脱・マニュアル化」の方針によって、同じブランドの店舗でもさまざまなカラーが出てきそうですね。
はい。店舗ごとの個性という点で特徴的なのが秋葉原店です。特徴的というか、“特殊”と言えるかもしれません。
ご存知の通り、秋葉原はさまざまな愛好家やアニメの街です。来店されるお客様にもアニメ好き、サブカルチャー好きの方が多くいます。そこで「カラダファクトリー」では、秋葉原店を愛好家やアニメ・ゲーム好きしか働けない店舗にしました。
──なるほど(笑)。そこまで大胆にやると、スタッフ側から自発性や独自性が生まれてきそうです。
店舗を運営するのは、手を挙げてくれた熱心な有志5~6人です。担当ベッドスペースに推しのフィギュアを置いたり、ポスターを貼ったりしても良いというルールにしています。施術家側は趣味の会話をしながら60分や90分を過ごせて、お客様にとっては新たな居場所になる可能性がある。どちらにも特別感がある、秋葉原の店舗ならではの取り組みと言えるかもしれません。
──他の地域の店舗と違うデザインが採用されている京都のスターバックスみたいですね。「そこでしか得られない体験価値」があれば、それがその店に行く動機になります。
おっしゃる通りです。秋葉原店では「ペンライトを持つ手が疲れないハンドマッサージ」など、通常店舗とは違うメニューも考えています。まだグランドオープン前(2025年5月時点)ですが、パブリシティ効果も期待できそうです。「脱・マニュアル化」の成功例としたいですね。

お客様優先主義ではあっても、施術家ファースト経営ではなかった
──髙橋さんが目指す経営の方向性を教えてください。
ひと言でまとめるなら、CX(顧客体験)とEX(従業員体験)の両立です。会社の成長や売上アップを考えたとき、軸となる考え方に「顧客中心主義」があります。顧客中心主義では「お客様といかに長期的に関係を維持できるか」が重要で、そのカギとなるのが施術家です。
そこで私は、施術家ファーストの経営を徹底することにしました。すなわち、従業員の満足度を追求し、「最高の環境を作って従業員もお客様も喜ばせよう!」というのが当社の戦略の大まかな方向性ですね。
──施術家ファーストの施策として、具体的にはどのようなことに取り組みましたか?
先ほど少し触れた人事制度の変更もその一つです。どれだけ価値を創っても、給料が上がらなければモチベーションになりません。他にも、サービス業なので土日に休めない問題、年齢が上がるほど体力的につらくなる問題などがあります。以前の制度ではこうした点が考慮されていませんでした。お客様優先主義ではあっても、施術家ファースト経営ではなかったんです。
こうした課題に向き合い、人事制度の刷新や働き方の見直しを行いました。当初は「技術ランク」が上がっていくと給料が上がるという仕組みだったのですが、これをファン(指名顧客数)が多い人ほど給料が多くなる仕組みに変えています。「稼ぎたい」「自分が良いと思った施術を提供したい」という施術家の思いを実現できれば、離職者は出ないと考えました。
──ちなみに、サービスを提供する施術者の離職率は業界的に高いのでしょうか?
当社は業界の中では平均的な部類だと思いますが、異業種から来た私から見ると高いですね(汗)。先ほどお伝えしたように当社は先行投資(技術教育)にかなり力を入れているので、すぐに辞めてしまわれると厳しいです。
──となると、「離職率の改善」と「サービス体験価値の向上」の両立は優先度の高いテーマになりますね。
はい。そういった背景もあり、私がジョインしてから社内改革を行いました。入社後数ヶ月は現状調査を行い、続く3ヶ月で情報を整理。管理職の意識改革を進めた上で、本部長以上に対しては認識のすり合わせや経営方針の共有を行い、担当領域における具体的なアクションプランの整理を求める――というのが、最初の半年で取り組んだアクションです。
当社は1月が期初なのですが、そのタイミングで中期経営計画の提示やブランドプロミス、「どういう体験価値を提供していくか」などをトップダウンで作成し、全社共有しました。人事制度の変更など、できたところから順々にローンチしているところです。
──「辞める理由」を潰しながら、同時に業績を伸ばしていく仕組みを作っていったわけですね。そこはさすが外資系のコンサル出身経営者、という感じがします。
改革はまだ途中段階ですが、うまくいけば年収1,000万円プレイヤーを何人も出せると思っています。創出した価値によって高い報酬をもらえるようになり、キープレーヤーが報われる仕組みを作っていきたいですね。
あと、「1回限りのお客様」を増やしたいわけではないので、そうした当社のビジョンと合致しないメニューやキャンペーンはやらない方針にしています。
──全国に店舗があり、1,400人以上の従業員がいる中で、インナーブランディングの浸透施策はどのように行っているのでしょうか?
ビジョンなどの施策を動画化・テキスト化し、社内ポータルで全員が見られるようにしました。また、いろんな店舗に私が出向き、ミーティングで繰り返し思いを伝えるという活動もしています。細かい部分では、全スタッフと各上長による1on1のやり方も変えました。これまでの「上位方針やミッションを部下に伝えるだけの場」から、「自分がどうなりたいかを相談し実現するための機会」にしたんです。
──それは素晴らしいですね。それが本来の1on1の姿とも言えますし、「ウチで続ければこんなキャリアも実現できるよ」という提案もしやすくなります。
今では、独立も奨励しています。「独立するなら貯蓄もしないとね」とか「3年後までに目標額を貯めるためにこんなことをやっていこう」といった話もするようになりました。

セルフプロデュースの支援は、ファンマーケティングにもつながる
──先ほどあった「そこでしか得られない体験価値」について、他にはどのような取り組みをされていますか?
重視しているのは「個店マーケティング」です。例えば、年配の方が比較的多い商店街の中にある店舗では待合スペースを休憩場所として使ってもらっても良いようにするなど、店舗や地域に合ったファンとの向き合い方を推奨しています。
他には、来店された方との会話の内容などを電子カルテで管理し、次回以降の来店時に会話のキャッチボールができるだけ続くような仕組み作りもしています。
──自分のことをわかってくれている先生がいれば通いやすいですよね。ちなみに、新規顧客はどのように集めているのでしょうか?
もちろんホットペーパーなどの広告も使っていますが、ショッピングモールなどのテナント店舗が多いので、泥臭く施設内でのチラシ配布などもやっています。
──なるほど。王道は王道でしっかりやる、大事ですよね。デジタルコミュニケーションは積極的にやられていますか?
アプリを運用しています。ダウンロード率は結構高いですね。現在はリピーターの約80%の方がアプリを通して予約してくれています。アプリでは何回来店されたかが見えるようになっていて、ユーザーの約85%がリピーター、うち60%が5回以上の継続ユーザーです。特にその中でも累計50回以上来てくれているお客様の割合が多いのが特徴です。
あとは、写真を通して姿勢の良し悪しを客観的に把握できる撮影アプリなども使っています。アプリから取得した顧客リストは本部でフォローしており、休眠顧客をすくう取り組みも行っています。店舗では手の届かないところを本部がデジタルでフォローするイメージですね。
──本部側の機能という部分で、各店舗の成功事例を紹介する仕組みもあるとお聞きしました。
「匠の技コンテスト」という、技術的に優れた施術家を表彰する社内イベントが年1回あります。また、月1回開催のエリアミーティングでは、良かった取り組み事例を共有してもらい、各店舗運営の参考にしてもらうようにしています。

──「匠の技コンテスト」で優勝すると、どのような良いことがあるのですか?
コンテストの優勝者やエキスパート(施術家ランクの上位者)は、自店舗で自分が名前をつけた施術メニューを出すことができます。ちなみに、料金を設定するのも自分です。申請書を会社に提出してもらい、技術部門トップの決裁があればOKという形にしています。
──独自メニューを開発できるのは面白いですね。現状、何店舗くらいが独自のメニューを出しているのでしょうか?
現時点(2025年5月)では36店舗です。技術ランク上位者のスタッフが面白がってメニュー開発に取り組んでくれているので、後輩スタッフのモチベーションも高いと聞いています。
また、エキスパートはユニフォームのカラーも別にしています。通常は白衣で、エキスパートは黒衣。1人だけ黒いユニフォームを着ているととても目立つので、本人たちのやりがいにもなっているようです。こうしたセルフプロデュースの支援は、ファンマーケティングにもつながると実感しています。
──最後に、今後の展望・やりたいことについても教えていただけますか?
運営しているいくつかブランドを、形を変えながら発展させていきたいと考えています。例えば他社さんの店舗内でスペースをいただき、サービスを提供するなど。コンビニ、フィットネスクラブ、薬局など、コラボレーションにはさまざまな可能性があると思うので、より広い層に届けていきたいですね。ゴルフ練習場なども良さそうです。
事業がダイナミックに広がっていくのが次のフェーズだと考えており、2年くらいかけて事業展開の下地をしっかり固めていければと思っています。
──なるほど。健康志向の高まりでヘルスケア市場は追い風ですから、多角的な展開ニーズがありそうですね。
それともう一つ、トップアスリートのメンテナンスを任せていただけることもアピールしていきたいです。現在はフェンシングの選手、ブレイキンのナショナルチーム、ビーチサッカーチームなどで専任トレーナーをやらせていただいていて、合宿などに帯同する機会も多くあります。もともと競技者を目指していたスタッフも多いので、施術家としてアスリートに寄り添える環境を整えることは、キャリアの選択肢を増やす意味でも重要なのかなと。
──ヘルスケアやウェルネス市場は年々拡大しています。今後はさらに競合も増えてくると予想されますが、そうした中、髙橋さんの経営手腕によって「カラダファクトリー」やファクトリージャパングループが今後どんな展開を見せるのかますます楽しみです。本日はありがとうございました!
LATEST
最新記事
TAGS
タグ























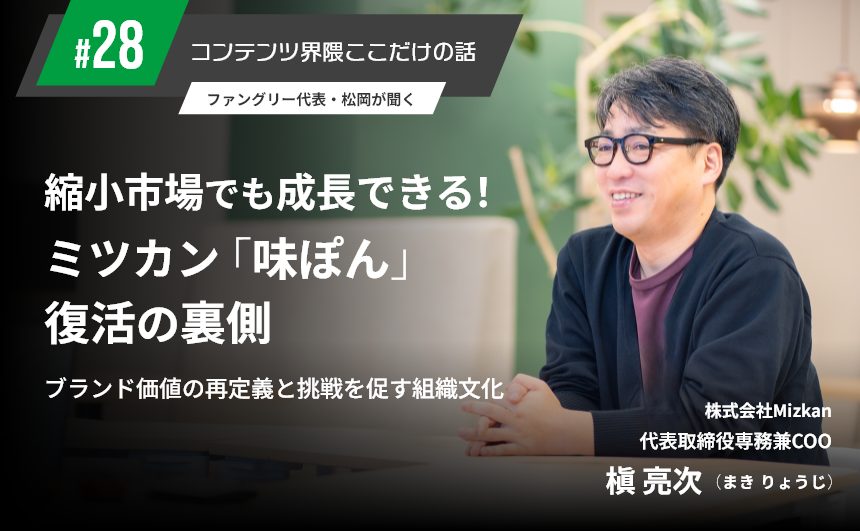




_s-1-1-1.jpg)