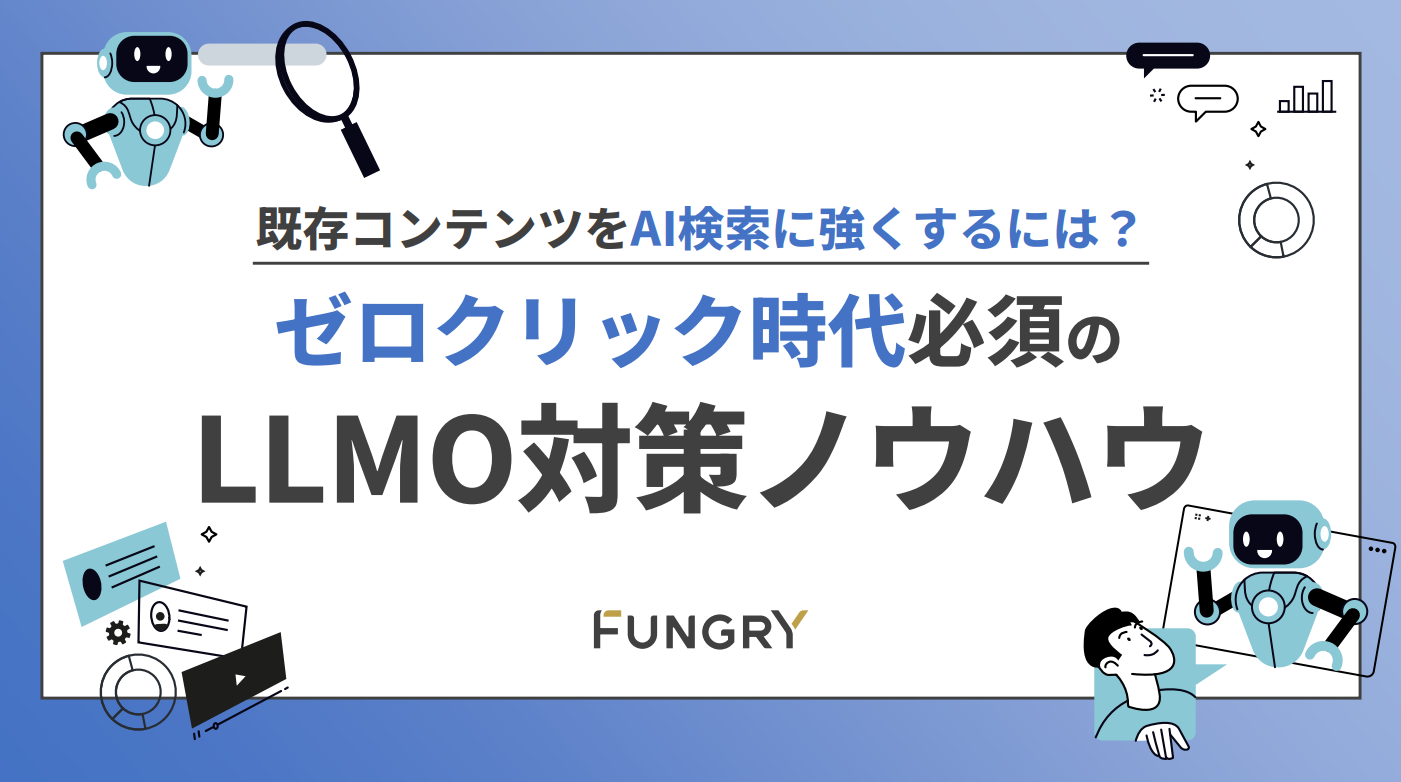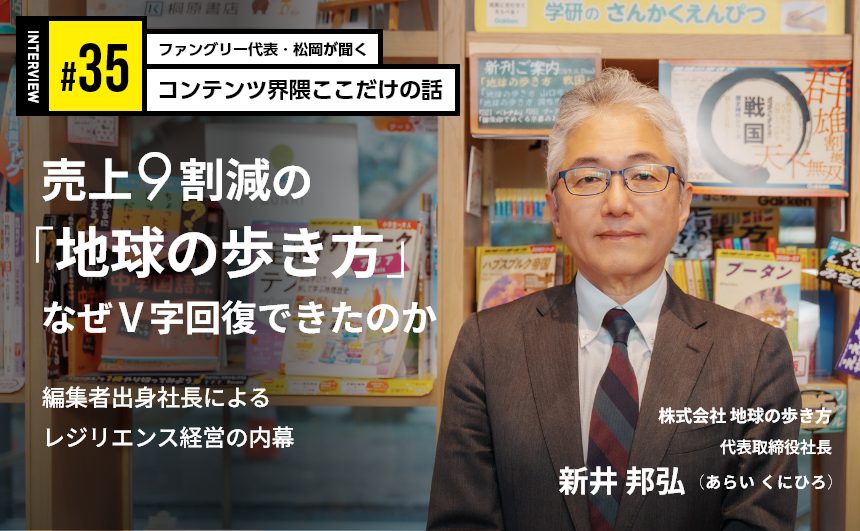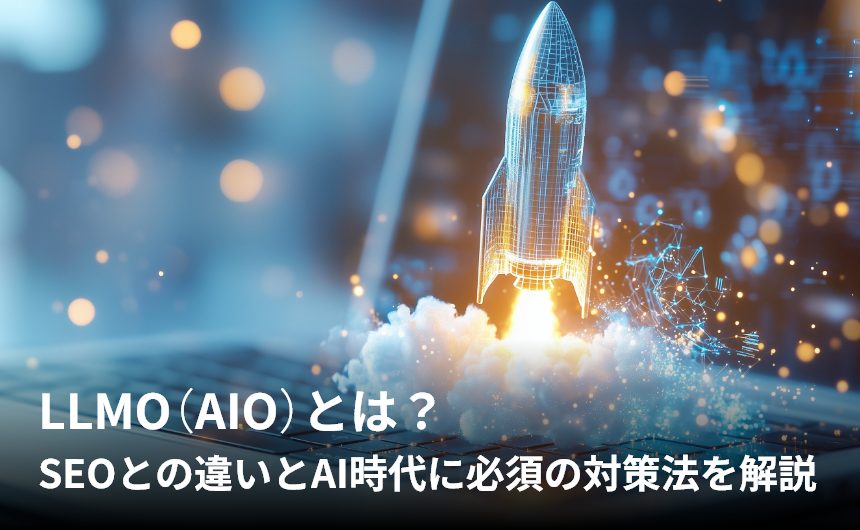
LLMO(AIO)とは?SEOとの違いとAI時代に必須の対策法を解説
LLMO(AIO)とは、生成AIによる回答に自社コンテンツが引用されるよう最適化を行う戦略およびWeb施策のことです。
従来のSEOでは「人の検索行動」を中心に、キーワード設計や構成を組み立てていました。これに対してLLMOでは、AIアシスタントがWeb上の情報をどう認識し、回答にどう反映させるかが重要視されます。つまり、ユーザーに見つけてもらうだけでなく、「AIに正確に引用されること」が今後のコンテンツ戦略の鍵となるのです。
本記事ではこうしたLLMO(AIO)の基本概念から、BtoBビジネスやオウンドメディア運営において実際に取り入れるべき対策、LLMOの実践ステップ、従来のSEOとの違いまで分かりやすく解説します。
この記事を最後まで読めば、AI検索時代のコンテンツ制作で重視すべきポイントがクリアになり、自社コンテンツの競争力を一歩先へ進めるためのヒントが得られるでしょう。
目次
LLMO(AIO)とは
LLMOとは、ChatGPTやGeminiなどのLLM(大規模言語モデル)を搭載したAIチャットツールが回答を生成する際に、自社のWebサイトが引用・参照されやすくなるよう最適化を図る戦略・施策の総称です。「大規模言語モデル最適化(Large Language Model Optimization)」の頭文字をとって「LLMO」と呼ばれています。
従来のSEO(検索エンジン最適化)がGoogleなどの検索結果で上位表示を目指すものであるのに対し、LLMOではユーザーがAIとの対話を通じて回答を得るという「新しい情報取得の形」に対応します。
こうしたAIチャット型の「回答エンジン」に最適化する手法は、「AI Optimization(AI最適化)」を略して「AIO」とも呼ばれ、LLMOとほぼ同義で扱われることが一般的です。検索から生成AIとの対話に移り変わりつつある時代のなか、生成AIの回答で自社コンテンツが引用・参照されることにより、ユーザーの認知度向上や新たな流入確保につながります。
LLM(大規模言語モデル)とは
LLM(大規模言語モデル)とは、膨大なテキストデータを学習し、人間のように自然な文章を生成できるAIモデルのことです。LLMは文章の要約や翻訳、質問応答、文章の校正・作成などさまざまなタスクを高精度にこなせるため、近年急速に注目度を高めています。
また、LLMは膨大なデータから文脈を読み取り、意味の通った回答を導き出す能力を持ちます。代表的なサービスとして挙げられるのがChatGPT(OpenAI提供)やGemini(Google提供)、Copilot(Microsoft提供)などで、いずれも業務効率化や情報収集、コンテンツ制作の現場で広く活用されています。LLMは今や情報社会のインフラとして浸透しており、効率良くマーケティングコンテンツを制作するにあたってはLLMの活用が不可欠になっていると言えるでしょう。
LLMO(AIO)とSEOの違い
LLMOとSEOは、どちらも自社の情報をインターネット上で適切に露出させるための施策です。その点では共通していますが、対象とするエンジンや目的、評価基準、ユーザー行動には明確な違いがあります。
LLMOとSEOの主な違いを表にまとめました。
| 項目 | LLMO | SEO |
|---|---|---|
| 対象 | 回答エンジン(ChatGPT、Geminiなど) | 検索エンジン(Google、Yahoo!など) |
| 目的 | AIの回答に自社情報を引用・参照させ、認知度や信頼性を高める | 検索結果で上位表示させ、サイトへのトラフィック(流入)を増やす |
| 評価基準 | LLMの学習データ・アルゴリズム(情報の正確性・網羅性・独自性) | 検索エンジンのアルゴリズム(E-E-A-T、被リンクなど) |
| ユーザー行動 | 質問を投げかけ、AIが生成した単一の回答を参考にする | キーワードで検索し、複数のサイトを比較・検討する |
SEOは「検索される」ことを前提とするのに対し、LLMOは「AIに答えてもらう」といった体験に最適化するための取り組みです。今後は双方の特性を理解し、併用する戦略が求められるようになるでしょう。
▼ SEOについては以下記事で解説しているのであわせてご覧ください。
LLMO(AIO)の重要性
近年、ChatGPTやGeminiといった生成AIツールの利用が世界的に拡大し、情報収集のスタイルは「検索」から「対話」へと大きく変化しつつあります。
従来の検索エンジンでは、ユーザーが複数のサイトを比較して情報を取捨選択するスタイルが一般的でした。それに対して、LLMではユーザーが質問を投げかけるだけで、最適な回答がひとつにまとめられ提示されます。このような変化においては、「自社の情報がAIに引用されるかどうか」が、企業の認知度や信頼性向上の鍵となります。
LLMOに取り組むことで、AIの提示する選択肢としてユーザーの目に触れる機会が増え、比較検討の手間なく自社ブランドを認知してもらえる可能性が高まります。AIという中立的な存在から推奨されれば企業の専門性や権威性が強化され、ブランディング効果も期待できるでしょう。
さらに、AIチャットはこれまで検索に消極的だったユーザー層や異なるニーズを持つ潜在顧客との新たな接点にもなり得ます。なぜなら、キーワードが思いつかなくても話し言葉で気軽に質問できる上、「どちらが良い?」といった相談やアイデア出しなど、従来の検索では難しかったニーズにも応えられるからです。
このようにLLMOは単にSEOに代わる位置づけではなく、未来のユーザーとの接点を広げる新しい戦略的施策として、今後ますます重要性を増していくでしょう。
LLMの仕組み
LLMOを理解するには、まずその基盤となるLLM(大規模言語モデル)がどのように情報を収集・処理し、回答を生成するのかを知ることが重要です。LLMは単に質問に応答するだけでなく、質問の文脈を読み取った上で信頼性の高い情報をもとに自然な文章を生み出すといった高度な仕組みを持っています。
ここでは、その主なプロセスを3つのステップに分けて解説します。
1. クローリング・学習
LLMはインターネット上に公開されている膨大なテキスト情報をクローリング(自動収集)し、それらを学習データとして取り込みます。クローリング・学習の対象となるのは、ニュース記事や企業の公式サイト、論文、ブログ、SNS投稿などさまざまな情報ソース。とくに、信頼性や権威性の高い情報源が優先的に活用される傾向があります。
LLMは、収集したデータをもとに「次にくる単語は何か」という学習を行います。例えば「今日の天気は」という文章があった場合に、次に「晴れ」や「雨」といった単語が来る確率が高いことを、データの中から統計的に学ぶのです。
このプロセスを何百億というパターンの文章で繰り返すことにより、LLMは単語同士のつながりや文法、文章スタイル、文脈といった言語に関する複雑なルールを内部的に獲得します。この学習モデルが、あらゆる質問に答えるための基礎となるのです。
2. 質問の文脈理解
文脈の理解は、LLMがテキストを理解する上で不可欠な機能です。ユーザーから質問(プロンプト)が入力されると、LLMはまずその文章の文脈を理解しようとします。ここで行われるのが、文章を「トークン(最小単位の単語や文字)」に分解する処理です。
例えば「日本の首都について教えて」という質問は、「日本」「の」「首都」「について」「教え」「て」といったトークンに分解されます。このとき、LLMに搭載された「アテンション(Attention)機構」という仕組みが「どの単語がとくに重要か」を判断し、ほかのトークンとの関連性を解釈します。これにより、「何が」「何について」尋ねられているのかという文脈の核心を正確に捉えられるのです。
3.回答生成
最終的にLLM内部で処理していたトークンから、最も関連性の高い単語やフレーズを選択し、自然な文章にまとめて回答を生成します。
回答を生成する際には情報源の網羅性・正確性・独自性が重視され、とくに公式情報や専門性の高いコンテンツが優先的に参照されやすいとされています。そのため、企業がLLMOを意識して情報発信を行うことで、AIの回答精度に間接的に影響を与えることが可能です。
LLMO(AIO)のアプローチ
LLMOのアプローチ方法としては、「間接的LLMO」と「直接的LLMO」の2種類があります。いずれもAIチャットにおける自社情報の最適表示を目指すという点では共通していますが、取り組み方や重視するポイントに違いがあります。
なお、これは従来のSEOにも通じる考え方であり、今後のWeb戦略において両アプローチのバランスが鍵となります。
間接的LLMO
間接的LLMOとは、LLMが学習する情報源であるWeb上の評価を高めることで、AIからの引用・参照を促すアプローチです。具体的な対策として、自社サイトのコンテンツを充実させ、専門性・網羅性・信頼性の高い情報を発信し続けることが挙げられます。
AIには、検索表示順位の高いコンテンツを優先的に参照する傾向があります。これは従来のSEO施策とも共通点が多いと考えられるため、「E-E-A-T」(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識したコンテンツ設計が必要です。
こうした間接的な取り組みによりAIが学習データとして自社サイトを高く評価する可能性が高まり、結果として回答文中での引用・参照につながります。
直接的LLMO
直接的LLMOは、LLMやAIシステムそのものに働きかけ、情報の理解や出力精度を高めることを目的とした施策です。例えばGoogleが提供する「Search Generative Experience(SGE)」のような生成AI検索への対応として、構造化データ(schema.orgなど)を活用して、AIがコンテンツの意味や関係性を正確に読み取れるようにする必要があります。
また、コンテンツ内のFAQの導入や、検索結果の右上部に表示されるナレッジグラフへの登録といった手法も、AIによる認識性を高める上で効果的です。こうした取り組みは、従来のSEOを超えた視点での「AIに読ませる情報設計」と言えるでしょう。
LLMO(AIO)の対策
LLMOの実践には検索エンジン最適化(SEO)と同様に、コンテンツ戦略と技術的な整備の両面からアプローチする必要があります。とくにAIは、明確な構造と信頼性のある情報を重視しており、その要求に応える形でWebサイトを最適化することが、AIからの引用・参照を促進する鍵となります。
ここでは「基本編」と「応用編」に分けて、LLMOに効果的な対策を紹介します。
【基本編】コンテンツ戦略
LLMOに対応する上でまず取り組むべきは、コンテンツの質や構成といった基礎部分の見直しです。基本編では、ユーザーにとって有益でかつ検索エンジンにも評価されやすいコンテンツをつくるための施策を紹介します。
E-E-A-Tの徹底強化
AIは人間と同様に、情報の発信元の信頼性や専門性を評価します。専門性(Expertise)、経験(Experience)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trustworthiness)の4つの観点がコンテンツの品質評価において重要な指標となるため、これらを高めるには以下の工夫が効果的です。
- 執筆者や監修者のプロフィールを明記し、実績や専門性を補強
- 独自調査やインタビュー、体験談の記載で「経験」を伝える
- 信頼できる外部リンクや参考文献の引用で客観性を担保
とくに医療や金融など専門性が求められるジャンル(YMYLジャンル)では、E-E-A-Tの強化が検索上位に直結します。
▼ E-E-A-TやYMYLについては、以下の記事をご覧ください。
網羅性と独自性の高いコンテンツ作成
LLMOは単なるキーワードの羅列ではなく、テーマに対する深さや広がり、そして視点のユニークさを重視します。そのため、以下を意識した構成が効果的です。
- 検索意図(テーマ)に関連する複数のトピックを含めて網羅性を確保
- 自社の事例、独自データ、インタビューなどによって独自性を付加
コンテンツ制作の際には他社の情報をなぞるだけでなく、業界独自のデータや自社ならではのノウハウ、具体的な事例などを盛り込むことで、AIが「価値のある情報源」と判断しやすくなります。
明確で論理的な文章構成
構成が整理され、文脈が一貫している文章は、人間にもAIにも理解しやすく、高く評価されます。ユーザーの離脱を防ぎ、AIがコンテンツの要点を正確に引用できるようにするには、以下の3つのポイントがとくに重要です。
1. 「結論ファースト」を徹底する
記事全体の冒頭(リード文)や各見出しの直下で、まず結論を提示しましょう。例えば「○○とは、~です」とユーザーの答えを最初に示し、その後に「この記事では〜を解説します」と続けることで、読者とAIの両方に内容が伝わりやすくなります。理由や具体例をその後に展開する「PREP法」を意識することが有効です。
2. Q&A形式を積極的に取り入れる
ユーザーがAIに投げかけるような具体的な疑問に答えるQ&A形式は、LLMO対策として非常に効果的です。AIはユーザーの質問に答える形で情報を参照するため、「○○とは?」「○○の方法は?」といった自然な疑問文を見出しにしたコンテンツは、回答の一部として引用されやすくなります。
3. 情報を視覚的に整理する
単なる文章の羅列ではなく、以下のように構造を分かりやすく示すことも重要です。
- 見出しの階層化:h2やh3などの見出しタグを正しく使い、情報の親子関係を明確にする
- 短い文章:一文を短くし、主語と述語の関係を分かりやすくする
- リストや表の活用:箇条書きや表を用いて情報を整理し、要点を視覚的に際立たせる
これらの手法は従来のSEO対策としても有効ですが、AIによる情報抽出が主流となるこれからの時代において、その重要性はさらに増していくと言えます。
【応用編】技術的な整備
前項で紹介したコンテンツ戦略を踏まえてより高度で技術的な整備を施すことで、LLMにアプローチしやすいサイトを構築できます。続いてはLLMOの応用編として、技術的・構造的な観点からの施策を紹介します。
構造化データの実装
構造化データとは、AIや検索エンジンがWebページ上の情報を理解できるように、HTML上で形式的に整理して意味づけを行うマークアップ(識別タグ)のことです。構造化データの実装によって、AIにテキストだけでなくその意味や文脈を明示的に伝えることが可能になります。
なお、構造化データの実装におけるLLMOでは、世界中の検索エンジンが共同で策定した共通語彙である「Schema.org」の埋め込みがとくに効果的です。以下にLLMOに有効なSchema.orgのプロパティをまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
▼ 記事(Article)に関するプロパティ
| プロパティ | 定義 | 効果 |
|---|---|---|
| headline | 記事のタイトル | 流入(クリック率)アップ |
| image | 画像のURL | 視覚的な訴求力アップ |
| dataPublished | 公開日 | 鮮度の高さアピール |
| dataModified | 更新日 | |
| author | 個人(Person)か組織(Organization)を選択 | 専門性のアピール |
| author.name | 著者の名前 | |
| author.url | 著者に関するURL |
▼ FAQ(FAQPage)に関するプロパティ
| プロパティ | 定義 | 効果 |
|---|---|---|
| mainEntity | FAQページにおける主要な質問・回答のリスト | FAQページの認識性アップ |
| Question | 質問内容 | 質問内容のアピール |
| Answer | 回答内容 | 回答内容のアピール |
XMLサイトマップの最適化
XMLサイトマップとは、Webサイト全体の情報を検索エンジンに伝えるファイルのことです。検索エンジンがWebサイト全体の構造を理解し、効率的にクロール・インデックスするのを助けるため、新しいWebページや階層のページが多いサイトでは重要性が高まります。
以下のように最適化を行うことで、AIに対してWebサイトの最新性や網羅性を効率的にアピールでき、LLMOとしても効果を発揮します。
- 定期的に更新されるよう自動生成を設定
- noindexページや重複ページを除外し、クロール効率を向上
- Googleサーチコンソールにサイトマップを送信し、インデックスを促進
パースペクティブ(Perspectives)への対応
GoogleのSGEにおける「Perspectives」機能では、記事のほか、動画や画像、SNS投稿、フォーラムなど多様なコンテンツからの情報が表示されます。パースペクティブへの対応には以下のポイントを押さえることが有効です。
- 実体験やレビューなど、ユーザーの声を反映したコンテンツ作成
- X(旧Twitter)やYouTubeなどへの情報発信で拡散を促進
- コンテンツの中で、レビューや体験談を引用
多様なプラットフォームで自社に関する言及や評価(サイテーション)を増やすことで、AIは多角的な視点から「信頼できる情報源」として認識しやすくなります。これは第三者からの評価を重視するという点で、従来のSEOにおける被リンク獲得の考え方に近いと言えます。
MFI(モバイルファーストインデックス)への完全対応
MFI(モバイルファーストインデックス)とは、Googleが検索表示順位を決定する際に、モバイル版ページを基準にコンテンツを評価する方式です。
2018年3月から完全にMFIへ移行されており、モバイル対応は必須と言えます。コンテンツ制作の際は以下の点に注意しましょう。
- スマートフォンでも文字が読めるフォントサイズと行間
- 画像や表、ボタンの表示崩れがないレスポンシブ設計
- PCと同等のコンテンツ量および構成の確保
AIは技術的な仕様だけでなく、最終的なユーザー体験(UX)も評価の指標としている可能性があります。スマートフォンでの表示崩れや読みにくさはユーザーの離脱につながるため、結果的にAIからの評価を下げる要因になり得ます。ユーザーがストレスなく情報を得られるサイト設計が、巡り巡ってLLMOにも有効となると考えておきましょう。
LLMO(AIO)の実践ステップ
LLMO対策を戦略的に実行するには感覚的な施策ではなく、具体的なプロセスに基づいたアプローチが重要です。SEO対策と同様に、現状の可視化から改善までを段階的に進めることで、AIからの引用率や評価を着実に高めることができます。
以下では、LLMOを進めるための6つの実践ステップを紹介します。
1. 現状分析
まずは自社名やサービス名、関連キーワードを使って実際にAIチャットに質問を投げかけ、どのような回答が生成されるかを確認します。自社情報が取り上げられているか、競合と比較してどのようなポジションにあるのかを把握することが、LLMOの出発点となります。
以下は、生成AIへの確認で活用できる質問のテンプレートです。
▼ サービス比較型
- ○○におすすめのサービス・ツールは?
- 初心者に向いている○○ツールはどれですか?
- 中小企業向けの○○サービスを比較してください
▼ 課題解決型
- ○○(ユーザーの課題)を解決するためのサービスは?
- ○○(業界・職種)でよく使われる〇〇ツールは?
- ○○を効率化するには、どんなサービスがありますか?
▼ トレンド・ランキング型
- ○○(業界・職種)で注目のサービスを教えてください」
- 2025年に人気が出ている○○ツールは?
2. キーワード・トピックの再定義
従来のSEOでは「単語」を意識していましたが、LLMOでは「問いの形式」を意識することが重要です。
「○○の選び方は?」「○○と△△の違いは?」など、ユーザーがAIに投げかける自然な質問形式のクエリを想定し、対策すべきキーワードやトピックを洗い出します。
3. 既存コンテンツのリライト
抽出した対話型クエリに対応できるよう、既存のコンテンツに手を加えます。具体的には、Q&A形式の項目追加やE-E-A-Tを強化するための著者情報の追記など、根拠となる一次情報や引用を加えましょう。
そうすることで、AIにとって「信頼できる情報源」としての精度を高められます。
4. 新規コンテンツの作成
LLMOでは、「AIが引用したくなるコンテンツ」を意識して制作することが重要です。
とくにあるテーマについて網羅的かつ体系的に整理された「まとめ記事」「とは記事」や、初心者にもわかりやすい「ハウツー記事」は、回答の根拠として採用されやすくなります。
5. 施策実装
コンテンツの質を高めるだけでなく、前述した構造化データの実装やサイトマップの整備、モバイル最適化といったテクニカルな対策も重要です。
エンジニアと連携しながら、AIが情報を正確に読み取れるサイト構造を整備しましょう。
6. 効果測定と改善
施策の実行後、定期的にAIチャットを使って成果を検証します。自社の情報がどのように扱われているか、以前と比べて引用状況や内容に変化があるかを観察しましょう。
この検証を踏まえて、必要に応じてコンテンツや技術的な対策をアップデートすることが継続的な最適化につながります。
LLMO(AIO)の注意点
LLMOは今後のデジタルマーケティングにおいて大きな可能性を秘めた施策ですが、すべてが万能というわけではありません。現時点ではまだ発展段階にあり、成果を得るまでにはいくつかの留意点があります。
ここでは、LLMOを実践する際にあらかじめ理解しておきたい主な注意点を4つ紹介します。
施策後の即効性がない
LLMOの効果は、SEOのように施策後すぐに目に見えて表れるものではありません。というのも、LLMが新たな情報を学習するには、定期的な再学習プロセスを経る必要があるためです。
Web上に有益な情報を公開しても、それがAIの回答に反映されるまでにはタイムラグがあるため、中長期的な視点で取り組む意識が求められます。
成果のコントロールが難しい
自社でLLMOを目的としたコンテンツ戦略を実施しても、狙い通りに成果を出せない現状があります。これは、大規模言語モデルの学習アルゴリズムはブラックボックスであり、どの情報がどのように引用されるかが不透明であるためです。
意図的に自社情報を表示させるのは困難なことから、間接的に評価されるための地道な施策が求められます。
誤情報のリスクがある
LLMは、事実とは異なる情報をもっともらしく生成してしまう「ハルシネーション」と呼ばれる現象を引き起こすことがあります。これにより、自社に関する誤った内容がAIによって広まってしまう可能性も否定できません。
AIチャット上で出力される自社情報の正確性を定期的にモニタリングし、必要に応じて修正・対処する体制が重要です。
LLMのハルシネーション対策としては、LLMが出す情報については必ずファクトチェックを実施しましょう。
LLMOはWebにおける情報収集の主流となりつつありますが、現時点ではまだ発展途上の領域です。そのため、LLMOに注力するあまり従来のSEO対策をおろそかにすると、かえって検索表示順位やAIからの引用率が下がる恐れがあります。
検索エンジンからのトラフィックは依然として重要な集客チャネルであり、SEOとLLMOは競合するものではなく、両立させて取り組むべき施策です。今はまだ「SEOの延長線上にあるLLMO」という意識で取り組むことが現実的と言えるでしょう。
LLMO(AIO)に関するよくある質問
ここではLLMO(AIO)に関するよくある質問をまとめました。
LLMO(AIO)とSEOの違いは?
LLMOとSEOはどちらも情報露出を目的とした施策ですが、対象や評価基準が異なります。SEOは検索を前提とし、LLMOはAIとの対話に最適化する新しい手法です。
詳しくは記事内の「LLMO(AIO)とSEOの違い」をご覧ください。
LLMO(AIO)の具体的な対策方法は?
LLMOを実践するには、SEO同様に技術的な整備とコンテンツ戦略の両面からの対策が必要です。具体的な対策法としては以下が考えられます。
- リード文の最適化
- E-E-A-Tの強化
- 網羅性と独自性の担保
- 明確で論理的な文章構成
- Q&Aコンテンツの作成
- 構造化データの実装
- XMLサイトマップの最適化
- パースペクティブ(Perspectives)への対応
- MFI(モバイルファーストインデックス)への完全対応
詳しくは記事内の「LLMO(AIO)の対策」で解説しています。
LLMO(AIO)対策の実践の流れは?
LLMO対策を戦略的に実行するには、以下のステップで実践することが大切です。
- 現状分析
- キーワード・トピックの再定義
- 既存コンテンツのリライト
- 新規コンテンツの作成
- 施策実装
- 効果測定と改善
詳しくは記事内の「LLMO(AIO)の実践ステップ」で解説しています。
まとめ
ユーザーの情報収集の方法が検索エンジンからAIチャットへと移行し始めている今、LLMO(AIO)はユーザーの「最初の選択肢」として自社の製品やサービスを認識させ、信頼を勝ち取るために不可欠な新戦略です。ユーザーはAIがまとめた「単一の回答」を信頼する傾向があるため、そこに自社情報が引用されれば、専門家のお墨付きのようにブランド認知と信頼性を高めます。
LLMOはE-E-A-Tの強化など従来のSEOとの共通点も多く、AIに最適化する視点を持つことが今後のWeb戦略の差別化につながります。

執筆者
コンテンツディレクター/ライター
Hinode Masaki
2024年ファングリー入社。新卒で不動産営業を経験後、キャラクター・エンタメ系に特化したWebメディアに転職し、約3年にわたってライティング・編集・取材業務に携わる。現在はSEOコンテンツを中心に、構成力を活かした“読みやすい記事づくり”を心がけている。不動産やエンタメ系に加え、人事労務や製造業など幅広いジャンルに対応。趣味は映画鑑賞とカメラ。
LATEST
最新記事
TAGS
タグ