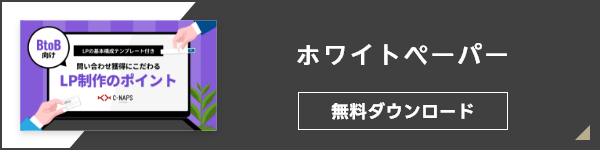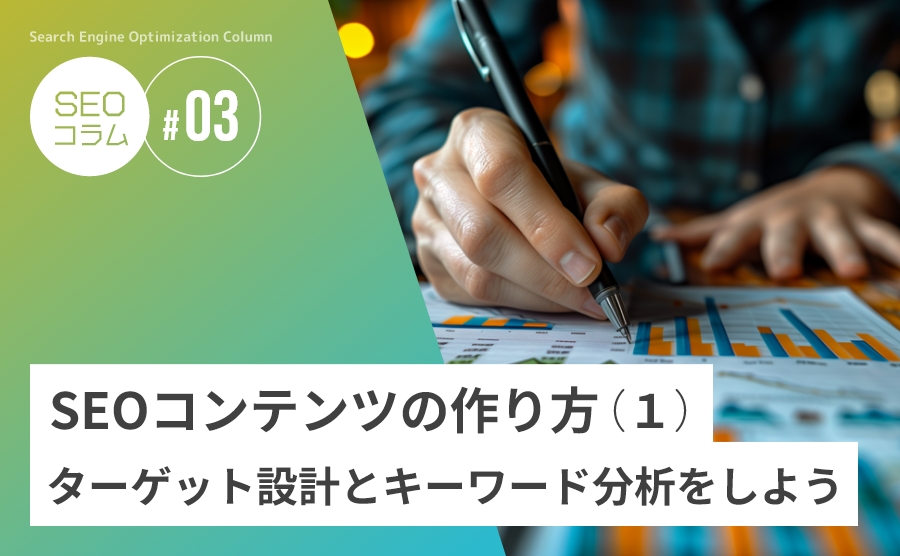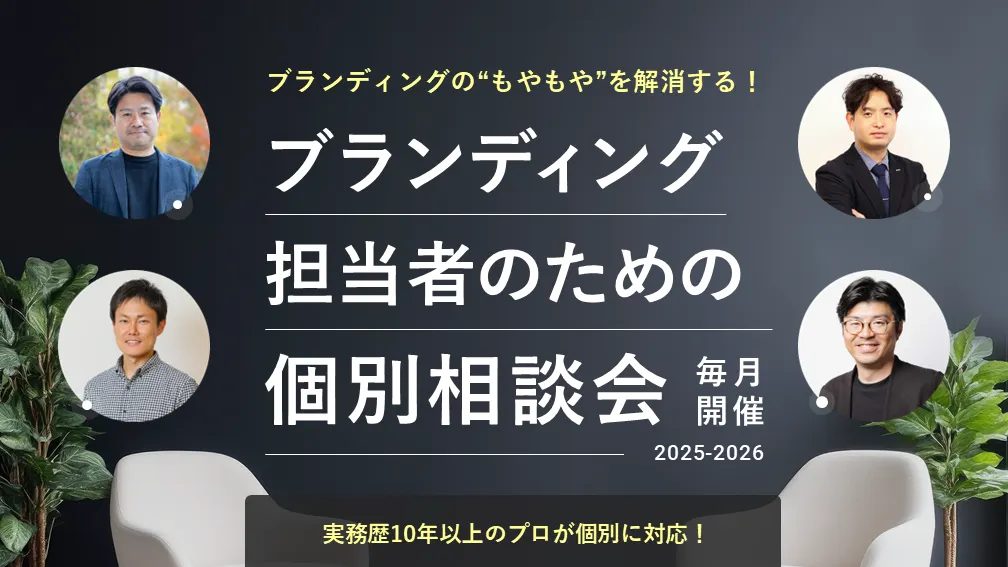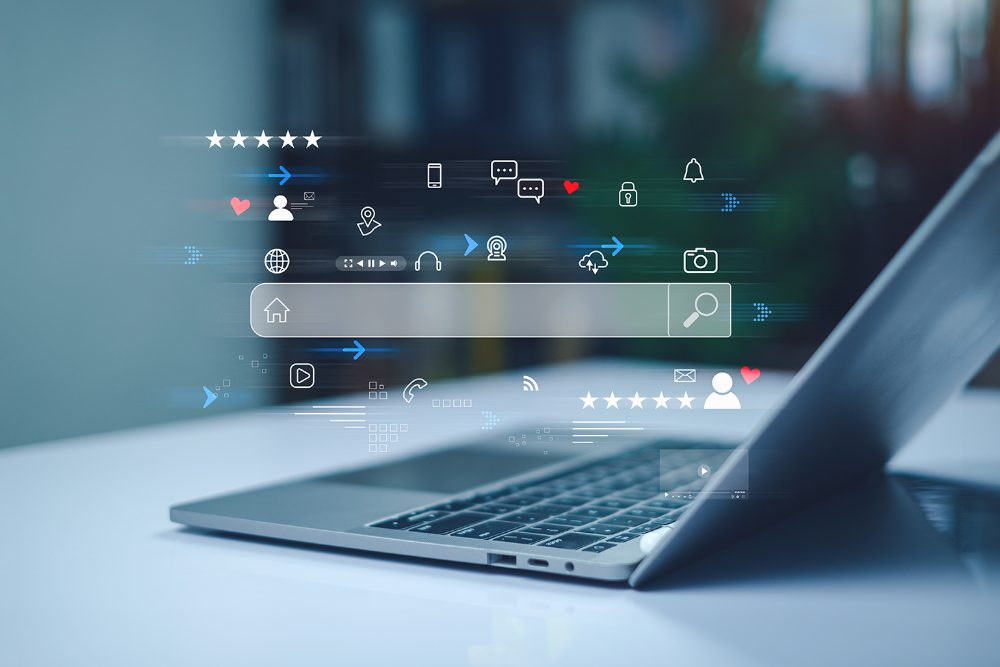LP(ランディングページ)のSEOはこれでOK!初心者にも分かる対策の基本
本記事では、LP(ランディングページ)におけるSEO対策の具体的な実践方法から、AI OverviewsやChatGPTの登場で重要度を増しているLLMO(大規模言語モデル最適化)との関係性までを網羅的に解説します。
「LPは広告用だからSEOは難しいのでは」「広告費に依存せず、LPを長期的なWeb資産として育てたい」と悩むマーケティング担当者は、従来のSEOとAI検索の両方に対応するLP戦略の基本をしっかり押さえておきましょう。
この記事を読めば、広告だけに依存した短期的な集客から脱却し、検索エンジンとAIの両方から評価され、持続的に成果を生み出すLPを構築するための具体的なステップが分かります。
\問い合わせにこだわるLP制作のポイントはこちら/
目次
LP(ランディングページ)のSEOは本当に必要?目的別の戦略を考えよう
コンテンツマーケティングにおいて、LPは商品やサービスの購入、資料請求、問い合わせといったコンバージョンを最大化することを目的に設計されます。そのコンバージョンの要となる集客施策は大きく「Web広告」と「自然検索(SEO)」の2つに分けられますが、すべてのLPがSEOを必要とするわけではありません。
例えば、短期間の販促キャンペーンやプロモーションで利用するLPは即効性が求められるため、広告運用が最優先です。広告に投じた費用の分だけ確実に流入が得られ、キャンペーン終了後にはページ自体の役割が終わる――というケースが大半でしょう。そのため、こうしたLPにおいてはSEOへの投資が最適とは言えません。
一方、サービス紹介や継続的なリード獲得を目的としたLPでは、広告だけに依存すると費用が膨らみ、ROI(投資対効果)が低下する恐れがあります。このようなケースでSEO施策を実施すれば、広告費を抑えつつ長期的に安定した集客が可能です。SEO施策によってGoogle検索やYahoo!検索などの自然流入を取り込み続けられれば、LP自体が単なる販促ツールを超えた「Web資産」として企業の成長を支える存在へと進化します。
つまり、SEOを実施すべきかどうかは「LPのライフサイクルの長さ」や「中長期的な集客戦略」によって判断されるべきなのです。
SEOに強いLPと広告用LPの違い
SEOに強いLPと広告用LPは、設計思想から根本的に異なります。まずは、両者の違いを整理しましょう。
| SEO型LP | 広告型LP | |
|---|---|---|
| 目的 | 情報探索ユーザーの悩みを解決し、自然な形でCVへ誘導 | 短期的にCV(申込・購入)へ誘導 |
| コンテンツ構成 | FAQ、導入事例、コラム、内部リンクなどユーザーインサイトを踏まえた情報を網羅 | キャッチコピー中心で、余計な情報は極力カット |
| デザイン | テキスト重視 | ビジュアル重視 |
SEOに向いているLPは、「自社製品・サービスを売り込む場」ではなく、ユーザーが「調べる場」として機能するものが理想です。導入事例やデータ、FAQなど比較検討段階のユーザーが求める情報をLP内に充実させることで、自然な導線で顕在層へとリーチできます。
一方で、広告型LPは即効性が求められるキャンペーンや商品販売など、短期間で成果を最大化するのに適していますが、コンテンツ量が少ない構成になるケースが多いためSEO流入には適していません。
このように、どちらのLPを採用するかは「成果を出すまでのスパン」や「施策の目的」によって決まります。
LP(ランディングページ)がSEOに弱いと言われる理由
LPは、デザイン性や訴求力の高さが求められる一方で、SEOの観点からは不利になりやすいと言われています。
ここでは、一般的にLPがSEOに弱いと言われる主な理由を3点で解説します。
1. コンテンツ量が不足している
広告用LPは最短で申込や購入につなげることを目的として設計されているため、不要な情報を極力削ぎ落とす構成になりがちです。
しかし、Googleの「検索品質評価ガイドライン(Search Quality Evaluator Guidelines)」でも明記されている通り、SEOでは「ユーザーの検索意図をどれだけ満たしているか」が評価基準となります。テキスト量が少なく情報の網羅性に乏しいLPは、検索エンジンにとってページ内容を十分に理解しづらいという課題があります。
2.キーワード最適化ができていない
広告用LPでは、ユーザーの目を引くキャッチコピーやデザインのインパクトが優先されます。しかし、SEOにおいては「検索エンジンが理解しやすい構造」と「適切なキーワード配置」が欠かせません。
例えば「見出し(hタグ)を乱用している」「画像内にテキストを多用している」といったLPの場合、検索クローラーがページ内容を正確に読み取れず、検索評価が伸びにくくなります。
SEOを意識するなら、まずはページ全体で狙うキーワードを明確に定義し、それに沿ったタイトル、見出し、本文とキーワード最適化を行うことが重要です。ページ構成は「課題 → 解決策 → 実績・根拠 →行動喚起」という流れに整理すると、検索エンジンにもユーザーにも理解されやすいLPになります。
3. 被リンクを獲得しづらい
検索エンジンのアルゴリズムでは、「ページがどれだけ被リンクを獲得しているか」が重要な評価軸のひとつです。被リンクは「他のWebサイトから信頼できる情報源として引用されている」と見なされるため、その数や質が高いほどSEO評価が向上しやすくなります。
しかし、情報提供よりも販促訴求を重視する広告目的のLPは、他社サイトから自然に引用・紹介されるケースが少なくなりがちです。この課題の解決策として、LPを自社サイト内の1ページとして設置し、関連するブログ記事やホワイトペーパーから内部リンクを送る方法が挙げられます。これによりドメイン全体のSEO評価をLPに集約し、LP単体で公開する弱点を補うことが可能です。
LP(ランディングページ)でSEOを強化するメリット
LPは、リスティング広告やSNS広告といった「広告」からの流入を主な目的として制作されることが一般的。そのためSEOは優先度が低い(あるいは難易度が高い)と後回しにされがちです。
しかし、LPにSEOを施すことで、「単なる販促ページ」以上の価値を生み出しやすくなります。以下では、LPでSEOを強化する具体的な3つのメリットを紹介します。
コンバージョン率が向上する
自然検索からLPに流入するユーザーは、課題や解決策が明確な「顕在層」が多く、購入や問い合わせの意思が高い状態でページを訪問します。そのため、広告経由で流入する潜在層に比べてコンバージョン率が高く、成果につながりやすい傾向があります。
LPのSEOを強化することは、「アクセス数を増やす」以上に「コンバージョンしやすい質の高い顧客」を呼び込むことに直結するのです。
持続的な集客の可能性がある
LPのSEOを強化し、ユーザーにとって有益な情報を提供し続けることで、検索エンジンからの評価が安定します。例えばLPに導入事例や専門的な解説コラムを追加し、それを定期的に更新することでLPの内容が評価されます。そして、広告出稿が終了してからも継続的な集客が可能になるのです。
広告は掲載を止めると流入が途絶えますが、SEOを施したLPが検索上位に表示され続ければ広告費をかけずにアクセス数を獲得できます。安定した「企業の重要なWeb資産」として運用できるため、長期的な視点でのマーケティング活動が可能となり、大幅なコスト削減効果にもつながるでしょう。
ブランド認知度が向上する
特定のキーワードで長く検索上位に表示され続けると、ユーザーに「この分野に精通した専門性の高い企業だ」と認識されやすくなります。また、検索上位を維持することで、単に露出やブランド認知が向上するだけでなく、企業の信頼性や権威性を裏付ける証明となり、ブランドイメージの向上にも貢献します。
とくにBtoB領域ではサービス導入の検討期間が長いため、顧客は多くの情報を比較検討します。その分、自社のLPが上位表示できていれば、顧客の認知獲得に加えて「この企業のサービスなら間違いない」という信頼感を与えるため、競合他社との差別化につながるのです。
効果的なLP(ランディングページ)のSEO施策戦略
LPのSEOは単なる一時的な集客ではなく、Webサイトを長期的な資産として育てるための重要な戦略です。
続けて、LPのSEO効果を最大化するために欠かせない具体的な戦略を紹介します。
1. 「質の高い」コンテンツを意識する
検索エンジンは、ユーザーにとって最も価値のある情報を提供しているページを高く評価します。そのためLPのSEOで成果を出すには、ユーザーの検索意図を深く理解し、それに応える「質の高い」コンテンツを意識して制作することが不可欠です。
具体的には、以下のようなことを意識しましょう。
検索意図を徹底的に分析し網羅する
まずは、ターゲットユーザーが抱える疑問を仮説立てて分析し、LP内で網羅的に情報や解決策を提供できるようにしましょう。
SEOでは単にキーワードや販促情報を詰め込むのではなく、ユーザーがそのキーワードを検索する目的を押さえることが重要です。例えばユーザーが製品のサービス名を検索している場合、その目的は機能だけでなく、導入事例や料金体系、競合との比較といった情報を求めている可能性があります。
こうした検索ニーズの仮説立てによってユーザーが求める情報を効果的かつ網羅的に提供できるようになり、「質の高いコンテンツ」として検索エンジンに評価されやすくなります。
独自性と専門性を確立する
競合との差別化を図るには、自社ならではのデータや導入事例などを活用し、LPの独自性と専門性を確立することが重要です。顧客アンケートや専門家による監修、自社製品・サービスの導入事例などの一次情報はLPの信頼性と専門性を高めます。
これにより検索エンジンだけでなく、ユーザーからも「この企業は信頼できる」と評価されやすくなります。
PREP法を活用して構成する
LPは、短時間で内容を理解してもらうことが重要です。そのため「結論 → 根拠 → 事例 → 再結論」の順序で構成する「PREP法」を用いることで要点が明確になり、ユーザーの離脱を防げます。
PREP法(Point, Reason, Example, Point)とは、情報をもっとも効率的に伝えるためのフレームワークです。最初に結論(Point)を提示し、その根拠(Reason)を示し、具体的な事例(Example)で説得力を高め、最後に再び結論(Point)へと導くことで、ユーザーはLPの内容を短時間で深く理解できます。とくにLPでは「要点を先に伝えること」が、コンバージョンにつながる鍵となります。
E-E-A-T(専門性・権威性・信頼性)の強化
E-E-A-Tとは、「専門性(Expertise)」「権威性(Authoritativeness)」「信頼性(Trustworthiness)」「経験(Experience)」の頭文字をとった用語で、Googleなどの検索エンジンがコンテンツの品質を評価するうえで重視する指標とされています。
LPのE-E-A-Tを強化する際は、著者情報や監修者のプロフィール、具体的な実績データなどを記載し、誰が、どんな根拠で語っているのかを明確にしましょう。そうすることで、検索エンジンの評価とユーザーの信頼を同時に得やすくなります。
UI/UXを改善する
検索順位を左右するのは、コンテンツの内容だけではありません。ページの使いやすさ(操作性)や見やすさ(視認性)、ページ読み込み速度といったユーザーインターフェース(UI)もSEOに関与します。
ユーザーエクスペリエンス(UX)を数値化した3つの指標である「Core Web Vitals(LCP・FID・CLS)」を意識し、モバイル環境での表示を最適化しましょう。画像サイズの圧縮や、不要なHTML/CSS/JavaScriptコードの削除、ブラウザキャッシュの活用といった基本的な改善でユーザー体験は大きく向上します。
▼ コアウェブバイタルについては、以下記事で詳しく解説しています。
構造化データを導入する
構造化データとは、検索エンジンがページの内容をより深く理解するための目印(マークアップ)です。具体的にはFAQやレビュー、「schema.org」タグによるマークアップなどを行うことで、検索エンジンがページ内容を理解しやすくなります。
また、構造化データを実装することで、検索結果にFAQや製品情報がリッチスニペットとして表示されます。これによりユーザーの目を引きやすくなれば、クリック率の向上も期待できるでしょう。
2. 効果測定と分析を繰り返す
LPを最適化するには、SEOの効果を測定し、改善を続けてPDCAサイクルを回すことが不可欠です。アクセス解析ツールやヒートマップツールを活用し、常にLPの状態を把握しましょう。
アクセス解析ツールの活用
Googleアナリティクス(GA4)やGoogleサーチコンソールといったアクセス解析ツールを活用することで、LPへの流入経路やユーザーの属性を詳細に分析できます。
Googleアナリティクスはユーザー行動・離脱ポイントを可視化し、改善点を特定するツール、Googleサーチコンソールは検索クエリ・順位変動を分析し、施策の成果を確認できるツールです。
これらのツールを定期的にチェックすることで、「狙ったキーワードで流入しているか」「CVに結びついているか」を判断できます。
▼GA4やサーチコンソールについては以下の記事で解説しています。
▼ SEO分析ツールについては以下の記事をご覧ください。
ユーザー行動の分析
ヒートマップツールなどを活用することで、ユーザーがLP上の「どこを見て」「どこで離脱しているか」が可視化できます。ユーザーの視線や行動の流れを分析することで、CTAの配置やコンテンツの順番を改善する具体的なヒントが得られます。
また、多角的にLPを分析・改善し続ける中で、CVR(コンバージョン率)を継続的に高めていくことができます。
▼ ヒートマップツールについては以下の記事をご覧ください。
3. 改善施策でA/Bテストを実施する
LPを改善する上では、勘や経験に頼るのではなく、科学的な根拠に基づいたA/Bテストが有効です。
A/Bテストとは、LPのキャッチコピー、画像、CTAボタンの色や文言など、変更したい要素を2パターン用意し、どちらがより高いコンバージョン率を達成できるかをテストする手法を指します。例えば「無料相談はこちら」という文言と「今すぐ資料をダウンロード」という文言で、どちらがクリック率が高いかを検証します。
このテストを通じて、「なぜこのパターンが成果を出したのか」という仮説を立て、検証・改善を繰り返すことで継続的な最適化が実現します。
LP構築にお悩みではありませんか?
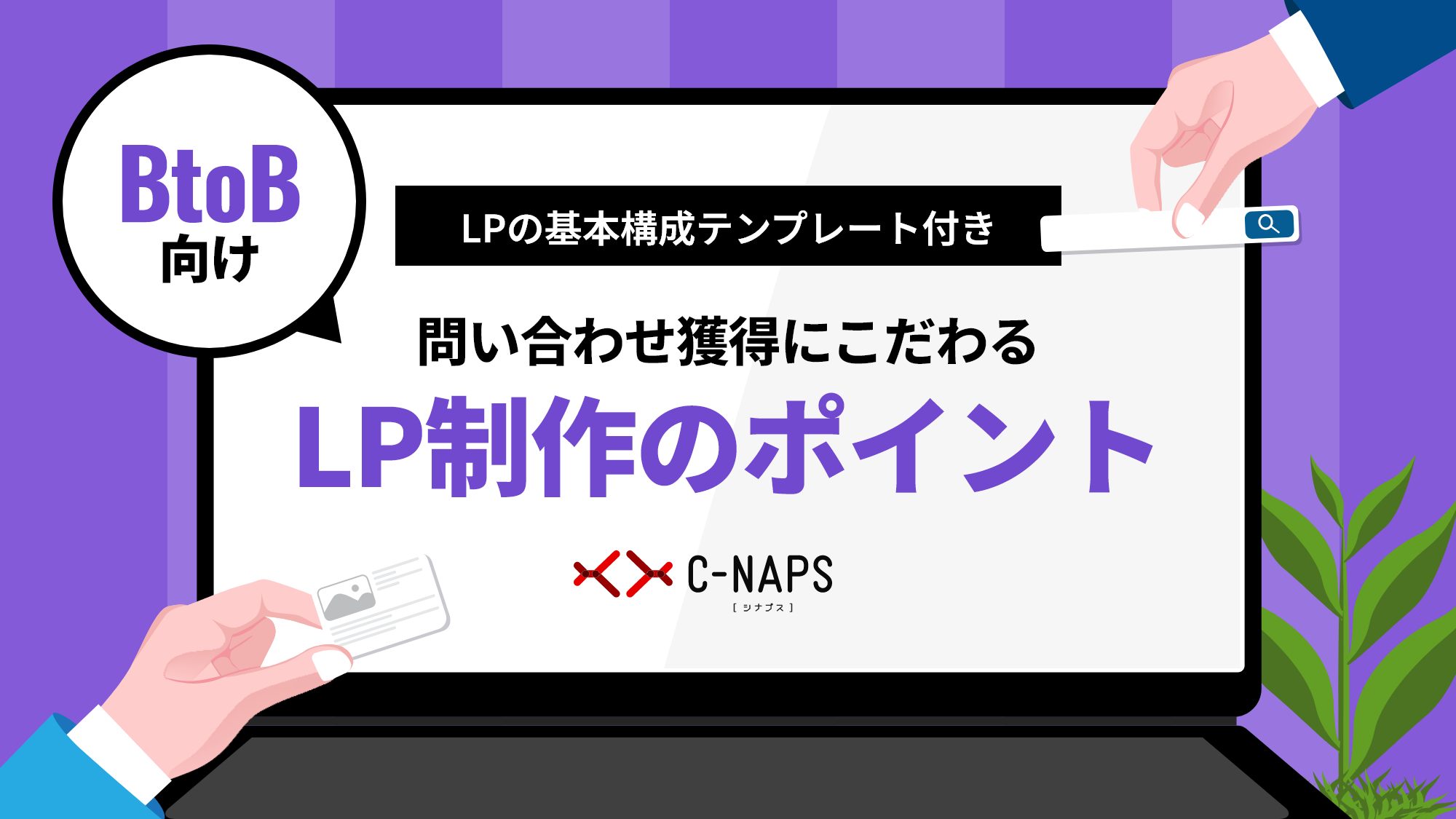
BtoB向けLPで気を付けるべきポイントから、BtoBマーケティングに活用できるLPの構成テンプレートまでまるっと紹介した資料をご用意しています。ぜひ以下よりダウンロードしてご活用ください。
LP(ランディングページ)のSEOを成功させやすくする3つのポイント
SEOの基本的なポイントを押さえておけば、成果を出しやすくなります。
次に、SEOを成功させるために特に重要な3つのポイントを確認しておきましょう。
1. キーワードのターゲットを明確にする
LPのSEOで最初にすべきアクションは、ターゲットと目的の明確化です。どんなユーザーに、どんな価値を伝えたいのかという軸が定まらないままキーワードを選んでも、検索意図とページ内容がズレてしまい、上位表示は難しくなります。
とくにLPの場合は検索ボリュームの大きいビッグキーワードよりも、具体的な課題や目的を含むミドルキーワードやスモールキーワードのようなロングテールキーワードを狙うのが効果的。例えば「SEO 対策 ツール 比較」「SEO 対策 初心者 LP」といったキーワードは、すでに課題が明確な顕在層を集めやすい傾向にあります。
| ビッグキーワード | ミドルキーワード スモールキーワード | |
|---|---|---|
| 例 | SEO | SEO 対策 初心者 LP |
| 特徴 | ・検索ボリュームが大きく競合性も高い ・ユーザーの検索意図が広範で上位表示が難しい ・ユーザーのコンバージョン意欲も低い傾向にある | ・検索ボリュームは小さいが、ユーザーの意図が明確 ・キーワードに沿ったコンテンツを提供することで、コンバージョンにつながりやすい |
こうしたキーワードを軸に設計されたLPは「今まさに解決策を探している」ユーザーとの接点を生み出すため、より高いコンバージョン率を実現できます。
▼ キーワード選定の方法については、以下の記事も参考にしてください。
2. 検索上位10個の競合サイト(ページ)を分析する
狙うキーワードが決まったら、そのキーワードで上位表示されている競合サイト(ページ)を最低でも10個は分析しましょう。
分析すべき項目は以下の通りです。
- コンテンツの内容・網羅性
- ページ構成・見出しの使い方
- タイトルの付け方
- 被リンクの状況
まずは、競合のLPがどんな情報でユーザーの疑問に応え、どれだけ内容を網羅しているかといった視点でコンテンツの内容や網羅性、切り口を分析します。同時に「論理的で読みやすいページ構成か」「見出し(hタグ)は適切に使われているか」といったLPの構造面も把握しましょう。
さらにLPのタイトルも重要です。ユーザーの興味を引きクリックを促すポイントとなるため、上位サイト(ページ)のタイトルも分析します。
最後にSEOツールなどを活用して被リンクの状況を確認し、競合LPがどの外部サイトから価値ある情報源として評価されているかを把握しましょう。競合にあって自社にない要素を洗い出し、データや導入事例、専門性などの強みを加えるアクションによって、差別化を図りながら競合を上回る質の高いLPを制作できます。
3. 公開後も継続的に更新する
「LP(ランディングページ)のSEOを成功させやすくする3つのポイント」で前述した通り、LPを「Webサイトの資産」として育てるには継続的な運用が不可欠です。
検索エンジンは情報の鮮度を評価するため、公開後も定期的にLPの内容を見直し、最新情報にアップデートする必要があります。例えば導入事例の追加や、統計データの年度更新、サービス内容の変更などの反映も効果的です。
LP(ランディングページ)はSEOだけでなくLLMOも重要となる
近年、ユーザーの検索行動は「検索エンジン上での検索」ではなく、Googleの生成AI(AI Overviews)やChatGPTといったAIを活用した「AI検索」へとシフトしています。これによりこれまでのSEOに加えて、LLMO(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化)の重要性が増しています。
「検索順位」を目標とする従来のSEOに対し、LLMOはAIが生成する回答に自社の情報が引用・参照されやすくするための対策のこと。AIは回答を生成する際、信頼できるソースを引用元として参照します。そのため、LPの内容をAIが理解しやすくすることで、自社情報がAIの回答に組み込まれる可能性が高まり、ブランドの認知や信頼性の向上につながります。
▼ LLMOについては以下の記事もあわせてご覧ください。
LLMO(AIO)とは?SEOとの違いとAI時代に必須の対策法を解説
LPにもLLMOが必要な理由
ユーザーの検索行動は、具体的には従来の「キーワード検索」から「○○とは?」「○○のおすすめ」「○○と△△の違いを教えて」といった対話型・質問型の検索へと変化しています。
AIがユーザーが求める情報に直接答えてくれるため、ユーザーは複数のサイトを比較検討する手間が省くことが可能。このAIの回答内で自社のLPが引用・紹介されれば、非常に信頼性の高い情報としてユーザーに認識され、広告以上に強力なコンバージョン効果を発揮する可能性もあるでしょう。
LPでのLLMO施策
SEOとLLMOは対立する概念ではなく、むしろ連動するものです。SEOを意識した構成や内部施策を行ったLPは、LLMO視点でも有用と言えます。具体的には、以下の3つを意識すると効果的です。
客観的な事実を明示する
AIは感情的なキャッチコピーよりも、客観的かつ正確で信頼できる事実を重視します。
LPにおいては製品のスペックや料金プラン、導入実績、成功事例の具体的な数値など、客観的なデータを明確に記載することでAIが情報を引用しやすくなります。
情報を構造化して伝える
AIがLPの内容を効率的に理解できるよう、データの構造化を意識することが重要です。
料金プランや機能比較、よくある質問(FAQ)などは箇条書きや表(テーブル)を用いて整理し、「schema.org」によるマークアップを行うと、AIが情報を抽出しやすくなります。
FAQを充実させる
AIは質問形式の回答を生成する際、FAQ構造を優先的に参照する傾向があります。
ユーザーがLPに訪問する際、どんな疑問や課題を抱いているかを想定し、FAQとしてまとめておくことも有効です。これによりAIがユーザーの質問に回答する際、自社のLPから情報が引用されるる可能性が高まります。
よくある質問
ここではLPのSEOに関するよくある質問をまとめました。
LPがSEOに弱い理由は?
LPは、一般的に広告用に最適化されており、検索エンジンが重視する「情報の網羅性」や「明確な構造」などが十分でないことから、SEOの観点で不利と言われています。
詳しくは、記事内の「SEOに強いLPと広告用LPの違い」をご覧ください。
SEOの効果が出るまでの時間は?
SEOは長期投資型の施策であり、一般的に効果が得られるまで数ヶ月〜半年以上を要します。短期的成果を求めるなら広告と組み合わせるべきです。
詳しくは、記事内の「LPでSEOを強化するメリット」をご覧ください。
LPのSEOは制作段階から考慮すれば良い?
初期段階でキーワード設計やサイト構成を定めておけば、公開後に大規模修正をせずに済みます。
詳しくは、記事内の「LPのSEOを成功させる3つのポイント」をご覧ください。
まとめ
LPには大きくSEO型と広告型といった2種類があり、長期的に成果を生み出す「Web資産」として育てるためには、SEOとLLMOの両面から最適化を進めることが欠かせません。
「検索意図への的確な対応」「専門性・信頼性の担保」「継続的な改善」を重視してLPのSEOを実践することで、安定した集客と高いコンバージョン率の両立が可能になります。
LPを「単なる広告の着地点」として扱わず、戦略的に育て続けることで安定したマーケティング基盤を築いていきましょう。
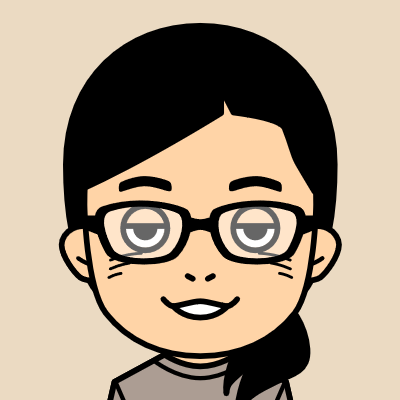
執筆者
Kambe Kumiko
編集プロダクションでの勤務を経て、2018年に入社。現在はライターとして、Webコンテンツ制作に従事している。目指しているのは、「読みやすく」「分かりやすい」文章。今後は取材の数を増やし、臨場感のある記事も書いていきたい。
LATEST
最新記事
TAGS
タグ