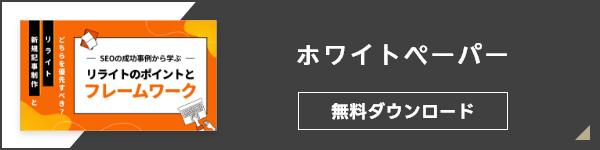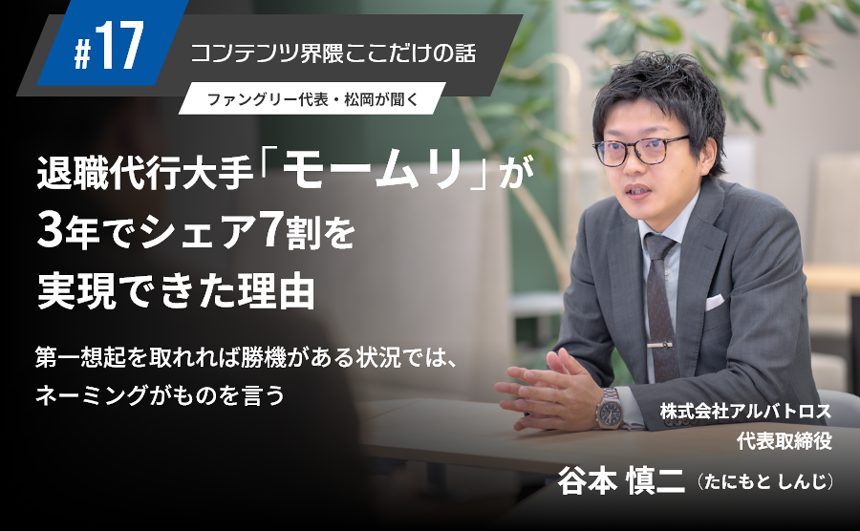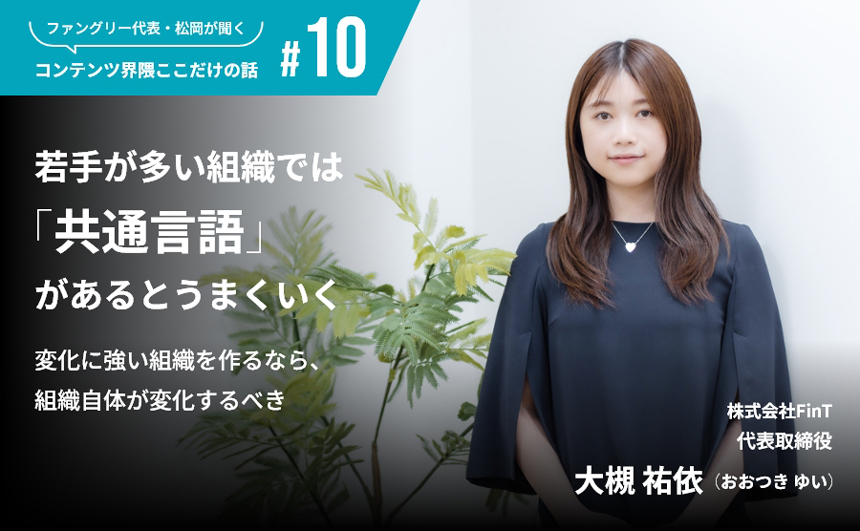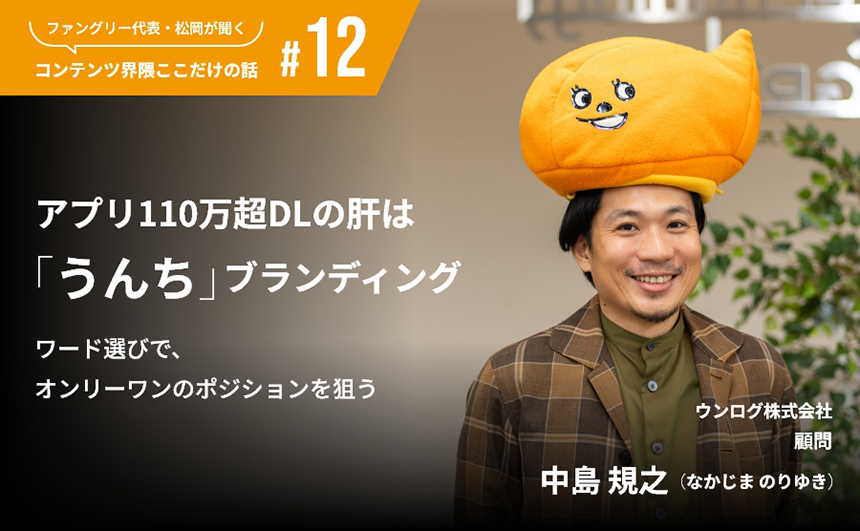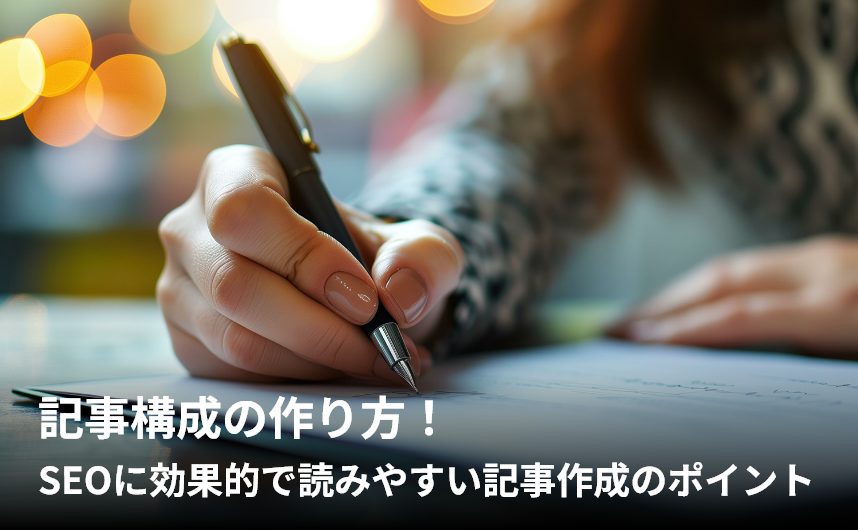
記事構成の作り方!SEOに効果的で読みやすい記事作成のポイント
文章作成に慣れないうちは「とにかく書いてみよう!」と、勢いで書き始めるのはよくあることでしょう。しかし、頭に浮かんだことをそのまま書き連ねただけの文章は、話が散漫になったり、結論が曖昧になったりと、読者に意図が伝わりにくくなりがちです。
読者に明確かつ論理的に情報を伝え、SEOでも効果を発揮する記事を書くためには、執筆前にしっかりと情報を整理し、記事構成を練るプロセスが欠かせません。
本記事では、SEO効果を高め、読者にスムーズに内容を理解してもらうための記事構成の重要性を解説します。初心者の方でも実践しやすい記事構成の具体的な作成ステップや、読まれる記事を作るために意識したいポイントを分かりやすく解説します。
\SEOリライトのポイントはこちら/
文章の書き方やSEOについては、以下の記事もご覧ください。
| 関連記事 文章の「トンマナ」が重要な理由 ライターが注意すべき系統別重複表現例 伝わらない文章の原因は“主述のねじれ”かも? 漢字の「とじ・ひらき」の使い分けでブランドイメージを確立 SEOとは?検索エンジンの仕組みから現在のトレンドを知ろう |
Table of Contents
記事構成を作成する4つの重要性
いきなり文章から書き始めず、記事構成を作成する重要性について説明します。
SEOキーワードを効果的に組み込める
SEOにおいて上位表示を狙う上で、適切なキーワードの配置は不可欠です。
記事構成の段階で対策したいSEOキーワードを意識的に盛り込めば、記事作成時にキーワードを不自然なく文章に組み込むことができます。そうすることで検索エンジンからの評価が高まり、上位表示されやすくなります。
情報収集や取材を効率化できる
記事構成を事前に作成しておくことで、記事に必要な情報や取材対象が明確になります。
「何を取材すべきか」「どのような情報を集めるべきか」が可視化されるため、無駄な作業を省き、効率的な記事作成が可能になります。
テーマと内容の整合性を確保できる
記事の構成案がないまま書き進めてしまうと、意図せず記事のテーマから逸脱してしまいかねません。
事前に詳細な記事構成を作成しておけば、各見出しや段落が記事全体のテーマと一貫しているかを客観的に確認できます。内容のズレも起こりにくくなり、信頼性の高い記事を作成できるのです。
全体像を把握でき、スムーズな執筆を可能にする
記事構成は、タイトルから始まり、導入、本文の各見出し、結論に至るまでの全体像を明確に示すもので、いわば記事の設計図となります。
記事構成があることで、執筆者(ライター)は記事全体の流れを常に把握しながらライティングを進めるのに役立ちます。論理的な文章展開が可能となり、質の高い記事作成につながるのです。
記事構成の作成ステップ
しっかり作り込んだ記事構成は、ユーザーが読みやすくSEOに強い記事を作るのに重要な土台となります。
次の大まかな3つのステップで進めることで、効果的な記事構成の作成が可能です。各ステップのポイントを押さえながら、魅力的な記事を作り上げましょう。
STEP1. ターゲットとニーズを想定し、綿密な企画を立てる
記事作成にあたって、まずはテーマとターゲットを選定します。単に何を書くかを決めるだけでなく、「誰に」「何を届けたいのか」といったターゲットの潜在的なニーズを徹底的に洗い出す必要があります。
例えば、「結婚式の出席マナー」をテーマに記事を作成する場合を考えてみましょう。この場合、記事構成を考える上で最初に意識すべきターゲットは「結婚式 マナー」と検索するユーザーです。結婚式への出席を控え、服装、当日の振る舞い、ご祝儀の準備など、具体的なマナーに関する情報を切実に求めていると考えられます。
ターゲットのニーズを把握するためには、キーワードリサーチが有効です。「結婚式 マナー」という主要キーワードに加え、関連キーワードを調査することで、読者の疑問や関心の核心が見えてきます。
実際に「結婚式 マナー」で検索してみると、以下のような関連キーワードが頻繁に表示されます。
| ・結婚式 マナー 服装 ・結婚式 マナー 当日 ・結婚式 マナー 食事 ・結婚式 祝儀・結婚式 持ち物 |
これらの関連キーワードから、ターゲットは結婚式の出席マナーの中でも、とくに服装や当日の振る舞い、食事の作法、ご祝儀や持ち物について知りたがっているということが分かります。
したがって、このニーズに応える情報を網羅的に盛り込んだ記事構成こそが読者の満足度を高め、SEOにおいても有利にはたらくでしょう。
ターゲット設計とキーワード分析について、詳しくは以下の記事もご覧ください。
STEP2. ニーズをもとに構成を組み立てる
ターゲット読者のニーズを深く理解したら、次は文章の構成を考えましょう。ここで重要なのは、洗い出した複数のニーズの中から、記事の核となる情報を絞り込み、読者が最も求めている情報に焦点を当てること。情報を詰め込みすぎると、記事が冗長的になり、読者は最後まで読むことなく離脱してしまう可能性が高まります。
効果的な記事構成を作成するには、まずターゲットのニーズを箇条書きにし、読者の疑問や課題解決にとってどれほど有益かを見極めましょう。このとき、キーワード調査ツールを活用するのもおすすめです。検索ボリュームが大きいキーワードは、多くの読者が関心を持っている証拠であり、それをメインキーワードに記事を作成することで高いSEO効果が期待できます。
発信したいトピックを決めたら、それぞれをどのような順番で、どの程度のボリュームで、どのような役割を持たせて配置するのかを具体的に設計します。一般的な記事構成として、読者が情報を理解しやすいように、以下の流れを意識すると良いでしょう。
| ●導入(読者の興味を引く) 記事のテーマとターゲット読者に明確に訴求し、SEOキーワードを自然に含みつつ、読者の「読みたい!」という気持ちを掻き立てる冒頭部分を作成します。 ●メイントピック①(最も伝えたい情報) 検索ボリュームが最も高く、読者の関心度が高いと考えられるニーズに対し、それに応える情報を具体的な事例やNG例を交えながら詳細に解説します。 例:【年代・関係性別】結婚式の服装マナー ●メイントピック②(関連性の高い情報) 2番目にニーズの高い情報について、それに応える情報を具体的な事例やNG例を交えながら詳細に解説します。 例:結婚式当日の流れとマナー ●補足(理解を深める周辺知識) メイントピックを補完し、読者の理解を深めるための関連情報や、さらに役立つ知識を提供します。 例:結婚式で渡す祝儀の相場とマナー、結婚式に持っていくべき持ち物リスト ●まとめ(記事全体の要約と行動喚起) 記事全体の重要なポイントを簡潔にまとめ、読者に最も伝えたいメッセージを改めて強調します。必要に応じて、関連する他の記事への導線や、コメント欄への質問を促すなど、具体的な行動喚起(CTA)を設置します。 |
記事構成が完成したら、各項目に沿って質の高い情報を収集・整理します。すでにトピックが決められているため、やみくもに情報収集をする必要がなく、効率的に情報を集めることができるでしょう。
STEP3. 収集した情報をもとに記事を執筆する
記事構成をしっかりと作り込み、必要な情報を集めたら、いよいよ文章を書き始めます。すでに文章の“設計図”と“材料”は揃っているので、そこまで難しく考える必要はありません。SEOキーワードを意識しながら、具体的な情報を盛り込んだ分かりやすい文章作成を心がけましょう。
記事の導入部分は、ターゲット読者が抱える疑問や悩みに共感を示すことで、その後の内容への興味をグッと引きつける重要な役割を担います。読者の「知りたい!」という気持ちに火をつけるような書き出しを意識しましょう。
また、記事の冒頭で最も重要な結論を最初に提示し、「なぜそう言えるのか?」という理由や根拠を本文で詳しく解説する結論ファーストも有効です。読者が記事の冒頭で疑問を解消できることで、離脱を防ぎ、読み進めてもらいやすくなります。
記事の核となるメイントピックと、読者の理解を深める補足情報は、先に想定したターゲットとニーズを常に意識しながら執筆します。もし執筆中に「この記事は、本当にターゲット読者の役に立つ情報だろうか?」「彼らの疑問を解決し、満足度を高める内容になっているだろうか?」と迷いが生じたら、一度立ち止まって自問自答することが大切です。常にターゲット読者の視点に立ち返り、記事構成からブレないように注意しましょう。
記事の最後に配置するまとめの段落では、本文全体の重要なポイントを簡潔に要約し、改めて最も伝えたい主旨を強調します。そのうえで、「あらかじめ服装や食事のマナーをしっかり把握し、万全の態勢で結婚式に臨みましょう」といったような、読者に具体的な行動を促すような文章(CTA)で締めくくると収まりが良くなります。
読まれる記事にするための構成作成ポイント
競合サイトがいくつもある中で、せっかく書いた記事を多くのユーザーに届けるためには、ちょっとしたした工夫が大きな差を生みます。
記事構成を作る際は、単に情報をまとめるだけでなく、次のようなポイントも意識するようにしましょう。
キーワードはタイトル前半に配置する
タイトルにSEOキーワードを含める際は、できる限り前半部分に配置するようにしましょう。検索エンジンはタイトルの前半部分をより重視して評価する傾向があるため、関連性の高いキーワードを冒頭に置くことで、検索順位の上昇が期待できます。
また、スマホなど表示文字数に制限がある端末では、タイトルが検索結果画面で途切れてしまうことも。読者にキーワードを認識させ、クリック率を高めるためにも、キーワードはタイトル前半に入れることをおすすめします。
見出し・本文にもキーワードを設置する
よりSEO効果を高めるためには、見出しと本文にもキーワードを散りばめることが大切です。文章中にキーワードを適宜入れることで、検索エンジンは記事を認識しやすくなり、上位表示されやすくなります。とくに「見出し直下部分」はSEOにとって重要度が高いため、自然な文章でキーワードを盛り込むことを意識しましょう。
ただし、キーワードを無理に詰め込むと読みにくくなるだけでなく、検索エンジンからの評価を下げる恐れもあります。スムーズな文章の流れの中で、キーワードを効果的に配置するように意識してください。
オリジナル要素を入れて独自性を高める
競合サイトと似た内容では検索エンジンの評価が伸びにくく、結果として上位表示は難しくなります。記事構成を検討する際には、次のような点を意識してオリジナルの要素を積極的に取り入れてみましょう。
| ・独自の視点と深掘り:執筆者自身の経験や知識に基づいた独自の視点や、競合が深掘りしていないニッチな情報。 ・一次情報の提供:独自の調査データ、アンケート結果、体験談、専門家へのインタビューなど、他のサイトでは得られない情報。 ・独自の切り口:競合サイトとは異なる視点からテーマを分析したり、読者の疑問をより効果的に解決できるような独自の情報の整理・提示方法。 ・最新情報や事例の活用:市場や業界に関する最新情報や具体的な事例。 ・独自の表現とトーン:執筆者ならではの分かりやすい表現や親しみやすいトーン。 |
まとめ
ターゲット読者の想定やニーズ分析、そして綿密な記事構成といった執筆の事前準備は、手間がかかると思われがちで敬遠される方もいるかもしれません。しかし、これらのステップを丁寧に行うことで、記事全体の整合性が高まり、文章のクオリティは飛躍的に向上します。
とくに、しっかりとした記事構成があれば、執筆中に内容が迷走したり、何度も書き直したりする無駄な工程を大幅に削減できます。結果として、質の高い記事を効率的に制作できるため、記事構成の作成は社内リソースの効率化にも大きく貢献するでしょう。
株式会社ファングリーでは、制作支援とマーケティング支援を一貫して行っています。とりわけBtoB向けのコンテンツ制作に強みを持っており、ブランディングを軸としたWebサイト制作・コンテンツ制作を通じてお客様のビジネス課題の解決に取り組んでいます。「リソース不足で記事を内製できない」「記事制作のノウハウが分からない」とお悩みの企業様は、ぜひ気軽にお問い合わせください。

執筆者
コンテンツディレクター/ライター
Miho Shimmori
2023年ファングリーに入社。以前はWebマーケティング会社で約2年半コンテンツマーケティングに携わり、不動産投資メディアの編集長を務める。SEOライティングが得意。ほかにも士業関連や政治など複数メディア運営の経験あり。Z世代の端くれ。趣味はサウナと競馬と街歩き。
LATEST
最新記事

カスタマーマーケティングはなぜ重要?成功事例から見る施策と成果
2025.4.17

コンテンツマーケティング会社選びのポイント!他社の成功事例も紹介
2025.4.15

ホームページ(Webサイト)の作成費用を依頼先・種類・ページ数別に詳しく解説
2025.4.10