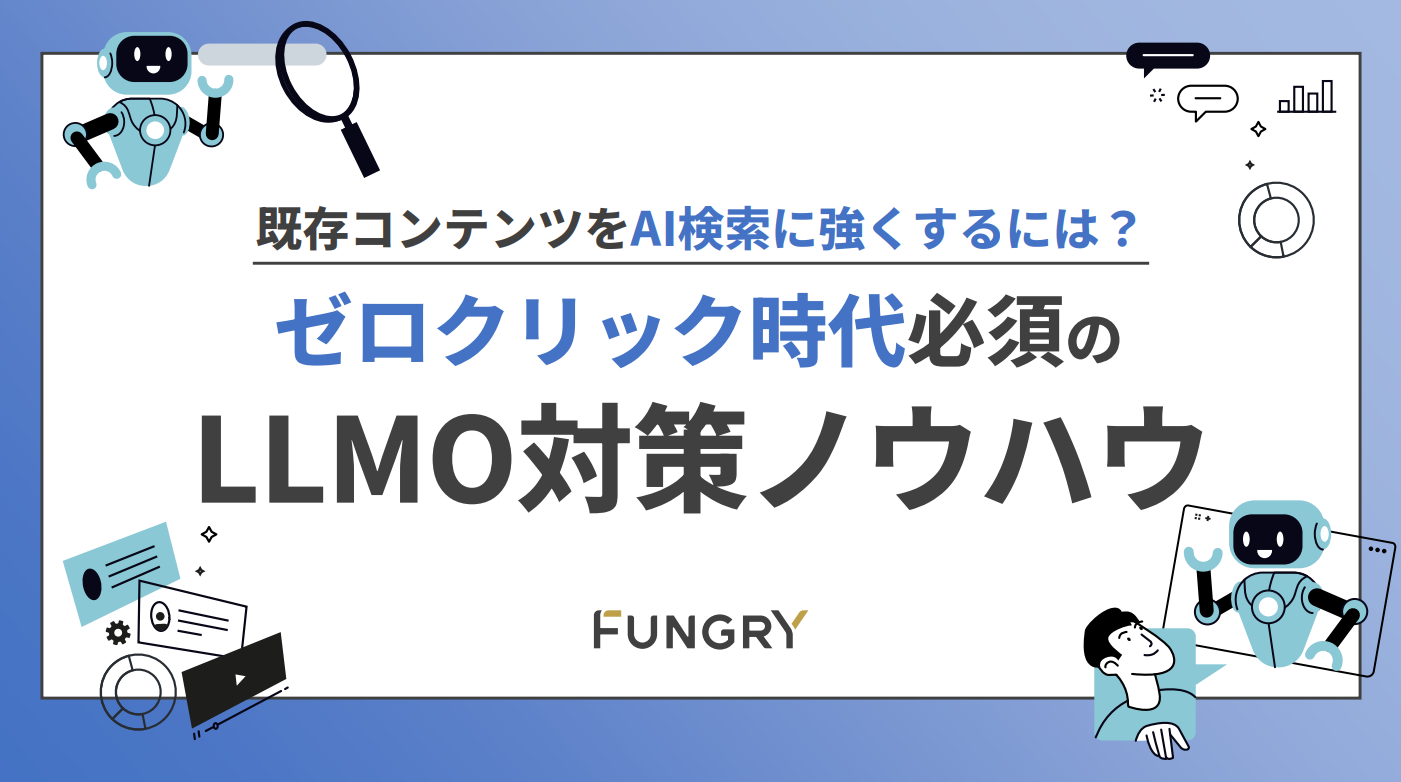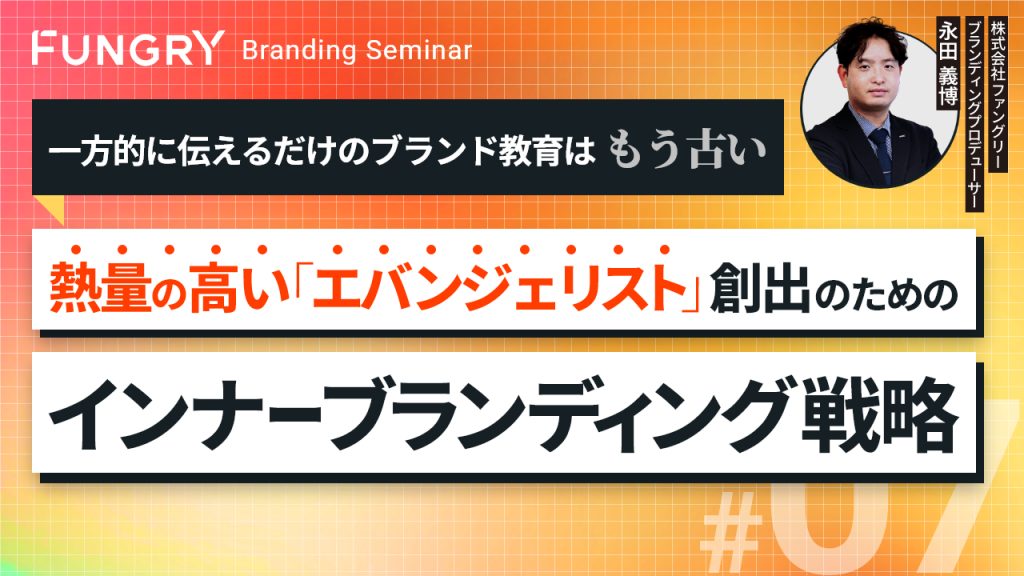LLM最適化とは?コスト・精度改善の技術からLLMOとの関係まで徹底解説
本記事では、大規模言語モデル(LLM)を活用した集客成果を最大化するための施策「LLM最適化」について、モデル自体の性能を高める「技術的アプローチ」と、AI検索での引用を目指す「LLMO(AIO)アプローチ」の2つの側面に分けて網羅的に解説しています。
「GoogleのAI Overviews登場で、これまでのSEO対策が通用しなくなるのでは?」
「自社開発AIのコストや精度を改善したいが、何から手をつければいいか分からない」
こうした悩みを抱えるマーケティングや開発の担当者向けに、それぞれの目的や立場に応じた具体的な手法と戦略を紹介します。
この記事を読めばこれまで曖昧だった「LLM最適化」の全体像が明確になり、具体的なアクションプランを描けるようになります。
Table of Contents
LLM最適化とは?成果を最大化する2つのアプローチ
大規模言語モデル(LLM)のビジネス活用が進む中、「LLM最適化」という言葉が注目されていますが、現状では話す人の立場によってその解釈が大きく異なることがあります。大規模言語モデル(LLM)の基盤技術は、2017年に発表された論文『Attention Is All You Need』で提唱されたTransformerモデルです。この技術の登場により、AIは文章の文脈を深く理解できるようになりました。
LLM最適化とは、広義には「大規模言語モデルの性能や出力を、特定の目的に合わせて改善するための一連の取り組み」を指す言葉で、その目的は多岐にわたります。
この広範な概念を実務レベルで理解するには、以下の2つの主要なアプローチへの分類が不可欠です。
- アプローチ1:モデルのコア性能を高める「技術的LLM最適化」
- アプローチ2:生成AIに引用されるための「LLMO」
それぞれについて、詳しく説明します。
アプローチ1:モデルのコア性能を高める「技術的LLM最適化」
技術的LLM最適化とは、LLMモデルそのものやモデルを動かす周辺システムに直接的な改良を加え、性能を向上させるアプローチです。
これは、AIの「エンジン」自体をチューニングする行為に例えられます。目的は極めて明確で、コスト削減や応答速度の向上、回答精度の向上といった測定可能なパフォーマンス指標を改善することにあります。
このアプローチによって、以下のことが可能です。
- モデルの内部パラメータを調整する
- より効率的な計算手法を導入する
- 外部の知識源と動的に連携させる
これらは、自社で開発・運用するAIアプリケーションや社内業務の自動化など、クローズドな環境でLLMのコア性能そのものを高めたい場合に不可欠な取り組みと言えるでしょう。具体的には、後述するファインチューニングやRAG、量子化といった技術がこの領域に含まれます。
アプローチ2:生成AIに引用されるための「LLMO」
LLMの成果を最大化するには、もうひとつの重要なアプローチがあります。それが、LLMが参照するWebサイトを整備し、間接的に出力の質を高める「LLMO(Large Language Model Optimization)」です。
ユーザーの情報収集の場が、従来の検索エンジンからGoogleの「AI Overviews」のようなAIとの対話へと移行するにつれて、企業がWeb上で自社を見つけてもらうためのルールも根本から変わりつつあります。
この新しい時代における目標は「検索結果でクリックされること」ではなく、「AIの生成する回答の中で、自社のコンテンツが引用・参照されること」です。
LLMOは、まさにこの目的を達成するための「次世代のSEO」と言えます。それは、LLMが対話する「世界」、つまりWeb上の情報環境そのものをAIにとって分かりやすく信頼できる形に整えていく戦略であり、Webでの情報発信をビジネスの核とする企業にとって、未来の集客を左右する不可欠な取り組みなのです。
LLMOの実践手法としては、「AIが理解しやすいコンテンツの構造化」や「E-E-A-Tで情報の信頼性を示す」などがあります。これらの手法についても、上記記事で分かりやすく紹介しています。
LLMの性能を高める「技術的LLM最適化」5つの手法
ここからは、LLM最適化の技術的な核心部分である、モデル内部に直接アプローチする5つの主要な手法を解説します。これらはそれぞれ異なる課題を解決するために設計されており、目的やコスト、求められる専門知識もさまざまです。
手法1. AIに専門知識や個性を与える「ファインチューニング」
ファインチューニングは、既存の学習済みモデルに独自の専門知識や応答スタイルを追加で学習させる手法です。例えば医療分野のチャットボットに専門文献を学習させ、正確な回答を生成させるケースなどが挙げられます。
この手法のメリットは、特定の業界用語などを学習させて専門性を高めたり、ブランド固有のトーンで応答を統一させたりできる点です。一方、高品質な学習データの準備に多大なコストがかかることや、特定のデータに特化しすぎて汎用性を失う「過学習」のリスクがデメリットとなります。
手法2. 外部データベースを参照し回答精度を向上する「RAG」
RAG(検索拡張生成)は、LLMに外部のデータベースをリアルタイムで参照させる手法です。ユーザーの質問に対してまず関連情報をデータベースから検索し、その情報を基にLLMが回答を生成します。
この手法の最大のメリットは、回答の根拠が明確であるため、LLMが誤った情報を生成するハルシネーションを抑制できる点です。また、データベースを更新するだけで最新情報に対応できます。反面、検索システムの精度が低いと回答の質が低下する点や、ベクトルデータベースなどの構築が複雑である点はデメリットです。
手法3. モデルを軽量化しコストと速度を改善する「量子化」
量子化は、モデルの計算精度を少し下げることでファイルサイズを圧縮して処理速度を向上させる手法です。通常32ビットで表現されるモデルのパラメータを、16ビットや8ビットといった低い精度に変換します。
この手法のメリットは、モデルが軽量化されることでメモリ使用量が削減され、計算を高速化できる点です。これにより、スマートフォンなどの「エッジデバイス」上でもLLMを実行可能になります。一方で、この手法では計算精度を下げることになるため、モデルの性能がわずかに低下する可能性があることがデメリットと言えます。
手法4. 高性能モデルの知識を軽量モデルに継承する「知識蒸留」
知識蒸留は、高性能で大規模な「教師モデル」の知識を、軽量で高速な「生徒モデル」に継承させる手法です。教師モデルの詳細な出力確率(ソフトターゲット)を生徒モデルに学習させることで、単なる正解だけでなく思考プロセスまで模倣させます。
この手法のメリットは、GPT-4のような高性能モデルの知識をより安価な軽量モデルへ凝縮するため、コストを抑えながら高い性能を維持できる点。デメリットとしては、教師と生徒の2つのモデルを準備・管理する必要があり、技術的な難易度が比較的高くなる点が挙げられます。
手法5. 指示の質でAIの性能を引き出す「プロンプトエンジニアリング」
プロンプトエンジニアリングは、LLMに入力する指示や質問(プロンプト)を最適化する技術です。モデル自体には手を加えず、「指示の質」を高めて出力の質を向上させます。具体的には、AIに役割を与えたり回答例を提示したりするといった手法があります。
この手法の最大のメリットは、モデル開発などが不要でコストがほとんどかからない点です。
また、プロンプトを改善すれば即座に応答が変化するため即効性も期待できます。対して、最適なプロンプトを見つけるには試行錯誤が必要なことや、モデルがもともと持っていない知識は引き出せないという限界がある点はデメリットです。
LLM最適化とSEOの関係性:次世代のLLMOとは?
ここまで、モデルの内部性能を高める「技術的LLM最適化」について解説してきました。しかし、LLMの成果を最大化するもうひとつの重要な視点は、LLMが対話する「世界」、すなわちWeb上の情報環境を整えるというアプローチです。
ユーザーの情報収集の主戦場が従来の検索エンジンからAIとの対話へと移行するにつれ、企業がWeb上で見つけてもらうためのルールも根本から変わりつつあります。この新しいパラダイムに対応する戦略こそが、次世代のSEOと位置づけられる「LLMO」です。
LLMOとは?AIに引用・参照されるための次世代SEO
LLMOとは、「AIによる生成文の中で、自社のコンテンツが優位に引用・参照されること」を目指す施策です。
従来のSEOは、検索結果の上位表示によるクリック獲得が目的でした。しかし、Googleの「AI Overviews」のようにAIが答えを直接提示するようになると、ユーザーが個別サイトを訪問する頻度が下がります。
LLMOは、このAIの回答に対して自社情報を引用させやすくするという新しい最適化手法です。従来のSEOとの主な違いは、対象が検索エンジンではなく生成AIモデルそのものである点、そして目的がクリック獲得ではなくAI回答内での引用を増やす(最終的にはそれによって認知度を高める)点です。
▼ LLMO、AI Overviesについては以下の記事をご覧ください。
LLMO(AIO)とは?SEOとの違いとAI時代に必須の対策法を解説
Googleの「AI Overviews」とは?基本的な使い方からSEO・広告への影響まで徹底解説
LLMOの実践手法1. AIが理解しやすいコンテンツの構造化
LLMに自社のコンテンツを正しく解釈・引用してもらうには、AIが理解しやすい情報構造にすることが重要です。AIにとって分かりやすいコンテンツは、人間が読んでも「高品質」と判断されるような内容であることがほとんど。具体的には、以下のような手法が挙げられます。
- h1やh2などの見出しタグで階層構造を明確にする
- 箇条書きや表を活用して情報を整理する
- 誰でも理解できる平易な言葉遣いを心がける
- 見出しの問いに対して結論から答える「結論ファースト」を徹底する
これらの手法は「AIという読者」を意識した、コンテンツの質を高めるための基本です。
LLMOの実践手法2. 情報の信頼性(E-E-A-T)の担保
LLMOにおいて、AIが生成する情報の基となる学習データの質は極めて重要です。そのため、Googleが提唱するE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を担保することが、AIから高く評価されるための基本的な施策となります。
具体的には、誰が書いたかを示す著者情報やサイトの運営者情報を明確に開示することが不可欠。さらに、主張の根拠となる公的データや論文などの参考文献を明記したり、独自の調査データといった一次情報を提示したりすることで信頼性が高まり、AIに「引用に値する質の高いコンテンツ」として評価されやすくなります。
LLMOの実践手法3. AIエージェントへのクロール制御
直接的なLLMOの手法として、AIエージェントのクロール制御があります。
Webサイトの「robots.txt」ファイルに「User-agent: Google-Extended」と「Disallow: /」を記述することで、GoogleのAIモデル学習用クローラーによるサイト全体の情報利用を拒否できます。この設定は通常の検索順位に影響を与えないため、コンテンツの権利を守りつつSEOを維持するのに効果的です。
さらに、AIへの情報提供をより詳細に制御する「llms.txt」という新しい仕組みもあります。
LLMOの実践手法4. 構造化データのマークアップ
「Schema.org」を用いた構造化データのマークアップも、LLMOには極めて重要です。このマークアップにより、Webページ上の「10,000円」が「価格」であることや、「田中太郎」が「著者」であるといった情報の文脈をAIが正確に解釈できるようになります。
AIはテキストの曖昧さを排除できるため、より的確で信頼性の高い回答を生成しやすくなるのです。結果としてAIによる参照・引用の可能性が高まり、コンテンツが価値ある情報源だと認識されるための重要なステップとなります。
技術的LLM最適化とLLMO、どちらを優先的に取り組めば良い?【目的別】
ここまで技術的LLM最適化とLLMOについて解説しましたが、多くのビジネス課題においてまず取り組むべきは、自社で直接制御可能な「技術的LLM最適化」です。とくに自社サービスにAIを組み込む場合や社内業務の効率化を目指す場合、その基盤となるLLM自体の性能が成果の質を直接的に決定づけます。
「LLMの応答が遅い」「コストがかかりすぎている」「不正確な情報(ハルシネーション)を生成する」といった問題を抱えたままでは、どのような優れたアプリケーションを構築しても価値を提供することは困難です。まずは自社の管理下にあるAIモデルの性能を安定させ、信頼性を確保すること。これがLLM活用の基本的な土台となります。
ただし目的や対象、手法、成功指標によってはLLMOを優先したいケースもあります。技術的LLM最適化とLLMOの具体的な目的や対象、手法、成功指標は以下の通りです。
| 技術的LLM最適化 | LLMO | |
|---|---|---|
| 主な目的 | ・モデルのコア性能(コスト、速度、精度)の改善 | ・AI生成回答内でのWebコンテンツの引用や可視性向上 |
| 対象システム | ・LLMモデル(そのもの自体と実行基盤) | ・Google AI Overviews、ChatGPTなどの外部AI ・Webサイト |
| 主要な手法 | ・ファインチューニング ・RAG ・量子化 ・知識蒸留 ・プロンプトエンジニアリング | ・E-E-A-Tの強化 ・網羅性や独自性の高いコンテンツ作成 ・SEOのベストプラクティス ・構造化データの実装 ・XMLサイトマップ最適化など |
| 成功指標(KPI) | ・独自AIサービスの開発 ・社内業務プロセスの自動化(問い合わせ要約など | ・コンテンツマーケティング ・ブランディング ・メディアサイトやECサイトへの自然流入促進 |
| 典型的なユースケース | ・独自AIサービスの開発 ・社内業務プロセスの自動化(問い合わせ要約など) | ・コンテンツマーケティング ・ブランディング ・メディアサイトやECサイトへの自然流入促進 |
| 必要な専門性 | ・機械学習エンジニアリング ・データサイエンス ・クラウドインフラ | ・コンテンツSEO ・テクニカルSEO ・デジタルマーケティング |
上記を踏まえて、どちらを優先的に対策したいかを目的別に解説します。
技術的LLM最適化を優先したいケース:自社AIサービス開発や社内業務自動化
技術的LLM最適化は、LLMのコア性能そのものがビジネス価値に直結する場合に優先したいアプローチです。具体的には、自社でAIを組み込んだSaaSプロダクトなどを開発・提供している場合が該当します。この場合、モデルの応答速度、精度、APIコストは、製品の競争力や収益性に直接影響するため、モデル性能の改善は最優先課題となります。
また、顧客サポートの自動化や社内ナレッジ検索など、クローズドな環境で特定の業務を効率化するためにLLMを利用する場合も技術的LLM最適化が中心です。外部への可視性は不要で、いかに低コストで正確かつ安全に社内タスクを処理できるかが成功の鍵です。
LLMOを優先したいケース:メディア運営やコンテンツマーケティング
LLMOは、パブリックなAIプラットフォーム上での認知度や可視性がビジネスの成功に不可欠な場合に検討すべきアプローチです。これは、コンテンツマーケティング戦略の自然な延長線上に位置づけられます。
例えばニュースサイトやECサイトのように、オーガニック検索からのトラフィックが事業の生命線であるビジネスがこれに該当します。ユーザーの検索行動がAIとの対話にシフトする中で、AIの回答に引用されることは新しいトラフィック源を確保するための必須戦略です。
また、コンテンツを起点に顧客獲得を図っているBtoB企業などもLLMOの優先対象となります。AIが自社製品を推奨する機会を創出することは、強力な認知拡大につながるでしょう。
技術的LLM最適化とLLMOの連携戦略も時には必要
前項では、技術的LLM最適化とLLMOのどちらを優先すべきかについて解説しましたが、競合を圧倒するレベルまでに自社AIの性能を引き上げるには、これらを戦略的に連携することも必要です。
AIの「頭脳」と、それが学ぶ「教科書」の両方を最高品質にすることで、単独の施策とは比較にならないほど回答の精度と信頼性の向上が可能になります。
その相乗効果を最大化するための実践的な2つのシナリオを見ていきましょう。
RAGの参照ソースをLLMOで強化する
RAGで外部データベースを参照する際、LLMOで最適化済みの自社サイトをコンテンツDBとして活用する方法は極めて有効です。
まず自社サイトのE-E-A-T(信頼性など)を高め、構造化データで情報をAI向けに分かりやすく整備します。この最適化されたサイトをRAGの参照先に指定することで、社内AIは常に最新かつ信頼性の高い、整理された社内情報を基に回答を生成できるようになります。
結果として不確かな外部情報源に頼る必要がなくなり、社内AIの回答は情報の鮮度と精度が劇的に向上するため、顧客対応や社内ナレッジ共有の質を大幅に高めることが可能です。
自社サービスに組み込むAIの応答品質を内外から高める
自社開発AIの回答品質を最大化するには、ファインチューニング(事前に学習済みのAIモデルを、特定のタスクやデータセットに合わせて調整する手法)とLLMOの組み合わせが有効です。
まずはファインチューニングで、AIの口調や性格といった応答スタイルをブランドイメージに合わせて制御します。AIが参照する知識は、LLMOでE-E-A-Tや構造化データを整備した自社コンテンツやヘルプページを情報源とします。
この「個性(スタイル)」と「正確な知識」の両立により、ユーザーはブランドに合った親しみやすいスタイルで常に最新かつ正確な回答を得られるようになり、顧客満足度の最大化を図れるのです。
LLM最適化を支える運用基盤「LLMOps」とは
LLM最適化について議論する際、しばしば「LLMOps」という類似した用語が出てきます。
LLM最適化は「何を」するか、すなわち性能向上のための「技術」に焦点を当てています。これに対してLLMOpsは「どのように」それを行うか、つまりそれらの技術を安定的に開発・運用・管理するための「仕組み」や「文化」を指します。両者の違いを理解することは、LLMプロジェクトを成功に導く上で非常に重要です。
ここでは、その「LLMOps」について解説します。
LLMOpsとは?LLMシステムの安定運用を支える開発基盤
LLMOpsとは、LLMを活用したアプリケーションを安定的かつ効率的に開発、テスト、デプロイ、監視、改善するための一連のプラクティスやツール、文化全体を指す言葉です。
これは従来のソフトウェア開発におけるDevOpsや、機械学習全般を対象とするMLOpsの考え方を、LLM特有の課題に合わせて発展させたものです。具体的には、以下のような活動が含まれます。
- プロンプトのバージョン管理
- モデルのデプロイとパフォーマンス監視
- API利用料などのコスト監視
- モデルの出力品質を評価し改善につなげるフィードバックループの構築
レシピ(最適化)とキッチン(LLMOps)の相互関係
LLM最適化とLLMOpsの関係は、料理に例えるとイメージしやすいかもしれません。
LLM最適化の各手法は、最高のパフォーマンスという「美味しい料理」を作り出すための具体的な「レシピ(技術)」です。一方でLLMOpsは、安全かつ効率的に料理を提供し続けるために必要な「キッチン(仕組み)」全体を指します。
つまり、優れたレシピがあっても、整ったキッチンがなければレストランは開業できません。高品質なAIサービスを継続的に提供するためには、優れた「レシピ」と、それを支える頑健な「キッチン」の両方が不可欠なのです。
LLM最適化に関するよくある質問
LLM最適化に関してよく寄せられる質問に回答します。
LLM最適化には、どのような種類がある?
LLM最適化は、大きく2つのアプローチに分けられます。ひとつはAIモデル自体のコストや速度、精度などを改善する「技術的LLM最適化」。もうひとつは、GoogleのAI Overviewsなどで自社のWebコンテンツが引用されることを目指す、次世代のSEO「LLMO」です。
詳しくは、記事内の「LLM最適化とは?成果を最大化する2つのアプローチ」をご覧ください。
GoogleのAI検索(AI Overviews)に引用される方法は?
AIに引用されるためには、LLMO(AIO)と呼ばれる取り組みが重要です。具体的には、「コンテンツの構造を明確にする」「E-E-A-Tを担保し情報の信頼性を高める」「構造化データで情報の意味をAIに正しく伝える」といった手法が有効です。
詳しくは、記事内の「LLM最適化とSEOの関係性:次世代のLLMOとは?」をご覧ください。
LLM最適化と「LLMOps」は何が違う?
LLM最適化が性能を向上させるための「技術(レシピ)」そのものを指すのに対し、LLMOpsは、それらの技術を安定的に開発・運用・管理するための「仕組みや文化(キッチン)」全体を指します。高品質なAIサービスには、この両方が不可欠です。
詳しくは記事内の「LLM最適化を支える運用基盤『LLMOps』とは」をご覧ください。
まとめ
LLMのポテンシャルを最大限に引き出すためには、AIのエンジンそのものを改良し、コストや精度、速度を高める「技術的LLM最適化」と、AIが見つけやすいようにWeb環境を整え、良い教科書(Webサイト)として自社の情報を引用させる「LLMO」という、両面からのアプローチが不可欠です。前者はAI開発者やエンジニア、後者はマーケターやコンテンツ制作者が中心となって進める施策となります。
LLM最適化で重要なのは、自社の目的が「AIの性能を上げること」なのか、「AIに見つけてもらうこと」なのかを明確にし、適切なアプローチを選択することです。本記事が、皆さまのビジネスにおけるAI活用の羅針盤となれば幸いです。

執筆者
生成AIエンジニア / Webマーケティング・生成AI講師
シバッタマン(柴田義彦)
Webマーケティング講師 兼 生成AIエンジニアとして、GA4×BigQueryで計測設計と分析基盤を構築します。研修と伴走で自走化を促進し、広告・SEO・CRMを成果につなげます。
LATEST
最新記事
TAGS
タグ