
企業のSNS成功事例5選!ブランド価値を向上させるSNS活用のポイント
SNSが企業ブランディングにおいて重要な役割を果たす現代。SNSはただの情報発信にとどまらず、ブランドの個性や価値観を伝える場としての活用が求められています。
しかし、単に投稿を行うだけではSNSでのブランディング効果を期待することは難しく、戦略的なアプローチが必要です。ターゲット層に響くメッセージの発信や、ブランドの世界観を体現するコンテンツの制作、そしてフォロワーとの積極的なコミュニケーションが、ブランドの認知度や信頼性を高めるカギとなります。
本記事では、SNSブランディングの基本から、実際にブランド価値向上に成功した企業の事例を通じて、効果的なブランディング戦略のポイントを詳しく解説します。
\ブランディングの基本的な考え方やプロセス、注意点を解説/
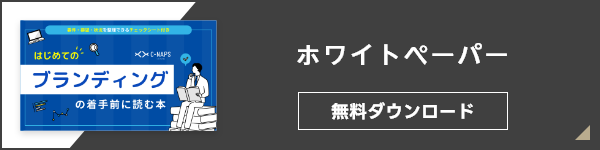
目次
SNSブランディングの重要性
市場の変化や顧客ニーズの多様化を背景に、事業変革やビジネス成長に課題を感じる企業が増えています。そこで重視されているのが「ブランディング」です。
スマートフォンとSNSの普及により、企業ブランディングのあり方は大きく変化しました。かつてはテレビCMや新聞広告など、マスメディアを通じた一方向の発信が主流でしたが、現在ではSNSを通じて、企業と消費者がダイレクトにつながる時代になっています。
この変化はブランドの価値・イメージ・ストーリーをよりリアルに、そしてタイムリーに届ける機会を生み出しました。そして、SNSは企業にとって顧客や消費者といったステークホルダーとの信頼関係を築くための強力なツールとなっています。
「ブランドの認知向上を目的としたSNS活用」に企業が注目
「月刊総務」を発行する株式会社月刊総務が行った調査によると、7割の企業がブランディングに力を入れていること、その手段としてSNS活用は必要だと考えている企業が9割以上いることが分かりました(※1)。
また、プレスリリース代行サービスを展開する株式会社PRIZMAが実施した「SNSの活用実態調査」によれば、公式アカウント・広報アカウントの運用目的で最も多かった回答は「企業やブランドの認知度向上」でした(※2)。
SNSブランディングは、単なる商品のPRやサービスの提供を行うだけでなく、双方向のコミュニケーションにより顧客とのつながり(エンゲージメント)を強固なものにします。その結果として、ブランドの成長につながるのです。SNSを活用することで他社との差別化が図れ、ブランドのファンを増やすことが期待できます。
※1 出典:株式会社月刊総務のプレスリリース「9割以上が企業のSNS活用は必要だと考えている一方、半数以上が自社のSNS活用は『全く進んでいない』と回答。企業が活用しているSNSは「YouTube」がトップで、3割は何も活用していない。」
※2 出典:株式会社PRIZMAのプレスリリース「【企業におけるSNSの活用実態調査】SNSマーケティングの最前線!投稿内容・DM・フォロワー施策を紹介!」
企業のSNSブランディングで成功するための実践フロー
SNS運用を成功させるため、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。ここでは、ブランド戦略を成功させる5つのステップについて解説します。
- ブランド価値の明確化とターゲット設定
- 適切なプラットフォームの選定
- ブランドの声の統一化
- ビジュアルアイデンティティの活用
- 顧客との関係構築
1. ブランド価値の明確化とターゲット設定
SNSにおけるブランド認知は、投稿の頻度とターゲットに合わせたメッセージ設計がカギと言えます。アルゴリズムに好まれるための定期的な更新と、明確なターゲット設定が成功の第一歩となるでしょう。
「企業の想い=コアメッセージ」と「メッセージを届けたいターゲット」が曖昧なまま運用を続けると、発信内容がブレてしまい、逆にマイナスイメージの醸成につながりかねません。ファーストステップはSNSで伝えたいコアメッセージと、それを届けるターゲット層を明確にすることです。
2. 適切なプラットフォームの選定
SNSの魅力は、その拡散力にあります。しかし、SNSとひと口に言ってもさまざまな種類があり、その特徴や機能によって得られる効果も異なります。
「テキストベースでPRしたい」「写真や動画コンテンツを充実させたい」など、拡散したいコンテンツ内容と利用ユーザーの特性・機能といった各SNSの特徴を見極め、最適なプラットフォームを選定することが重要です。
また、誤配信やリソース不足といったリスクを回避するため、慣れないうちは複数のアカウントを同時に運用するのは避けたほうが無難です。SNS運用に余裕が生まれたら、訴求効果を高めるために複数のSNS活用を視野に入れてみましょう。
3. ブランドの声の統一化
トーン&マナー(トンマナ)を統一することで、「この投稿ならこのブランド」と認識されやすくなります。投稿する文章やメッセージに一貫性を持たせることで、フォロワーにブランド価値を訴求できます。
こうしたブランドの「声」を確立させながらも、SNSの失敗にありがちな「炎上」といったトラブルを防ぐ取り組みも同時に行う必要があります。企業イメージを守る厳格なガイドラインやポリシーの策定は必須と言えるでしょう。
トンマナについては、別記事「トンマナとは?基本知識からSEOとの関係性や設定項目、メリット」もご覧ください。
4. ビジュアルアイデンティティの活用
ビジュアルアイデンティティ(VI)とは、ブランドの視覚的要素にあたる部分を意味します。画像・動画などのビジュアルコンテンツはSNSでの印象に直結するため、積極的に活用することをおすすめします。
例えばInstagramで写真をフィードに投稿する際、加工をしたり画像を補足するテキストを付け加えたりといった工夫をすることで、より目を引く効果が期待できます。画像や動画に加えるブランドカラーやロゴの一貫性、洗練されたデザインは、視覚的ブランディングにも効果的です。
5. 顧客との関係構築
SNS運用では、「運用担当者が日記のような投稿をする」「自社商品のPRばかりを行う」といったループに陥りがちです。企業からの一方的な投稿ばかりを繰り返しては、フォロワーが増えるどころか、減ってしまうことも。コメントへのこまめな返信や共感を呼ぶ投稿などを行えば、ブランドと顧客の双方向のコミュニケーションが生まれるでしょう。SNSを起点としたエンゲージメントは、長期的なブランドロイヤルティにつながります。
ユーザーとの関係構築における炎上リスクを回避したい場合は、「STEP3. ブランドの声の統一化」で触れたブランドガイドラインを活用しましょう。
\ブランディングの基本的な考え方やプロセス、注意点を解説/
企業SNSのブランディング成功事例5選
SNS活用によって、製品やサービスの売上アップ、認知度の向上、新ブランドの拡散といった成果を上げた企業は、どういった方法でブランド価値を高めたのでしょうか。ここでは、海外と国内のSNS活用の成功事例を5つ紹介します。
事例1. 化粧品「e.l.f. Beauty(エルフ ビューティー)」
「e.l.f. Beauty(エルフ ビューティー)」は、アメリカのメイクアップブランドです。TikTokで1850万人のフォロワーを持つインフルエンサーを起用したり、飲料水のスタートアップ「Liquid Death(リキッド・デス)」の限定コラボ商品を発売したりするなど、ターゲット層の関心を引くマーケティング戦略を次々と成功させています。
SNSを活用したブランディングとしては、e.l.f. BeautyのInstagramにおいて、インパクトのあるフォトやムービーを使ったフィードで購買意欲の促進にひと役買っています。メタルロックミュージシャンを彷彿とさせるコープスペイントを訴求したLiquid Death限定コラボのフィードは、33万以上の「いいね」を獲得しました。
事例2. 氷削り器魔法瓶「きょろちゃん」
炊飯器や電気ケトル、コーヒーメーカーなど電気調理器具の製造販売を手がけるタイガー魔法瓶株式会社。1976年に販売を開始した氷削り器「きょろちゃん」が、昨今の「昭和レトロブーム」の追い風を受けてSNSなどで話題になりました。
”昭和100年”の節目となる2025年に再復刻を果たし、SNSフォトコンテストキャンペーンを開始。復刻版商品の写真を投稿すると毎月抽選で限定グッズが当たるという内容で、古参のファンから昭和レトロにハマる若い世代と、幅広いファン層を取り込むSNSブランディングが成功につながった要因と言えるでしょう。
事例3. 食べるコーヒー「YOINED(ヨインド)」
ユーシーシー上島珈琲株式会社は、「飲まないコーヒー」という斬新なコンセプトの商品「YOINED(ヨインド)」を2023年に発売しました。「YOINED」の見た目はチョコレートのようですが、カカオは一切入っておらず、コーヒー豆を丸ごと粉砕した独自製法を採用。「コーヒーを食べる」という新スタイルを提案しています。
「香りの余韻を楽しむ」という体験価値を提供するコンセプトが話題を呼びました。UCC上島珈琲店舗と公式オンラインストアのみで販売したにもかかわらず、発売5日で年内販売目標を達成するほどのヒットを叩き出しています。
2024年にX(旧Twitter)にて「YOINED」がもらえるフォロー&リポストキャンペーンを実施したところ、33万以上の「いいね」を獲得。当選した人がSNSでレビューをポストし、それを見た人が「YOINED」を検索するという好循環を生んだSNS戦略は、コーヒーファンの好奇心をくすぐる成功事例のひとつと言えるでしょう。
事例4. ブロックおもちゃ「ナノブロック」
世界最小級サイズのブロック「ナノブロック」の企画・開発・販売を行う株式会社カワダは、2010年にオリジナル作品を募集するコンテストをスタートしました。SNSアカウントから応募可能という気軽さもあり、応募数も年々増加。2025年には応募総数が539作品にも上りました。
ここで注目すべきは、以下の流れでナノブロックを購入するという訴求効果が期待できるSNSブランディングを実現した点です。
ブロック玩具とSNSの相性は非常に良いため、このサイクルが実現したと言えるでしょう。
事例5. 袋型ラップブランド「アイラップ」
岩谷マテリアル株式会社が1976年に販売を開始した「アイラップ」は、同社のロングセラー商品です。Xの公式アカウントは、2025年4月現在で約34万フォロワーを抱えています。
「アイラップ」は一部地域には定着しているものの、全国区での知名度はいまひとつという課題がありました。そこで、認知度を高める取り組みとして商品の活用法をポストするSNS運用をスタート。
SNSユーザーから大きな反響があったのが、2025年3月11日にアイラップ公式アカウントがポストしたアイラップを使った炊飯の方法です。災害時のライフハックとして話題となり、5000を超える「いいね」がありました。アカウント運用の担当者を取り上げたインタビュー記事が別サイトで公開されるなど、SNSブランディングの成功例としても知られています。
企業がSNSブランディングで失敗しないための3つのポイント
SNSブランディングは長期的な運用を前提としたマーケティング施策です。失敗しないためにも、次の3つのポイントに注意しましょう。
運用ルールの周知を徹底する
SNSブランディングは非対面のコミュニケーションなので、ちょっとしたことで誤解や解釈違いが生まれやすく、炎上などのトラブルに発展するリスクが潜んでいます。また、トーンのバラつきや統一感の欠如は、ブランドイメージの崩壊につながります。そういった問題を防ぐには、明確なコミュニケーションルールを策定し、周知徹底することが重要です。
エンゲージメントを高める
フォロワーとの会話、フィードバックへの対応を意識することでブランドの信頼性が高まり、ファンの獲得に直結します。コメントへの返信やアンケートといったユーザー参加型の施策を打ち出して、信頼関係を深めましょう。
PDCAをしっかり回す
エンゲージメント率やクリック数などをもとに、PDCAを回すことが重要です。投稿ごとのパフォーマンスを分析し、改善を重ねることで長期的な成果が得られるでしょう。
まとめ
SNS活用が企業ブランディングに有効な手段となることを、感覚的に理解されている方も少なくないでしょう。しかし、どうしたら良いのか分からずファーストステップから躓いている担当者もいるはずです。
SNSブランディングを成功させるには、「一貫したブランドメッセージ」「ターゲット層とのエンゲージメント」「戦略的なコンテンツ設計」が重要となります。
本記事で紹介した成功事例を参考にしつつ、SNS上でも「ブランドの人格」を確立し、ファンとの信頼関係を築くことがカギです。今すぐ、自社のSNSブランディングを見直し、強化していきましょう!
株式会社ファングリーでは、お客様の目的や課題に合わせてブランディング支援を行っております。コンセプトや方針の策定からクリエイティブの企画制作まで一貫したご支援も可能ですので、ブランディングをご検討中の企業様はお気軽にお問い合わせください。
執筆者
Takehiro Miyagawa
編プロ、出版社、フリーペーパー制作会社などで雑誌編集の経験を経て、現在はコンテンツディレクターとして多様なプロジェクトで活躍中。特に芸能人やタレント・YouTuber・マイクロインフエンサー・経営者・医師などの有識者や専門家のキャスティングやインタビュー企画を得意としている。
LATEST
最新記事
TAGS
タグ




























