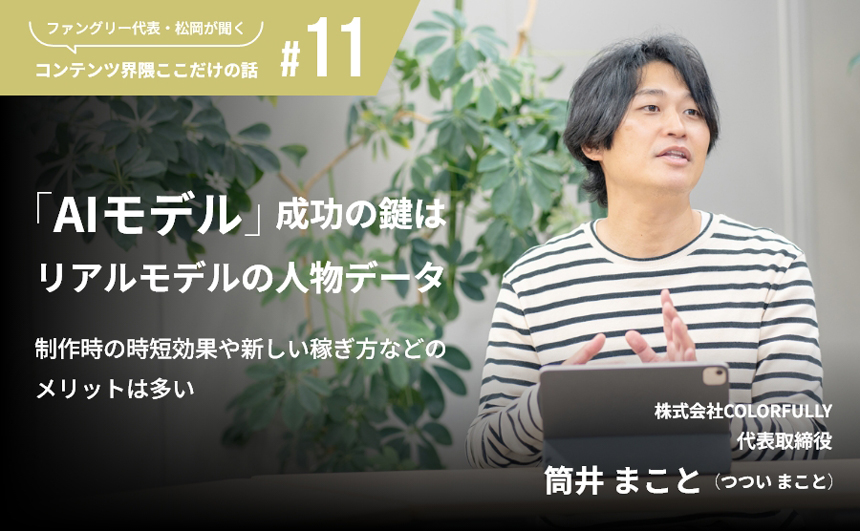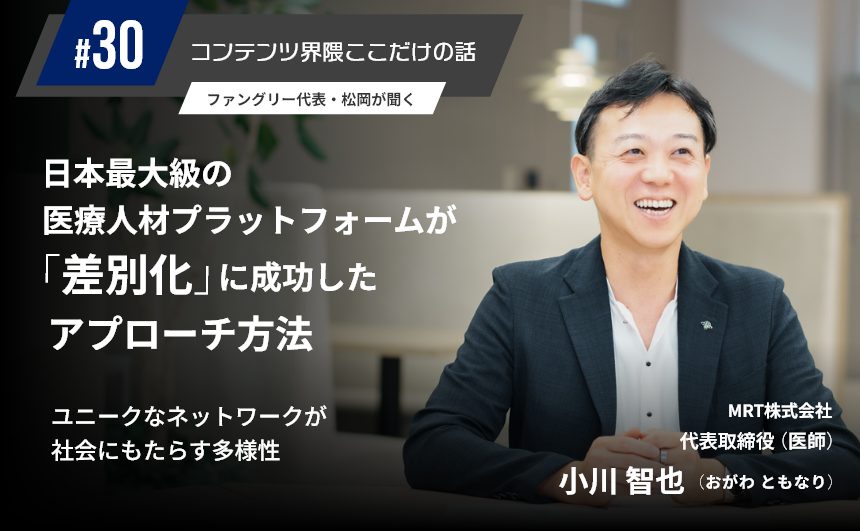
Interview
# 30
日本最大級の医療人材プラットフォームが「差別化」に成功したアプローチ方法|ユニークなネットワークが社会にもたらす多様性
MRT株式会社
代表取締役(医師)
小川 智也(おがわ・ともなり)
コンテンツプロデュースカンパニーとして、企業のコンテンツマーケティングやブランディング活動を伴走支援する株式会社ファングリーの代表・松岡でございます。
「コンテンツ界隈ここだけの話」、第30話のゲストは、全国で約20万人の医療従事者会員を有する医療人材プラットフォームを展開し、医師や看護師を中心に常勤・非常勤の人材紹介サービスを提供するMRT株式会社で代表取締役を務める小川智也さんです。
同社の医療従事者会員ネットワークは、なぜここまで規模を拡大できたのか。そして、医療業界が直面する社会課題に対してどのような価値を発揮しているのか。さまざまなビジネスを仕掛ける小川さんに、事業戦略やブランディングの軸を詳しく伺いました。

MRT株式会社
代表取締役(医師)
小川 智也(おがわ・ともなり)
1973年生まれ。医師・英国国立ウェールズ大学院MBA ・救急科専門医・英国大規模災害対策MIMMS会員。大阪府立千里救命救急センターや国立病院機構大阪医療センター救命救急センターなどを経て、2011年からMRT株式会社の取締役事業本部長に就任。2016年4月には、国内初の遠隔診療・健康相談サービスの提供を開始する。以降、経営戦略室長や副社長などを歴任し、2019年4月から現職。

医師同士で「代診」の相互サポートをするために始まったサービス
──医療業界は、一般の企業以上に医師や看護師などの人材不足が深刻化していると聞きます。そんな中で、医師と医療機関のマッチングサービスという時流に即したビジネスモデルはたいへん興味深いです。本日はよろしくお願いいたします。
こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。
──さて早速ですが、はじめにMRT社がどのような事業を展開しているのか、簡単にお教えいただけますか?
主力事業となっているのは、非常勤の勤務形態に特化した医療人材紹介サービス「MRT WORK」です。人手が不足していてスポット対応でも繁忙期の健診や当直をお願いしたい医療機関と、通常業務外で働ける医療現場を探している医師をマッチングするサービスを提供しています。ちなみにこのサービス、もともとは若手の医師が集まった互助組織からスタートしたのです。
──割とクローズドな業界だと思うので、経営陣に医師が複数いるというのはすごく大きな強みですよね。
はい。医師は「平日は大学病院などで勤務し、夜や土日に非常勤として別の現場に従事する」といったように複数の医療機関で働くスタイルが一般的なのですが、「別の現場で当直の予定があるのに手術が入って行けなくなった」といった事態も頻繁に起こります。そうしたとき、医師同士が代診(主たる医師に代わって診察を行うこと)をサポートし合える仕組みがあると便利だという発想から、ネットワークづくりが始まりました。
こうした背景から、「数時間のみ」「健診対応のみ」「当直対応のみ」といったニーズに最適な非常勤医師の紹介を得意としています。そもそも「ビジネスを拡大したい」というよりも、「現場を支えたい」「医師が働きやすい環境をつくりたい」という想いが原動力となっています。
──単なるビジネスの拡大ではなく、医療現場の改善に軸足を置いている点が特徴的ですね。小川さんはどの段階で参画されたのですか?
会社として立ち上げ、これから大きくしていこうという段階で参画しました。もともとは私自身もユーザーで、はじめは利用する立場から関わっています。
──医師としてユーザーとして関わり、そこからジョインされ、いろいろ役割を経て代表を務められていると。
はい。現在は代表として事業を拡大し、社会的価値を高めていくことが私の役割です。医療現場での課題を、事業を通じて解決していくことを目指しています。「この部分は事業で改善できる」とか「現場だけでは限界がある」といったポイントを、医師の視点から見出すことも私の重要な役割だと感じています。
──MRT社はアライアンスや資本提携、M&Aなどファイナンスの領域にも積極的な印象です。
重要なのは、社会から求められるサービスをいかに提供するかという点です。その実現のために、さまざまな事業展開をしている企業とアライアンスを組んだり、M&Aによってグループとしてその事業に取り組んだりすることが大事だと考えています。
──貴社のビジネスは基本的にBtoD(Business to Doctor)と考えてよいでしょうか?
医師、看護師、薬剤師、放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士などの有資格者が主な顧客です。また近年では、企業への産業医紹介や自治体のワクチン接種会場運営支援など、多様化する医療従事者の働き方支援や保健衛生事業にも注力しています。そのため医療機関のみならず、企業、自治体、官公庁との連携も強化しています。
また、これまでは医療機関に対するサービス提供、いわゆるBtoDがメインの領域でしたが、オンライン診療などのサービスでは患者に対するアプローチ(BtoC)も必要になります。
──現在、医療プラットフォームには約20万人の会員がいると聞きました。どのように開拓していったのでしょうか?
MRTの会員は、友人や先輩・後輩といった信頼できる人脈を通じて広がっていったという特徴があります。「信頼できる仲間が集う場所」という軸が、ユーザーとしての安心感を生み出している部分はあるかもしれません。
それともう一つ、「困っている人がいたら助けたい」という医療従事者特有のマインドも大きいですね。コロナ禍の時もそうでしたが、「医療現場が困っている」「地域医療が逼迫している」といった状況下で「自分にできることがあれば」と多くの医療従事者が協力してくださいました。
──口コミ的な活動で20万人も集まるのはすごいですね。この業界ならではと言えるかもしれません。
ありがとうございます。私たちは社会課題を見つけ、それを適切な文脈で発信することで共感を呼び、ユーザーが自ら集まる仕組みを構築してきました。
自分たちのつながりだけでは「広く周知する」にも限界がありますが、Webサイトなどを使うことで「実はこういった人が困っている」「こういう課題が日本社会にはある」という状況を広く発信できます。それが一番の集客になっていると思いますね。

現場を知る医師の存在が「(他社と)ちょっと違う」の評判を作る
──医療業界はそもそも新規参入が難しいと思います。ドアノック(見込み顧客への接触やきっかけづくり)は苦労なくできたのでしょうか?
医学生や若手医師が集まる医学会や医学研究会への参加など、地道な周知活動を繰り返し、先生方との対話を通じて現場の課題感などを共有したりもしていました。
──「MRT WORK」の場合は運営側にもドクターがいるので、そのハードルが低かったのかもしれません。
それもあると思います。医療現場の実情を理解している医師が現場の課題をいち早く察知し、医療機関と医師の双方にとって重要となるポイントを的確に把握した上で、スタッフに直接共有できるという点は大きな強みです。それが「(他社とは)ちょっと違う」という評判になり、信頼の獲得につながったと思っています。
──国内外の市場規模は、どのような感じで広がっているのでしょう?
「人材が充足したら成り立たないビジネスモデルなのでは」と指摘されることもありますが、実際は医療機関向けの人材紹介だけでもまだまだ開拓の余地が残されています。
というのも、多くの非常勤医師が大学病院人事のもとで勤務しており、いわゆる「表に出てきていないニーズ」が数多く存在しているためです。そうしたニーズを医師人事のアウトソーシングという観点から支援していくと考えれば、今後も大きな市場拡張が見込める分野だと捉えています。
──副業も含め、空き時間で自身の知見を活かせるオンライン診療にも可能性を感じますが、実際のところどんな状況なのでしょうか?傍から見ると、まだまだ浸透していないのかなという印象ですが。
はい、これからといった感じですね。例えば、産休明けでまだ現場復帰できない先生でも、オンラインなら医療とのタッチポイントを持てます。その点でも、新たな働き方を提供できる余地は大いにあると考えています。
医療DXは国が方針として進めようとしていますし、そこは追随していきたいです。また、自治体との連携ではワーケーション支援などにも取り組んでいます。
──「医療版ワーケーション」の取り組み成果に関するリリースを拝見しましたが、すごく有意義な取り組みですね。
現在取り組んでいるのは、観光地でありながら「医療過疎」とされる地域における医師の、新たな働き方の提案です。例えば、小児科や救急など地域で不足している診療科の医師を1日~数日単位で地域の医療機関に紹介し、地域医療に従事していただきながら勤務日以外は観光を楽しんでいただく。つまり、「医療過疎の改善」と観光を通した「地域経済の活性化」を掛け合わせた仕組みです。最近では単身での赴任にとどまらず、ご家族そろってその地域に滞在されるケースも増えてきました。
もうひとつは、IターンやJターンですね。都市部で働いている先生の中には、「いずれ地元に戻りたい」とか「今より少しゆっくり働ける場所を見つけたい」という方もいます。

──将来的な地域医療の人材確保を見据え、まず新しい働き方を試してもらう。
そうです。和歌山県のある地域では、医師の高齢化により救急科の存続が危ぶまれている状況がありました。しかし医療版ワーケーションを通じて30〜40代の医師が地域に赴任したことで、地域住民の命と健康を支える救急医療体制を維持できました。このような成功事例を受け、医師確保対策の一貫として検討してくださる自治体も着実に増えつつあります。
──ちなみに、ワーケーション以外にも医療課題に即した取り組みはありますか?
ワーケーション以外では、「オンラインこども診療」があります。昼間は小児科の先生がいるものの、夜間や休日は救急しか空いておらず、小児科専門の先生に診てもらえないという自治体は少なくありません。そういった課題に対応するため、オンラインで専門の先生が診療できる環境作りをサポートしています。
また、医療の緊急事態、医療ひっ迫を回避するという観点では「医療MaaS」の運用も重要です。医療MaaSは車両を使って必要な場所へ医療を届ける仕組みのことで、車内の大型モニターを通じて病院にいる医師と患者をオンラインでつなぎ、その車内で診療を行うサービスを提供しています。現場には看護師が患者宅付近まで出向き、車両内でバイタル測定なども行います。医療MaaSは、医療的処置が必要になった場合やインバウンドで来られた方の対応が必要なときなどに評価をいただいています。
──インバウンドの方が医療を必要とする場合、何が一番の課題になるのですか?
まずは言語の問題です。また「どの医療機関を紹介すべきか」で困ることもありますし、宗教的な問題で治療内容が限られるケースもあります。そういった点をオンラインで事前に整理するだけでも、現場の混乱は防げると感じています。
──インバウンドの方への医療の提供は、事業としても成立するのでしょうか?
インバウンド対応に関しては、海外の方は健康保険ではなく旅行保険を使われることから費用の支払いについて理解があり、事業的には成立すると考えています。
また、他社でもインバウンド向けのオンライン診療サービスを手掛ける動きが見られます。しかし、診察のみの対応で処方箋は手に入らず、結局現地の医療機関を受診しなければならない――といった課題もあると耳にしています。その点、MRTのサービスは診療にとどまらず、薬の配送や医療従事者の現地派遣にも対応しており、患者にとっての安心が確保されている点が大きな特徴です。このように、診療からフォローアップまで一貫してサポートできる体制こそが、他社サービスとの差別化につながっていると自負しています。
──なるほど。オンライン診療だけでは補完できないリアル面までサポートできる会員ネットワークがある点が、他社との差別化につながっているわけですね。
はい。コロナ禍におけるワクチンの大規模接種会場の運営に携わった際にも、同時期に多くの医療従事者の確保と配置が求められました。その中で、自治体から求められる人数や専門性に応じた医師・看護師をタイムリーかつ的確に配置できた点は、特に高くご評価いただきました。

ビジョンや共感を呼ぶようなメッセージがないと人は集まらない
──MRT社の事業を支えている人材プラットフォームに関して、今後の事業戦略や拡張性の観点から、どのような展開をお考えでしょうか。
まさに今年、海外展開をスタートさせたところです。ベトナムから始まり、東南アジアの全エリアで医療従事者と連携していきたいと考えています。
──それは現地の日本人医師との連携ですか?
日本人医師だけでなく、外国人医師も含みます。現地(国内)で働きたいケースもありますし、クロスボーダーで働きたいという要望も今後増えてくるでしょう。オンライン診療が一般化すれば、「自国の先生に診てほしい」という声も出てくるはず。こうしたニーズの広がりを考慮し、当たり前のように世界と連携できるプラットフォームを構築していきたいです。
──まず東南アジアから海外事業を開始された背景には、どのような戦略的な判断があったのでしょう?
一つは、人口増加率に医療ニーズが追いついていない市場であること。加えて、東南アジアで40万人ほどのドクターネットワークを持っているシンガポールのDocquity(ドクイティ)社と事業連携できたことが大きいですね。
その会社は、製薬ビジネスやドクターが専門医資格を取得する際のeラーニングシステム運営などを手掛けています。一方でMRTは、人材紹介を通じて医療機関とのリアルなタッチポイントを増やしていくアプローチを取っています。データベースの活用目的が違うので、連携しながら違う事業を広げていくことも可能だと思っています。

──パートナー開拓やアライアンスは、小川さんご自身が進められているのですか?
もちろん私も探しますが、引き合いがあったり紹介をいただいたりもします。医療制度や保険制度に関しては、こちらがマーケットを作り出していくより、ニーズや課題があるところに入り込んでいくほうがスムーズに展開できると思っています。
──それは、相談が来るような下地(=ブランド)ができている証拠だと思います。投資家や全国の取引先に対して、何かブランド価値を意識した情報発信をされているのですか?
そうした取り組みは、対医療関係者のそれに比べるとまだまだ発展の余地があると感じています。私たちが重視してきたのは、あくまで「医療従事者からどう見られるか」。現場に寄り添い、現場の信頼を得ることで企業としての価値を築いてきた、というのがこれまでのスタンスです。
しかし、取引先やサービス領域が広がりを見せる中で、私たち自身のあり方も変わるタイミングに差し掛かっていると感じています。「現場からの信頼」に加え、「社会からの信頼」も得るべきフェーズに入りつつある――。まさに、今がブランド戦略の転換期なのだと思います。
──東大医学部出身メンバーが作ったというユニークネスや独自の医師ネットワークは、ブランド価値になるのでしょうか。
確かに、関東圏の展開においては「東大ブランド」が一定の信頼や注目を得る上で大きな強みになっていました。ただ、私たちは「医療従事者に寄り添う医師の組織である」という本質的な価値に、ブランディングの軸を置いています。
「学閥」というよりは、現場で働く医師・看護師・医療従事者のリアルな課題を理解し、支える存在であること。それこそが、私たちが本当に届けたい「ブランドの信頼性」だと思っています。
──BtoDのマーケティングや広報は、どういった優先度でやられているのですか?
マーケティングや広報に十分な人材を割けていないのが現状です。裏を返せば、そこに積極投資せずとも事業を拡大できているとは言えますが……。
──海外事業展開について、今後の計画やトピックスがあれば教えてください。
ネットワークで抱えている人材をフックとして、官公庁や地域の大学病院などと連携していくことが重要です。ほかに、規制が多い日本ではできないようなサービスの展開も考えています。すでに現地で活躍してくれているメンバーもいるので、ローカライズに関する情報も集めやすいですね。
ベトナムでは、日本で展開しているサービスをそのまま持ち込む準備をしています。「医療施設が増える一方で医師は全然足りていない」という現状があるので、転職サービスを入り口としつつ「非常勤で働く」という新たなワークスタイルを作り出していくことも必要と考えています。ベトナム以外では、インドネシア、マレーシア、シンガポールも検討しています。
──医療業界における競争優位性や差別化戦略として、小川さんが最も重視している要素は何でしょうか?
ネットワークの規模だけでなく、どこに向かっているのかというビジョン、医療従事者の共感を呼ぶようなメッセージがないと人は集まりません。ですから、医療従事者、医療機関、そして医療を必要としている社会全体に対して、共感を生み出すようなメッセージをどう伝えられるかが重要なのではないでしょうか。
──外向けのコミュニケーションにも内向けのコミュニケーションにも一貫性が重要ですね。
「共感を生み出す」という点では、今よりも医療現場にいたときのほうが簡単に感じました。「患者を助ける」「命を救う」という極めて明確な目的のもと、何も言わなくても皆が同じ方向を向いてくれるので。
──事業規模が大きくなるにつれて、社内の一体感が失われていくこともあるかもしれません。そのあたりのマネジメントはどう工夫されているのでしょう?
私たちが大切にしているのは、役職に関係なくフラットに意見を交わせる風通しの良い組織風土です。トップダウンではなく、むしろ一人ひとりが「こうしたい」と自ら考え、行動に移せるカルチャーが会社を強くし続けていく鍵だと考えています。組織の人数が増えても、根底にあるのは「医療を想い、社会に貢献する。」という共通のミッション。この想いが全員に浸透していれば、どれだけ組織が大きくなっても本質的な一体感は失われないのでは、と考えています。
──3年後、5年後、どんな会社にしていきたいというイメージはありますか?
M&Aも実施している関係で、MRTという名前を社名に冠していないグループ会社も多くあります。しかし、事業を行っていく中で「MRT」というキーワードが社名にあるほうがユーザーにとっても分かりやすく、事業も複合的に展開しやすかったんですよね。なので、グループ会社のネーミングやグループ全体としての見せ方をMRTブランドに寄せていこうかなと考えています。
──グループ全体としてのMVVはあるのでしょうか?
いや。今はグループ会社それぞれが個別のミッションやビジョンを掲げている状態で、それを包括するようなグループ全体のメッセージについてはこれからというところです。
──まずはグループとしてのMVVを策定し、それをスタッフに浸透させる。合わせて、外向けにも一貫性をもって情報発信していく。これから海外事業に注力することも考えれば、ブランディングによる土台固めが非常に重要になりそうですね。
はい、そう思います。
──インナーブランディングもアウターブランディングも、ぜひファングリーにご用命いただければ(笑)。
ありがとうございます。ぜひ相談させてください。
──少子化や技術革新などの影響で医療のオンライン化が進む中、小川さんが「リアルをサポートできるネットワーク」というMRT社の強みを武器に、どう社会課題を解決していくのかぜひ注目していきたいです。本日はありがとうございました!
LATEST
最新記事
TAGS
タグ