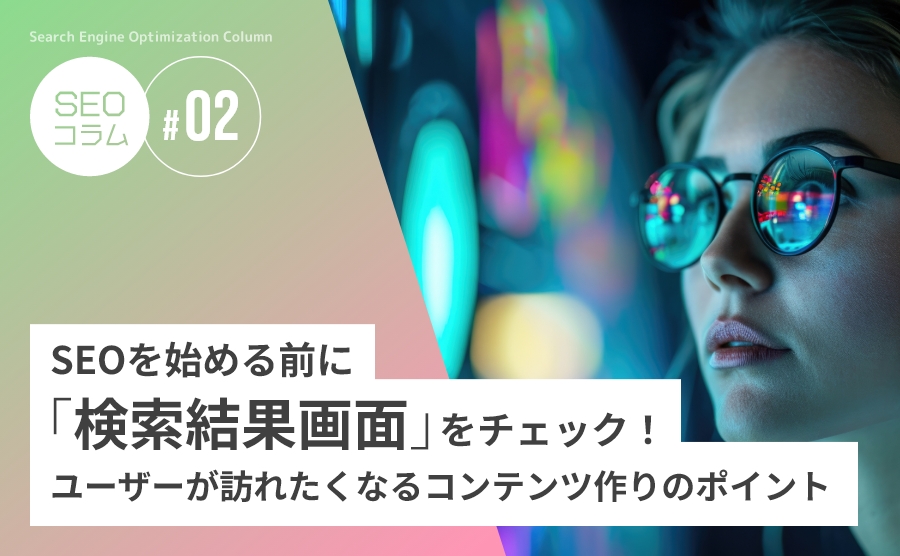Interview
# 32
カウンセリングといえば「cotree」。第一想起を取るための戦略と選択|カウンセラーの採用広告費ゼロを実現したアプローチとは
株式会社JMDC
オンラインカウンセリング「cotree」フェロー
西岡 恵子(にしおか・けいこ)
コンテンツプロデュースカンパニーとして、企業のコンテンツマーケティングやブランディング活動を伴走支援する株式会社ファングリーの代表・松岡でございます。
「コンテンツ界隈ここだけの話」、第32話のゲストは、国内最大級のカウンセリングプラットフォーム「cotree」(コトリー)を運営する株式会社JMDCの西岡恵子さん。カウンセリング提供件数15万件超、登録カウンセラーは総勢約220名という大規模なカウンセリング事業の推進を担う西岡さんに、マーケットの「作り方」と「動かし方」をお聞きしました。

株式会社JMDC
オンラインカウンセリング「cotree」フェロー
西岡 恵子(にしおか・けいこ)
1990年、浜松市生まれ。大学卒業後、森永製菓株式会社や株式会社サイバーエージェントを経て、コネヒト株式会社では事業責任者としてママ向けアプリのサービス戦略設計・ビジネスグロースを手掛けた。2021年から株式会社cotreeに参画し、2022年1月に代表取締役へ就任。2025年2月の吸収合併後は、株式会社JMDCでcotree事業のフェローとして引き続き事業推進の役割を担う。一般社団法人日本フェムテック協会顧問。

「いつかこの領域に携わりたい」が、まさに「今なら」へ
──メンタルヘルスは現代の社会課題とも言えるテーマであり、「ウェルビーイング経営」は近年のトレンドにもなっています。その中で、西岡さんが日本最大級のオンラインカウンセリングプラットフォームなどの事業をどのように広げているのか、詳しく伺えればと思っています。
取材していただき嬉しいです。メンタルヘルス業界には独特のマーケティング手法があるので、私たちが実践していることなどから何か参考にしていただけることがあるかもしれません。よろしくお願いします。
──それではまず、西岡さんの簡単な自己紹介とcotree(コトリー)に参画された背景についてお聞きしたいです。途中から参画されて、その後経営を引き継がれたのですよね?
はい。2021年から株式会社cotreeにジョインし、その数ヶ月後に2代目の代表に就任しました。今年2月にcotreeが親会社であるJMDCに吸収合併されたため、現在はJMDCにおけるcotree事業のフェローという肩書きで、引き続き事業推進やスポークスマンとしての活動を担っています。
──なるほど。ということは、最初から代表を引き継ぐことを想定してジョインされたんですね。吸収合併に至るまでの経緯についてもお聞きしたいです。
会社の売却は2021年に行われ、それからの約3年半はJMDCの完全子会社として経営を続けていました。ちょうどコロナ禍でオンラインカウンセリングがブームになった頃で、事業のフェーズが大きく変わったことが理由です。このブームを文化として根付かせるには、スタートアップ一社単体ではなくヘルスケア領域で大きな事業基盤を持つ会社のもとで運営するほうが良いだろう――と考え、未来を見据えて体制を変化させてきました。
──激動のタイミングで西岡さんはジョインされていますが、そもそもどのようなきっかけでcotreeに加わられたのですか?
今お話ししたコロナ禍で事業フェーズが変わったタイミングで、代表を交代することを前提としたオファーをいただきました。
──数ヶ月後に代表就任ですもんね。
ええ(笑)。創業者は、事業の急成長を見据えるフェーズであっても、いわゆる「プロ経営者」ではなく事業への思いをしっかり継承してくれ、未来を創ってくれる人が望ましいと考えていたようです。私が前職で「ママリ」というママ向けアプリ・サービスの事業責任者をしており、ユーザーに寄り添った事業創造経験があったこと、そして私自身の生き様も踏まえたスタンス、事業や組織への向き合い方などから、「託したい」と思ってもらえたのではないかと思っています。
──森永製菓やサイバーエージェントといった、メンタルヘルスやカウンセリングとは直接関係のない業界にいらっしゃったと思いますが、もともとこの分野には興味をお持ちだったのですか?
ありました。社会人キャリアとしてはまったく違う分野にいましたが、私自身が幼少期に自分らしくいることが難しかった経験から、「いつかこの領域に携わりたい」という思いをずっと持っていたんです。
ただ、原体験が強すぎると事業としてうまくいかないことも理解していたので、ある程度スキルを身につけてからと考えていました。20代後半、仕事の面白さが分かってきた頃に声をかけていただき、まさに「今なら」という使命感を感じられるタイミングでしたね。「誰もが自分らしく生きられる社会を作りたい」という、本当にやりたかったことへ舵を切るきっかけとなりました。
──cotreeの事業内容について、具体的に教えていただけますか?
オンラインカウンセリングでは、「話すカウンセリング」と「書くカウンセリング」の2サービスを展開しています。事業をスタートしたのは2014年からで、この領域ではパイオニア的な存在として10年以上サービスを提供してきました。臨床心理士(※1)や公認心理師(※2)といった心理資格を持つ専門家が多くカウンセリングを担当しており、現在は約220名のカウンセラーが登録しています。
※1 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する民間資格
※2 2017年に施行された「公認心理師法」に基づき設立された、日本初の心理職の国家資格

──「書くカウンセリング」とは、どのようなものなのでしょうか?
いわゆるチャットのようなリアルタイムコミュニケーションではなく、オンライン上で手紙を交換するようなイメージです。 相談者の方が文章で悩みを書いて送ると、1日約1往復のペースでカウンセラーから返事が届く仕組みです。 口頭では悩みを打ち明けづらい方、話すより文章を書くほうが得意な方、あるいは育児中でまとまった時間が取れない方などが、空いた時間に下書きをしながら利用されています。
──事業規模について、公表されている数字やデータなどがあれば教えていただけますか?
これまでのカウンセリング提供件数は15万件を超えます。カウンセリングの時間枠(45分間)を設けた形でのオンラインカウンセリング提供件数としては、国内で最大級の規模だと思います。2021年から開始した法人向け事業も順調に拡大しており、事業全体として成長を続けています。

「自社サービスの価値」よりも「業界全体の価値」を高める意識
──カウンセリングはどのような方が利用されているのでしょうか。個人向け、法人向けそれぞれの利用者層について教えてください。
個人向けでは、過去に精神科への通院経験がある、もしくは通院中の方が約半分。もう半分は、身近な人には相談しにくい悩みや、キャリアや人生をより良くしたいといった前向きな悩みを、利害関係のない第三者に聞いてもらいたいというニーズで利用されています。私たちのカウンセリングではマイナスの状態をゼロに戻すだけでなく、キャリアプランニングなどコーチングに近い領域までカバーしているのが特徴です。
法人向けは、外部の相談窓口として導入いただくケースが多いですね。「産業医に相談しづらい」「上司に関する悩みを社内の人には話せない」といったような従業員の不安に応える形で活用されています。福利厚生を充実させたい大手企業から、人事担当者が多忙でメンタルヘルス不調者への対応まで手が回らない中堅・中小企業まで、お客様の規模はさまざまです。
──個人向けと法人向けでは、マーケティングの手法も大きく異なるかと思います。どのようにブランドコミュニケーションを設計し、展開されているのでしょうか?
私たちの基本的なスタンスは、目の前の一人をしっかりサポートすること。これは個人向けでも法人向けでも変わりません。ただ、法人向けの場合は決裁者が経営者や人事責任者になるため、「誰のためにサービスを提供するのか」という点は非常に難しい部分だったりしますね。直接のお客様は決裁者の方なのですが、私たちとしては、その先にいる従業員の方々のメンタルヘルスが本当に改善されるかどうかを最優先に考えたいと思っています。
個人向けに関しては、創業当初から第一想起を取るためのブランディングに力を入れてきました。その結果、現在は個人のお客様のほとんどが自然流入、つまりオーガニック検索や「cotree」という指名検索でサービスにたどり着いてくださっています。「cotreeではじめてカウンセリングを受けます」というお客様も増えているので、マーケットを作れている感覚はあります。
──「オンラインカウンセリング」というキーワードで第一想起されるポジションを築くため、具体的にどのような戦略を採ってきたのでしょうか?
私たちは「自社サービスの価値を高める」こと以上に、「業界全体の価値を高める」というスタンスを貫いてきました。例えば、メンタルヘルス業界の「カオスマップ」をパートナー企業と共同で作成したり、ユーザーの悩みに関するデータを研究に活用してもらう「データドネーション」のような取り組みを主導したりしてきました。

──市場が成熟していない段階でのマーケティング戦略として、とても参考になります。大学の先生方などの協力のもと、学会などで研究成果を発表したりもしてきたのでしょうか?
はい。大学との共同研究を実施させていただいており、その成果はオープンソースとして公開しています。このような活動を積極的に行ってきたこともあり、業界関係者の方々から「この領域を語るならcotreeは外せない」と認識していただけるようになりました。お客様だけでなく、アカデミアや専門家の方々からも信頼される存在になれたことが、結果として大きなブランド価値につながっていると考えています。
──具体的にはどのようなビジネス成果がありましたか?
研究レポートがいろいろな資料やメディアで引用されることで、cotreeの認知度はさらに高まります。またカウンセラー採用においても、こうした取り組みを見て「cotreeで働きたい」と応募してくださる方が増えたため、採用広告費はまったくかけていません。ブランディングへの投資が事業の根幹であるカウンセラーの確保、ひいては売上に大きく寄与するという好循環が生まれています。
──先ほどオーガニック検索からの流入がメインというお話がありましたが、コンテンツマーケティングにおいてはどのような点を意識されていますか?
10年以上の運営で蓄積してきた1,000本以上の記事コンテンツを資産とし、常に最新の情報にアップデートしながら活用しています。特に意識しているのは、社会問題や世の中のトレンドと関連性の高いテーマを、できるだけタイムリーに発信することです。チーム内では毎日トレンドニュースや最新の論文を共有し合い、海外の新しいメンタルヘルスサービスの情報など、まだ国内で報道されていないような情報も積極的にキャッチアップしています。
──デリケートな領域だけに、コンテンツ制作や広告表現においては書き方・伝え方が難しいケースもあるかと思います。
おっしゃる通り、メンタル不調を抱えている方が記事を読んだ際には、傷ついたり不安になったりするケースもあるかもしれません。そういった点を踏まえて、言葉遣いやキーワードの選び方にも細心の注意を払っています。この「誰も傷つけない表現」についてもノウハウがあり、私たちの大きな強みとなっています。
──記事はどのような体制で作っているのでしょうか?
プロジェクトマネージャーの指揮のもとで内製しています。ナレッジを熟知したライターが記事を書き、テーマによっては専門家の監修も入れています。
──E-E-A-T対策もしっかりされているわけですね。メディア運営のKPIはどのように設定されていますか?
もちろん、PV数や送客数といった一般的なマーケティング指標も追っていますが、数字を追い求めるあまり過度にバズを狙うようなテーマで記事を作成することは避けています。

cotreeが選ばれる理由は「安心・安全」とカウンセラーの質
──これまで特に反響が大きかった記事や、うまくいったマーケティング施策はありますか?
直接的な売上に大きく貢献したわけではありませんが、「ピーターパン症候群」や「スーパーウーマン症候群」といった心理状態に関する言葉を解説した記事は、公開から時間が経った今でも定期的にSNSで話題になることがあります。社会的な出来事としてニュースになった際や、関連テーマで著名人の方が発信をされた際などに、私たちの記事が引用されるというケースです。
このように、長く参照され続ける「ロングセラー記事」が複数存在することが、メディア全体の安定した評価につながっていると感じます。
──SEO以外のコンテンツ戦略、例えばインフルエンサーやタレントを起用した施策に取り組んだことはあるのでしょうか?
過去に試みたことはありますが、残念ながらほとんど効果がありませんでした。ママインフルエンサーの方にカウンセリングを体験していただき、その感想を発信してもらうという企画を実施したものの、新規ユーザー獲得にはつながらず……。やはりカウンセリングというサービスの性質上、悩みの詳細をオープンに語ることは難しく、キラキラした見せ方に持っていくと本質からずれてしまうという課題があります。
一方で、タレントさんがご自身の著書の中でcotreeのカウンセリングを紹介してくださったり、YouTuberの方が名前を出してくださったりすることもありました。そのようなご紹介の機会は時々あって、そういった際には問い合わせが急増しましたね。
──カテゴリが育ち、競合サービスも増えている中、cotreeが選ばれる理由は何だとお考えですか?
一番の強みは「安心・安全」である点です。悩みを聞くサービスだからこそ、個人情報がどう扱われるか、本当に信頼できるサービスか、という点はユーザーにとって非常に重要です。先ほどお話しした業界全体の価値を高める活動や、ユーザーが安心して使える言葉づかいや色彩(強すぎる色を使わないなど)にこだわったUI/UXデザインなどが、選んでいただける要因になっていると思っています。
──小さな配慮の積み重ねが、積もり積もって信頼性を高めている。
はい。もう一つの強みは、経験豊富でさまざまな領域で活躍されているカウンセラーとのネットワークです。私たちはカウンセラーの皆様も「お客様」と捉えて運営をしており、その姿勢から専門家をサポートする体制がサービスの質を担保し、自社の強みにつながっていると考えています。
──カウンセラーの数は足りているのでしょうか?他の業界のように人材の獲得競争のような状況はありますか?
カウンセリングに関する資格保有者は増加傾向にあります。社会全体でメンタルヘルスへの関心が高まっていること、公認心理師という国家資格ができたこと、若い世代にとってスクールカウンセラーが身近な存在になったことなどから、カウンセラーを目指す人が増えるべき状況が整いつつあると考えています。
一方で、カウンセリングを受ける文化は、諸外国に比べてまだ十分に根付いているとは言えません。そのため、市場のボトルネックは供給不足ではなく、利用者の心理的・文化的なハードルにあります。ですから、人材の取り合いというよりは、カウンセリングを日常的に利用する文化をどう社会全体に広げていくかが業界全体の課題となっています。
──では最後に、事業の課題と今後の展望についてお聞かせください。
最大の課題は、日本における「未病・予防」への意識の低さです。日本には優れた国民皆保険制度があるため、体調が悪くなってから病院に行けば適切な医療を安価で受けられます。それゆえ、「病気になる前のケアにお金を使う」という習慣が根付きにくいのです。
──それはよく言われますよね。文化的な背景が、メンタルヘルスケアの普及においても大きな壁となっているのですね。
この課題を乗り越えるため、今後はアプローチを少し変えていくことも検討していかなくてはならないと思っています。例えば、「心の病」という直接的な表現ではなく、「女性の健康」といった切り口へのシフトですね。生理痛や妊娠・出産、産後の不調といった具体的な悩みからアプローチし、その背景にあるストレスや心の課題に気づいていただく、という導線を強化していくことなども考えられると思っています。
そのほかには、JMDCの一員となったことで同社の健康管理アプリ「Pep Up」との連携などグループシナジーを活かした展開も加速させていく予定です。
──企業におけるカウンセラー導入や早期に専門家への相談を促すカウンセリングサービスの活用は、今後ニーズが高まっていくかもしれません。その中で、cotreeと西岡さんが業界をどうけん引し、新しい文化として根付かせていくのか注目しています。本日はありがとうございました!
LATEST
最新記事
TAGS
タグ