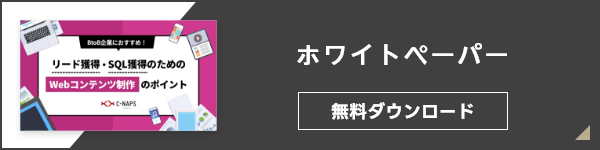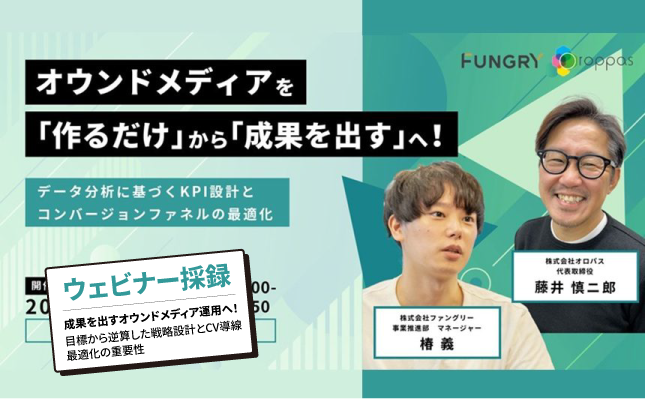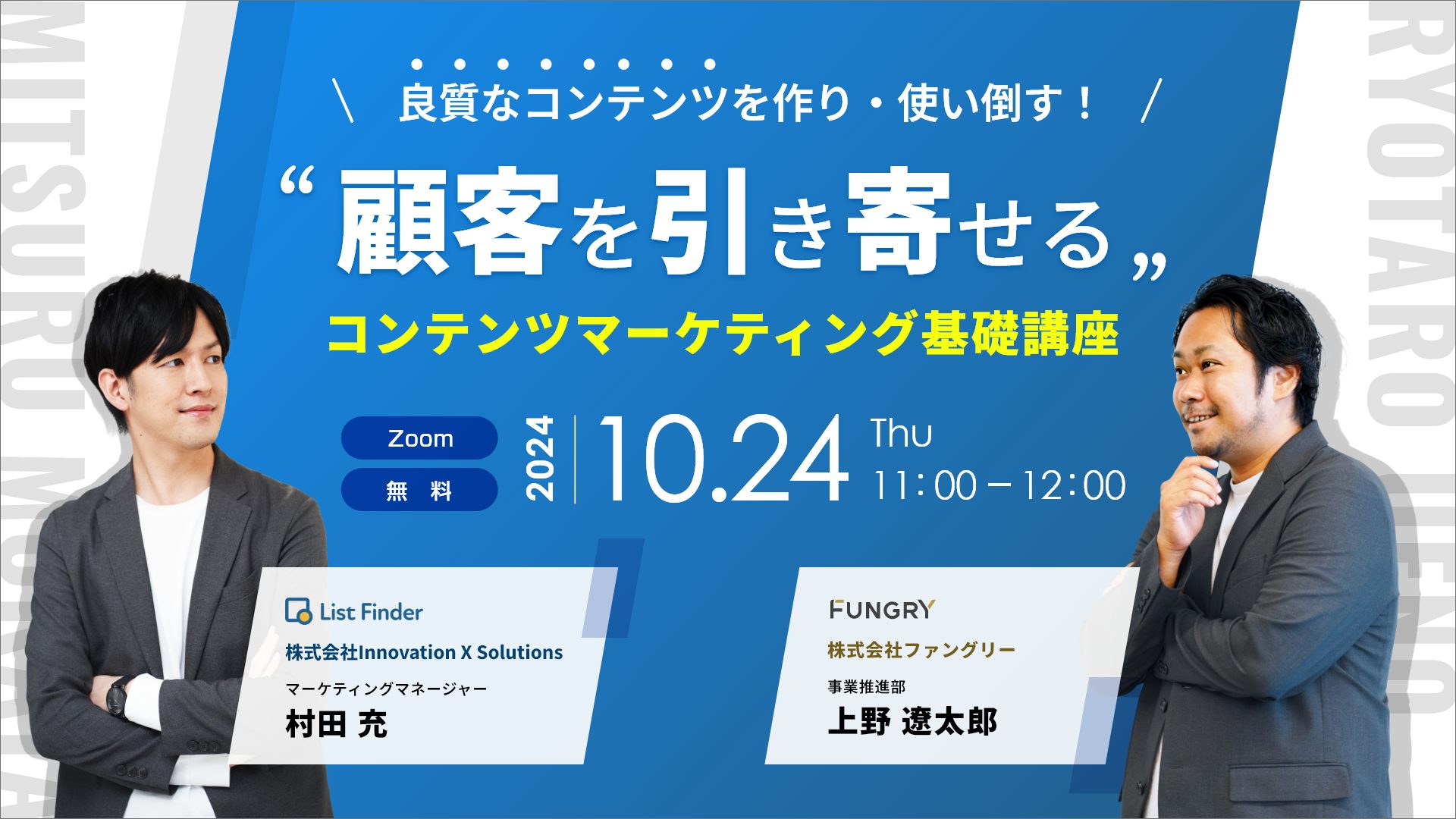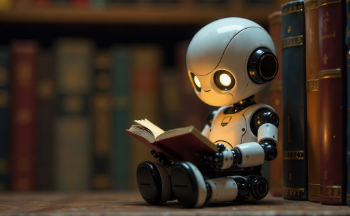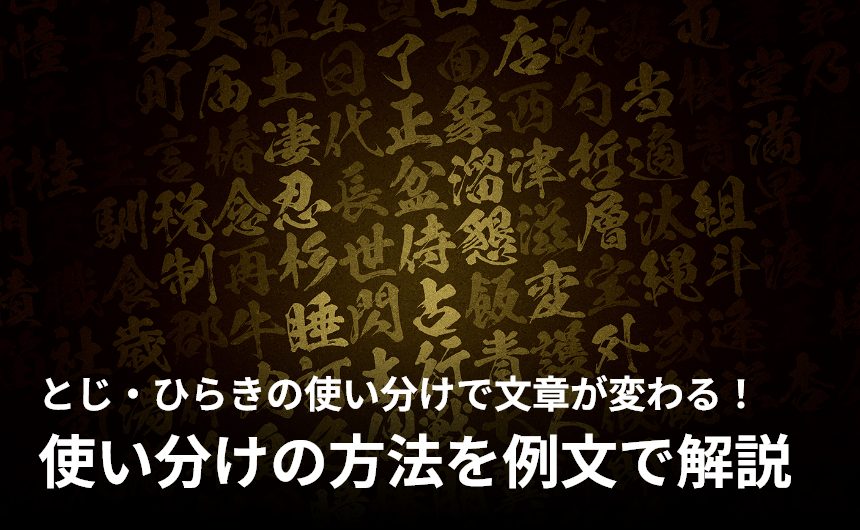
とじ・ひらきの使い分けで文章が変わる!使い分けの方法を例文で解説
本記事では、文章作成における漢字の閉じ(とじ)と開き(ひらき)の使い分けの重要性、具体的なルール、そして文章の質を向上させるための便利なツールについて解説しています。
文章の読みやすさや専門性で悩んでいる企業の広報・マーケティング担当者やオウンドメディア編集者、Webライターの方向けに、文章の印象を大きく左右する「閉じ・開き(とじ・ひらき)」の基本的な使い分け方を紹介します。
この記事を読めば、文章の目的に応じて「閉じ・開き(とじ・ひらき)」を適切に使い分けられるようになり、より読みやすく、洗練された印象を与える文章を作成できるようになります。
\SQL獲得のためのWebコンテンツ制作のポイントはこちら!/
| 関連記事 トンマナとは?基本知識やSEOとの関係性、設定項目などを徹底解説! 「違和感を感じる」?ライターが注意すべき、系統別重複表現例 伝わらない文章の原因は“主述のねじれ”かも? ライティングレギュレーションの作り方!具体例や作成ポイントを紹介 |
Table of Contents
漢字の閉じ(とじ)・開き(ひらき)とは
文章作成において、特定の言葉を漢字で表記することを「閉じ(とじ)」、ひらがなで表記することを「開き(ひらき)」と呼びます。例えば「出来る」「事」「為に」などと漢字で書くのが「閉じ(とじ)」、「できる」「こと」「ために」とひらがなで書くのが「開き(ひらき)」にあたります。
これらは意味の違いではなく、表記スタイルの違いです。どちらが正しいということではなく、文章の目的や読み手の層、媒体のトーンによって最適な表現を選ぶ必要があります。
この閉じ(とじ)・開き(ひらき)の使い分けによって、文章の印象や伝わり方は大きく変わるため、読者にとって読みやすく、意図が伝わりやすい文章を書くために、欠かせない技術のひとつです。
漢字の閉じ(とじ)・開き(ひらき)の印象の違い
普段文章を読んでいるときに、漢字とひらがなの比率について気にする人はそんなに多くはないでしょう。しかし、意識して見てみるとその違いは歴然です。まずは、閉じている文章と開いている文章の印象を比べてみます。
▼開いている文章例
くじけそうになったときに、この“へたれ編集者”のコラムを読んで元気になってもらったり、さらにお仕事のご用命をいただいたりできるような、そんなコラムを目指していきます!どうぞよろしくお願いいたします。
全体的に開いた文章となっており、読みやすい印象を抱くのではないでしょうか。では、この文章を徹底的に閉じてみると、印象はどのように変わるでしょうか。
▼閉じている文章例
挫けそうになった時に、この“へたれ編集者”のコラムを読んで元気になって貰ったり、更にお仕事のご用命を頂いたり出来るような、そんなコラムを目指して行きます!どうぞ宜しくお願い致します。
このように、印象がかなり変わりますよね。せっかく明るい内容の文章であるにも関わらず、読む側にフォーマルな印象を抱かせてしまいがちです。
漢字の閉じ(とじ)・開き(ひらき)の必要性
では、漢字の閉じ(とじ)・開き(ひらき)を使い分けることには、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。その必要性を見ていきましょう。
意図した意味を正確に伝えられる
読み手に正確な意味を伝えるためには、漢字・ひらがな・カタカナの適切な使い分けが欠かせません。とくに同じ読みでも、異なる意味を持つ言葉には注意が必要です。
例えば、次の文章を見てみましょう。
この一文では、「あめ」が「雨」なのか「飴」なのかが判断できません。天気に関する話なのか、それとも趣味のお菓子集めなのか、読み手によって受け取り方が変わってしまいます。
このような曖昧さを避けるには、「彼女は飴を集めている」のように漢字を使って明示することが有効です。書き手にとっては意図が明確でも、読み手にとっては文脈だけでは判断しきれないケースがあります。伝えたい内容が正しく伝わるように、言葉の表記は慎重に選びましょう。
文章バランスが整い、読みやすくなる
日本語の文章は漢字とひらがな、カタカナの組み合わせで構成され、その使い方ひとつで読みやすさが大きく変わります。とくに漢字を使いすぎると堅く難解な印象に、逆にひらがなが多すぎると間延びした幼い印象になってしまいます。
一般的に、読みやすい文章の目安は「漢字3割・ひらがな7割」です。このバランスを意識するだけでも文章の印象はぐっと洗練され、読者の離脱を防ぐ効果があります。
それでは、次のような例を比べてみましょう。
- 御足元の悪い中、ご来社頂き誠に有難う御座いました。
- お足元の悪い中、ご来社いただきありがとうございました。
- おあしもとのわるいなか、ごらいしゃいただきありがとうございました。
極端な例ですが、①は形式が堅く、漢字が詰まっていて読みにくく感じる人が多いでしょう。③はすべてひらがなで構成されており、視線の流れが悪く、内容の把握に時間がかかります。②のように、適度に「とじ」と「ひらき」を使い分けた表記がもっとも自然で伝わりやすい文章になります。
読み手は、一文ごとに無意識のうちに読みやすさを判断しています。そのため、ほんの少し読みにくいと感じた瞬間にそのページを離れてしまう可能性も。執筆後には、漢字を使うべきか、あえてひらくべきかを見直すことで文章の伝わり方は格段にアップします。
漢字の閉じ(とじ)・開き(ひらき)の使い分け方
実際に文章を書くとなると、閉じ(とじ)・開き(ひらき)の判断が難しい場合もありますよね。ここでは、開いて書くのが望ましい語句例をいくつか紹介します。
形式名詞
形式名詞は単体で意味がはっきりするわけではなく、ほかの語句を文法的に支える名詞です。文章ではつい漢字に変換しがちですが、読みやすさを考えるとひらがなにした方が適切な場合も少なくありません。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
| 閉じ | 開き | 使用例 |
|---|---|---|
| 物 | もの | 思い出のものを大切にしている。 |
| 事 | こと | 留学したことを思い出す。 |
| 時 | とき | 忙しいときほど集中力が高まる。 |
| 所 | ところ | 今ちょうど出かけるところです。 |
| 方 | ほう | どちらのほうを選びますか? |
| 他 | ほか | ほかに気になる点はありますか? |
| 為 | ため | 自分の将来のために学ぶ。 |
| 毎 | ごと | 週ごとに報告書を提出する。 |
ただし、「緊急時」や「発生した所」など、語句そのものが意味を持っている場合は、閉じて表記するほうが自然です。
接続詞
接続詞は、文章同士のつながりや展開を示す語です。ビジネス文や説明文では、読みやすくリズムを保つためにもひらがな表記が推奨されます。
| 閉じ | 開き | 使用例 |
|---|---|---|
| 尚 | なお | なお、詳細は別紙をご確認ください。 |
| 又は | または | メールまたは電話でご連絡ください。 |
| 或いは | あるいは | 会議は、水曜あるいは金曜に実施します。 |
| 若しくは | もしくは | 担当者、もしくは上司へご確認を。 |
| 故に | ゆえに | 信頼を失った。ゆえに契約は解除された。 |
ただし、契約書や法律文書などでは閉じて表記される場合も多いため、文体に応じて庁瀬しましょう。
形容詞
形容詞を漢字にすると堅く、冷たい印象になってしまうことがあります。とくに読み手が一般読者の場合は、感情表現などはひらがな表記にする方が伝わりやすいでしょう。
| 閉じ | 開き | 使用例 |
|---|---|---|
| 可愛い | かわいい | このキャラクター、すごくかわいいね。 |
| 有難い | ありがたい | 応援してくれるのはありがたいことだ。 |
| 羨ましい | うらやましい | 海外赴任が決まった友人がうらやましい。 |
| 面倒くさい | めんどうくさい | 朝の満員電車は本当にめんどくさい。 |
| 堅苦しい | かたくるしい | かたくるしい挨拶は省略して本題へ。 |
ただし、ビジネス文では「明確」「重要」など一部の形容詞は漢字表記がふさわしい場合もあります。
動詞・補助動詞
「わかる」「できる」「あげる」などは、意味の違いによって複数の漢字表記が存在します。誤解を避けるためにも、ひらがなで書くのが安全です。
| 閉じ | 開き | 使用例 |
|---|---|---|
| 分かる・判る・解る | わかる | 彼の気持ちはなんとなくわかる。 |
| 出来る | できる | 今日は早く帰ることができる。 |
| 上げる・挙げる | あげる | 手をあげる。声をあげる。 |
| 下さい | ください | ご意見をお聞かせください。 |
| 頂く | いただく | お茶をいただく。ご協力をいただく。 |
| 来た | きた | コンビニに行ってきた。 |
| 出す | だす | 子どもが急に泣きだす。 |
ただし、「致す」「申す」などフォーマルな補助動詞は、敬語表現として漢字で表記するのが適切な場合もあります。
副詞
副詞は文全体のトーンを調整する働きがあります。漢字で書くと意味は伝わっても堅苦しく感じられるため、ひらがな表記にすると親しみやすくなります。
| 閉じ | 開き | 使用例 |
|---|---|---|
| 全て | すべて | すべて準備が整いました。 |
| 一杯 | いっぱい | ご飯をいっぱい食べた。 |
| 時々 | ときどき | ときどき実家に帰ります。 |
| 更に | さらに | さらに便利な機能が追加されました。 |
| 既に | すでに | 商品はすでに売り切れです。 |
| 随分 | ずいぶん | ずいぶん寒くなってきた。 |
| 何故 | なぜ | なぜそれを選んだのですか? |
| 最も | もっとも | もっとも重要なのは継続することだ。 |
当て字・慣用句的表現
読み手がすぐに理解できないような当て字や、古風すぎる漢字表現もひらがなで書くのが一般的です。
| 閉じ | 開き |
|---|---|
| 御目出度う | おめでとう |
| 御免下さい | ごめんください |
| 生憎 | あいにく |
| 成程 | なるほど |
とくに上記のような言葉は日常でよく使う一方、漢字表記だと古めかしく読みにくく感じる人が多いため、ひらがながおすすめです。
複合動詞
2つの動詞が連なってひとつの意味を持つ複合動詞では、後半部分をひらがなにすると読みやすくなります。
| 閉じ | 開き |
|---|---|
| 笑い始める | 笑いはじめる |
| 見送る | 見おくる |
| 話し掛ける | 話しかける |
| 考え込む | 考えこむ |
後ろの動詞に重点が置かれるため、開くことでリズムが生まれ、読者の理解がスムーズになります。
常用漢字外の漢字
常用漢字に含まれない漢字や、常用外の読み方をする場合は、読みにくさを避けるためにひらがなで書くのが無難です。
| 閉じ | 開き |
|---|---|
| 煩わしい | わずらわしい |
| 齎す | もたらす |
| 予め | あらかじめ |
| 悉く | ことごとく |
とくにビジネス文書やウェブ記事では、ひらがな表記の方が視認性が高く、広い読者層に適しています。
閉じ(とじ)・開き(ひらき)を適切に使う方法
最後は、漢字の閉じ(とじ)・開き(ひらき)の使い分けに悩むという方に向けて、ライティングの際に取り入れたいおすすめのアイテムやツールを紹介します。
記者ハンドブックを活用する
漢字のとじ・ひらくを使い分ける際、その判断に役立つのが「記者ハンドブック」です。これは、新聞やメディアでの表記に関するルールをまとめたガイドブックで、日常的なライティングにも重宝できます。
漢字の使い方やひらがなとの使い分け、送り仮名のルールなど、細かな部分までカバーされているため、文章を一貫性のあるものに仕上げる際には必須のアイテムです。とくにプロフェッショナルなライティングを求められる場面では、このハンドブックを手元に置いておくことで、文章のクオリティを格段にアップさせることができます。
文章校正ツールを活用する
ライティングの効率を上げ、表記ゆれを防ぐためには文章校正ツールの活用がおすすめです。とくにオンラインの校正ツールは、誤字脱字だけでなく、表記の統一感もチェックしてくれるため非常に便利です。例えば、「出来る」と「できる」、「お疲れ様」と「お疲れさま」など、人では見落としがちな微妙な違いも修正できます。こうしたツールを活用することで、文章全体の統一感が増し、スムーズで読みやすいコンテンツの作成が可能です。
AI校正ツールのひとつ「Typoless」については別記事「AI校正ツール「Typoless(タイポレス)」を使ってみた!料金や機能、評判を徹底レビュー」で詳しく紹介しています。
漢字の閉じ(とじ)・開き(ひらき)に関するよくある質問
漢字の閉じ(とじ)・開き(ひらき)に関するよくある質問をまとめました。
閉じ(とじ)・開き(ひらき)とは?
文章作成において、特定の言葉を漢字で表記することを「閉じ(とじ)」、ひらがなで表記することを「開き(ひらき)」と呼びます。閉じ(とじ)・開き(ひらき)の使い分けによって、文章の印象や伝わり方は大きく変わります。読者にとって読みやすく、意図が伝わりやすい文章を書くためには欠かせません。
詳しくは、記事内「漢字の閉じ(とじ)・開き(ひらき)とは」をご覧ください。
漢字の閉じ(とじ)・開き(ひらき)の必要性は?
漢字の閉じ(とじ)・開き(ひらき)を使い分けることには、以下のような必要性があります。
- 意図した意味を正確に伝えられる
- 文章バランスが整い、読みやすくなる
それぞれの必要性については、記事内「漢字の閉じ(とじ)・開き(ひらき)の必要性」で詳しく解説しています。
閉じ(とじ)・開き(ひらき)を適切に使うには?
漢字の閉じ(とじ)・開き(ひらき)を適切に使うには、以下のような方法が挙げられます。
- 記者ハンドブックを活用する
- 文章校正ツールを活用する
それぞれの方法について、詳しくは記事内の「閉じ(とじ)・開き(ひらき)を適切に使う方法」をご覧ください。
まとめ
日常的な文章作成では、パソコンやスマートフォンの変換機能に頼ってしまうことが多く、漢字の閉じ(とじ)・開き(ひらき)の使い分けを普段から意識している人は少ないかもしれません。
しかし、企業やメディアが発信するコンテンツにおいては、このような細かな表現の使い分けが、ブランドの印象や消費者の行動に影響を与えることがあります。表現の一つひとつがブランドの個性や信頼性につながるため、意識的に適切な使い分けましょう。

執筆者
コンテンツディレクター/ライター
Miho Shimmori
2023年ファングリーに入社。以前はWebマーケティング会社で約2年半コンテンツマーケティングに携わり、不動産投資メディアの編集長を務める。SEOライティングが得意。ほかにも士業関連や政治など複数メディア運営の経験あり。Z世代の端くれ。趣味はサウナと競馬と街歩き。