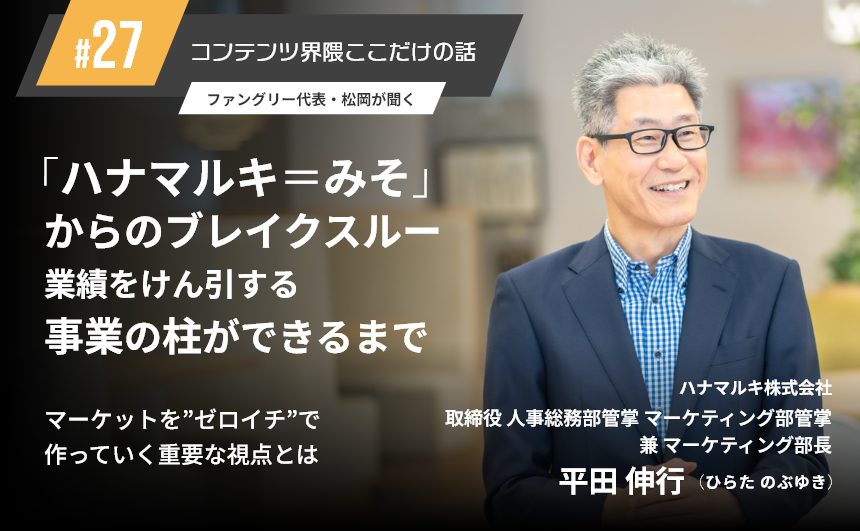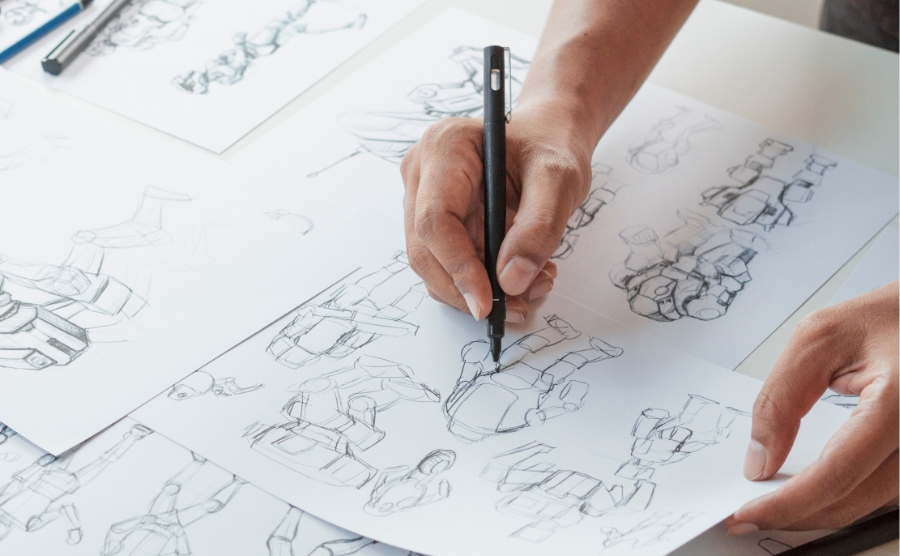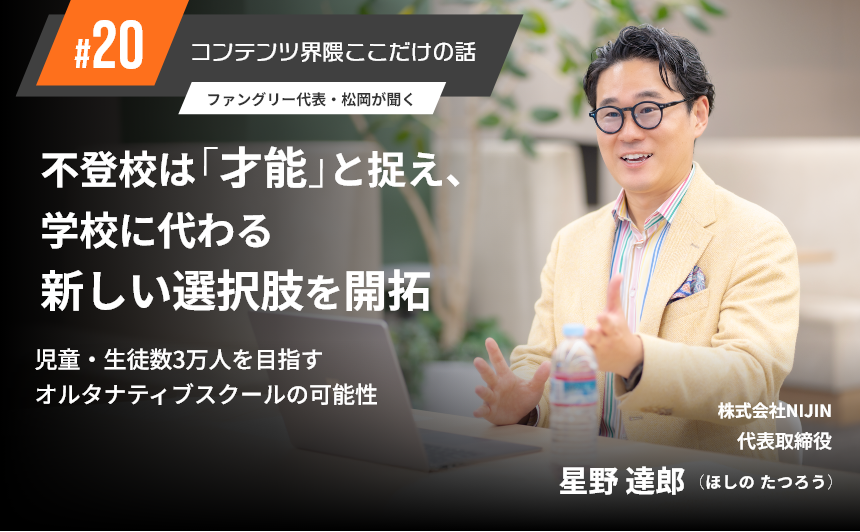Interview
# 13
「Do層」と「Watch層」の接続で卓球のビジネス価値は高まる|野球やサッカーとは違うコンテンツの作り方が鍵に
株式会社Tマーケティング
コミュニケーション部
浅賀 康彦(あさが・やすひこ)
コンテンツプロデュースカンパニーを標榜する株式会社ファングリー代表の松岡でございます。
「コンテンツ界隈ここだけの話」の第13話、今回のゲストは2017年に設立され、翌年に開幕した日本の卓球リーグである「Tリーグ」でセールス領域・マーケティング領域を担う浅賀康彦さん。興行としてのマネタイズを成立させるための苦労や工夫、マーケティング戦略、卓球界の今後のビジネス展望などについて、詳しくお話を伺いました。

株式会社Tマーケティング
コミュニケーション部
浅賀 康彦(あさが・やすひこ)
1995年に新卒でぴあ株式会社へ入社し、広告担当、Webメディアプランナー、API営業担当などを経験。2018年7月に卓球の新リーグ「Tリーグ」が立ち上がるタイミングでジョインし、その後、株式会社Tマーケティングへ転籍。以降はTリーグのチケット販促やWebマーケティングなどに裏方として携わっている。卓球の価値を高め、たくさんの人がワクワクする機会を創出するのが目標だが、卓球は未経験。

大阪にある卓球場を訪問し、ステークホルダー像が明確になった
──インタビューの機会をいただきありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。
──早速なのですが、「Tリーグ」について簡単に概要を教えていただけますか?
Tリーグは2017年4月に設立され、2018年10月よりスタートしたプロ・アマ混成の卓球リーグです。1チームの登録選手は最大8名で、男子6チームと女子6チームが所属。毎年8月頃から翌年2~3月にかけてレギュラーシーズンを戦い、上位チームによるプレーオフ(優勝決定戦)で勝者を決めます。
男子では張本智和選手や篠塚大登選手、女子では早田ひな選手や平野美宇選手、張本美和選手など、オリンピックに出場している有名選手もプレーしています。
──Tリーグはプロ・アマ混成なのですね。
「プロリーグ」と紹介してくださるところもあるのですが、学生や社員契約の選手もいるので正確には「プロ・アマ混成のリーグ」です。
──浅賀さんが所属するTマーケティング社は、一般社団法人であるTリーグの事業会社的な位置づけとしてマーケティングや各種プロモーション活動を担っていますよね。
はい。サッカーのJリーグやバスケットボールのBリーグにならって、運営部門(社団法人)と事業部門(株式会社)を分けています。Tマーケティングは事業拡大、収入の最大化を目的としており、得た利益をスポーツ振興に還元する形になっています。
──Tマーケティングでの浅賀さんの役割について教えてください。
チケット販促、集客、ファンクラブ運営など「toC」で売上を作る役割を担っています。
──浅賀さんはもともとスポーツビジネスに関わっていたのですか?
いいえ。前職はぴあという会社で音楽や映画、演劇といった、スポーツとはまったく関係ない領域を担当していました(笑)。
──なるほど(笑)。では、なぜ卓球を……?
そのときの僕は、「想像できないことをやりたい」という気持ちが強くて。一番興味があるのは音楽でしたが、音楽業界への転職となると自分の座る椅子がある程度分かるというか、これまでの経験からやるべきことが何となく見えてしまっている。それに対して、「何か違うことがやりたい」と思っていました。
そんなとき、たまたま「新しいスポーツリーグの立ち上げメンバーになりませんか?」と声をかけてもらったんです。
──Tリーグといえば、2018年に立ち上がったものの2シーズン赤字が続き、コロナ禍へ突入していますね。
コロナ禍……Tリーグも大変でしたよ。2019-2020シーズン中にコロナが発生し、最も集客が見込める3月のプレーオフを開催できなかったんです。その次のシーズンは無観客だったり、観客を入れられても半分だったり。当然ながら、赤字スタートでした。
──しかし、2020年以降の決算では黒字転換されています。
当時は男女各4チーム所属でうち2つが大阪拠点だったことから、月の半分以上を大阪での営業に充てました。特に力を入れたのは、卓球場(一般の方が卓球を習う場所)の訪問ですね。大阪にあるほぼすべての卓球場に行きました。そこでプレーしている方に「新しいシリーズ、見に来てください」とダイレクトにアプローチしたんです。
入社1年目にスポンサー営業をしていたときは、東京オリンピック前ということで「一緒に盛り上がっていきましょう!」といったアバウトなトークしかできませんでした。それが、大阪の卓球場を訪問して競技者や卓球場経営者の声に触れたことで、ステークホルダー像がくっきりしてきて。Tリーグの選手を連れて行ったときにどうすると盛り上がるかも分かってきました。卓球の「シズル感」と言いますか、そういったものを理解するいいきっかけになったと思います。
──なるほど、それはすごい行動力ですね。まったくの未経験者だった浅賀さんが現場のリアルな声に触れたことで、ファンが何に興味・関心を持ち、どういったことに熱狂するのか、といったイメージがクリアになっていった。
そうです。あとは、大阪のテレビ・ラジオ番組に出たり、自治体のスポーツ振興課や教育委員会を訪ねて子供たちを招待したりもしました。そういった取り組みも功を奏し、最終的には難波のど真ん中にある会場(エディオンアリーナ大阪)を満員にするというミッションをほぼ達成できました。

ゆくゆくは卓球に関連するすべてのサービスを一元的に受けられるようにしたい
──先ほど大阪で営業したというお話がありましたが、地域コミュニティとの関わりはスポーツリーグにとって生命線とも言えます。浅賀さんが考えている、地域のファンづくりについても伺いたいです。
地域で言うと、今は関東、 中部、関西、中国、九州・沖縄に拠点を置くチームが男女6ずつあります。リーグ側で把握しきれていない部分もあるのですが、選手が子供たちと一緒に遊ぶイベントを開催したりするなど、チームごとに地域コミュニティとの関係を深める取り組みをしてくれているんですよね。配布用のチラシを見せてもらったこともあるのですが、リーグを盛り上げるためのコンテンツが充実していることに驚きました。
──地場活動や小規模なオフラインイベントはリーグ主導ではなく、チーム主導なんですね。
おっしゃる通りです。Tマーケティングはリーグ全般のマーケティング機能を担っているので、オンラインでの情報集約や発信をメインでやっています。また、リーグが主催する興行を「セントラル」と言うのですが、セントラル以外のチームが主催する試合に関するアドバイスなどもできる範囲で行っています。
──浅賀さんは各チームとどういった形で関わっているのでしょうか?
全12チームに対して、月1回くらいの頻度で1on1ミーティング(オンライン)を行っています。チームごとの課題に対して、壁打ちをするイメージですね。各チームのWebサイトにマーケティングオートメーションを導入するにあたって、マニュアルやテンプレートの作成を支援したりすることもあります。
またそれとは別に、チケット販促ミーティング(オンライン)を週1回実施しています。週末に試合があると、パートナーであるローソンチケットさんから週明けに売上報告が送られてくるんですよ。加えて公式が出してくれた入場者数なども見ながら「前週はこんな実績でした」「目標に対して何%進捗しています」「こういったトピックがありました」といった共有・報告を行います。個別に成功事例があった場合は、そのチームにナレッジをシェアしてもらうケースもありますね。
──リーグが主導したマーケティング施策の成功例はありますか?
リーグ側のプラットフォームで申し込みフォームを作成し、それを活用して招待客管理や割引管理、それぞれに合わせた販促活動(メールマーケティングなど)を行っている例があります。Tリーグの大会を観に来た方には共通の会員ID(Tid)を割り振っており、それをプラットフォームで一元管理しているイメージです。
卓球場に習いに行くとか、卓球の試合やイベントを見に行くとか、卓球用品を買うとか、究極的にはすべての卓球に関連するサービスが共通の会員IDのもとで提供されるところまで持っていけたらなと思っています。
──“卓球におけるマイナンバー制度”みたいな話は聞いたことがあります。
「チケットを買いやすい」「キャンペーンの提供を受けやすい」となればより行動しやすくなりますからね。まだ道半ばですが、将来的には卓球がしたい「Do層」と一流のプレーを観戦したい「Watch層」をつなげ、それぞれ重なる部分を行き来させるとどういう経済効果が生まれるか――みたいなところにチャレンジしたいです。

「画面の中で楽しむスポーツ」としてポテンシャルがある
──スポーツビジネスとしてのブランド戦略についてもお聞きしたいです。Tリーグで特に打ち出したいのはどんなところでしょうか?
最高レベルのプレーを見られる環境があることでしょうか。冒頭でも少し触れましたが、有名選手が多いこともあって日本人選手のレベルが高い。それに加えて、アジア、ヨーロッパの各国から南米まで、世界中のトップ選手たちがそのスピードや迫力をTリーグで見せてくれています。そこは最大の魅力と言えると思います。
中国の国内リーグは基本的に自国の選手オンリーなので、「各国のトップ選手たちが集う」という意味では、Tリーグは世界最高峰と言ってもいいのではないかと思っています。
──各国の代表選手が日本に来ている理由や、来たくなる魅力は何でしょうか?
シンプルにプレーレベルが高いというのは魅力として大きいと思います。以前聞いた話ですが、「Tリーグは観客が入っていて人気がある」「盛り上がっている」という環境面のプラス要素もあるようです。「実力試し」の面でも好影響があるのではないでしょうか。
──さまざまなプロスポーツにおいて、国際戦略(グローバル展開)は大きな課題です。現在、海外向けの施策は行っていますか?
今、Webサイトの外国語対応を始めています。試合を見に来てくれるインバウンド観光客を想定し、まずはアジア中心。中国向けに番組(放映権)を販売したりもしています。
──世界的な競技人口を考えると、どんどん海外進出すべきかもしれないですね。
重要なのは、卓球をスポーツビジネスとしてどう成立させるかだと思っています。野球の場合は東京ドームで4万人超、サッカーでは国立競技場で6万人超の集客が可能ですが、卓球でその規模の「箱」を用意しても、ほとんどの観客は何が行われているかわからないでしょう。数万人規模の興行を打てない時点で、野球やサッカーとは違うビジネスにしていかなければならない。
──チケット収入だけじゃスケールしないですね。
でも卓球って、オリンピックでは印象に残った競技として上位にランキングされるスポーツなんですよ。なので、「画面の中で楽しむスポーツ」としてはかなりポテンシャルがあると思っています。となると、中継・配信がビジネスの軸になるんじゃないかなと。
──卓球が「配信向きのスポーツ」というのは、なるほどです。
国内では、週1回以上卓球をやる人が100万人いると言われています。また、少子化で中学校の部活動では部員が減っているにもかかわらず、卓球部は増えているそうです。海外では中国、韓国、台湾、香港などに加えてドイツなどでも卓球が盛んなので、マーケティングでそこをどう開拓できるかが重要と言えます。
これから裾野が広がっていけば、他のスポーツと同様に「お酒を飲みながら卓球の試合を見て応援する」といったスタイルが定着する可能性もあると思います。
──TリーグはYouTubeチャンネルでの配信も頻繁に行っています。
今のところ、試合のダイジェストを作ってアップするくらいですね。インタラクティブな仕掛けはまだ十分にやれていません。全部自分たちでやるのは難しいので、次のステップとして卓球系YouTuberさんと組んでPRしていきたいという考えはあります。
──卓球系YouTuber、ありですね!
卓球系YouTuberさんの中には、登録者数が200万人規模の方、ショート動画が2億回見られている方もいます。けっこう海外の視聴者・登録者が多いんですよね。いろんな人たちにリーチできるようになるので、可能性を感じています。

──卓球系YouTuberとのコラボ以外に、今後やっていきたいことはありますか?
コンテンツとしての見せ方やゲーム性の追求でしょうか。卓球は、「100メートルを全力で走りながらチェスをしているようなスポーツ」と言われることがあります。つまり、運動能力や技術の勝負と頭脳戦の両方を楽しめると言うことです。卓球の「3球目攻撃」(※)では、相手にレシーブをどう返させるかを考えて戦略的にサーブを打ちます。そうした駆け引きが分かると、卓球観戦が何倍も面白くなると思います。ここをどうエンターテイメントとして昇華させるかですね。
※相手のレシーブに対してドライブやスマッシュなどを駆使する戦術。自分のサーブ(1球目)、相手のレシーブ(2球目)に対する3球目のアクションという意味
──将棋や囲碁では、AIによるシミュレーションや勝率の算出などが視聴者に新たな楽しみを提供しています。卓球の未来についてはどう考えていますか?
「なじみのあるスポーツ」から「文化」までランクを上げたいですね。スタイリッシュでファッショナブルなイメージにしていくこともそうですし、中継や配信を誰でも手軽に見られる環境を作るという部分でもできることは多いと思っています。
たとえば、みんなで楽しめるパブリックビューイングをリーグで運営するとか。Tリーグの提供価値やポジションを活かして、どんどんブランドを高めていきたいですね。
──日本のリーグから世界を巻き込んで卓球のビジネス価値を高められるかもしれないなんて、めちゃくちゃ夢がありますね。ポテンシャルを考えると、今後のマーケティングやブランド戦略次第でブレイクスルーする可能性も十分にありそうです。今後のTリーグに注目したいと思います。本日はありがとうございました!
LATEST
最新記事
TAGS
タグ