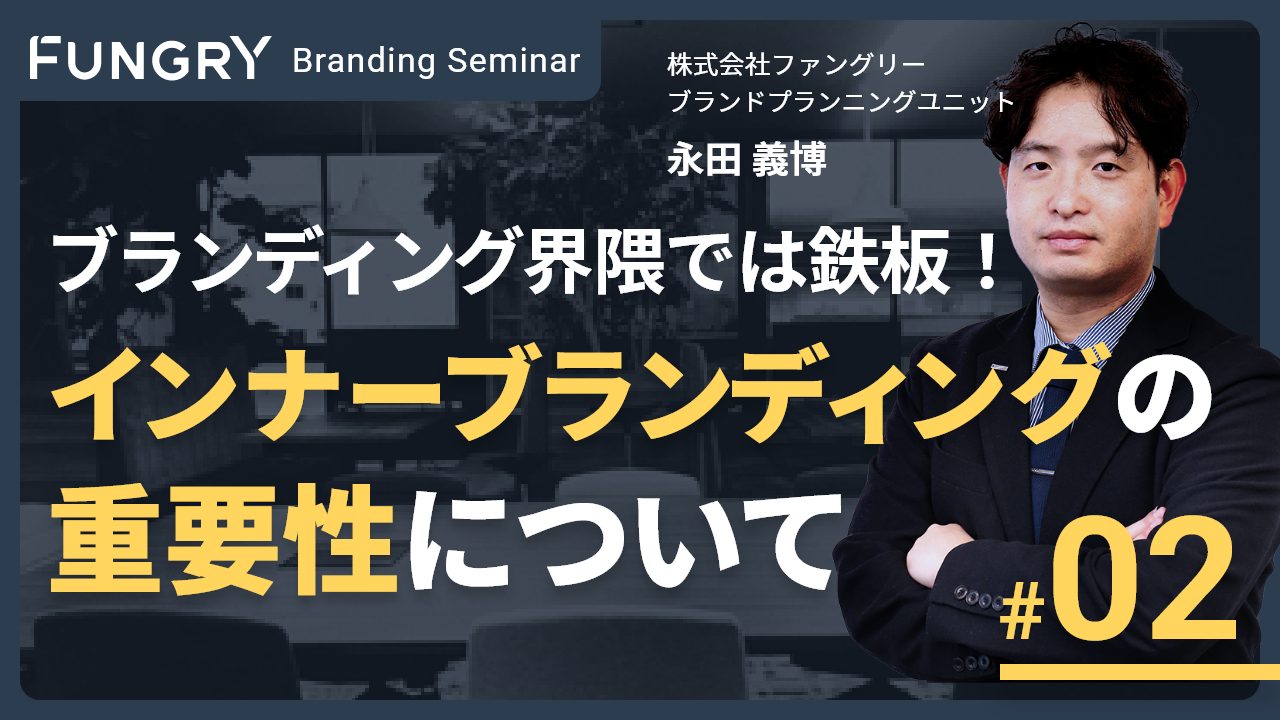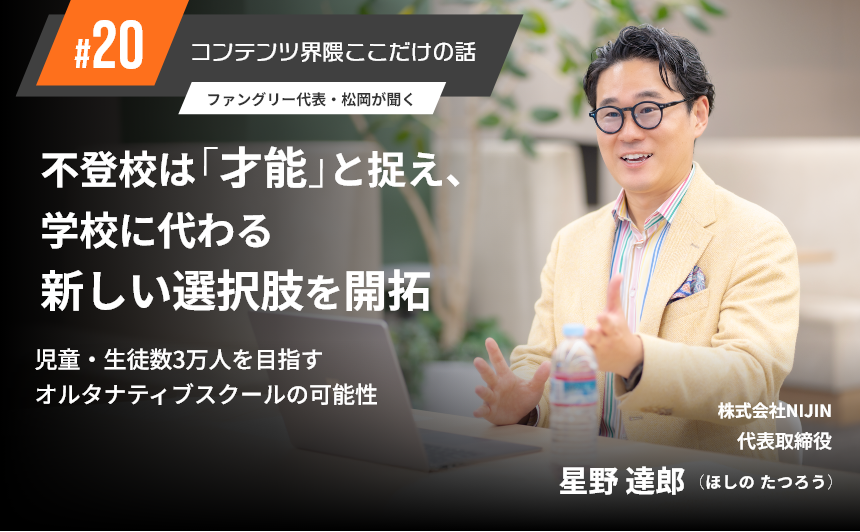Interview
# 15
SNSは魔法じゃない。成功の鍵は感覚よりロジック。赤字1500万円から年商3億円を実現したSNS戦略
株式会社EMOLVA
代表取締役
榊󠄀原 清一(さかきばら・せいいち)
コンテンツプロデュースカンパニーを標榜する株式会社ファングリー代表の松岡でございます。
「コンテンツ界隈ここだけ話」第15話のゲストは、SNSマーケティングの会社を経営し、自身も50万人超のSNS総フォロワーを持つインフルエンサーとして活動している榊󠄀原清一さんです。
2015年の会社設立から10年以上にわたって企業SNSアカウントの運用や、インフルエンサーのキャスティングなどの企業SNSマーケティングの総合的なマネジメントを手掛けてきた榊󠄀原さん。衆目を集める個人としての活動の裏で「経営者」としてビジネスや組織運営にどう向き合い、トレンドの移り変わりが激しい業界でどのようにシェアを拡大してきたのか、聞いてみました。

株式会社EMOLVA
代表取締役
榊󠄀原 清一(さかきばら・せいいち)
1984年静岡県生まれ。2009年にインフラエンジニアとしてサイバーエージェント社へ新卒⼊社。その後、ソーシャルゲームのWebアナリストなどを経験し、退職後の2015年に株式会社EMOLVA を設立。これまでに500社以上の企業にSNSマーケティングサービスを提供し、自らのSNS総フォロワー数は50万人を超えている。「令和の虎」「人財版 令和の虎」「青い令和の虎」に「虎」としてレギュラー出演中。

お金をいただいている企業に対し、論理的に説明できなければならない
──取材をお受けいただきありがとうございます。
こちらこそどうぞよろしくお願いします。
──経歴を拝見しましたが、意外性があってユニークですね!
私は高校生の頃からずっと「理系畑」で活動してきました。こういう派手な格好をしていたり、インフルエンサーとして活動していたりするので意外に思われることも多いのですが、それはもう「ド」が付くくらいの理系でして(笑)。
──見た目とのギャップもそうですし、現在のポジションからも想像できないというか(笑)。
東京理科大学・大学院では「材料力学」をテーマにした研究室に入っていました。具体的には、当時流行っていたAjax(エージャックス)という技術を活かしてインターネットを材料力学の分野でどのように有効活用するか――といった研究です。研究室ではプログラミングも行っており、自身でWebアプリを作っていました。
──2007年から2008年当時は、いわゆるクラウドサービスの普及が限定的でした。
はい。なので、自分のPCでサーバーを立ててやっていましたね。でも、Ajaxを動かすとサーバーに相応の負荷がかかるので、自前のPCだとすぐ止まってしまうんですよ。これは困ったぞと。そこでネットワークやインフラ部分の重要性に気づき、バックエンドのサーバーサイドに興味を持つようになりました。
──それで、エンジニアを目指して就職活動すると。
そうです。そういった背景もあって、就職活動はインフラエンジニア一本でしたね。僕の周りには「新卒でインフラエンジニアをやりたい」なんていう人はいませんでしたし、サイバーエージェントに入社した際も、101人いた新卒同期の中で私1人でした。
──ちなみに、当時培った技術的なスキルで今も役に立っているものはありますか?
直接的な技術ではありませんが、エンジニア時代の考え方や経験がすごく生きていると感じることはあります。具体的にはロジカルシンキングですね。
エンジニアリングは「0か1かの世界」なので、「こうすればこうなる」といったようにロジックに落とし込んでいかなければなりません。なんとなくSNS業界は「感覚でやっているんじゃないか」と思われがちですが、私はロジックに落とし込んで再現性を高めることがサービスの肝だと思っています。
──榊󠄀原さんのようなタイプは、SNS界隈にはなかなかいないかもしれませんね。
私もそう思います。そこが自分の強みなんじゃないかと。
SNSにおいて感覚はとても大事ですが、あくまでそれは半分。残りはロジックです。私たちは企業からお金をいただいてサービスを提供しているので、成果を出さなければなりませんし、論理的に説明できなければならないと思っています。感覚だけでやっているとどうしても胡散臭くなってしまいますし、論理的に説明することがビジネスパーソンとしての義務だとも思っています。
──エンジニアからのキャリアチェンジは、何がきっかけだったのですか?
エンジニアになって4年くらい経った頃に、スマホゲーム(ソシャゲ)が台頭してきました。そのタイミングで「Webアナリスト」という募集職種や部署が新たにできたんです。そこで「やってみないか」というオファーがあり、転向することにしました。
──2010年代前半はスマホの台頭、SNSの台頭、ソシャゲの台頭と、いろんな変化がありました。
Webアナリストはそこから2年くらいやりました。当時はガチャのシステム全盛期で、どこでユーザーが離脱したか、どんな施策が成功したかなどをひたすら数字分析していましたね。プロデューサーとアナリストがチームを組み、プロデューサーが立てた仮説をアナリストがロジックに落とし込んで改善策を組み立てる、という関わり方でした。
その後はキュレーションサービスが一気に流行ったこともあり、サイバーエージェントに所属した最後の1年はキュレーションメディアの運用部署に異動。そこではアンバサダーを集めたり、管理したり、実際に情報を拡散させたりして、「メディアを外に広げること」に注力していました。
──時代の変化に合わせて、榊󠄀原さんのやりたいことがつながっていったのですね。
はい。そのときの経験が起業にもつながっていると思います。

SNS施策の「簡単で時間がかからない」「安くできる」は誤解
──EMOLVA社の事業について教えていただけますか?
EMOLVAでは、「企業SNSマーケティングに対する総合的マネジメント(ができる会社)」という面を打ち出しています。
──「総合的マネジメント」とはどういうことでしょうか?
ベンチャーから大手企業、地方自治体から国の機関、またBtoCからBtoB企業まで、業態や規模を問わずSNS活用のソリューションを提供しています。当社の場合は会う方すべてが顧客になり得るような感じなので、どこのジャンルやプラットフォームにも特化せず、課題に応じたベストなソリューションの提供を心掛けています。
今はInstagram特化、TikTok特化などプラットフォームごとに事業者が分かれていることが多いのですが、「どんな悩みもInstagramで解決できる」なんてことはないですよね? サービスやターゲット、課題の内容によっては、XやYouTubeに注力すべきケースもあります。
EMOLVAは領域特化の方針を採っていないので、俯瞰的な立場から中長期的な計画の立案、施策の決定、プラットフォームの選定ができる。そういう意味で「総合的マネジメント」という言葉を使っています。
──なるほど。具体的な施策ありきではなく、あくまで課題解決への道筋を立てられるところを強みとしているのですね。
SNSは数あるソリューションのひとつでしかありません。「SNSをやりたい」といった相談をいただいても、仮に他の施策がボロボロだったら「まずそちらから取り組んだほうがいい」「現状の最適解はSNSじゃない」と説明することもあります。
──榊󠄀原さん自身はすごくキャラが立っていて、ガンガン表に出ていく印象があります。実際に営業もされているのですよね?
初期の商談にはほとんど参加していますね。私のほうである程度要件や戦略を固めて、運用サイドのスタッフにパスをするイメージです。
──「トップ営業あるある」で、お客様側の期待値が上がりすぎて困ることはないですか?
確かにそれはあるかもしれません(笑)。ただ、お客様には「SNSは魔法のツールじゃないので、やれば100%成功するわけじゃない」とあらかじめ伝えています。
──SNSについて「簡単で時間がかからない」「他の施策より安くできる」と考えている方は、一定数いそうですね。
そう思っている方はかなり多いです。でも実際は真逆で、SNSは成果が出るまでに時間がかかるし、しっかり注力したいと思えば費用も高くなります。
例えば、最新の仕様ではInstagramはカルーセル投稿と呼ばれる1投稿で20枚もの画像を投稿できて動画も入れられますし、クオリティの高いクリエイティブを作って運用している企業もそれなりに多い。なので、ちょっとやった程度ではリーチもインプレッションもなかなか伸びません。
──違う場所で何パターンも写真を撮影し、動画を制作し、投稿も1日何回か行うとなったら、片手間ではできない。
成功事例について説明するときは、仮に大成功して数カ月で成果が出た案件であっても「これは1年かけて取り組むもの」とちゃんと伝えます。そして、年間計画の中で毎月振り返りを行い、「なぜ良かったのか」「今後どうするか」を判断するんです。運が良ければ早期に目標を達成することもありますが、それは偶然です。私は偶発性には頼る奇策をすすめませんし、KPIで背伸びさせることもしません。いかに論理的にPDCAを回せるかが重要ですね。
── そこですよね。あくまで、マーケティング成果を継続的に生み出していくための可能性を追求していく、という。
「理想論と計画は違う」という基本的な考え方を伝えて、それから期待値を擦り合わせて乖離を最小限にしていくようにしていますね。
──「赤字1500万→年商3億へ拡大」というフレーズを見ましたが、具体的にはどのように業績を伸ばしていったのでしょうか?
市場のニーズにベストタイミングで応えられたのが大きかったですね。例えば、TikTokのように新しいプラットフォームができると、企業はまずインフルエンサーマーケティングを始めます。次に、プラットフォームがある程度世の中に浸透すると、自社アカウント(いわゆる公式アカウント)運用の需要が出てきます。
当社の場合、初期のInstagramニーズが高まり始めた時点でインスタグラマーとの提携を完了し、また自社アカウントの運用に成功していました。Instagramのニーズが上がれば次は既存プラットフォームのX(当時はTwitter)、YouTubeでもニーズが高まることは想定できるので、各プラットフォームのインフルエンサーと提携して自社アカウントを成長させました。
TikTokが流行った際にもその基礎があったので、TikTokerとの提携により私のアカウントも2つで合計15万フォロワーを獲得しています。さらに、SNSの新たな活用領域として採用分野が注目され始めた時期にいち早く参入し、自社アカウントを通じて12,000名を超える採用応募を獲得することにも成功しました。
つまり、世の中が「やりたい!」と思った時点で当社では「それがすでにできている状態」を作っていた、ということかなと思います。

競合優位性をどんどん高めていかないと、埋もれていってしまう
──マーケティングリードや商談はどのように獲得しているのでしょうか?
当社はすべてSNS経由での問い合わせのみです。アウトバウンドもやるべきだと思ってはいますが、それは次のフェーズとして考えています。
ありがたいことに、SNSをきっかけにいろんなメディアに取り上げてもらえているので、私個人と会社を合わせれば月100件くらいの問い合わせを獲得できています。日々SNSで配信を行っていることもあり、「SNSなら榊󠄀原」という第一想起をある程度取れているんじゃないでしょうか。
──社長のインフルエンス力を高めることは企業のマーケティングにおいて重要でしょうか?
社長でなくてもOKだと思います。ちゃんと運用できるなら、広報のスタッフでも一般のメンバーでも。当社でも、私が出る想定だったアカウントに別の社員が出ることがありますしね。「理想的な社員がいない(見つからない)」という場合は、イメージに合う人を当社がキャスティングして、ストーリーを作りながら運用していくという方法もあります。
ショート動画において重要なのは、企業アカウントを属人化させること。これは、「特定の人しか運用できないようにする」という意味ではなく、表に出る人を固定化して「キャラを打ち出していく」ということです。「運用の属人化」ではなく「見た目の属人化」ですね。「企業アカウントではあまりキャラクターを打ち出したくない」というケースもあるかと思いますが、属人化させないと差別化が難しく、ターゲットに覚えてもらえない可能性もあります。
──プラットフォーム単位で見たときに、再現性の高い、オススメの施策などはあるのでしょうか?
ショート動画の中でも最も拡散力の高いTikTokで、初期認知を作っていくのが最善です。ただ、良くも悪くもショート動画は「暇つぶし」で何となく見ている人が多いので、適切な導線を用意し、各プラットフォームで何を伝えるかをしっかり作り込まなければなりません。
私の場合は、Xでは経営論を述べ、Instagramではプライベートにも触れながら、世界観を作っています。そして最終的に視聴者の方がYouTubeへたどり着くと、SNSマーケティングについて1時間にわたり詳しく解説した動画を公開しています。そこまで見ていただければ、「この人は『確実に』SNSに詳しい人なんだな」と思っていただけるでしょう。このような段階的な導線作りが、月100件以上の問い合わせや12,000名の入社希望につながっています。
──いろんなSNSのアカウントを持っているのに、運用を徹底できていないケースはとても多いですよね。
中途半端な運用を続けるとマイナスブランディングになってしまうこともあるので、戦略と計画に合わせてどこまでやるかを決め、決めたことはやり切るのが大切です。方針や企画に不安がある場合は、ベンチマークとなる企業アカウントを設定し、最初はそこを真似しながら続けていくのもありだと思います。
──BtoB領域でSNSをうまく運用して成果につなげた事例はありますか?
ちょうど数カ月前から運用を始めた、ある警備会社さんの事例があります。採用目的でTikTokとInstagramを運用しているのですが、キャストや台本など世界観が本当にうまくできたというのもあり、ショート動画が初月で合計100万再生を超えました。
こういうのって、コンセプトが重要なんですよ。こちらの警備会社さんのショート動画は、警備員の方々がお昼に円になって地べたでお弁当を食べるシーンのイメージからヒントを得ました。そこで感じた人間味や仲の良さが、外向けのブランディングにつながった形です。他の業界でもそうですが、まずは流行っているものが何かを見極め、その要素をロジックで落とし込んでいくことが差別化のポイントになると思います。
──榊󠄀原さんの今後の展望や自身の注力領域について教えてください。
やはり、EMOLVA社の事業拡大ですね。「総合SNSマネジメント」の質と量を確保するための採用・育成は注力領域になると思います。当社には10年の歴史がありますが、環境が変われば1~2年で淘汰されてしまうかもしれない。ですので、「総合的マネジメント」という特徴や500社以上ある実績、私のインフルエンサーとしての認知度も含めて、競合優位性をますます高めていかないと、埋もれていってしまうと思っています。
──具体的に計画していることがあれば教えてください!
新規事業として、BtoC向けのプロダクトを自社でローンチする予定です。今の時代、商品設計の段階でSNSの運用を考えなければならないと思っているので、自社のプロダクトを自社のSNSで伸ばせたら大きな競合優位性になるんじゃないかと。
それと、行く行くはIPOを実現したいです。道のりは大変ですが、組織構造を考える良い機会だと捉えたいですね。採用はどこも厳しいのが現状。だからこそクライアントと同じように、求職者への差別化も図っていく必要があると思っています。社長の発信力は採用のパワーにつながりやすいので、これまで以上に「会社の経営に特化したインフルエンサー」として前に出て行きたいですね。
──実際にインタビューさせていただくまでは「令和の虎」のイメージが強かったですが、日頃から真摯に事業に向き合い続けている「経営者としての側面」が垣間見えた気がします。インフルエンサーとしてはもちろん、経営者としても今後の活躍に注目したいです。本日はありがとうございました!
LATEST
最新記事
TAGS
タグ