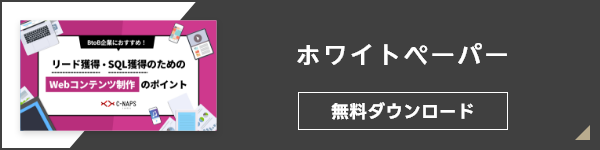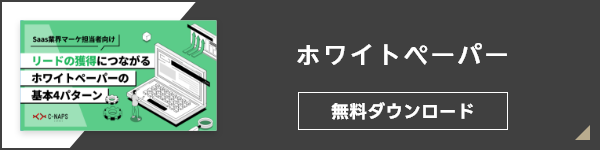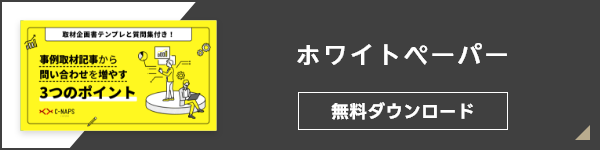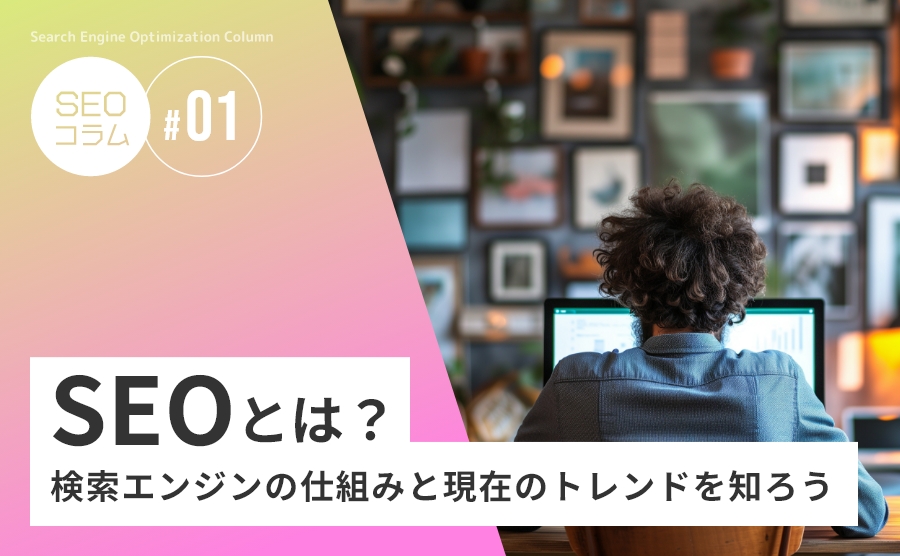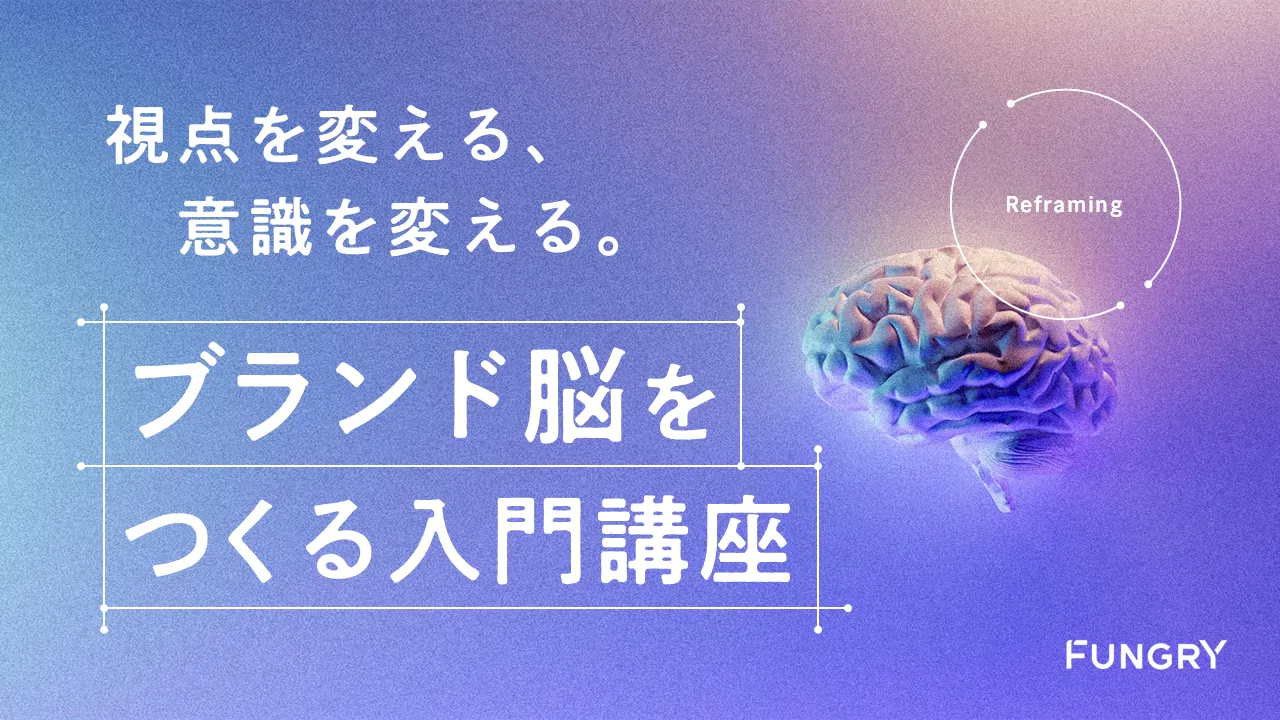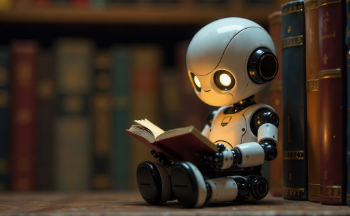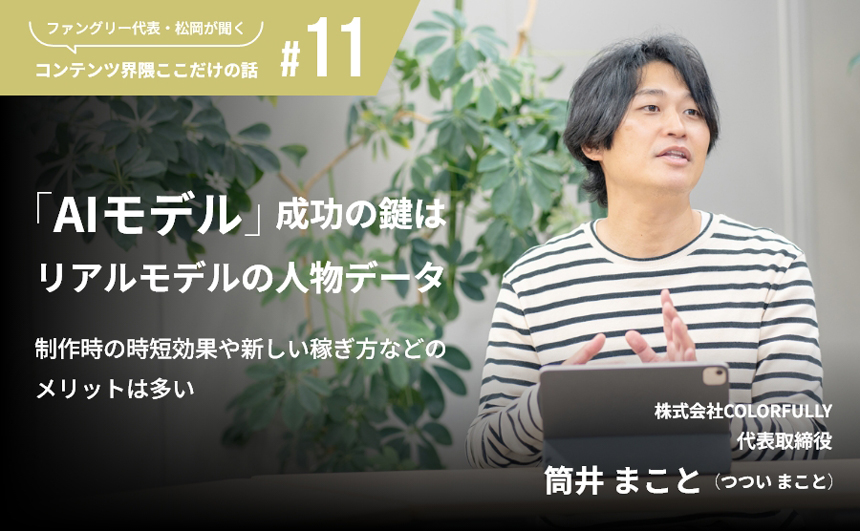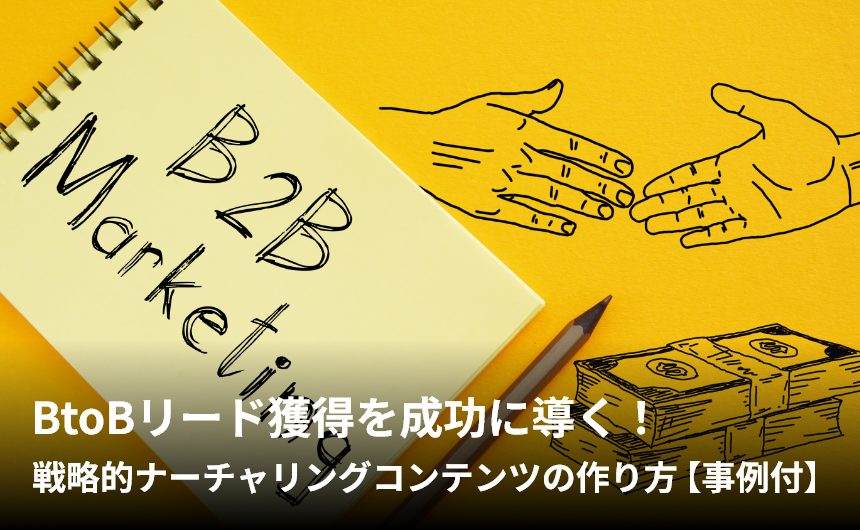
BtoBリード獲得を成功に導く!戦略的ナーチャリングコンテンツの作り方【事例付】
本記事では、BtoBのリード獲得を成功に導くための、再現性の高い「仕組み」の作り方について解説しています。
「BtoBのリード獲得施策が単発で終わってしまい成果に繋がらない」「短期的なKPIに疲弊している」といった課題で悩んでいるマーケティング担当者の方に向けて、属人化しない戦略的なアプローチを紹介します。
この記事を読めば、感覚的な施策から脱却し、データに基づいた再現性の高いBtoBリード獲得の仕組みを構築できるようになります。
コンテンツマーケティングについて詳しくは、別記事「コンテンツマーケティングを成功させるポイント」もあわせてご覧ください。
\リード獲得のためのWebコンテンツ制作のポイント/
\この記事が音声・動画コンテンツになりました!/
目次
BtoBのリード獲得とは?基本を分かりやすく解説
BtoBマーケティングにおけるリード獲得の基本的な概念を理解することは、あらゆる施策を成功させるための第一歩です。
ここでは、意外に誤解されているケースも多いリード獲得の定義やBtoC(Business to Consumer)との違い、現代ビジネスにおける不可欠性、そしてBtoB特有のマーケティングの難しさとそれを乗り越えるアプローチについて分かりやすく解説します。
BtoBマーケティングにおけるリード獲得の定義
リードとは、将来的に顧客となる可能性を持つユーザー(見込み顧客)を指します。BtoBマーケティングにおける見込み顧客は、企業やその担当者となります。
リード獲得はこうした見込み顧客の連絡先など、関係構築の起点となる情報を得るための活動です。BtoBの製品・サービスはBtoCに比べて高額で、検討期間も長期に及ぶ傾向があります。そのため、顧客の課題解決に役立つ有益な情報提供を通じて信頼関係を築き、製品やサービスへの理解を徐々に深めてもらうプロセスが欠かせません。
この点は、個人の感情や即時的な欲求に訴えるBtoCマーケティングとの大きな違いです。BtoBでは、組織内の多くの関係者が合理的かつ長期的に導入や購入を検討します。このBtoB特有の購買プロセスを理解することが、効果的なリード獲得戦略の第一歩となります。
なお、リード獲得の最終的な目的は、質の高い商談機会を創出し、持続的な売上の向上、そして顧客生涯価値(LTV)の最大化につなげることです。
なぜ今、BtoBでリード獲得が不可欠なのか?
今日のBtoB市場では、リード獲得の重要性が一層高まっています。購買担当者(バイヤー)は営業担当者を待つのではなく、自らオンライン上で積極的に情報収集を行うようになったからです。
2024年に株式会社wibが調査したデータによると、購買担当者の84%が営業担当者と接触する前に購買を決定づけた情報に触れており、決裁者の67%が営業担当者以外の経路から購⼊を決定しているという結果が出ています。さらに6senseが発表したデータでは、購買プロセスの69%が完了するまで営業担当者と接触しないと報告されています。このような状況下で、従来のプッシュ型営業だけで見込み顧客との接点を持つことは困難でしょう。
また、2024年にトゥモローマーケティング株式会社が実施した調査によれば、比較検討したサービスを見つけたきっかけ(流入元)の67.3%が「オンライン」であり、展示会やイベントより多いことが分かりました。質の高いリードを継続的に獲得することは、効率的な商談機会の創出や売上拡大、市場シェアの拡大などビジネス全体の成長に欠かせません。
さらにガートナージャパン株式会社の発表によると、2025年までにBtoBの営業インタラクションの80%がデジタルチャネルで行われると予測しています。つまり、デジタルを起点としたリード獲得戦略の立案は急務だといえるのです。
BtoBマーケティング成功への道筋
BtoBマーケティングのリード獲得には、BtoCと比べて特有の難しさがあります。その主な理由は、BtoBならではの購買プロセスにあります。BtoBでは、製品やサービスの導入が組織全体の決定事項となり、それに向けて複数の意思決定者が関わるためです。
この複雑な状況を乗り越えるには、まず相手を深く理解することが欠かせません。ターゲットとなる企業やその担当者だけでなく、購買に関わるさまざまな立場の人(担当者の上司や決裁者など)が抱える課題や関心事に寄り添う必要があります。
そのために重要になるのが、コンテンツマーケティングです。ブログ記事やホワイトペーパー、ウェビナーといった多様なコンテンツを通じて継続的に有益な情報を発信し、時間をかけて信頼関係を築いていくことが求められます。
BtoBにおけるコンテンツマーケティングについては、別記事「BtoBのコンテンツマーケティングで効果を高める施策【目的別】」もご覧ください。
BtoBリード獲得のためのチャネル戦略

BtoBにおけるリード獲得の機会を最大化するには、多様なチャネルを戦略的に活用することが不可欠です。
先述のとおり、今日の購買担当者はオンライン中心に情報収集し、意思決定を行う傾向にあります。一方で、とくに高額な商材や企業の根幹に関わるような複雑なサービスの導入を検討するケースでは、オフラインでの接点が決定的な役割を果たすことが少なくありません。
その理由としては、オンラインでは得にくい「深い理解」と「強い信頼関係」を築ける点に集約されます。具体的には、以下のとおりです。
- 直接対面で話すことで熱意が伝わり、信頼感が生まれやすい
- 実物を見たり操作したりすることで理解しやすくなる
- 課題意識の高い顧客や決裁者と直接対話できる機会になる
このように、オフラインでの接点は獲得したリードとの関係を深化させ、信頼を醸成し、最終的な購買決定を後押しする上で重要な要素となります。「オンラインか、オフラインか」という二者択一で考えるのではなく、購買担当者の検討フェーズに合わせてオンライン/オフラインの接点を戦略的に設計し、連携させていくことが現代のBtoBマーケティング成功のカギといえるでしょう。
ここでは、BtoBマーケティングで有効な主要リード獲得チャネルをオンラインとオフラインに大別し、それぞれの特徴と活用ポイントを解説します。
オンライン施策
1. SEO
検索エンジン最適化(SEO)は、見込み顧客が情報を探す際に自社コンテンツを見つけてもらうための重要な施策です。BtoBの製品・サービスの購入を検討している企業や担当者も、意思決定初期の情報収集段階で検索エンジンを利用するケースが多いでしょう。
前項でも挙げたトゥモローマーケティング株式会社の調査では、BtoBサービス導入時の流入元として「Web検索で出てきた比較サイトや提供企業のWebサイト」という回答の割合が最多でした。
このことからも分かるように、適切なキーワード戦略と質の高いコンテンツの設計によって検索上位表示させられれば、広告費用をかけずに継続的・安定的なリード獲得を目指せるでしょう。
なお、SEO戦略の核心はキーワード設計とその背景にあるターゲットの課題やニーズ(検索意図)を深く理解すること。その上で、顧客の課題解決に貢献する専門的で信頼性の高い情報をコンテンツとして発信していきます。コンテンツの質に加え、Webサイトの構造を検索エンジンに最適化するテクニカルSEOも重要です。
SEOについては、別記事「SEOとは?検索エンジンの仕組みから現在のトレンドを知ろう」をご覧ください。
2. SNS
LinkedInやFacebook、X(旧Twitter)などのSNSは、BtoB企業にとってターゲット層へのリーチ拡大やブランド認知度向上、見込み顧客とのエンゲージメント構築に有効なオンラインチャネルです。これらのSNSは、とくにBtoB領域において意思決定に関わるキーパーソンを特定しやすく、専門性の高い情報を共有するプラットフォームとして価値が高まっています。
実際、トゥモローマーケティング株式会社の調査によると、オンラインの情報源の中では「Web検索結果」や「提携企業のWebサイト」に次いで「SNS」や「SNS広告」も多く利用されています。
これらのSNSには、それぞれ以下のような特性があります。
| SNSの種類 | 特性 |
|---|---|
| ビジネスプロフェッショナル向け | |
| 詳細なターゲティングが可能 | |
| X(旧Twitter) | リアルタイム性が高い |
BtoBマーケティングにSNSを活用する際は、製品情報だけでなく業界の洞察や課題解決のヒントなどの「価値」を提供することが重要です。双方向のコミュニケーションでコミュニティを形成し、長期的な信頼関係を構築してリード獲得につなげましょう。
また、SNSでの通常の情報発信だけでなくSNS広告の併用も効果的です。エンゲージメント率やWebサイトへのトラフィックなどを定期的に分析し、戦略を最適化していきます。
企業のSNS活用については、成功事例とあわせて別記事「企業のSNS成功事例5選!ブランド価値を向上させるSNS活用のポイント」で紹介しています。
3. メールマーケティング
メールマーケティングは、獲得したリード情報を活用して見込み顧客との関係を深化させ、育成(ナーチャリング)するのに効果的なオンラインチャネルです。BtoBマーケティングにおいては、休眠リードの掘り起こしや既存顧客へのアップセル・クロスセル機会の創出、新規リード獲得にも役立ちます。
メールマーケティング成功のカギは、ニーズや特性に基づいて顧客を分類する「セグメンテーション」と、各顧客の属性や行動履歴などのデータからニーズに合った情報を提供する「パーソナライゼーション」です。リードの属性や興味関心、行動履歴に基づいてリストを細分化(セグメンテーション)し、各顧客に対して最適化されたメッセージを配信(パーソナライゼーション)します。
例えば、ホワイトペーパーAをダウンロードした見込み顧客に対しては関連ブログ記事を送り、ホワイトペーパーBをダウンロードした見込み顧客に対しては導入事例を送るといったステップメールが有効となります。
また、メールマーケティングにおいてはターゲットが開封したくなる「魅力的な件名(タイトル)」と、ターゲットが次の行動に移しやすい「明確なCTA(行動喚起)への導線」も重要です。
BtoBのメールマーケティングについては、別記事「BtoBのメールマーケティングで効果的な“やり方”とは」をご覧ください。
4. ホワイトペーパー
ホワイトペーパーは、BtoB企業が持つ専門知識やノウハウ、調査結果などをまとめた資料です。見込み顧客が抱える課題を解決するのに役立つ「価値の高い情報」と引き換えに、リード情報を獲得することが主な目的となります。BtoB向け製品・サービスの購買担当者は、情報収集の段階で詳細な情報を求める傾向が強いため、ホワイトペーパーはこれを解消する有効な手段のひとつといえるでしょう。
ターゲットニーズに合ったホワイトペーパーを作るのに外せない要件定義項目は、以下のとおりです。
- ターゲットのペルソナ
- マーケティングフェーズ
- ターゲットのインサイト
- 課題解決につながるテーマやキーワード
- ホワイトペーパーへの導線設計
そして、ホワイトペーパーの作成フローは以下となります。
- 構成の作成
- 原稿・デザイン作成
- ダウンロードページ設定
また、ホワイトペーパーは「作って終わり」ではなく、公開後の拡散・プロモーション施策や効果測定が重要です。
ホワイトペーパー制作については、別記事「ホワイトペーパーとは?問い合わせ数アップにつなげる制作ポイントを解説」をご覧ください。
\リード獲得につながるホワイトペーパー基本パターン/
5. Web広告
Web広告は、特定のターゲット層にピンポイントで自社の製品やサービス、コンテンツを届け、効率的にリードを獲得するオンラインチャネルです。
BtoBマーケティングではリスティング広告やSNS広告、ディスプレイ広告などが有効です。それぞれの広告について、具体的には以下のような特性があります。
| 広告 | 特性 |
|---|---|
| リスティング広告 | 検索キーワードに連動し顕在層に有効 |
| SNS広告 | 詳細な属性ターゲティングでニッチ層に有効 |
| ディスプレイ広告 | ブランド認知向上やリターゲティングに有効 |
なお、BtoBマーケティングでWeb広告を運用する際は、CPA(※1)やCPC(※2)といった費用対効果を意識しましょう。
※1 コンバージョンを1件獲得するために、1人あたりにかかった費用。
※2 広告が1クリックされるごとに発生する費用。
6. 動画
BtoBマーケティングにおいて、動画は複雑な製品や専門情報を分かりやすく伝え、見込み顧客の共感を深めるのに有効なオンラインチャネルです。製品デモ動画で機能の魅力を視覚的に伝えたり、顧客事例インタビュー動画で導入後の成功イメージを共有したりと、多様な見せ方・使い方があります。
実際に動画を作る際にはターゲットの課題解決に役立つ内容を心がけ、視聴者を惹きつける工夫や次の行動を促すCTAの設置が成功のカギとなります。完成した動画は自社サイトやSNSで活用し、見込み顧客の育成やブランドイメージ向上につなげましょう。
7. プレスリリース
プレスリリースとは、企業や団体が新聞やテレビ、Webメディアなどの報道機関に対して新製品や新規事業、イベント開催といった公式情報を発表するための文書です。「ニュースリリース」とも呼ばれます。
プレスリリースの目的は、メディアにニュース価値のある情報として取り上げてもらい、記事や番組として報道・拡散・紹介してもらうことです。広告費をかけずに幅広い層へ情報を届け、社会的な認知度や信頼性の向上を図ることが可能です。
プレスリリースを作る際は「単なる宣伝」ではなく、客観的な事実に基づいて新規性・社会性・独自性といった側面から「報道・拡散・紹介するに相応しい価値」を盛り込まなければなりません。効果的な構成としては、まずタイトルで結論を伝え、本文で詳細を分かりやすく説明するといった流れとなります。
プレスリリースの具体的な書き方は別記事「プレスリリースの書き方のコツ・配信方法」をご覧ください。
8. ウェビナー
ウェビナーは、後述するオフライン施策のひとつ「セミナー」と「Web」を組み合わせた造語で、オンラインで実施されるセミナーのこと。基本的にはセミナーと同じく専門知識を提供し、質の高い見込み顧客を獲得・育成するBtoBマーケティングの有力なチャネルです。
ただし一方的に配信するのではなく、Q&Aセッションやリアルタイム投票、チャット機能といったWebで開催する仕組みならではの双方向性を活かした作り方がおすすめ。このようなコミュニケーションによって、ウェビナー参加者の満足度とエンゲージメントを高めやすくなります。
さらにウェビナー開催後は、アンケート結果や視聴データから参加者の関心度を測り、フォローを最適化します。例えば関心の高い参加者には個別相談会を案内し、検討段階の見込み顧客には限定資料を提供するなど、個別のニーズに合わせたアプローチによって商談化率を高めましょう。
9. 業界メディア連携
業界メディアとの連携は、BtoB企業が新たなターゲット層へアプローチし、専門家としての権威性を高め、質の高いリードを獲得する有効なオンライン施策です。特定の業界やテーマに特化したメディアは関心の高い読者や専門家を抱えており、自社メッセージを効率的に届けられます。共同ウェビナーの開催や広告掲載も効果的です。
連携メディアの選定時には、自社のターゲット層と連携候補メディアの読者層が一致しているかといった点や、メディアの信頼性・専門性・影響力を見極めましょう。成功のカギは提供コンテンツの質であり、とくに価値ある独自情報をユーザーに提供することが信頼獲得とリード化に不可欠です。
オフライン施策
1. 展示会・イベント
展示会やイベント(ワークショップや交流会など)は見込み顧客と直接対話し、製品の価値を実際に体験してもらいながら関係を築くことのできる、貴重なオフラインチャネルです。明確な目標のもと魅力的なブースで集客し、対話を通じて顧客ニーズを深く把握しましょう。
展示会やイベントは、オンライン施策と統合することでより成果を得やすくなります。具体的には、商談などで獲得した名刺情報をMA(マーケティングオートメーション)ツールへ登録し、お礼メールやウェビナー案内を配信するといった流れが挙げられます。このようなオンライン施策との連携によって、一過性の出会いを商談へとつなげる確率を飛躍的に高められるでしょう。
2. セミナー
セミナーは主催者と参加者が同じ会場に集まり、参加者に向けて対面で実施する講演会や勉強会のことで、企業の専門性を示して質の高い関係を築く貴重な機会です。時には主催者と参加者の間で深い議論を行うこともあります。
前述の展示会・イベントと同様に、オンライン施策との連携が重要です。ターゲットの課題に沿ったテーマを設定し、メールやSNS、オンライン広告などを駆使して効果的に集客します。集客時だけでなく、開催後のオンライン施策との連携も必要です。
参加者リストをMAツールへ登録し、アンケート結果に基づき個別にフォローを実施します。そこから限定ウェビナーへの招待やインサイドセールスによるアプローチなどを実施することで、獲得したリードをナーチャリングします。
3. テレアポ・DM
テレアポやDMはターゲット企業に直接アプローチする伝統的な手法ですが、今日ではオンライン施策と統合することでより一層の効果を発揮します。
例えば、DMにはQRコードを掲載し、限定コンテンツやウェビナー申込ページへ誘導。ほかにも、Webサイトの行動履歴などを追跡してオンラインで関心を示した見込み顧客に絞ってテレアポを行い、個別相談を提案するアクションなどが挙げられます。
このように、デジタル施策だけでは動かなかった顧客層に対して、オフラインでの個別アプローチという「ひと押し」を加えることが、オンラインで築いた関係性を確実な商談へとつなげるカギとなります。
BtoBで獲得リードを顧客へ育成する「ナーチャリングコンテンツ戦略」

BtoBマーケティングにおいて、リード獲得はゴールではなくスタートです。とくにBtoBのビジネスでは先述のとおり製品・サービスの検討期間が長く、顧客がすぐに購入を決定するケースのほうが珍しいと言えます。そのため、獲得したリードに継続的に有益な情報を提供し、信頼関係を築きながら購買意欲を高めていく「リードナーチャリング(見込み顧客育成)」のプロセスが非常に重要です。
続いては、獲得リードを効果的に育成するためのナーチャリング戦略について、ペルソナとカスタマージャーニー設計から、具体的なコンテンツの種類や作成方法、MA(マーケティングオートメーション)ツールの活用まで、全体像を体系的に解説します。
戦略的なナーチャリングコンテンツを通じてリードとの長期的な関係を築き、最終的な成果である成約へとつなげましょう。
1. ペルソナとカスタマージャーニーの設計
効果的なリードナーチャリング戦略の第一歩は、ターゲットを深く理解すること。そのために不可欠なのが、ペルソナとカスタマージャーニーマップの設計です。
ペルソナは自社の理想的な顧客像を具体的に描き出したもので、BtoBでは担当者の役職や業務内容、課題、情報収集行動、意思決定における役割などを細かく設定します。ペルソナが明確なら明確なほど、求められる情報や響くコミュニケーションを具体的にイメージしやすくなります。
ペルソナについて詳しくは、別記事「SEOコラム#3 ターゲット設計とキーワード分析をしよう」をご覧ください。
カスタマージャーニーマップは、ペルソナが製品やサービスを認知し、情報収集から興味・関心、比較検討を経て購入やその後のリピート・推奨に至るまでの一連のプロセスを可視化したものです。各フェーズ(段階)での顧客の行動や思考、課題をマッピングし、企業とのタッチポイントや提供すべき最適なコンテンツ・施策を明確にします。
例えば、認知段階では課題喚起のブログ記事、興味・関心段階では詳細な製品紹介やホワイトペーパー、比較検討段階では導入事例や製品比較資料などが有効と考えられます。この設計により、顧客視点に立ったナーチャリング戦略基盤の構築が可能です。
カスタマージャーニーについては、別記事「カスタマージャーニーマップで顧客を深く知ろう」もあわせてご覧ください。
2. リードの興味・行動に基づくセグメンテーションとシナリオ設計
すべてのリードに画一的なアプローチをしても、得られるナーチャリング効果は限定的です。リードごとに課題や関心度、検討状況は異なるため、状況に合わせたきめ細やかなコミュニケーション設計が求められます。
セグメンテーションとは、獲得リードを共通の属性や行動パターンでグループ分けすることです。BtoBの主なセグメント基準は以下のとおり。
| セグメント基準 | 内容 |
|---|---|
| 属性情報 | 業種や企業規模、役職など |
| 興味関心 | 閲覧ページやダウンロード資料など |
| 行動履歴 | サイト訪問頻度やメール反応、イベント参加履歴など |
また、先述したカスタマージャーニー上の「検討フェーズ」なども該当します。
ナーチャリングシナリオとは、各セグメントに対して「いつ」「どのような情報を」「どのチャネルで」「どの順番で」提供するか、というコミュニケーションプランです。特定のホワイトペーパーをダウンロードしたリードに対するナーチャリングシナリオとしては、以下のようなものが想定されます。
- お礼メールの送付
- 関連ブログ記事紹介
- 導入事例送付
- 個別相談会やウェビナーへの誘導
これらはMAツールでリードの行動をトリガーに自動実行したり、スコアリングで分岐させたりできます。重要なのは、シナリオを定期的に効果測定して改善することです。
3. ナーチャリングコンテンツの作成【事例紹介】
リードナーチャリングの成否は、提供するコンテンツの質と適切性にかかっています。リードの状況やカスタマージャーニーのフェーズ、ナーチャリングの目的に応じて最適なコンテンツは異なります。
リードが求める価値を提供することが、信頼関係を深めて次のステップへ進んでもらうカギです。2024年のDemandGenによる調査では、購入担当者の42%は営業担当者と接触する前に平均3~7つのコンテンツを消費(閲覧)しているという結果が出ています。このことからも、多様なコンテンツタイプを戦略的に組み合わせる必要性がうかがえるでしょう。
ここでは、実際にナーチャリングコンテンツの事例を作成ポイントとともに解説します。
メールコンテンツ
メールコンテンツは、先述したようにリードナーチャリングの中心的な手段です。より効果的にナーチャリングするには、開封・読了・行動喚起を促す「パーソナライゼーション」が重要です。
パーソナライズとは、リードの属性や行動履歴に基づきメール内容を個別最適化すること。メールコンテンツにおいては、以下のような工夫を施すことで「自分に関係ある情報」と認識させ、開封率やエンゲージメントの向上が期待できます。
- 件名に企業名を入れる
- 過去に閲覧した製品・サービスと関連した最新情報を提供する
とくに件名のパーソナライズは極めて重要です。実際に2023年にZIPPIAが公表したデータでは、メール受信者の47%が件名だけでメールを開封するかどうかを判断しているという結果が出ています。受け手側のメリットが明確で、かつ興味を惹く言葉を選びましょう。
メール本文については「PREP法」を意識し、簡潔で読みやすく、提供価値が一目で分かるように構成することが重要です。設置するCTA(行動喚起)は、次に取ってほしい行動を明確に示し、目立つボタン形式にするなどクリックしやすいデザインを心がけましょう。
お役立ち情報・ノウハウ提供型コンテンツ(記事、ホワイトペーパーなど)
BtoBのリードナーチャリングでは、製品・サービスを直接売り込むより、リードの課題解決に役立つ情報や専門的ノウハウを提供するほうが重要です。
このような「お役立ち情報・ノウハウ提供型コンテンツ」は企業の専門性と信頼性を高め、リードとの長期的な関係構築の基盤となります。コンテンツ形式としては、記事やホワイトペーパーなどがあります。
お役立ち情報・ノウハウ提供型コンテンツの作成で最も重要なのは、ターゲットの課題や求める情報を深く理解することです。その上で自社の専門知識や独自見解、具体例を盛り込み、ほかでは得られない価値を提供しましょう。情報の正確性はもちろん、専門的な内容を分かりやすい言葉で解説し、図やグラフを効果的に用いるなど読みやすさにも配慮が必要です。
事例取材コンテンツ(導入事例・お客様の声)
購買担当者がBtoB製品・サービスを比較検討する際に最も信頼する情報のひとつが、実際に導入して成果を上げた事例を取材したコンテンツ(他社の導入事例やお客様の声)です。これらは企業が自ら語るメリットよりも客観的で、説得力があります。見込み顧客に対して「自分たちと同様の課題を抱えた企業が成功した」という具体的なイメージを与え、共感と安心感を生みます。
より効果的な事例取材コンテンツ作成のポイントは、ストーリーテリング(「物語」を通して情報を伝える手法)です。単に事実や成果数値を羅列するのではなく、読者が感情移入できるストーリーを構築し、その文脈に伝えたい情報を載せます。
事例取材コンテンツの一般的な構成要素は、以下のとおり。
- 導入前の課題
- 導入の経緯や決め手
- 具体的な活用方法
- 導入後の成果(定量的・定性的)
- お客様の声
事例取材コンテンツ作成時には、以下のポイントを意識しましょう。
- 具体的な数値やエピソードを含める
- 写真や動画を盛り込む
- 顧客の言葉を活かす
- 視覚的に分かりやすい構成とデザインを心がける
事例取材コンテンツ制作については、別記事「BtoBマーケティングに有効な事例取材記事の制作フロー」もあわせてご覧ください。
\事例取材コンテンツ取材企画書テンプレ付き資料はこちら/
限定動画・診断コンテンツ
リードナーチャリングでエンゲージメントを高めるには、一方的な情報提供だけでなく、特別感や双方向性を演出するコンテンツが有効です。限定動画や診断コンテンツは、その代表例と言えます。
限定動画は、特定のリードやセグメントにのみ提供される動画コンテンツです。製品・サービスの詳細デモや特定業界向け活用事例などが考えられます。「限定」という言葉が付加価値となり、視聴意欲を高めます。
診断コンテンツは、リードが質問に答えることで自身の課題やニーズに関するパーソナライズされた結果やアドバイスを得られるインタラクティブなコンテンツです。例えば、「あなたの会社の課題解決度診断」などが考えられます。リードは能動的に参加することで「自分事」として捉えやすくなり、関与度が高まります。
これらのコンテンツの作成ポイントは、以下のとおりです。
- 提供情報や診断結果がリードに有益であること
- 手軽に参加・視聴できる設計にすること
- 体験後に自然な形で次のアクションにつながる導線を設けること
関係構築型コンテンツ
高額なBtoB製品・サービスでは、「即決」は稀です。そのため、顧客との長期的な信頼関係を築く関係構築型コンテンツが重要となります。これは製品の訴求ではなく、リードの広範な課題解決に役立つ情報提供を継続するアプローチです。
関係構築型コンテンツの例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 業界トレンドレポート
- 専門家インタビュー
- コミュニティ運営
関係構築型コンテンツの作成ポイントは、直接的な売り込みを避け、顧客が抱える課題の解決に役立つ専門的な情報やノウハウを提供し続けることです。継続的な価値提供を通じて、「有益な相談相手」として想起される存在を目指しましょう。
4. MAツールを活用したナーチャリング自動化とパーソナライズ
セールスフォースの継続的な調査によると、BtoB領域におけるパーソナライゼーションへの期待は急速に高まっていることが明らかになりました。とくに2023年から2024年にかけて、個別扱いを受けていると感じていた顧客の割合は39%から73%へと大幅に増加しています。
このことからも、リードナーチャリング戦略を効率的かつ高度に実行するには、MA(マーケティングオートメーション)ツールの活用が欠かせません。
MAツールは、BtoBマーケティングに必要な以下の一連のコミュニケーションを自動化・パーソナライズするシステムです。
- 見込み顧客情報の一元管理
- 属性や行動履歴に基づいたセグメンテーション
- 設計されたシナリオに沿ったメール配信やコンテンツ提供
MAツールの主要機能には、以下のようなものがあります。
- リード情報DB管理
- Webサイト行動トラッキング
- メール作成・配信
- LP・フォーム作成
- リードスコアリング
- 効果測定・レポーティングなど
MAツールの選定ポイントは、以下のとおりです。
- 自社の事業規模や目的に合った機能が搭載されているか
- 操作性が高いか
- 価格体系が自社の予算に合っているか
- サポート体制が整っているか
- 既存SFA/CRMとの連携しやすいか
MAツールを活用してBtoBマーケティングの効果を最大限に出すには、以下を意識しましょう。
- カスタマージャーニーに基づく精緻なシナリオ設計
- ダイナミックコンテンツ活用
- 購買意欲の高いリード(ホットリード)を可視化するスコアリング機能の適切な設定
MAツールで特定されたホットリードは、速やかにインサイドセールスや営業部門に連携され、タイムリーなアプローチにつなげられます。
BtoBのリード獲得効果を測る分析と改善方法
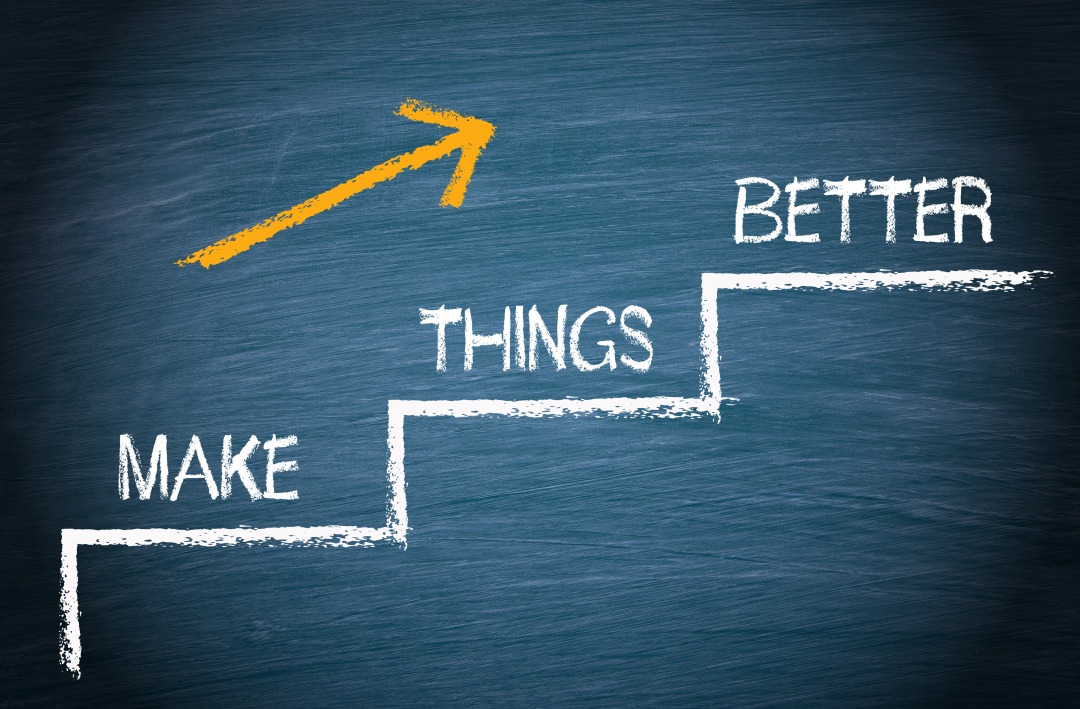
BtoBのリード獲得戦略では施策を実行するだけでなく、効果を正確に測定・分析しデータに基づいて継続的に改善することが重要です。定期的なKPI(重要業績評価指標)の確認と分析ツールの活用により、PDCAサイクルを回しながら施策を最適化していきましょう。
カスタマージャーニー段階別のKPI設定
BtoBマーケティングの成果を正しく評価して改善につなげるには、適切なKPIの設定が不可欠です。KPIは、活動がビジネス目標達成に向けて順調かどうかを示す指標となります。とくにBtoBでは購買プロセスが長いため、カスタマージャーニーの段階ごとにKPIを設定することが求められます。
各段階におけるKPI例は以下のとおりです。
| フェーズ | KPI例 |
|---|---|
| 認知 | ・PV数/セッション数 ・インプレッション数 |
| 興味・関心 | ・MQL数 ・資料ダウンロード数 |
| 比較検討 | ・SQL数 ・問い合わせ数 |
| 購入 | ・受注数 ・CVR |
| 推奨・継続 | ・LTV ・NPS |
KPIは過去実績や業界平均、ビジネス目標から逆算し、現実的かつ挑戦的な数値を設定しましょう。
Web解析ツールを活用した測定と分析
BtoBのリード獲得効果を測る分析方法としては、Web解析ツールの活用が重要となります。
Googleが提供するWeb解析ツール・Googleアナリティクス(GA4)は、自社が発信したコンテンツのパフォーマンスや成果を測定・分析し、改善点を発見するための強力なツールです。
Googleアナリティクスでは、以下のような指標を分析できます。
| 分析内容 | 主な指標例 |
|---|---|
| トラフィック分析 | ・訪問者数 ・流入チャネル ・新規 ・リピーター割合 |
| エンゲージメント分析 | ・平均ページ滞在時間 ・直帰率 ・エンゲージメント率 |
| コンバージョン分析 | ・資料請求 ・問い合わせ |
| ユーザー行動フロー分析 | ・サイト内ページ遷移 ・離脱箇所 |
これらのデータをもとに、どの施策が効果的かを評価し、改善策を立てていくことが重要です。
GA4については、以下の記事もあわせてご覧ください。
A/Bテストによるコンテンツ改善
A/Bテストは、異なる2つのバージョンのコンテンツを実際のユーザーに提示し、どちらが高い成果(クリック率やCVRなど)を上げるかを比較検証する手法です。
テストは以下の流れで進めることが一般的です。
- 目的と仮説の設定
- テスト対象の選定
- テストパターンの作成
- 実施とデータ収集
- 結果の測定と比較
- 改善策の実施
キャッチコピーやCTAボタンの文言・色・配置、メインビジュアル、フォームの項目数、メール件名などを対象にテストを繰り返すことで、データに基づく最適化が可能です。
定期的な効果検証とPDCAサイクルの実践
BtoBの市場環境や顧客ニーズ、競合動向は常に変化しています。BtoBのリード獲得戦略を持続的に成功させるには、計画の実行だけでなく定期的な効果検証と戦略の柔軟な見直し・改善を続けるPDCAサイクルを回すことが不可欠です。
BtoBマーケティングにおけるPDCAサイクルの具体例は、以下のとおり。
| 項目 | 具体例 |
|---|---|
| 計画(Plan) | KGI・KPI設定、施策・予算・リソース計画 |
| 実行(Do) | 計画に基づいた施策実行 |
| 評価(Check) | KPI進捗確認、効果測定、目標達成度評価、成功・失敗要因分析 |
| 改善(Action) | 評価結果を踏まえた施策の継続・改善・中止判断、次の計画へ活用 |
効果検証の頻度は施策により異なり、Web広告なら週次、コンテンツSEOなら月次や四半期ごとなどと決めて実施しましょう。
PDCAを効果的に回し、成果を継続的に高めるコツは以下のとおりです。
- データに基づく客観的評価
- 部門間での情報共有・連携
- 迅速な意思決定・行動
BtoBのリード獲得を成功させたコンテンツ戦略事例
BtoBのリード獲得とナーチャリングの戦略や手法が、実際のビジネス現場でどのように成果につながっているのかを理解するには、成功事例から学ぶことが有効です。
ここでは、業種や施策の異なるBtoB企業の成功事例を紹介します。
事例1. 株式会社シマテック:ニッチ市場特化コンテンツで安定リード獲得
特殊部品メーカーの株式会社シマテックは、ニッチ市場で高い技術力を持っています。
これまで同社には、「専門技術が伝わりにくく受注につながらない」という課題がありました。同時に、同社の顧客は部品仕様変更ごとのコストや納期、既存設備の故障、微小部品の静電気による搬送トラブルなどを抱えていました。
そこで、同社はパーツフィーダ(部品供給装置)に特化したコンテンツ戦略を展開。具体的には、以下のようなコンテンツを発信していきました。
- 動画・写真コンテンツ:高い技術力を動画や写真で視覚的に解説
- ブログ記事:製造工程の裏側や他社比較、顧客課題への具体的解決策を平易な言葉で紹介
顧客課題に寄り添い、解決できる技術やノウハウを前面に出したコンテンツを専門外のユーザー向けに作成したのです。この結果、新規顧客からの問い合わせが大幅に増加し、Webサイト経由の問い合わせ数は3.1倍、年間売上は1.7倍に伸長。広告費を削減しつつ質の高いリードを安定獲得し、成約率も2倍以上に向上しました。
このコンテンツ戦略の成功要因は、「高い技術力を分かりやすく伝える」といった努力を徹底した点です。具体的な課題解決に直結する情報提供で信頼を確立し、安定的なリード獲得と高い成約率を実現しました。
事例2. ロジスティード株式会社:MA連携メールで休眠リードを掘り起こし
EC事業者向けにシェアリング自動倉庫サービスを提供するロジスティード株式会社では、「多くのリード情報を保有しているものの、多くが休眠状態で有効活用できていない」といった課題を抱えていました。
営業リソースに限りがあり、全休眠リードへの手作業アプローチは非現実的という状態。そこでMAツールを導入し、休眠リードの掘り起こしとナーチャリングを実施。各セグメントの特性や想定関心事に合わせ、段階的に情報提供するステップメールシナリオを設計しMAツールで自動配信しました。
配信コンテンツは価値の高い情報(最新情報、成功事例、限定オファーなど)を中心に構成。MAツールのWebトラッキング機能で休眠リードのサイト再訪問を検知し、営業担当者にアラート通知、即座にフォローアップする体制を構築しました。
このような戦略的なメールマーケティングにより、保有休眠リードを再アクティブ化し、複数の大型案件を創出。さらにMA活用施策起点の受注件数は、前年比264%に増加しました。成功はMAツールを効果的に活用し、休眠リードへ網羅的かつ効率的なアプローチを実現した点にあります。
事例3. フリー株式会社:オウンドメディアとウェビナー連携で専門性を確立
クラウド会計ソフトなどのSaaS型ソリューションを提供するフリー株式会社は、「創業初期の知名度不足と、専門性の高いサービスの価値を伝達する難しさ」に課題を抱えていました。そこで同社は、コンテンツマーケティングを軸にオウンドメディアとウェビナーを戦略的に連携させ、ソートリーダーシップ(特定の分野において業界や社会をリードすること)の確立とリード獲得を目指しました。
オウンドメディアでは会計・経理に関する専門ノウハウや法改正情報、導入事例などを発信し、SEO対策で検索流入を獲得。さらに専門テーマのウェビナーを定期開催し、オウンドメディアで集客するとともに、ウェビナー内容をブログ記事として二次利用しました。
これらの情報をSNSでも発信することで、リーチを最大化。詳細ノウハウや独自データをまとめたホワイトペーパーも提供しました。
この施策の結果、業界内における認知度と信頼性が向上しました。さらに質の高い引き合いが増加し、広告費をかけずに多くのリードが増加。専門性の高い独自コンテンツによる価値提供と、複数チャネルの戦略的連携・コンテンツ多角的展開・再利用による相乗効果が、成功のポイントになったといえます。
BtoBのリード獲得・ナーチャリングに関するよくある質問
BtoBビジネスにおけるリード獲得およびナーチャリングに関するよくある質問をまとめました。
BtoBにおけるリード獲得とは?
リードとは、将来的に顧客となる可能性を持つユーザー(見込み顧客)を指します。BtoBマーケティングにおける見込み顧客は、企業やその担当者となります。リード獲得はこうした見込み顧客の連絡先など、関係構築の起点となる情報を得るための活動です。
詳しくは、記事内「BtoBマーケティングにおけるリード獲得の定義」をご覧ください。
BtoBにおいてリード獲得が不可欠な理由は?
BtoB市場では、購買担当者(バイヤー)は営業担当者を待つのではなく、自らオンライン上で積極的に情報収集を行うようになっているためです。
より詳細な背景については、記事内「なぜ今、BtoBでリード獲得が不可欠なのか?」で解説しています。
BtoBにおけるナーチャリングコンテンツ戦略とは?
BtoBで獲得したリードを顧客へ育成するためには、以下のような「ナーチャリングコンテンツ戦略」が重要です。
- ペルソナとカスタマージャーニーの設計
- リードの興味・行動に基づくセグメンテーションとシナリオ設計
- ナーチャリングコンテンツの作成【事例紹介】
- MAツールを活用したナーチャリング自動化とパーソナライズ
各戦略の詳細は、記事内の「BtoBで獲得リードを顧客へ育成する『ナーチャリングコンテンツ戦略』」をご確認ください。
まとめ
今日において、BtoB製品・サービスの購入担当者は自らオンラインで情報収集を進める傾向にあります。そのため、BtoB企業はカスタマージャーニーの各段階で価値ある情報を提供し続け、信頼関係を築かなければなりません。
多様なチャネルを戦略的に組み合わせ、ペルソナやカスタマージャーニーに基づくナーチャリングを徹底することが、マーケティング成果を左右します。お役立ち情報や事例取材記事など、リードナーチャリングに効果的なコンテンツを適切なタイミングで提供し、MAツールを活用しながら効率化・パーソナライズを図りましょう。
さらに、BtoBマーケティングにおけるすべての活動は、データに基づく効果測定と改善を通じてより一層の効果を発揮します。顧客課題に寄り添い、価値あるコンテンツを提供し続けることが、BtoBリード獲得の未来を切り拓くカギとなるでしょう。
\リード獲得のためのWebコンテンツ制作のポイント/

執筆者
生成AIエンジニア / Webマーケティング・生成AI講師
シバッタマン(柴田義彦)
Webマーケティング講師 兼 生成AIエンジニアとして、GA4×BigQueryで計測設計と分析基盤を構築します。研修と伴走で自走化を促進し、広告・SEO・CRMを成果につなげます。
LATEST
最新記事
TAGS
タグ